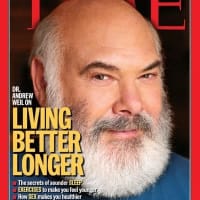今やイチゴの季節でもあり、4年近く前のブログ 「いちご カレンベリーを植える」が多くの方の興味を引くらしく、今尚アクセスが続いています。
このいちごを育てて見た結果に就いては、その後のブログでは殆ど触れて来ませんでしたが、実は家庭園芸品種として育てるには一寸問題があると思って居ります。
今般それで、其の事に就いて取り上げて見たくなり、表記のような題名でお話しさせて頂くことに致します。
此のイチゴ品種 「高度の病害複合抵抗性と優れた果実品質を活かし、減農薬栽培が可能な省力型品種として、また家庭園芸用品種としての普及が見込まれます・・・・」と、2008年のプレスリリーズで紹介されました。

―カレンベリーの新ポット栽培の姿、果実数が大変少ない!-
ところが、その「カレンベリー」の商業栽培された果実は先ず市場で見掛ける事はなかったようであり、一方家庭用の品種としては園芸店などで比較的多くの苗が出回って 「枯れないベリー」の宣伝文句にも魅かれて購入し、育てて見た方は多く居られ様には思われますが、家庭園芸栽培での成果、その後の経過を知る由もありません。唯、紹介された品種通りの特徴が認識できたかどうか多分に疑問に思います。
扨て、何故そんな事を今更申し上げるかと言いますと、弊方の新ポットポニックス栽培の経験では 此の「枯れないベリー」は、採苗からしっかり育てて 「クラウン」部分も十分に充実させた株であっても、果房の出蕾数が甚だ少ないのであり、頂花房の発達だけで、えき芽から出る筈の第2、第3の花房が殆ど伸びて来ないのです。その結果、いちごとしては株全体の実付き量が大変少ない品種と分かったのです。
一般のいちご品種と較べて見ると、頂花房から分伎する花房の伸長が全く見られないのです。その結果、ポット栽培では特に果実の数が少なくて、一株で多くて7~8個の果実が収穫出来たら良い方であり、なんとも実応えの悪い「いちご品種」と申せます。

―大株に育てても果実の収量が限られるカレンベリー
その『カレンベリー』の品種特徴、「農研機構」九州沖縄農業センターが2008年に情報公開された中では 「中間直枝型の果房形態を有し、果房当たりの着果数が少ないために、摘果作業が不要です」と説明されていましたが、その意味が、その時は具体的には何を指しているのか良く理解出来ませんでした。
苺品種には、本来その性質で果数型と果重型に分けられて居て、その「果重型」の特徴が強く出ているのが 『カレンベリー』の品種特徴であったのであり、その利点を生かすには、それなりの栽培上の大体的な管理が先ず必要であります。

―果数型いちごの典型的な姿、標準ププランターで育つ宝交早生―
それを具体的に申せば、種苗の採取から始まっての株の育成であり、季節に合わせての花芽分化に必要な低温と短日条件の時期の勘案であり、その時点での株の栄養条件((窒素レベルなど)で大きく影響を受けるのです。
栄養条件が良すぎると、苗が育ち過ぎとなって花芽分化に支障を来し、結果的には実成り数が少なくなるのであり、いわゆる昔から良く言われて来た発生ランナーからの採苗には、1段目の太郎苗は老化苗となるので避ける意味、其処に理由があったと言う事です。
しかし、今日の営利苺栽培では、花芽分化やその後の休眠などの生育条件を、人為的にコントロールして、収穫期を調節し、収穫量を増大させる栽培技術が著しく進んでいるのであり、それに合わせての品種や促成栽培や半促成栽培と言った作型の選択をされているのであり、栽培地域の日照量や温度条件に合わせて品種採用が、最も大切な要件とされているのです。
それが、それぞれの地域の自然条件下で、花芽分化や休眠条件で育てる一般露地栽培となると、家庭園芸レベルでの栽培知識や能力では、花芽分化しても出蕾数が限られる、このような品種を育てる事は、当然、至難の業があり、栽培地域条件で適、不適が当然あり、大変難しいいちご栽培と言えるのです。

―カレンベリーの鉢植えの参考写真の姿―農研機構より
それが 「ポット栽培も可能です」とばかりに立派なポット栽培の参考写真を見せられて 『カレンベリー』の苗を植えられた方々にすれば、誠に難しい挑戦を強いられる結果となった筈と言う事です。
それでは此処で、商業栽培では今では殆どその姿を消してしまっている一季成り苺の作型である本来の気候に合わせた露地栽培いちご、それに替わっての今の促成栽培、半促成栽培の背景の違いに就いて一寸言及して見たいと思います。
何しろ、今の日本の苺は品種改良が著しく、その食味の良さ、品質の高さには目を見張るものがあり、その果実の評価には海外でも注目に値するのですが、その季節をずらした作型の進化に基ずく栽培法がもたらした、行き過ぎた栽培技術の弊害とでも申しましょうか、結果として生み出されたのが、過剰な迄の農薬の繰り返し投与無くしては、発生する病虫害リスク回避が出来ない事態の発生であります。
栽培環境が或る程度コントロールできる施設内栽培でありながら、農薬散布回数が、1栽培シーズンの合計で、40回から50回以上にも及ぶと言う、常識からは考えられない、正に「農薬漬け」が当然の姿となっている事実です。
尤も、農薬残留成分は、その基準値以内であれば何十回使用しても安全と大方の人は思って居られるでしょうが、国それぞれで違うのであり、必ずしもその安全がどこでも認められるわけでは無いのです。
先だって、日本の優れた苺の高品質果実を台湾に輸出しようと試みた結果、その含まれる残留農薬基準値の高さが明らかにされて、門前払いに終わった事が報道されました。
具体的には日本で通っている殺虫剤の残留基準では、台湾では許可されないと言うことであります。
その点では、日本の柑橘類などでも同じような理由から、EU諸国では輸入禁止となっていると聞きます。そんな日本の農薬漬けの施設栽培いちごの現状、それを如何捉えるかは消費者の選択次第であります。

ー全くの無農薬のプランター栽培のいちご、宝交早生を摘む孫娘―
其処で、諸外国での苺栽培のその辺の農薬使用状況をネット検索で追って見たのですが、一般の苺栽培の季節に合わせた作型であれば、それ程の農薬の多投は先ず考えられないのであり、いちごの農薬問題があっても、特に取り立て言及する程の事態に無い事が良く分かりました。
それは日本でも同様であり、通常の苺の作型である季節に合わせた無加温の露地栽培であるならば、苺が他の作物と比べても、特に病虫害に脆弱である訳が無く、農薬使用を減らしてもそれなりの収量は充分に確保できる筈であります。
その1季成り苺、低温性の作物であり、生育適温は15℃から20℃と言います。ポット栽培ですと東京や南関東なら、3月下旬から5月中旬がその最適な生育シーズンであり、その間の温度条件や日照量にもよりますが、開花、結実、収穫までの日数から、収穫できる期間も約1か月余りで終わってしまう計算になります。

ー典型的な施設園芸栽培のいちご圃場の姿―webpagesより
それが、季節に逆らっての早期育苗から始まって、花芽分化と強制的な休眠処理などに続いての季節の早取りとなる生育環境の制御下に置いての大体的なストレス栽培いちごでは、施肥管理ともども従来より、2倍、3倍と長くなる期間の生殖成長を持続させる栽培法であります。
それは想像するに植物が、本来植物が備えている病虫害等々に対する抵抗性を、根本から全く失わされる結果に繋がっていると思われるのです。
其処に持ち込まれている徹底的しての薬剤防除での対応措置、最早日本の苺施設栽培は、考えれば、自然との不毛の闘いを強いられていると言わざるを得ません。
其処に品種面からの病害抵抗性に挑んだ新品種開発、その 「カレンベリー」の作出目的の意義は大いに評価すべきです。 唯、肝心な得られるべき「果実」の収量や食味の点で何か足らない?ところがあり、個人的な感想で敢えて 「カレンベリー」は未完成品種ではと申させて頂いたのです。

―同じ農研機構から発表されたいちご「おおきみ」の姿―
実は 「カレンベリー」と時同じくして発表された苺品種 「おおきみ」があり、こちらのほうはより大果種の同じような果重型品種ですが、その果実の食味の良さは食べ比べるとはっきり違いが分かるのであり、そのうえに 「カレンベリー」同様の病害抵抗性も亦供えていると言います。
唯、残念な事に、見た目には「カレンベリー」とそっくりの葉体でありながら、樹勢が比べると劣るのであり、育苗の為のランナーの発生も少なくて簡単に増やせないのです。
今年も亦、「カレンベリー」をポットポニックスで12株程、育てているのですが、その目的は、何処に紛れ込まれて区別のつかない 「おおきみ」を、その成った果実の違いで見つけ出す積りもあるのです。
その「おおきみ」、商業栽培品種いちごとして既に市場出荷もされていますし、栽培難易度は一寸高いのですが、種苗の入手は容易です。
![]()