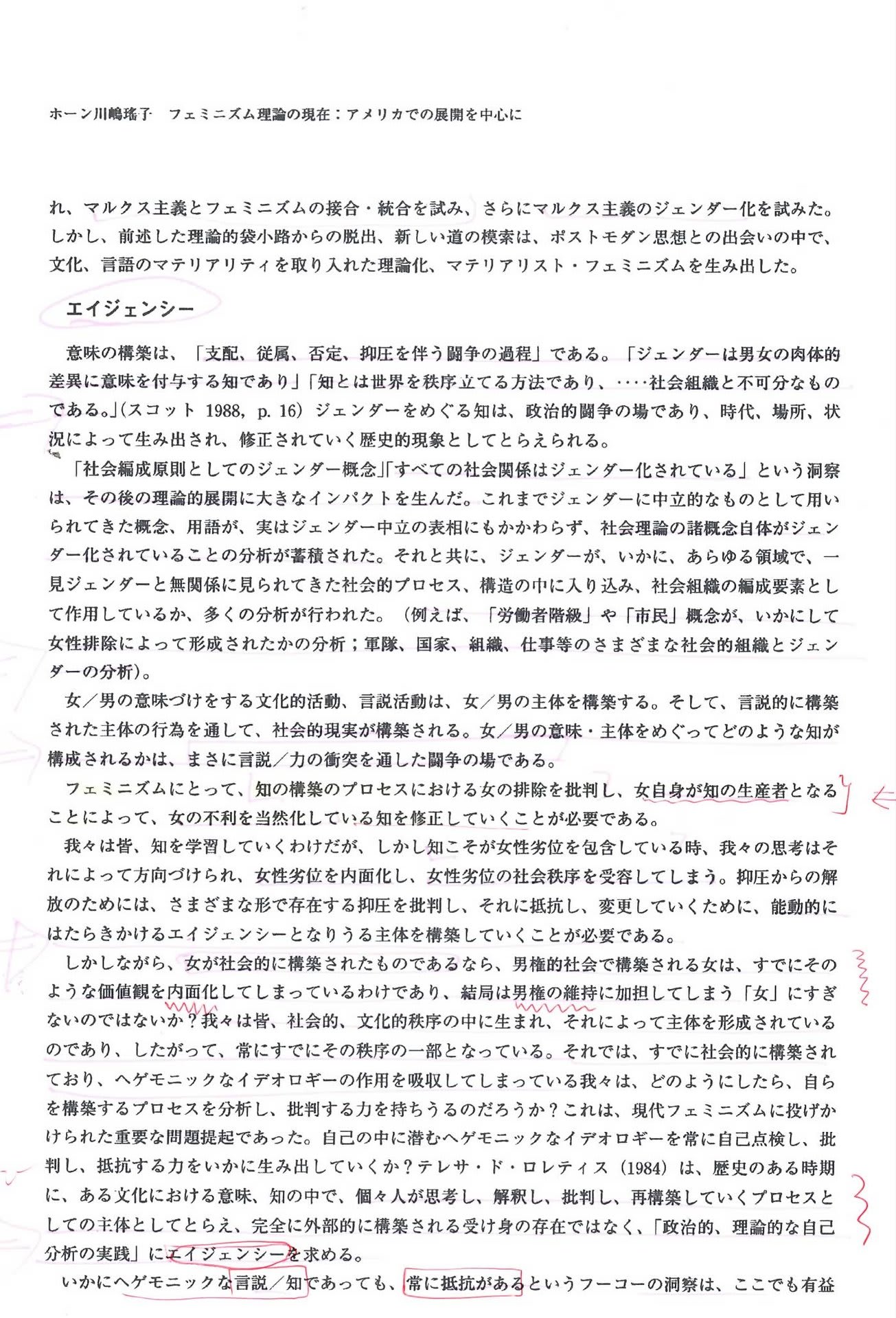

**********************************************************
実際は論稿の最終校正の過程で、feminism かfeminist theory なのか、基本的なところが気になって調べてみた。NETだが、ただ理論的なところでは欧米ははるかに進んでいる。全く日本でお目にかからない言葉が、専門語が飛び出してくるのは、欧米、特にアメリカの論文だ。それらに丁寧に目を通す余裕がないままだが、ただ日本の場合昨今は大衆受容がしやすい方向で、フェミニズムがジェンダーに置き変えられている傾向になる。SEXとGenderに違いはないとの認識も深まる中、ますます辺り障りのいいジェンダーが飛び跳ねていくのだろう。
2、3年前から取り組んでいた「フェミニズム論から見る沖縄演劇」-組踊「忠孝婦人」を中心にーがやっと日の目をみる。今回、組踊が登場した1719年にすでに辻や仲島の遊里も存在していて、その分断された舞台表出の根も見据えてみた。また近代以降の流れもみた。世界の演劇史に照らした時、スーエレンのfeminism and theatreを羅針盤に据えてみたのだが、そこから上演史なり演劇史を見ると世界の動向と重なる日本や沖縄の動向がまたあった、ということである。
この論文は親友で病のため組踊の「間の者」についての博論を完成することなく他界してしまったフランセス・マンマナに捧げたいと思う。フランセスがハワイで死去の知らせを受けた時、とても悔しかった。今でも悔しい。頑張り屋のフランセスのあの笑顔が忘れられない。いっしょに日本演劇学会に参加した事もあった。韓国でも彼女の発表を拝聴した。しかし、彼女はいない!いつでもそこにいるような彼女がいない、ということが信じられない。彼女のお嬢さんはフォトグラファーとして頑張っていて、ハワイとこちらとメールのやり取りをした。彼女の残した資料のことがメインのテーマだった、彼女の資料はハワイ大学やハワイ沖縄センターなどに寄贈されたのだと思う。映像関係や写真など、大事に保管して欲しい旨メールした。ケイラさんは無事インドから戻ってきたのだろうか?
ともあれ、深夜にネットで全部公開されているホーン川嶋瑤子さんの≪「フェミニズム理論の現在」アメリカでの展開を中心に≫を読んだ。最後のあがきのような確認である。自分の論文でも中心概念として使用したエイジェンシー、エイジェントの用語だが、フランセスが以前「沖縄演劇特集」の日本演劇学会紀要で展開した論稿(調査報告に入っているが、それはわたしの論稿「沖縄のハムレット」もそうだ。その扱いには今でも不満を持っている。大城立裕さんは論文として読んでくださった)の中で、彼女が導入した概念でもある。フランセスに導かれるように、このキーワードを意識したのである。
ホーンさんの論考は全体の流れを認識する上でとてもいいと思う。最後に「エイジェンシー」がきている。その部分だけ「備忘録」としてこちらに添付することにした。この論稿の最後をここに引用したい。
≪現代フェミニズムは、「伝統的知への女性の追加」を超えて、女性を劣位に置くことに加担している「知そのもの」の構成を批判し、再編成していくこと、およびそれを通して既存の社会組織の再編成を目指す作業を行っていると言える。学問知から大衆文化までのすべての「文化的生産活動」は、「主体を構築し、社会的現実を規定する力」として、作用しているからである。≫



















