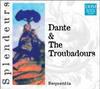 Dante and the Troubadours
Dante and the TroubadoursSequentia
Benjamin Bagby & Barbara Thornton
このアルバムはダンテが「俗語詩論」および「神曲」などで言及したトルバドゥールたちの作品を集めたもの。
12世紀の南仏プロヴァンスにおいて王侯貴族を中心にトルバドゥールと呼ばれる一群の詩人兼音楽家が現れた。彼らは俗語であるオック語を詩作に用い、満たされない愛を歌った。彼ら以前には恋愛は病気や狂気、あるいは別離の悲劇として描かれる場合がほとんどで、満たされない愛を抱え煩悶し、それを昇華することで精神的な高みへ至り、その喜びを歌うといったことはなされたことがなかった。
トルバドゥールの文化が栄えた背景には、学問の中心地であるフランスで、ラテン語の教養と詩作を学ぶ者があまりに多すぎたため、教会での役職を得られず、あふれた者たちが宮廷に吸収されたということがあった。そしてこの宮廷文化の中心には最初のトルバドゥールであるギョーム9世を祖父に持ち、フランスのルイ7世の妃となり、離婚後はイングランド王ヘンリー2世の妃となり、フィリップ尊厳王とリチャード獅子心王を子に持つアリエノール・ダキテーヌがいた。
トルバドゥールの起源には諸説あり、定かではないが、一時有力だったのがアラブ起源説で、そのため、トルバドゥールの楽曲の演奏においては多分にアラブ的な要素を強調したものが多かった。確かにフィドルなど弓で弾く弦楽器は中央アジアからイスラム圏を経由してヨーロッパに伝わったので、演奏においてはアラブ的な影響による即興がなされていたと考えられる。
このアルバムに収録されたトルバドゥールのうち、アルノー・ダニエルは「神曲」の浄火篇第26曲にあらわれ、グィード・グィニツェッリの口から「我よりもよくその国語を鍛えし者なり」と称賛されている。このトロバール・クロ(密閉体)と呼ばれる晦渋な語彙と謎めいた比喩を用いた極めて技巧的な詩人からダンテは多大な影響を受けている。ギラウト・デ・ボルネイユはレモゼスの人として語られ、ボルネイユをダニエルよりも優れた詩人とみなすものは愚かだとされている。また、フォルケット・デ・マルセイヤは天堂篇第9曲に登場し、ベルトラン・デ・ボルンは地獄篇第28曲において詩人としてではなく、ヘンリー2世の子であるヘンリーを父に背くよう教唆した罰を受け、体から首を切り離されてしまった姿が描かれている。
トルバドゥールの詩はヨーロッパ各地へ波及した。もちろんイタリアにも流れ込んだ。12世紀頃のイタリアは都市国家の建設などに力を注いでいたために芸術の分野では建築以外に見るべきものがなかった。13世紀になってシチリア王フェデリコ2世がプロヴァンスから詩人を引き連れて帰還したのち、「シチリア派」と呼ばれる俗語を用いた詩人たちが登場するようになった。13世紀後半になって文化の中心がトスカーナ地方に移動すると、シチリア派を継承する「シチリア=トスカーナ派」が誕生した。そしてさらに、ボローニャの詩人グィード・グイニツェッリを始祖と仰ぐ、従来の詩から離れ独自の境地を切り開こうとする若い世代が現れた。これを「清新体派」(Dolce Stil Novo)といい、ダンテはこの派に属した。この派は超俗的な傾向を持ち、極度に抽象化された表現を用い、愛の観念を純化した。
イタリアの詩人にとって、ラテン語と俗語はその親近性のゆえにかえって緊張関係にあるもので、ダンテが「俗語詩論」を書いた背景にはこの緊張関係の切実さがあった。この「俗語詩論」はラテン語に抗して俗語を称揚するかに見えながら、実のところ俗語をラテン語の修辞学に拘束することによってより高めることを目指しており、彼の言う「高貴な俗語」とは「イタリアのどの都市にもありながらどの都市にも属するように見えない、高次の詩的創造に適した俗語」とされ、極めて理念的、人工的な性格を持つ。この「高貴な俗語」の性格をダンテが被った亡命という根無し草の運命と重ね合わせてみるのも興味深いところであるとともに、シトー派修道会が純粋な聖歌を求める果てにたどり着いた聖歌の改良と重ね合わせてみるのも面白い。さらには哲学史上有名な論争である実念論と唯名論との間の「普遍論争」とも。
ダンテ・アリギエーリ「新生」(岩波文庫)
ダンテ・アリギエーリ「神曲」(岩波文庫)
E.R.クルツィウス「ヨーロッパ文学とラテン中世」(みすず書房)
上尾信也「歴史としての音」(柏書房)
田村毅/塩川徹也編「フランス文学史」(東京大学出版会)
岩倉具忠/清水純一他編「イタリア文学史」(東京大学出版会)










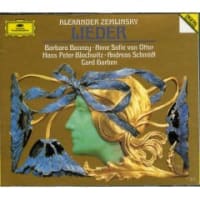
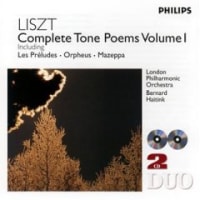
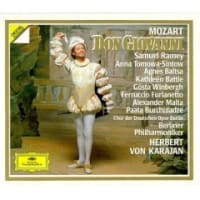
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます