 「フィツカラルド」(Fitzcarraldo)
「フィツカラルド」(Fitzcarraldo)1981年ドイツ
監督・脚本:ヴェルナー・ヘルツォーク
出演:クラウス・キンスキー、クラウディア・カルディナーレ 他
ゴム景気で沸く南米の都市マナウスには、パリ・オペラ座を模した「アマゾナス劇場」があり、ヨーロッパから有名歌手など招いてオペラの上演をしていた。ちょうどエンリコ・カルーソーとサラ・ベルナール(どういうわけか、女装した男性が演じている)の共演によるオペラの上演中にカヌーを漕いで一組の男女がやってくる。特別公演なので途中入場ができないと案内人にさえぎられるが、血にまみれた両手を見せてイキトスからカルーソーを見るためにやっとの思いで来たことを強く訴える。この男がクラウス・キンスキー演じる主人公フィツカラルドであり、そばにいる女性はクラウディア・カルディナーレ演じるモリーである。このシーンだけで、フィツカラルドが目的を達するためには尋常でない執着を見せる男であることがわかる。
フィツカラルドは野心的な事業家で、数年前にアンデス横断鉄道を敷設しようとして破産し、今は製氷事業を営んでいる。彼の夢はジャングルの奥地にオペラハウスを建設し、そこでカルーソーに歌ってもらうというものだ。それには莫大な費用が必要だ。彼は自らの製氷のノウハウを特許申請しようとするが取り合ってもらえない。儲けるならやはりゴムということで、ゴム成金に話を聞き、現地を案内してもらう。手つかずの土地は「ポンゴの瀬」という急流に阻まれ船が進めないところ、そしてヒバロ族という首狩り族がいる危険地帯しかない。
フィツカラルドは地図を見ながらひとつのアイデアを思いつく。それは二つの川が最接近している場所の山を切り開き、船を山越えさせればポンゴの瀬を避けることができるというものだ。
首狩り族の太鼓が鳴り響き、緊迫した状況に見舞われたとき、フィツカラルドはカルーソーのレコードを蓄音機にかける。この対立はアポロンとマルシュアースの音楽の闘いがそうであったように、先住民族と新しい支配者の闘いという意味を持つ。この
 映画では首狩り族も船の山越えに協力するが、それは屈服したのではなく、首狩り族に伝えられている、いわゆる積荷信仰に似たような伝説があり、たまたま利害が一致したので協力したという形で、先住民族を搾取する白人という図式からはずれている。無事に山を越え、宴を開いたあと、船は首狩り族によって艫綱を切られ、動き出し、避けなければならないはずのポンゴの瀬に突入する。ほとんど沈没寸前になりながらもどうにかポンゴの瀬を乗り切った後、首狩り族の目的が明らかになる。
映画では首狩り族も船の山越えに協力するが、それは屈服したのではなく、首狩り族に伝えられている、いわゆる積荷信仰に似たような伝説があり、たまたま利害が一致したので協力したという形で、先住民族を搾取する白人という図式からはずれている。無事に山を越え、宴を開いたあと、船は首狩り族によって艫綱を切られ、動き出し、避けなければならないはずのポンゴの瀬に突入する。ほとんど沈没寸前になりながらもどうにかポンゴの瀬を乗り切った後、首狩り族の目的が明らかになる。船の山越えというアイデアを思いつくフィツカラルドもすごいが、それを映画で「実際」にやってしまうヘルツォークの映画製作に対する常軌を逸した情熱もまたすごい。
この映画は準備から完成まで4年の歳月がかかり、撮影中のトラブルも枚挙に暇がないほどで、そうした撮影の裏話も映画になりうるほどのものだ。フィツカラルドの野心と執念はヘルツォークの映画へのそれと結びつき、同一化する。ラストで見せるクラウス・キンスキーの誇らしげな表情とクラウディア・カルディナーレの喜びに満ちた笑顔はあらゆる困難を乗り越えた映画の完成を祝福してもいるのだ。










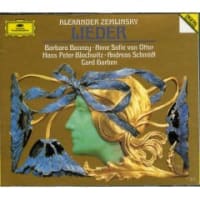
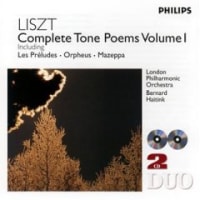
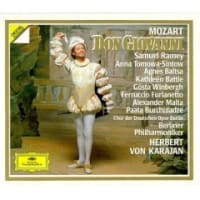
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます