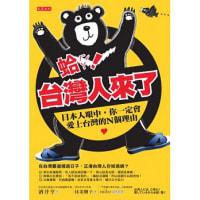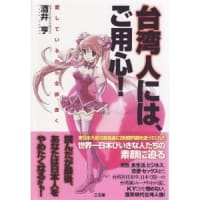7月に本放送が始まった台湾の原住民電視台(原住民テレビ)は、11月から原住民の各部族語によるニュース(族語新聞)を放送している。
最近、あまり台湾のニュース紹介として役にたたない<台湾の声ニュース>でも2005.11.16付けで「原住民テレビ:族語ニュース放送中」(URLは:http://www.emaga.com/bn/?2005110063468134002233.3407)として紹介された。
ただその後の発展もあって、「台湾の声」とはズレが出ているので、現状と意味についてここで紹介しておきたい。
まず、原住民電視台(原住民テレビ)には公式HPがある(http://www.ch16.com.tw/)。しかし、ここにはなぜか、番組表がアップされていない(かつてはあった)ので、番組表は次のサイトを参考のこと(番組検索サイト:http://www.hytv.com.tw/cgi/tvsearch.cgi)
12月下旬の時点では、部族語ニュースは次の時間に放送されている。
族語新聞
平日0600-0700(1時間版);0930-1000;1430-1500;1600-1630;1800-1830live;2230-2300;2430-0100;02:00-03:00(?)
土曜0600-0700(1時間版);0930-1000;1800-1830;2200-0100(の中の一部の枠)
日曜0600-0700(1時間版);0930-1000;1800-1830;2230-2300
午前6時からと午後6時から以外のは、重播(再放送)となっている。
同局は民進党政権の「多元文化政策」の沿って、客家人向けで客家語を使う客家テレビに次ぐ政府肝いりの少数エスニシティ尊重のテレビ局として、今年7月に正式開局した。だが、開局当初は番組のすべてが北京語で、部族語は挨拶言葉などを教える申し訳程度に限られていて、原住民当人から不満も出ていた。
客家テレビではニュースだけでなく、すべての番組が原則客家語となっていることを範をとって、10月から部族語のニュース放映を決定、11月からアミス語、タイヤル語、ブヌン語で始めた。この3言語が人口が多いからである。現在はさらにパイワン語、ルカイ語でも放送されている(プユマ語もあるとのことだが未見)。今後は現在原住民と認定されている12部族の部族語すべてによるニュース放映を目指すであろう。
私が見たところでは、言葉がわからないが、キャスター(主播)として上手だと思ったのは、ブヌン語の倫敦.伊斯瑪哈善(ロンドン・イスマハサン?)、次に上手なのはパイワン語の依棒.佳力克斯(イバン・カリクス?)で、ほかはあんまりうまくないという感じだった。
とくにブヌン語のロンドン氏は、一般の北京語ニュースキャスターと比べても遜色はない良いできである。ブヌン族の場合、一部のでは、部族会議でもブヌン語を堅持して、北京語をむしろ見下しているところもあるようで、それがこうした優秀な人材を生んだのかもしれない。母語流失が著しいと見られるタイヤル語の場合、苦しいだろう。人口が最も多く母語保存もそこそこのアミス語はもっとがんばるべきだと思う。
30分バージョンしか見ていないが、10-15分ごとに言語を交代して、同じ内容のものを放送する。下には中国語の字幕をつける。
原住民言語は、オーストロネシア語族なので、ニュースの響きを聞いていると、フィリピンでよく見たフィリピノ語ニュースを彷彿とさせるものがある。台湾にとって海峡両岸とは、バシー海峡の両岸なのだ。
面白いのは、よく知られているように、原住民言語には日本語の借用語が多い。とくに、何月何日、何時何分という言い方は日本語を使っていることだ。ただし8月8日は「ハチガツ・ヨウカ」ではなく、「ハチガツ・ハチニチ」と漢語音を使っているのが面白い。もっとも、台北は普通原住民語では「たいほく」が普通なのに、アミス語、タイヤル語、ブヌン語のニュースは北京語読みの「タイペイ」、ただパイワン語とルカイ語がちゃんと「たいほく」だった。
(日本語漢語読みといえば、原住民のに行くと、漢字語は戦後中華民国の制度であっても、日本語読みするのが広く行われているようで「郵政****制度」みたいなものを「ユウセイ****セイド」と若い人間も日本語読みしているのを聞いたことがあって、おどろいたことがある)
ちなみに原住民テレビは10月23日からは経営・制作権が国民党穏健派系の東森に移っていて、ニュースが国民党寄りになることが心配されたが、私が見ている限りではそうでもない。
ニュースだけでなく、ドキュメンタリー番組でも、部族語が使われ始めた。「探索蘭嶼」という番組では、パイワン語による放送が行われている。今後、こうした番組は増えていくだろうし、それを期待したい。
部族語放送ということについていえば、難題もある。
というのも、原住民として現在認定されているのは12部族があり、いずれも相互にまったく通じないほど違っているうえ、最大部族のアミスも人口が13万人で、小さなサオ族となれば、数百人しかいない。この中からニュースキャスターの人材を探すのは並大抵ではない。育成するにしても、これまで経験がないため、これからの課題となっている。
また、同じ「**語」といってもごとの方言差が大きく、方言どうしでは通じにくいものもある。ルカイ語やブヌン語はそうである。だから、「ルカイ語でニュースを放送しています」といっても、そのキャスター出身のは理解できても、ほかの人は理解できない。
そういう意味で、原住民言語の言語規範化は図れるのかも問題となる。
とはいえ、原住民諸語の場合、文字は長老教会が広めたローマ字が部族語、方言ごとにほぼ確立しているし、原住民はキリスト教徒も多く、程度差はあれローマ字ができるというのは、ホーロー語や客家語を母語とする平地「漢人」と比べての利点ではある。
ところで、話は変わるが、実は民族語も使って全国で見られる原住民のためのチャンネルというのは、世界で初めてのはずである。同様の試みは、すでにカナダやオーストラリアにはあるが、カナダの原住民テレビは「全国向け」といいつつケーブルチャンネルはカナダで普及していない地域も多いため実質全国ではないし、オーストラリアの場合は聞くところによると州レベルだという話である。
そういう意味では、台湾の試みは、実は世界で画期的で、最先端だといっても過言ではない。また、これは中道やや左のリベラル政党民進党が政権をとったからこそである。いかに国民党ではリベラルなほうの李登輝とはいえども、国民党時代だったら考えられなかった。いや、民進党が立派というよりは、それをシンボルとして支えて闘ってきた民主化運動、市民社会の意識が立派だったというべきだろう。
翻って日本を見てみよう。お寒い限りである。
テレビで多言語というのは、外国人移民向けに本国のチャンネルや番組を編集しなおしたものがスカパーに存在しているが、ただそれだけのことであり、移民を直接対象に番組を制作した専門局はない。
ラジオには、関西地方には震災後に在日外国人を対象としたミニFM局、市民団体と財界が共同でつくった一般FM局FMCocoloなどがあるが、これは全国ではない。関東のインターFMは同様の趣旨でできたはずだが、現在では洋楽・英語オタクの日本人向けになった。関西だけは細々とながらエスニック放送が存在できるというのは、関西の東京に対する優位というか良いところだというべきか(私は北陸出身ということで、東京よりは関西のほうに愛着がある)。
では、日本における少数エスニシティが集中している沖縄諸島、小笠原諸島、北海道はどうか。
沖縄ではラジオ沖縄が昼間に20分間だけの方言ニュースをやっている(今でもあるはず)が、これは古めかしい首里方言であって、本島でも理解不能な人が多い。
北海道にはアイヌ語のラジオ局も番組もないはずで、わずかに札幌テレビ放送ラジオが、1988年からアイヌ語講座を始め、現在はアイヌ文化振興法の支援もあって細々と続いているだけ。
80年代に読んだ話では、80年代にある人が北海道でアイヌ語を使う幼稚園を作ろうとしたら、官憲に禁止、閉鎖させられたという話もある。
小笠原にいたっては、ボニン語での放送はないはずである。
つまり、現実に多言語・多文化国家である日本は、少数エスニシティの保護という点ではお寒い状況だ。
参考:
http://www.emaga.com/bn/?2005110063468134002233.3407
<台湾の声ニュース> 2005.11.16
原住民テレビ:族語ニュース放送中
台湾原住民の文化振興のため今年7月に正式に放送開始した原住民テレビ(第16チャンネル)で、原住民族の母語によるニュース番組が11月8日から一時間番組に拡大されて放送されている。
原住民テレビは7月のスタート以来、原住民族語学習番組や一部のドキュメント番組は原住民の各族語で放送されていたが、ニュースは中国語で行なわれていた。
2003年に開局された客家テレビでは、24時間客家語放送を実現し、ニュースもすべて客家語で行なっている。原住民テレビの視聴者からは、客家テレビは客家の母語でニュースをやるのに、どうして原住民テレビは原住民の母語でできないのか、という声があがっていた。
客家テレビも方言の違いをどうするかという問題があったが、客家語ニュースでは、基本的に中文の字幕をつけ、時間帯やキャスターによって四県(Si- yen)方言や海陸(Hoi-liuk)方言を使いわけるという方式で放送をはじめた。結果、はじめは慣れなかったが見ているうちに双方の方言が聞き取れ るようになった、という効果も生まれている。
しかし、原住民テレビの場合は、それぞれ言葉が違う民族が政府認定だけで12族あり、視聴者の市場が250万~400万と言われる客家テレビよりさらに 小さく、族語別に聞き取れる視聴者となると10~100分の1になってしまう。民族別のキャスターの育成も大変な作業となる。
原住民テレビでは、まず比較的人口が多いアミ語、タイヤル語、ブヌン語から族語ニュースをはじめている。1時間の番組中、ほぼ同じ内容のニュースをアミ 語の時間、タイヤル語の時間、ブヌン語の時間に分けて繰り返して放送する。キャスターは民族衣装で登場し、原住民語でニュースを読む。ニュース内容は中文 の字幕をつけ、異なる部族や聞き取れない人にも配慮されている。
インターネット上の掲示板などではパイワン族からも族語ニュースをやってほしいという声が出ていて、各族語のバランスは今後の課題となるが、原住民語に よるテレビニュース番組は初めての試みであり、原住民の村では「母語の美しさに感動した」「聞き取れなくても原住民の声が伝わる」「政権交代による成果 だ」など新鮮に受け止められている。
原住民テレビ「族語新聞」
毎日
6:00~7:00(一時間版)
16:00~16:30(30分版)
22:30~23:00(30分版)
最近、あまり台湾のニュース紹介として役にたたない<台湾の声ニュース>でも2005.11.16付けで「原住民テレビ:族語ニュース放送中」(URLは:http://www.emaga.com/bn/?2005110063468134002233.3407)として紹介された。
ただその後の発展もあって、「台湾の声」とはズレが出ているので、現状と意味についてここで紹介しておきたい。
まず、原住民電視台(原住民テレビ)には公式HPがある(http://www.ch16.com.tw/)。しかし、ここにはなぜか、番組表がアップされていない(かつてはあった)ので、番組表は次のサイトを参考のこと(番組検索サイト:http://www.hytv.com.tw/cgi/tvsearch.cgi)
12月下旬の時点では、部族語ニュースは次の時間に放送されている。
族語新聞
平日0600-0700(1時間版);0930-1000;1430-1500;1600-1630;1800-1830live;2230-2300;2430-0100;02:00-03:00(?)
土曜0600-0700(1時間版);0930-1000;1800-1830;2200-0100(の中の一部の枠)
日曜0600-0700(1時間版);0930-1000;1800-1830;2230-2300
午前6時からと午後6時から以外のは、重播(再放送)となっている。
同局は民進党政権の「多元文化政策」の沿って、客家人向けで客家語を使う客家テレビに次ぐ政府肝いりの少数エスニシティ尊重のテレビ局として、今年7月に正式開局した。だが、開局当初は番組のすべてが北京語で、部族語は挨拶言葉などを教える申し訳程度に限られていて、原住民当人から不満も出ていた。
客家テレビではニュースだけでなく、すべての番組が原則客家語となっていることを範をとって、10月から部族語のニュース放映を決定、11月からアミス語、タイヤル語、ブヌン語で始めた。この3言語が人口が多いからである。現在はさらにパイワン語、ルカイ語でも放送されている(プユマ語もあるとのことだが未見)。今後は現在原住民と認定されている12部族の部族語すべてによるニュース放映を目指すであろう。
私が見たところでは、言葉がわからないが、キャスター(主播)として上手だと思ったのは、ブヌン語の倫敦.伊斯瑪哈善(ロンドン・イスマハサン?)、次に上手なのはパイワン語の依棒.佳力克斯(イバン・カリクス?)で、ほかはあんまりうまくないという感じだった。
とくにブヌン語のロンドン氏は、一般の北京語ニュースキャスターと比べても遜色はない良いできである。ブヌン族の場合、一部のでは、部族会議でもブヌン語を堅持して、北京語をむしろ見下しているところもあるようで、それがこうした優秀な人材を生んだのかもしれない。母語流失が著しいと見られるタイヤル語の場合、苦しいだろう。人口が最も多く母語保存もそこそこのアミス語はもっとがんばるべきだと思う。
30分バージョンしか見ていないが、10-15分ごとに言語を交代して、同じ内容のものを放送する。下には中国語の字幕をつける。
原住民言語は、オーストロネシア語族なので、ニュースの響きを聞いていると、フィリピンでよく見たフィリピノ語ニュースを彷彿とさせるものがある。台湾にとって海峡両岸とは、バシー海峡の両岸なのだ。
面白いのは、よく知られているように、原住民言語には日本語の借用語が多い。とくに、何月何日、何時何分という言い方は日本語を使っていることだ。ただし8月8日は「ハチガツ・ヨウカ」ではなく、「ハチガツ・ハチニチ」と漢語音を使っているのが面白い。もっとも、台北は普通原住民語では「たいほく」が普通なのに、アミス語、タイヤル語、ブヌン語のニュースは北京語読みの「タイペイ」、ただパイワン語とルカイ語がちゃんと「たいほく」だった。
(日本語漢語読みといえば、原住民のに行くと、漢字語は戦後中華民国の制度であっても、日本語読みするのが広く行われているようで「郵政****制度」みたいなものを「ユウセイ****セイド」と若い人間も日本語読みしているのを聞いたことがあって、おどろいたことがある)
ちなみに原住民テレビは10月23日からは経営・制作権が国民党穏健派系の東森に移っていて、ニュースが国民党寄りになることが心配されたが、私が見ている限りではそうでもない。
ニュースだけでなく、ドキュメンタリー番組でも、部族語が使われ始めた。「探索蘭嶼」という番組では、パイワン語による放送が行われている。今後、こうした番組は増えていくだろうし、それを期待したい。
部族語放送ということについていえば、難題もある。
というのも、原住民として現在認定されているのは12部族があり、いずれも相互にまったく通じないほど違っているうえ、最大部族のアミスも人口が13万人で、小さなサオ族となれば、数百人しかいない。この中からニュースキャスターの人材を探すのは並大抵ではない。育成するにしても、これまで経験がないため、これからの課題となっている。
また、同じ「**語」といってもごとの方言差が大きく、方言どうしでは通じにくいものもある。ルカイ語やブヌン語はそうである。だから、「ルカイ語でニュースを放送しています」といっても、そのキャスター出身のは理解できても、ほかの人は理解できない。
そういう意味で、原住民言語の言語規範化は図れるのかも問題となる。
とはいえ、原住民諸語の場合、文字は長老教会が広めたローマ字が部族語、方言ごとにほぼ確立しているし、原住民はキリスト教徒も多く、程度差はあれローマ字ができるというのは、ホーロー語や客家語を母語とする平地「漢人」と比べての利点ではある。
ところで、話は変わるが、実は民族語も使って全国で見られる原住民のためのチャンネルというのは、世界で初めてのはずである。同様の試みは、すでにカナダやオーストラリアにはあるが、カナダの原住民テレビは「全国向け」といいつつケーブルチャンネルはカナダで普及していない地域も多いため実質全国ではないし、オーストラリアの場合は聞くところによると州レベルだという話である。
そういう意味では、台湾の試みは、実は世界で画期的で、最先端だといっても過言ではない。また、これは中道やや左のリベラル政党民進党が政権をとったからこそである。いかに国民党ではリベラルなほうの李登輝とはいえども、国民党時代だったら考えられなかった。いや、民進党が立派というよりは、それをシンボルとして支えて闘ってきた民主化運動、市民社会の意識が立派だったというべきだろう。
翻って日本を見てみよう。お寒い限りである。
テレビで多言語というのは、外国人移民向けに本国のチャンネルや番組を編集しなおしたものがスカパーに存在しているが、ただそれだけのことであり、移民を直接対象に番組を制作した専門局はない。
ラジオには、関西地方には震災後に在日外国人を対象としたミニFM局、市民団体と財界が共同でつくった一般FM局FMCocoloなどがあるが、これは全国ではない。関東のインターFMは同様の趣旨でできたはずだが、現在では洋楽・英語オタクの日本人向けになった。関西だけは細々とながらエスニック放送が存在できるというのは、関西の東京に対する優位というか良いところだというべきか(私は北陸出身ということで、東京よりは関西のほうに愛着がある)。
では、日本における少数エスニシティが集中している沖縄諸島、小笠原諸島、北海道はどうか。
沖縄ではラジオ沖縄が昼間に20分間だけの方言ニュースをやっている(今でもあるはず)が、これは古めかしい首里方言であって、本島でも理解不能な人が多い。
北海道にはアイヌ語のラジオ局も番組もないはずで、わずかに札幌テレビ放送ラジオが、1988年からアイヌ語講座を始め、現在はアイヌ文化振興法の支援もあって細々と続いているだけ。
80年代に読んだ話では、80年代にある人が北海道でアイヌ語を使う幼稚園を作ろうとしたら、官憲に禁止、閉鎖させられたという話もある。
小笠原にいたっては、ボニン語での放送はないはずである。
つまり、現実に多言語・多文化国家である日本は、少数エスニシティの保護という点ではお寒い状況だ。
参考:
http://www.emaga.com/bn/?2005110063468134002233.3407
<台湾の声ニュース> 2005.11.16
原住民テレビ:族語ニュース放送中
台湾原住民の文化振興のため今年7月に正式に放送開始した原住民テレビ(第16チャンネル)で、原住民族の母語によるニュース番組が11月8日から一時間番組に拡大されて放送されている。
原住民テレビは7月のスタート以来、原住民族語学習番組や一部のドキュメント番組は原住民の各族語で放送されていたが、ニュースは中国語で行なわれていた。
2003年に開局された客家テレビでは、24時間客家語放送を実現し、ニュースもすべて客家語で行なっている。原住民テレビの視聴者からは、客家テレビは客家の母語でニュースをやるのに、どうして原住民テレビは原住民の母語でできないのか、という声があがっていた。
客家テレビも方言の違いをどうするかという問題があったが、客家語ニュースでは、基本的に中文の字幕をつけ、時間帯やキャスターによって四県(Si- yen)方言や海陸(Hoi-liuk)方言を使いわけるという方式で放送をはじめた。結果、はじめは慣れなかったが見ているうちに双方の方言が聞き取れ るようになった、という効果も生まれている。
しかし、原住民テレビの場合は、それぞれ言葉が違う民族が政府認定だけで12族あり、視聴者の市場が250万~400万と言われる客家テレビよりさらに 小さく、族語別に聞き取れる視聴者となると10~100分の1になってしまう。民族別のキャスターの育成も大変な作業となる。
原住民テレビでは、まず比較的人口が多いアミ語、タイヤル語、ブヌン語から族語ニュースをはじめている。1時間の番組中、ほぼ同じ内容のニュースをアミ 語の時間、タイヤル語の時間、ブヌン語の時間に分けて繰り返して放送する。キャスターは民族衣装で登場し、原住民語でニュースを読む。ニュース内容は中文 の字幕をつけ、異なる部族や聞き取れない人にも配慮されている。
インターネット上の掲示板などではパイワン族からも族語ニュースをやってほしいという声が出ていて、各族語のバランスは今後の課題となるが、原住民語に よるテレビニュース番組は初めての試みであり、原住民の村では「母語の美しさに感動した」「聞き取れなくても原住民の声が伝わる」「政権交代による成果 だ」など新鮮に受け止められている。
原住民テレビ「族語新聞」
毎日
6:00~7:00(一時間版)
16:00~16:30(30分版)
22:30~23:00(30分版)