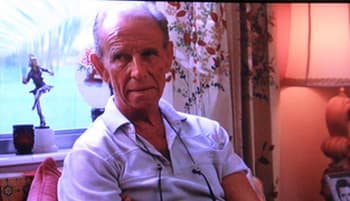●「アンブレイカブル」(「Unbreakbale」)
2000年
監督 M・ナイト・シャマラン(M. Night Shyamalan)
『シックス センス』(「The Sixth Sense」)『サイン』(「Signs」)『ハプニング』(「The Happenning」)と、正直どれも肩透かしを食らった感じのつまらなさを感じたこの監督の映画の中で、本作はサミュエル・L・ジャクソン(Samuel・ L ・Jackson)が良かったという記憶があった作品。


(列車の乗客の一人というチョイ役。期待させる出方でしたが、他の登場人物同様にほとんど意味を持たされていません。レズリー・ステファンソン。Leslie Stefanson)


(冒頭のこの列車内でのシーン、座席の隙間から人物を映すというアングルが続く、心憎いのですけれど・・・・・撮影を担当したエドゥアルド・セラのセンスでしょうか)
この監督作品の中でブルース・ウィリス(Bruce Willis) 主演でストーリー展開が良かったのは『シックス・センス』かなと。本作もラストのどんでん返しというストーリー展開は『シックス・センス』同じで、既視感さえ抱いたほどで、カメラワークはどきりとするほど面白いシーンがあったのに、内容的には正直イマイチなのが残念です。

(ブルース・ウィリスが演じるのは、ダンと言う男ですが、以下、ブルース名でご紹介します)
大惨事となった列車の脱線事故で唯一の生存者で、しかも無傷の主人公。これってホントにホラー映画なのかと思うのは、こうした役にタフガイのイメージのブルース・ウィリスを起用していることで、ちょっと笑えるシーンが本作ではてんこ盛りです。

唯一の生存者であるということ、しかも無傷であるということは、何らかの精神的な外傷を生むものなのか。家庭内別居の妻との暮らしで問題を抱えている中年男性ながら、奇跡ともいえる事が自分の身に起こったことに彼は釈然としないものを感じて悩み始めます。なぜなら、彼には病気になった記憶がないからです。
そんなとき、彼の心を読んでいるかのような手紙がきて、
ブルース・ウィリスは男に会いに行くのですが・・・・
その男がサミュエル・L・ジャクソン扮するイライジャ・プライスという男ですが、以下本部ログでは俳優名でご紹介していきます。

コミックを子供向けと思っている客を許さず、登場人物の原画を芸術だと語るサミュエル・ジャクソンの凄みは、現在よりもこの頃がなかなかです。

(彼のこの子供時代の映像にはぞくっとします。撮影のエドゥアルド・セラのセンスには感心。子供時代の母親役はシャーリー・ウッダード)

(この漫画、後でまた出てきます)
骨の形成不全という難病の子供を持った母親が、家の中に引きこもってしまわないように外に出す工夫として与えた漫画。子供はやがてこの漫画の世界と現実の世界が実は繋がっているのだという哲学を持つ大人に成長していくわけですが、

漫画オタクを超えたコミック信仰者となったサミュエル・ジャクソンのこのヘアースタイルのアンバランスさ、考えさせられちゃいます。

コミックに描かれていることは誰かが体験した真実であり、コミックには人間の歴史が書かれていると語る。ブルース・ウィリスが朝、目覚めたときに感じる空しさや悲しさの感情は、本当に自分がすべきことをしていないからだと。自分が何者かを知らないのだと語る様子は、まるでカウンセラーのようですが、

(ここ、笑ってしまいました。やっぱりホラーサスペンスじゃないですよね、この映画)
正義のヒーローとなるべき人間は、乗客全員が死亡するような飛行機の墜落事故でも死なず、全員が死亡するようなホテルが全焼した火災でも生き残り、乗客全員が死亡した列車の脱線事故のような大惨事になった自己でも一人生き残るのだ。本人が無自覚なこともある。それがお前だと審判者のように語られても困りますよね。

けれど、彼の言葉はご宣託のようにブルース・ウィリス父子の心に入り込んでいきます。
強い父親に憧れる息子と自分の道が見えないでいる中年男の心にこうしたご宣託が入り込むのは分からないではないですが、そこが怖いといえば怖いけれど、それでホラーサスペンスになるなら世話はない。
体を鍛えなおそうかと思って始めた重量挙げが、
何とオリンピック選手も青ざめるような記録!

それでもまだ半信半疑・・・・心の空虚さを埋めるのは簡単ではないところ、まだ理性があるわけですが、戸惑い続けるブルース。
そんな優柔不断に思える父親の姿に業を煮やした息子は、

(「パパは不死身なんだ。だから銃で撃っても死なない」と叫ぶシーン)
ここで思わずオーム真理教の信者たちのことを思い出してしまいました。尊師は解脱したゆえに浮遊できると信じ、命じられるままに相手の今生の人生を終わらせてやることが功徳だと信じ多くの人たちを殺害した信者たち・・・・彼らとそっくり。
かつてフットボールのスター選手だったブルース・ウィリスは、若いときの交通事故を契機にフットボールを断念し恋人と結婚したという過去を持っていたのですが、彼には触れた人間が抱いているイメージを映像として読み取ってしまう能力があった。恋人が彼にフットボールを止めて欲しいと願っていることを読み取ってしまったせいで、その道を断念したのでしょう。
何だかホームドラマのノリですが・・・・再起不能という嘘でその後の人生を送ってきたブルースに、サミュエル・ジャクソンは、その能力を正義のヒーローとして使えと諭します。こうなると、ホームドラマとオカルトサスペンスの競合です。

ミスター・ガラスと称されるほど体が脆い男と大事故に遭っても無傷でいられる男・・・・
サミュエル・ジャクソンは、ブルース・ウィリスの能力を確かめるべく行動し全身ほぼ骨折状態となって病院に運ばれますが、体の痛みよりも確信できた喜びの方が大きい。あいつは、ヒーローとなるべき男だと。
そして、そこのリハビリで彼の妻ロビン・ライト・ペン(Robin Wright Penn )と遭遇。こうなると、たとえ偶然でも運命を感じるものなのでしょう。俺とあいつは繋がっているのだと確信するわけです。

(「あんたが、彼からフットボールを奪った女か」という台詞、いかにブルースにめり込み過ぎかを物語っています)

(意味不明の言葉に、???となりながら、なぜフットボールが嫌いかを語り始めまる妻)
ミスターガラスとタフガイは一本の線の両極なのだと言うサミュエル・ジャクソンの哲学に示唆されて、
とうとうブルース・ウィリスは、

タフガイに変貌します。弱点は水だという言葉、いかに子供の頃にプールでおぼれかけたからと言って、二人の共通の弱点だということにどんな意味があるのかイマイチ不明ですが、
その雨の日に悪を懲らしめ弱きを助けるヒーローになるべく出かけるブルース。

一般人でありながら、そんなことしちゃっていいのかなァ・・・・
という突っ込みはなしにして、
翌日の新聞では雨合羽姿のヒーローが。

ヒーローとなった父親に驚愕する息子。
スペンサー・トリート・クラーク(Spenser Treat Clark)という子役ですが、どこかで見た顔だと思ったら、スリラー向けの子役なのか、『隣人は静かに笑う』というスリラーにも出ていた子役です。
かくして、朝に悲しい気分を味わうこともなくなって、いまや「友人」として彼のパーティに出向くブルース。

ここでの母親の台詞が意味深です。
そして、
ラストのどんでん返し(と製作者側が意図している)・・・・

(このときのサミュエル・L・ジャクソンの表情は、必見ですね)
ということで、
これをサスペンスホラー映画とは、とても言えないわけです。
本作では力が抜けるほど全然良くないブルース・ウィリスに代わって、今回見てもサミュエル・L・ジャクソンが一人存在感を示していたように思えました。
52歳にもなった男(本作でサミュエル・L・ジャクソンは52歳)が、漫画のヒーローの存在をあんなふうに哲学したら、もう完全にイッチャッテルことになるけれど、そういう風に感じさせないでラストのどんでん返し(製作者側にとっては、どんでん返しのつもり・・・)まで引っ張っていく存在感は、サミュエル・L・ジャクソンくらいかも。
それにしても、ブルース・ウィリスとの俳優としての個性での相性がいいとはとても思えないのに、この二人、『パルプ・フィクション』(「Pulp Fiction 」)『ダイ・ハード3』(「Die Hard: With a Vengeance」)に引き続いての共演。そんなところに一人勝手に感心しながら観ちゃいましたが、精神疾患というのを落ちにしていいのだろうかとイマイチ、「そんなこと、途中で分かるだろうに」と、その手軽さにはやはり不満が残りました。