前回"絶唱"を読んであまり感じるところのなかった私、
今度は受賞という意味では彼女のキャリアハイと思われる作品を読んでみる。
第一印象、かなり面白く読めた。
あらすじは。。。ある中学校で、シングルマザーで働く教師の娘が
クラスの生徒の悪意に遭って殺されてしまう。
それを知った教師が、間接的に実行犯に復讐を働く、といったところ。
超シンプル。登場人物も5人+モブという程度で読むのが楽。
殺人を犯した側にも復讐する側にもそれぞれに理由があり思惑は理解できるように描かれているが、そのいずれも独りよがりな考え。
代表的なものは、娘殺人の実行犯Aの"愛する母親と離婚して会えなくなってしまって辛い。母から授かった電子工学の技術を使って殺人でもなんでもして社会で大々的に取り上げられ、自分の存在を知ってもらい、あわよくば戻ってきてもらう"というもの。
なので、いやーなんかヤバいっすね、俺に関係ないけどと思いながら
独りよがりの応酬を野次馬のように眺めてました、という読後感であった。
世間では"イヤミス"と言われているらしいが…そんなカテゴリができるほど
この手の作品はたくさん描かれているのか?
この作品の主題とは思わないが、めいめいが真意を見せないまま行動しているため
会話が全く噛み合わないまま交わることもないコミュニケーションとなっている。
(おそらくは各々の中にやりたいことがあるほど、)こうも人は理解し合えないのかということを感じさせた。
おそらくキャラクタの描写という点で成功を収めた小説になると思う。
本小説は6部構成になっていて宗教観のあるタイトルとなっているが、
各章は各登場人物のモノローグになっていて、のべ6人のモノローグを聞くことになる。
聖職者:娘を殺された教師
殉教者:教師のクラスの女子生徒
慈愛者:娘を殺した実行犯Bの母親
求道者:実行犯B
信奉者:実行犯A
伝道者:娘を殺された教師 実行犯Aへの餞の言葉
何かになぞらえているのかも知れないが、西洋宗教の知見がなく、これの考察は必要以上に時間がかかりそうなので省く。
フィクションながら、どの人物も自律的に動いている感じが読み取れ、
キャラクタの掘り下げが良くできていると思える。
ただ、教師(主人公)のキャラクタは丁寧語で説明さえすればどんなエグい復讐をしても良いと肚を決めたキャラ付けになっており、強い言葉が多く、刺激的。
他の人物が比較的現実的なところに収まっていたのに比べると、爆弾をみつけて他の人にバレないように別の場所に設置するなど、全知全能のようなチートキャラ感があり、読んでいて面白いものの現実感には乏しかった。
リアリティの考察とかせずにエンタメに徹して読むのが吉。










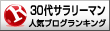

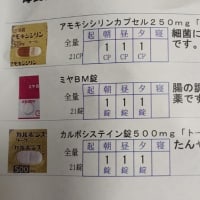
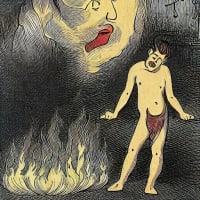


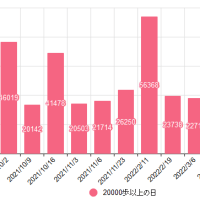
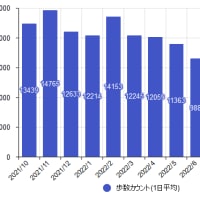
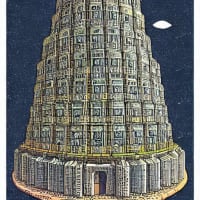
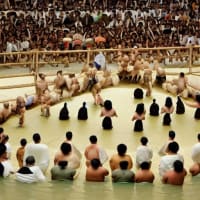
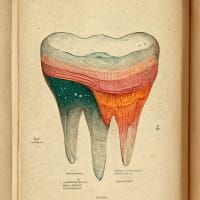






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます