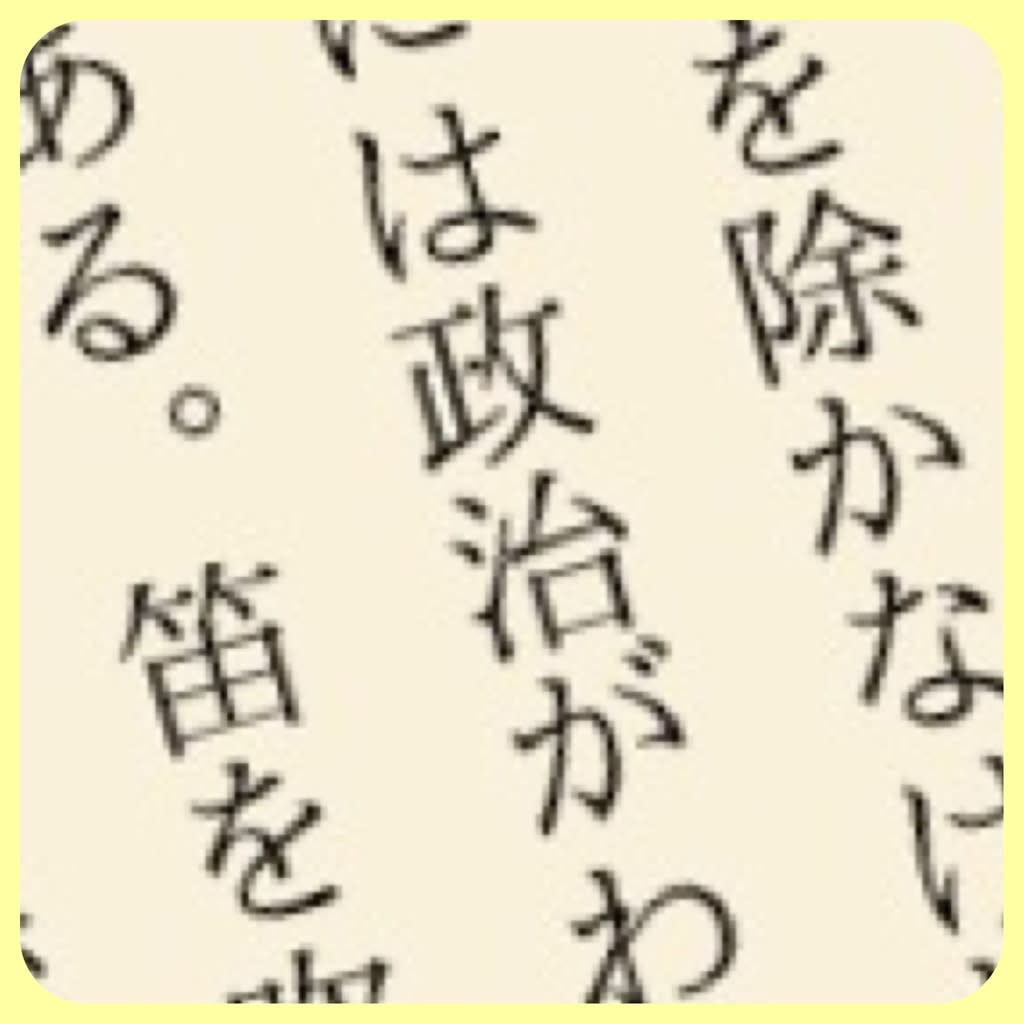わたしの下の娘が小学校6年生のときでした。
2008年の頃でした。
小学校の個人懇談会に行くと、担任の先生から言われました。
「お父さん、家でもっとお子さんの勉強をみてあげないと、中学校にいったら授業で『お客さん』になりますよ」。
お客さんとは、授業に招かれるだけで、自分から進んで学習するのではなく、授業が理解できなくても、ただ授業の話を聞くだけの、勉強のできない受け身の子どもという意味です。
私は、その言葉を聞いて驚きました。「お客さん」の意味は、聞くと直感でその意味あいを理解しました。
その若い学級担任は、私が中学校に勤める現役の中堅教員だとは知らなかったようでした。
わたしには、そもそも子ども学校の勉強は学校が責任をもち学力向上を担うものという考えがありました。
だから、その当時学力不振の子を放課後に学習会に残して、補習をしたりして、高校進学の力添えをしていました。
家庭でも子どもの学習はみますが、それはあくまで補助的なものであり、学校での子どもの学習は学校が第一の責任を持つべきと考えていましたし、今もそう考えています。
だから、教職経験の浅い教員からそう言われたことは、少なからずショッキングなことでした。
その教員は、何のために教職に就いているのか、自分の役割とは何かを自覚しなければならないでしょう。
その経験からくる思いと結びついたのが、最近の新聞記事でした。
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
長女が中学3年だった8年前、中学校で本人、保護者、担任の先生との進路に関する三者面談があった。
その際の先生の一言を今でも時々思い出す。「塾に行かなくても大丈夫ですか」。塾に通わず大学まで進学した私は、子どもを塾に通わすという発想、選択肢がなかった。
「学校の先生が通塾を勧める時代になったのだなあ」と思うと同時に、「子どもの学力向上を学校教育だけに頼るな」と言われているようにも感じた。
あの時、「学校は、これからどんどん空洞化していくのかもしれない」とぼんやり考えていたのを覚えている。
今、中学校の部活動は、学校から地域へと本格的に移行されようとしている。
塾で本格的な勉強をし、地域で部活動をするようになった時、果たして学校に何が残るのだろうか。
学校は誰のために、何のために存在しているのか。
最近、私にはよく分からなくなっている。
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
この記事は、長崎県の50歳代の女性が投稿されたものです。
子どもの学力保障は学校が担うべきものです。
中学生は、授業がわかりたい、仲間とともに過ごし、部活でうまくなりたい。
その切なる願いで、毎日学校へやってくるのです。
子どもの願いに応えるのが、公立学校の使命です。
それ以上でも、それ以下でもないのです。
今一度、学校のシンプルな役割を見直したほうがいいとわたしは考えます。