≪書道の歴史概観 その9≫
(2021年2月14日投稿)
【石川九楊『中国書史』はこちらから】


中国書史
今回のブログでは、元代から清代の書について解説する。
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
約90年間の元代は、書道の上では反省の時代と捉えられている。すなわち宋人が自由と個性とを尊重して粗放になったのは、古法を軽んじたからだという事実を認めるにいたり、晋唐の温雅整斉な書風が流行した。しかし、独創力にとぼしく、しかも規格は唐宋にも及ばず、「意余って筆足まらず」の時代ともいえる。
趙孟頫(ちょうもうふ、趙子昴1254-1322)は、その「行書千字文」がすぐれているとされる。王羲之を専心学んだ人の書だけにその形意を得ている。しかし、格調はそれほど高くないと評されるが、筆がよく暢達(ちょうだつ)して、特に形も整っているから実用書の手本として、この「行書千字文」はよいものとされる。趙子昴は、宋の太祖十一世の孫、孝宗の兄の五世の孫にあたる貴族である。しかし、宋元二朝の臣となったので、節義上から日本人には特に評判が悪く、藤田東湖は彼の書を手本とする時、机上におかなかったという。
ただし、明清の書家の多くは、趙子昴の追随者であるといわれる。
(鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会、1996年[2010年版]、72頁~73頁。伏見冲敬『書の歴史 中国篇』二玄社、1960年[2003年版]、158頁)
【鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会はこちらから】


新説和漢書道史
【伏見冲敬『書の歴史 中国篇』二玄社はこちらから】


書の歴史 中国篇
東京国立博物館には、趙子昴の「蘭亭十三跋(らんていじゅうさんばつ)」がある。本帖について、次のようなことが伝えられている。
王羲之から10世紀を隔てた至大3年(1310)の9月、趙子昴は、皇太子(後の仁宗)のお召しにより、夫人を同伴して郷里の呉興(浙江省)から大都(北京)へと月余の旅に出発した。
その途次、独孤(どっこ)僧から「定武蘭亭帖」の佳本をゆずりうけた。そのすばらしさにうたれ、喜びのあまり、趙子昴は日々蓬窓の下にひろげ、9月5日から10月7日までの30余日の間に13回の跋を重ねた。これが世に喧伝されている「蘭亭十三跋」のゆえんである。その第十一跋の後に「蘭亭序」の全文を臨書しているが、その一部分が東京国立博物館にある。本帖は、清の乾隆年間に譚組綬(たんそじゅ)が愛蔵していたが、彼の没後火災にあい、譚の門人英和が断片を集めて帖装をほどこした。
趙子昴は、王羲之の書の正統をまもろうとした元朝第一の能筆で、その書は遒麗(しゅうれい)な美と整粛な気分とを備え、後世に大きな影響を及ぼした。
(上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館、1970年[1971年版]、4頁)
【上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館はこちらから】


現代書道全書 第2巻 改訂新版 行書・草書
元代後半期の書の世界には、放縦な主観主義と元の趙子昴風の典雅な格調美とがはげしく対立していた。その対立を総合統一したのが、明代初期の傾向であった。この傾向は鮮烈な精神性を失う結果となったが、明代の書の方向を一応決定し、文徴明(1470-1559)の書は、その頂点を示している。姿はあくまで理知的な端正さを保ち、平明さに終始しており、したがって観念的・散文的という無感動を露呈することになると堀江は評している。この文徴明の様式は、日本の江戸時代の唐様の世界に、追随者を生んだ
(堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版、1991年、134頁~135頁)
【堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版はこちらから】


中国風の書―日本の名筆・その歴史と美と鑑賞法 (名筆鑑賞入門)
英主康熙帝は、清朝300年の基礎を築き、在位は1661~1722年で、中国歴代皇帝で最も長く在位した。中国歴代皇帝の中で大帝という呼称を与えうるとしたら、漢の武帝、唐の太宗、そして清朝の康熙帝であろうといわれる。漢字の字書として、あの『康熙字典』(1716年刊)を編纂したことはよく知られている。『説文解字』『字彙』『正字通』など歴代の字書を集大成したもので、4万7000余の漢字を楷書の部首画数順に配列し、字音・字義・用例を示し、以後の字書の範となった。
康熙帝の書としては、「行書避暑詩軸」などが残っている。書の場合は、とくに明代の董其昌が好きであった。董其昌は、明代の万暦末に華亭派の頭領として一世を風靡し、頭脳明晰の代表者でもあった。その董其昌の字を、皇帝中の知性派の筆頭のような康熙帝は好んだ。
元来、董其昌の書は、その基礎を王羲之の書に求めたといわれる。つまり董其昌の書を掘り下げていくと、結局は王羲之の書に辿りつくというのである。だから、康熙帝の「行書避暑詩軸」という書も、王羲之風の書である。逆にいえば、王羲之書法に果敢な挑戦を試みた金石書法―すなわち碑学派といわれる人々も出現したが、一般に清朝の書は、温雅と典麗を求める書の風靡から新しい仕事のできる書家は現れず、結果として董其昌を越えるほどの書の生まれなかった時代であったともいわれる。
(青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社、1982年、113頁~121頁。榊莫山『書の歴史―中国と日本―』創元社、1970年[1995年版]、94頁)
【青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社はこちらから】


書の実相―中国書道史話
【榊莫山『書の歴史―中国と日本―』創元社はこちらから】


書の歴史―中国と日本 (1970年)
(2021年2月14日投稿)
【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史
【はじめに】
今回のブログでは、元代から清代の書について解説する。
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・元代の書について
・元代から明代へ
・清朝の康熙帝の書について
元代の書について
約90年間の元代は、書道の上では反省の時代と捉えられている。すなわち宋人が自由と個性とを尊重して粗放になったのは、古法を軽んじたからだという事実を認めるにいたり、晋唐の温雅整斉な書風が流行した。しかし、独創力にとぼしく、しかも規格は唐宋にも及ばず、「意余って筆足まらず」の時代ともいえる。
趙孟頫(ちょうもうふ、趙子昴1254-1322)は、その「行書千字文」がすぐれているとされる。王羲之を専心学んだ人の書だけにその形意を得ている。しかし、格調はそれほど高くないと評されるが、筆がよく暢達(ちょうだつ)して、特に形も整っているから実用書の手本として、この「行書千字文」はよいものとされる。趙子昴は、宋の太祖十一世の孫、孝宗の兄の五世の孫にあたる貴族である。しかし、宋元二朝の臣となったので、節義上から日本人には特に評判が悪く、藤田東湖は彼の書を手本とする時、机上におかなかったという。
ただし、明清の書家の多くは、趙子昴の追随者であるといわれる。
(鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会、1996年[2010年版]、72頁~73頁。伏見冲敬『書の歴史 中国篇』二玄社、1960年[2003年版]、158頁)
【鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会はこちらから】

新説和漢書道史
【伏見冲敬『書の歴史 中国篇』二玄社はこちらから】

書の歴史 中国篇
東京国立博物館には、趙子昴の「蘭亭十三跋(らんていじゅうさんばつ)」がある。本帖について、次のようなことが伝えられている。
王羲之から10世紀を隔てた至大3年(1310)の9月、趙子昴は、皇太子(後の仁宗)のお召しにより、夫人を同伴して郷里の呉興(浙江省)から大都(北京)へと月余の旅に出発した。
その途次、独孤(どっこ)僧から「定武蘭亭帖」の佳本をゆずりうけた。そのすばらしさにうたれ、喜びのあまり、趙子昴は日々蓬窓の下にひろげ、9月5日から10月7日までの30余日の間に13回の跋を重ねた。これが世に喧伝されている「蘭亭十三跋」のゆえんである。その第十一跋の後に「蘭亭序」の全文を臨書しているが、その一部分が東京国立博物館にある。本帖は、清の乾隆年間に譚組綬(たんそじゅ)が愛蔵していたが、彼の没後火災にあい、譚の門人英和が断片を集めて帖装をほどこした。
趙子昴は、王羲之の書の正統をまもろうとした元朝第一の能筆で、その書は遒麗(しゅうれい)な美と整粛な気分とを備え、後世に大きな影響を及ぼした。
(上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館、1970年[1971年版]、4頁)
【上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館はこちらから】

現代書道全書 第2巻 改訂新版 行書・草書
元代から明代へ
元代後半期の書の世界には、放縦な主観主義と元の趙子昴風の典雅な格調美とがはげしく対立していた。その対立を総合統一したのが、明代初期の傾向であった。この傾向は鮮烈な精神性を失う結果となったが、明代の書の方向を一応決定し、文徴明(1470-1559)の書は、その頂点を示している。姿はあくまで理知的な端正さを保ち、平明さに終始しており、したがって観念的・散文的という無感動を露呈することになると堀江は評している。この文徴明の様式は、日本の江戸時代の唐様の世界に、追随者を生んだ
(堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版、1991年、134頁~135頁)
【堀江知彦『名筆鑑賞入門 中国風の書―日本の名筆・その歴史と美の鑑賞法』知道出版はこちらから】

中国風の書―日本の名筆・その歴史と美と鑑賞法 (名筆鑑賞入門)
清朝の康熙帝の書について
英主康熙帝は、清朝300年の基礎を築き、在位は1661~1722年で、中国歴代皇帝で最も長く在位した。中国歴代皇帝の中で大帝という呼称を与えうるとしたら、漢の武帝、唐の太宗、そして清朝の康熙帝であろうといわれる。漢字の字書として、あの『康熙字典』(1716年刊)を編纂したことはよく知られている。『説文解字』『字彙』『正字通』など歴代の字書を集大成したもので、4万7000余の漢字を楷書の部首画数順に配列し、字音・字義・用例を示し、以後の字書の範となった。
康熙帝の書としては、「行書避暑詩軸」などが残っている。書の場合は、とくに明代の董其昌が好きであった。董其昌は、明代の万暦末に華亭派の頭領として一世を風靡し、頭脳明晰の代表者でもあった。その董其昌の字を、皇帝中の知性派の筆頭のような康熙帝は好んだ。
元来、董其昌の書は、その基礎を王羲之の書に求めたといわれる。つまり董其昌の書を掘り下げていくと、結局は王羲之の書に辿りつくというのである。だから、康熙帝の「行書避暑詩軸」という書も、王羲之風の書である。逆にいえば、王羲之書法に果敢な挑戦を試みた金石書法―すなわち碑学派といわれる人々も出現したが、一般に清朝の書は、温雅と典麗を求める書の風靡から新しい仕事のできる書家は現れず、結果として董其昌を越えるほどの書の生まれなかった時代であったともいわれる。
(青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社、1982年、113頁~121頁。榊莫山『書の歴史―中国と日本―』創元社、1970年[1995年版]、94頁)
【青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社はこちらから】

書の実相―中国書道史話
【榊莫山『書の歴史―中国と日本―』創元社はこちらから】

書の歴史―中国と日本 (1970年)












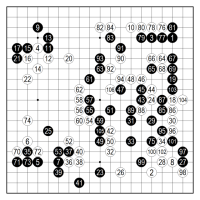
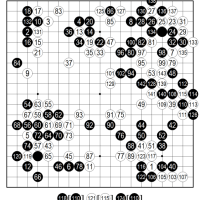
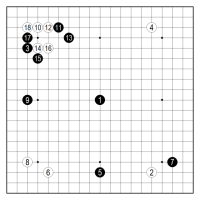
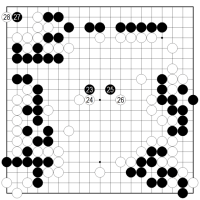
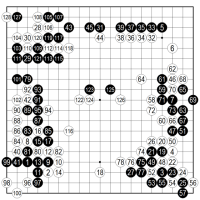
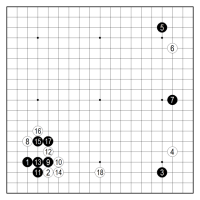
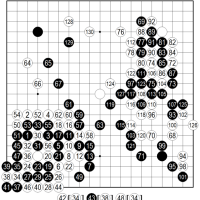
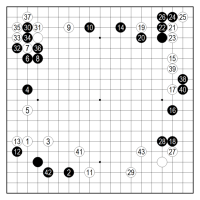
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます