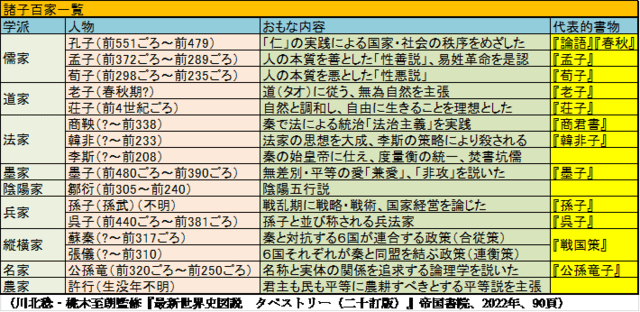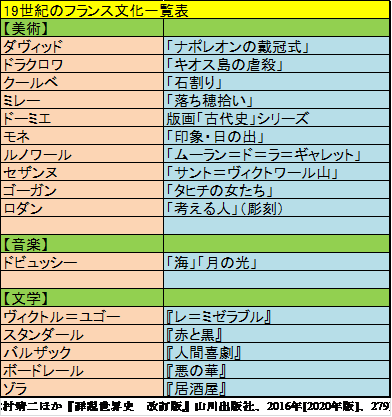(2023年9月3日投稿)
【はじめに】
今回のブログでは、高校世界史において、中国文化史(宋代から清代まで)について、どのように記述されているかについて、考えてみたい。
参考とした世界史の教科書は、次のものである。
〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]
〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]
また、前者の高校世界史教科書に準じた英文についても、見ておきたい。
〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]
【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】
本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社
〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]
【目次】
本村凌二『英語で読む高校世界史』
Contents
Introduction to World History
1 Natural Environments: the Stage for World History
2 Position of Japan in East Asia
3 Disease and Epidemic
Part 1 Various Regional Worlds
Prologue
The Humans before Civilization
1 Appearance of the Human Race
2 Formation of Regional Culture
Chapter 1
The Ancient Near East (Orient) and the Eastern Mediterranean World
1 Formation of the Oriental World
2 Deployment of the Oriental World
3 Greek World
4 Hellenistic World
Chapter 2
The Mediterranean World and the West Asia
1 From the City State to the Global Empire
2 Prosperity of the Roman Empire
3 Society of the Late Antiquity and Breaking up
of the Mediterranean World
4 The Mediterranean World and West Asia
World in the 2nd century
Chapter 3
The South Asian World
1 Expansion of the North Indian World
2 Establishment of the Hindu World
Chapter 4
The East Asian World
1 Civilization Growth in East Asia
2 Birth of Chinese Empire
3 World Empire in the East
Chapter 5
Inland Eurasian World
1 Rises and Falls of Horse-riding Nomadic Nations
2 Assimilation of the Steppes into Turkey and Islam
Chapter 6
1 Formation of the Sea Road and Southeast Asia
2 Reorganizaion of Southeast Asian Countries
Chapter 7
The Ancient American World
Part 2 Interconnecting Regional Worlds
Chapter 8
Formation of the Islamic World
1 Establishment of the Islamic World
2 Development of the Islamic World
3 Islamic Civilization
World in the 8th century
Chapter 9
Establishment of European Society
1 The Eastern European World
2 The Middle Ages of the Western Europe
3 Feudal Society and Cities
4 The Catholic Church and the Crusades
5 Culture of Medieval Europe
6 The Middle Ages in Crisis
7 The Renaissance
Chapter 10
Transformation of East Asia and the Mongol Empire
1 East Asia after the Collapse of the Tang Dynasty
2 New Developments during the Song Era ―Advent of Urban Age
3 The Mongolian Empire Ruling over the Eurasian Continent
4 Establishment of the Yuan Dynasty
Part 3 Unification of the World
Chapter 11
Development of the Maritime World
1 Formation of the Three Maritime Worlds
2 Expansion of the Maritime World
3 Connection of Sea and Land; Development of Southeast Asia World
Chapter 12
Prosperity of Empires in the Eurasian Continent
1 Prosperity of Iran and Central Asia
2 The Ottoman Empire; A Strong Power Surrounding
the East Mediterranean
3 The Mughal Empire; Big Power in India
4 The Ming Dynasty and the East Asian World
5 Qing and the World of East Asia
Chapter 13
The Age of Commerce
1 Emergence of Maritime Empire
2 World in the Age of Commerce
World in the 17th century
Chapter 14
Modern Europe
1 Formation of Sovereign States and Religious Reformation
2 Prosperity of the Dutch Republic
and the Up-and-Coming England and France
3 Europe in the 18th Century and the Enlightened Absolute Monarchy
4 Society and Culture in the Early Modern Europe
Chapter 15
Industrialization in the West and the Formation of Nation States
1 Intensified Struggle for Economic Supremacy
2 Industrialization and Social Problems
3 Independence of the United States and Latin American Countries
4 French Revolution and the Vienna System
5 Dream of Social Change; Waves of New Revolutions
Part 4 Unifying and Transforming the World
Chapter 16
Development of Industrial Capitalism and Imperialism
1 Reorganization of the Order in the Western World
2 Economic Development of Europe
and the United States and Changes in Society and Culture
3 Imperialism and World Order
World in the latter half of 19th century
Chapter 17
Reformation in Various Regions in Asia
1 Reform Movements in West Asia
2 Colonization of South Asia and Southeast Asia,
and the Dawn of National Movements
3 Instability of the Qing Dynasty and Alteration of East Asia
Chapter 18
The Age of the World Wars
1 World War I
2 The Versailles System and Reorganization of International Order
3 Europe and the United States after the War
4 Movement of Nation Building in Asia and Africa
5 The Great Depression and Intensifying International Conflicts
6 World War II
Part 5 Establishment of the Global World
Chapter 19
Nation-State System and the Cold War
1 Hegemony of the United States and the Development of the Cold War
2 Independence of the Asian-African Countries and the "Third World"
3 Disturbance of the Postwar Regime
4 Multi-polarization of the World and the Collapse of the U.S.S.R.
Final Chapter
Globalization of Economy and New Regional Order
1 Globalization of Economy and Regional Integration
2 Questions about Globalization and New World Order
3 Life in the 21st Century; Time of Global Issues
The Rises and Falls of Main Nations
Index(English)
Index(Japanese)
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・中国文化史(宋代から)の記述~『世界史B』(東京書籍)より
・中国文化史(宋代から)の記述~『詳説世界史』(山川出版社)より
・英文の記述~本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』(講談社)より
中国文化史(宋代から)の記述~『世界史B』(東京書籍)より
〇宋代の文化
儒学では、万物生成の理法や人間の本性を論理的に追究する宋学が、北宋の周敦頤(1017~73)らによっておこされた。南宗の朱熹(朱子、1130~1200)は、宋学を大成し(朱子学)、君臣上下の秩序を絶対視する大義名分論を唱え、儒学の経典として四書(『大学』『中庸』『論語』『孟子』)を重視した。また、朱子はきびしい国際情勢に対応して、周辺諸民族に対する中華帝国の優位論を展開した。朱子学は、その後、儒学の正統とされ、日本や朝鮮半島、またベトナムにも伝えられ、官学として繁栄した。客観的な事物の理を追究する朱子に対して、陸九淵(陸象山、1139~92)は心(主体性)の確立を主張し、実践を重視するその思想は、のちの陽明学に影響を与えた。北宋の司馬光(1019~86)は、歴史のうえから大義名分を説き、編年体の通史『資治通鑑』を編纂した。仏教では、禅宗と浄土宗が栄えたが、禅宗は道教に刺激を与え、修養を重んじる全真教が金治下の華北で創始された。文学では、散文がさかんとなって欧陽脩(1007~72)・王安石(1021~86)・蘇軾(蘇東坡、1036~1101)らの名文家が輩出し、韻文では、唐代の詩に対して、民謡から発展した叙情的な詞が流行した。また民間では、一種の歌劇である雑劇がさかんとなった。
手工業の発達を背景に、美術工芸も発展をとげた。絵画では、宮廷の画院を中心に写実的で装飾性の強い院体画(北宗画)が成立し、文人や禅僧の間では水墨画の手法による文人画(南宗画)が全盛となった。工芸の面では、すぐれた漆器や織物のほか、景徳鎮などで青磁・白磁に代表される高度な水準の陶磁器(宋磁)がつくられた。科学技術も発達し、五代以来の木版印刷の技術はさらに発展して普及し、大量の書物が出版された。また火薬と磁針(のちの羅針盤)が実用化され、これらの技術はムスリム商人を介して西方に伝えられた。
<「桃鳩図」と「漁村夕照図」>
・「桃鳩図(とうきゅうず)」~北宋の徽宗皇帝は画院を保護し、自らもすぐれた絵画を残した。図は、彼が描いた院体画の代表作である。
・「漁村夕照図」~南宋の禅僧である牧谿(もっけい)の作品。日本の室町期の水墨画に大きな影響を与えた。
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、177頁~178頁)
〇元代の社会と文化
元は、農耕社会の統治にあたって、遊牧系の軍事政権でありながら、中華帝国の伝統そのままに、官僚制による中央集権体制を採用した。しかし、モンゴル語を公用語とし、政府の高官や地方長官にはモンゴル人をあて、中央は遊牧系の近衛兵で固め、実際にはモンゴル伝統の側近政治を行った。中央アジアや西アジアの出身者(色目人)はとくに優遇され、ムスリム商人出身のイスラーム教徒を、徴税や物資の流通の面で活躍させた。ただし、こうした出身にもとづく差別は、必ずしも厳格なものではなく、有能な人材であれば、民族を問わずに要所に採用した。同様に、初期には儒教を重視せず、科挙を廃止したが、やがて、膨大な官僚なくしては大陸統治は困難であることから、とくに江南の地では、儒教を学ぶ学院(廟堂)の設立を奨励し、14世紀初頭には科挙を復活させた。
元は、徴税請負人を使ってきびしく徴税したが、農耕社会の内部にはあまり干渉せず、佃戸制はそのまま維持された。また駅伝制(ジャムチ)によって交通・交易網は整備され、大運河をはじめ運河の修復にも努め、都市の商工業もさかんであった。貨幣経済はいっそう進展し、元が発行した紙幣(交鈔)は、銀との交換が保証されたため普及し、ときには西アジアでも流通した。
宋代からの庶民文化は、モンゴル人の統治下でもひきつづき発展し、モンゴル支配への抵抗を秘めた民謡や雑劇(元曲)が流行した。元曲の代表作品としては、封建的な束縛に抗して自由な恋愛をえがく『西廂記』、匈奴に嫁いだ王昭君の悲劇を劇化した『漢宮秋』、琵琶を弾きつつ出世した夫との再会を果たす女性を主人公とした『琵琶記』などがある。また民間での講談もさかんであり、『水滸伝』『西遊記』『三国志演義』の原型がつくられた。書画の分野では、東晋の王羲之の伝統をつぐ趙孟頫(趙子昂、1254~1322)や文人画の黄公望(1269~1354)、倪瓚(1301~74)などがあらわれ、物語の挿絵として流行した細密画(ミニアチュール)は、イル=ハン国を通して西方に影響を及ぼした。いっぽう、イスラーム天文学の知識にもとづいて郭守敬(1231~1316)が授時暦をつくり、この暦は、日本の江戸時代、渋川春海(安井算哲、1639~1715)が作成した貞享暦の基礎となった。
宗教は、唐・宋の時代とおなじく道教と仏教が民間でさかんであった。ただ、チベット仏教サキャ派の法王、パスパ(パクパ、1235ごろ~80)がフビライの帝師となったことで、モンゴル貴族層の信仰を集めたのはチベット仏教であり、これへの過度の帰依・寄進が元末の財政破綻の一因となった。
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、184頁~185頁)
〇明代の思想と文化
産業の発達は都市の発展を促し、とくに江南では豊かな郷紳層や商人を中心とする都市文化が生まれた。喫茶の習慣や陶磁器が普及し、大衆芸能や木版印刷による出版がさかんになり、戯曲、小説がひろく読まれ、『水滸伝』・『三国志演義』・『西遊記』・『金瓶梅』の四大奇書が完成した。また、科学技術への関心が高まって実用的な学問(実学)が発達し、李時珍(1523ごろ~96ごろ)の『本草綱目』、宋応星(1590ごろ~1650ごろ)の『天工開物』、徐光啓(1562~1633)の『農政全書』などが刊行された。
こうした科学技術の発展の背景には、ヨーロッパからの刺激がある。16世紀半ばから、イエズス会系の宣教師の来航があいつぎ、イタリア人のマテオ=リッチ(Matteo Ricci、利瑪竇、1552~1610)、ドイツ人のアダム=シャール(Adam Schall、湯若望、1591~1666)らが、布教の手段として西洋の科学技術を伝えた。明の士大夫も刺激を受け、徐光啓はマテオ=リッチとともに、エウクレイデスの幾何学を翻訳した(『幾何原本』)。
思想面では、朱子学が知識や教養を重視したのに対して、16世紀初頭に王守仁(王陽明、1472~1528)が、子どもや庶民が心にそなえているという真正なる道徳を実践する「知行合一」説を説く陽明学をおこした。
キリスト教、科学技術、実用書、陽明学のいずれもが日本など東アジア諸国にも広まっていった。
<マテオ=リッチとアダム=シャール>
・明の皇帝は、天文学、暦学、地理学、数学、砲術などの新知識の受容を認めた。マテオ=リッチは『坤輿万国全図』を作成して、世界の地理・地誌を地球球体説とともに紹介した。アダム=シャールは『崇禎暦書』の編纂を指導した。
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、229頁)
〇清代の経済と文化
明は、16世紀の世界経済の発展に対して十分に適応できないまま衰退したが、清は現状肯定的な政策を採用した。まず、満洲人の王朝であり、モンゴル人を体制内にとりいれていたため、北方防衛の負担が少なかった。また、海上貿易は、1684年に海禁を解いて民間貿易を認めたので、ふたたび活発となった。清からは、生糸や陶磁器、茶が輸出され、多量の外国銀が流入した。
1757年、清は欧米諸国との貿易を広州一港に限定した。特許商人組合である公行(広東十三行)を中心に対外貿易を請け負わせたり、広州ではなくマカオに外国人商人や家族を居住させて貿易の際に広州に出入りさせたりするなど、欧米からみれば強い管理のもとに置かれた。18世紀後半には清からの茶の輸入が増加したイギリスは、清に対して貿易に関する障壁を撤廃するように求めた。
税制では、明の後期からすでに一条鞭法など銀納に移行していたが、清もこれを継承した。18世紀初頭には丁銀(人頭税)が地銀(土地税)にくりいれられ(地丁銀)、やがて廃止されて課税対象が土地に一本化された。そのため、国家は小農の家族を把握する必要がなくなり、郷紳を通じた徴税や治安維持にたよるようになった。
清代には明にひきつづき、郷紳や商人らによる都市文化が発展した。彼らの生活は、社会の上層家庭の日常生活における感情の機微を描いた『紅楼夢』や科挙と社会生活をあつかった『儒林外史』などに描きだされている。また短編の怪奇小説を集めた『聊斎志異』も歓迎された。陶磁器や工芸品などの品質や技術も向上したが、その意匠はしだいに繊細で精緻なものとなっていった。
思想では、明末清初という政治激動期に、顧炎武(1613~82)や黄宗羲(1610~95)らが、より現実的な学問のあり方を主張し、清の体制を批判して考証学の道を開いた。この考証学は、清のきびしい思想統制のもとで、純学問的な古典研究へと性格をかえたが、清の中期にはその厳密な史料批判の方法が歴史学の発展をもたらし、銭大昕(1728~1804)などによる史学(清朝考証学)が栄えた。
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、234頁~235頁)
中国文化史(宋代から)の記述~『詳説世界史』(山川出版社)より
【宋代の文化】
唐代を代表する陶磁器の唐三彩と、宋代を代表する白磁・青磁をくらべてみると、色彩豊かで具象的な唐三彩に対し、宋の白磁・青磁はすっきりした理知的な美しさをもっている。それは、外面的な装飾をそぎ落とし、ものごとの本質に直接せまろうとする宋代文化の特徴をあらわしている。このような変化は、学問・思想から美術までさまざまな分野にみられるが、唐代後期以来のこの文化革新の流れを担ったのは、貴族にかわり官界に進出した士大夫、すなわち儒学の教養を身につけた知識層であった。
儒学では、経典のなかの一つ一つの字句の解釈を重んずる訓詁学にかわって、経典全体を哲学的に読みこんで宇宙万物の正しい本質(理)にいたろうとする宋学がおこった。それは北宋の周敦頤(しゅうとんい、1017~73)に始まり、南宋の朱熹(朱子、1130~1200)によって大成されたので朱子学ともいわれる。朱子学はその後長く儒学の正統とされ、日本や朝鮮の思想にも大きな影響を与えた。経典のなかでは、とくに四書(『大学』『中庸』『論語』『孟子』)が重んじられるようになった。宋代の儒学の発展は、社会秩序を正そうとする士大夫の実践的意欲とも結びつき、華夷・君臣・父子などの区別を重視する大義名分論が盛んになった。宋代の歴史学を代表する司馬光(1019~86)の『資治通鑑』は、君主の統治に資する(役立つ)ことを目的に書かれた編年体の通史である。唐末以来の古文復興の動きを受け継ぎ、宋代にも欧陽脩(1007~72)・蘇軾(1036~1101)らの名文家が出た。
美術では、宮廷画家を中心とする写実的な院体画とならんで、士大夫による文人画も盛んになった。水墨あるいは淡彩で自由な筆さばきをたっとぶ文人画は、対象のたんなる模写ではなく、観察をつうじて作者の心がつかみとった自然の生気をうつし出そうとするものであった。工芸では、白磁や青磁など、高温で焼いたかたい磁器の生産が盛んになった。
都市商業の繁栄を背景に庶民文化も発展し、小説・雑劇や、音曲にあわせてうたう詞が盛んにつくられた。宗教では禅宗が官僚層によって支持され、また金の統治する華北では、儒・仏・道を調和した全真教(開祖は王重陽(1113~70))が道教の革新をとなえておこった。唐代頃に始まった木版印刷は宋代に普及し、また活字印刷術も発明された。同じ頃にすすんだ羅針盤や火薬の実用化の技術は、イスラーム世界をつうじてヨーロッパに伝わった。
<院体画(「桃鳩図」)>
「風流天子」といわれた徽宗の作。
宋代には美術を愛好する皇帝が天下の巨匠を画院に集め、写実や装飾性を重んずる画風をうみだした。
<文人画(墨竹図)>
書家・文豪としても知られる蘇軾の作。
胸のなかにある竹のイメージを墨一色で一気に描きあげた作品である。
(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、163頁~165頁)
【元の東アジア支配】
相続争いを経て即位した第5代のフビライ(Khubilai, 在位1260~94)は、自分の勢力の強い東方に支配の重心を移し、大都(現在の北京[ペキン])に都を定め、国名を中国風に元(1271~1368)と称し(1271年)、ついでに南宋を滅ぼして中国全土を支配した。(中略)
元は中国の統治に際して、中国の伝統的な官僚制度を採用したが、実質的な政策決定は、中央政府の首脳部を独占するモンゴル人によっておこなわれた。また、色目人と総称される中央アジア・西アジア出身の人々が、財務官僚として重用された。金の支配下にあった人々は漢人、南宋の支配下にあった人々は南人と呼ばれた。武人や実務官僚が重視され、科挙のおこなわれた回数も少なかったため、儒学の古典につうじた士大夫が官界で活躍する機会は少なかった。
(中略)
元の政府は、支配下の地域の社会や文化には概して放任的な態度をとったので、大土地所有も宋代以来引き続き発展し、また都市の庶民文化も栄えた。なかでも戯曲は元曲として中国文学史上に重要な地位を占め、『西廂記』『琵琶記』などがその代表作として知られる。
【モンゴル時代の東西交流】
モンゴル帝国の成立により、東西の交通路が整備されたため、東西文化の交流が盛んになった。当時十字軍をおこしていた西ヨーロッパは、イスラーム地域を征服したモンゴル帝国に関心をもち、ローマ教皇はプラノ=カルピニ(Plano Carpini, 1182頃~1252)、フランス王ルイ9世はルブルック(Rubruck, 1220頃~93頃)を使節としてモンゴル高原におくった。またイタリアの商人マルコ=ポーロ(Marco Polo, 1254~1324)は大都にきて元につかえ、その見聞をまとめた『世界の記述』(『東方見聞録』)はヨーロッパで反響を呼んだ。
モンゴル帝国ではムスリム商人がユーラシアの東西を結んで活躍し、キプチャク=ハン国やイル=ハン国のモンゴル君主はイスラームに改宗した。また当時、元にきた色目人にイスラーム教徒が多かったことから、中国にもイスラーム教がしだいに広まった。イスラームの天文学を取り入れて郭守敬(1231~1316)がつくった授時暦は、のち日本にも取り入れられた(江戸時代の貞享暦)。また元からはイル=ハン国に中国絵画が伝えられ、それがイランで発達した細密画(ミニアチュール)に大きな影響を与えた。
イル=ハン国はその初期にネストリウス派のキリスト教を保護し、ヨーロッパのキリスト教諸国やローマ教皇庁と使節を交換していたが、これがきっかけとなって、13世紀末にはモンテ=コルヴィノ(Monte Corvino, 1247~1328)が派遣され、大都の大司教に任ぜられた。中国でカトリックが布教されたのは、これがはじめてであった。
モンゴル支配下の広大な地域では、漢語・チベット語・トルコ語・ペルシア語・ロシア語・ラテン語など多様な言語がもちいられていた。モンゴル語を表記するパスパ文字は、フビライの師であったチベット仏教の教主のパスパ('Phagspa, 1235/39~80)がつくったものであるが、しだいにすたれて、ウイグル文字でモンゴル語を表記することが一般的になった。
(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、167頁~169頁)
【明後期の社会と文化】
国際商業の活発化は、中国国内の商工業の発展をうながした。長江下流域では綿織物や生糸に代表される家内制手工業が盛んになり、原料となる綿花や養蚕に必要な桑の栽培が普及した。このため、明末には長江中流域の湖広(現在の湖北・湖南省)があらたな穀倉地帯となり、「湖広熟すれば天下足る」と称せられた。また江西省の景徳鎮に代表される陶磁器も生産をのばした。生糸や陶磁器は、日本やアメリカ大陸・ヨーロッパに輸出される代表的な国際商品であった。
商業・手工業の発展にともない、山西商人や徽州(新安)商人など明の政府と結びついた特権商人が全国的に活動して巨大な富を築いた。大きな都市には、同郷出身者や同業者の互助や親睦をはかるための会館や公所もつくられた。税の納入も銀でおこなわれるようになり、16世紀には各種の税や徭役を銀に一本化して納入する一条鞭法の改革が実施された。貨幣経済の発展とともに都市には商人や郷紳など富裕な人々が集まり、庭園の建設や骨董の収集など文化生活を楽しんだ。明を代表する画家・書家の董其昌(とうきしょう、1555~1636)のように、高級官僚を経験しながら芸術家として名声を得た文化人も多かった。
木版印刷による書物の出版も急増し、科挙の参考書や小説、商業・技術関係の実用書などが多数出版されて書物の購買層は広がった。『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』などの小説が多くの読者を獲得し、庶民向けの講談や劇も都市の盛り場や農村でさかんに演じられた。儒学のなかでは、16世紀初めに王守仁(王陽明、1472~1528)が、無学な庶民や子どもでも本来その心のなかに真正の道徳をもっている(心即理)と主張し、外面的な知識や修養にたよる当時の朱子学の傾向を批判した。ありのままの善良な心を発揮し(致良知)、その心のままに実践をおこなう(知行合一)ことを説いた陽明学は、学者のみならず庶民のあいだにも広い支持を得た。
明末文化の一つの特色は、科学技術への関心の高まりである。『本草綱目』(李時珍[1523頃~96頃]著)、『農政全書』(徐光啓[1562~1633]編)、『天工開物』(宋応星[1590頃~1650頃]著)などの科学技術書がつくられ、日本など東アジア諸国にも影響を与えた。当時の科学技術の発展には、16世紀半ば以降東アジアに来航したキリスト教宣教師の活動も重要な役割をはたした。日本でのキリスト教普及の基礎を築いたイエズス会宣教師のフランシスコ=ザビエル(Francisco Xavier, 1506頃~52)は、中国布教をめざしたが実現せず、その後マテオ=リッチ(Matteo Ricci, 1552~1610)らが16世紀末に中国にはいって布教をおこなった。キリスト教が庶民層にまで広まった日本と異なり、中国では、ヨーロッパの自然科学や軍事技術に関心をもつ士大夫層がキリスト教を受け入れた。リッチが作製した世界地図の「坤輿万国全図」は、中国に新しい地理知識を広め、日本などにも伝えられた。西洋暦法による『崇禎暦書』や「ユークリッド幾何学」の翻訳である『幾何原本』なども刊行された。
<郷紳>
科挙の合格者や官僚経験者は、郷里の名士として勢力をもった。このような人々を郷紳という。
(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、182頁~184頁)
【清代の社会と文化】
三藩の乱の鎮圧と台湾の占領によって清朝の支配が安定すると、清朝は海禁を解除し、中国商人のジャンク船による交易やヨーロッパ船の来航をつうじて、海上貿易は順調に発展した。生糸や陶磁器・茶などの輸出によって中国には銀が流れこみ、国内商業の発展を支えた。東南アジアとの貿易をおこなう福建や広東の人々の一部は、清朝の禁令をおかして東南アジアに住み着き、農村と国際市場を結ぶ商業網をにぎって経済力をのばし、のちの南洋華僑のもとになった。18世紀半ばになると乾隆帝はヨーロッパ船の来航を広州1港に制限し、公行(こうこう、コホン)という特定の商人組合に貿易を管理させた。
18世紀には政治の安定のもと、中国の人口は急増した。アメリカ大陸から伝来したトウモロコシやサツマイモなど、山地でも栽培可能な新作物は、山地の開墾をうながして、人口増を支えた。しかし土地の相対的な不足は多くの土地なし農民をうみだした。税制では、18世紀初めの地丁銀制により、丁税(人頭税)が土地税にくりこまれて制度の簡略化がはかられた。
明代後期の文化が動乱期の世相を反映してダイナミックな力強さを感じさせるとすれば、それに比較して清代の文化はおちついた繊細さをみせているといえる。明清交替の混乱を経験した顧炎武(1613~82)など清初の学者は、社会秩序を回復するには現実を離れた空論でなく、事実に基づく実証的な研究が必要だと主張した。実証を重視するその主張は清代中期の学者に受け継がれ、儒学の経典の校訂や言語学的研究を精密におこなう考証学が発展し、銭大昕(1728~1804)などの学者が出た。『紅楼夢』や『儒林外史』など清代中期の長編小説も、細密な筆致で上流階級や士大夫たちの生活を描写している。
清朝はイエズス会の宣教師を技術者として重用した。暦の改定をおこなったアダム=シャール(Adam Schall, 湯若望, 1591~1666)やフェルビースト(Verbiest, 南懐仁, 1623~88)、中国全図の「皇輿全覧図」作製に協力したブーヴェ(Bouvet, 白進, 1656~1730)、ヨーロッパの画法を紹介したり円明園の設計に加わったカスティリオーネ(Castiglione, 郎世寧, 1688~1766)らはその例である。イエズス会宣教師は布教にあたって中国文化を重んじ、信者に孔子の崇拝や祖先の祭祀などの儀礼を認めたが、これに反対する他派の宣教師がローマ教皇に訴えたことから、儀礼に関わる論争(典礼問題)がおこった。教皇はイエズス会宣教師の布教方法を否定したため、これに反発した清朝は雍正帝の時期にキリスト教の布教を禁止した。
一方、宣教師たちによってヨーロッパに伝えられた儒教・科挙など中国の思想・制度や造園術などの文化は、ヨーロッパ人のあいだに中国に対する興味を呼びおこした。18世紀の啓蒙思想家のあいだでは、中国と比較してヨーロッパの国家体制の優劣が論じられ、また芸術のうえでもシノワズリ(chinoiserie, 中国趣味)が流行した。
<円明園>
円明園は雍正帝から乾隆帝の時期に北京郊外に建設された離宮。
バロック様式の西洋建築を含む広大な庭園であったが、アロー戦争の際の英仏軍の略奪・破壊によって、廃墟と化した。
(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、191頁~192頁)
英文の記述~本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』(講談社)より
〇宋代の文化
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、177頁~178頁)
Culture of the Song Dynasty
In Confucianism, the Song Study(宋学) which studied the theory of generation of all things in
the universe as well as human nature, was theoretically founded by Zhou Dunyi (周敦頤) and others
of the Northern Song. Zhu Xi (朱熹 Zhuzi 朱子) of the Southern Song reconstituted the Confucian
tradition and shaped Neo-Confucianism (朱子学) where he justified the order between the sovereign
and subjects as an absolute principle and attached importance on the Four Books (四書、the Great
Learnig (大学), Doctrine of the Mean (中庸), the Analects (論語) and Mencius (孟子)) as the Confucian classics. Zhu Xi extended the theory of superiority of China over surrounding peoples corresponding to
the severe international environments. Zhu Xi’s Neo-Confucianism became the legitimate
Confucianism in China, and was introduced to Japan, the Korean peninsula and Vietnam,
and was prospered as bureaucratic learning. As opposed to Neo-Confucianism which
studied the principles of things objectively, Lu Jiuyuan (陸九淵) claimed the establishment of mind
(subjectivity) putting importance on practice, and his thought later influenced the philosophy
of Wang Yang-ming (陽明学). Sima Guang (司馬光) of the Northern Song justified the “theory of legitimate reasons” using Chinese history and compiled Zizhi Tongjian (資治通鑑, Comprehensive Mirror for Aid in Government) , a chronological historiography text of China. In Buddhism, the Zen sect
and the Pure Land sect prospered, and the Zen sect spurred a Taoism, and Quanzhen school (全真教)
which respected moral culture was founded in North China under the Jing government. In
literature, the prose style became popular, and masters of style such as Ouyang Xiu (欧陽脩), Wang
Anshi (王安石) and Su Shi (蘇東坡、蘇軾) appeared. In verse style, unlike the poems in the Tang period,
lyrical Ci (詞), evolved from folk songs, became popular. Among the common people zaju (a kind of
Chinese classical opera) became popular.
Arts and crafts developed with the handicraft manufacturing development as a
background. In paintings, very realistic and decorative yuan ti hua (the Northern Song school of painting, 院体画, 北宗画) materialized. This was led by the painting institute of the royal court,
and paintings by literary artists (the Southern Song School of paintin,文体画, 南宗画)
based on technical skills of China ink painting most prospered among writers and Zen priests.
In handicrafts, magnificent lacquerware and textiles were produced, and high quality ceramics (Song ceramics 宋磁) represented by celadon porcelain (青磁) and white porcelain (白磁) were produced mainly in Jingdezhen (景徳鎮). Scientific technologies also developed, woodblock printing techniques (木版印刷) from the Five Dynasties developed even further, and thus many books were published. Gunpowder and the magnetic needle were put to practical use, and such technologies were transferred
to the western area through Muslim merchants.
(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、139頁~140頁)
〇元代の社会と文化
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、184頁~185頁)
Society and Culture of the Yuan Dynasty
With regards to the governing of agricultural society, the Yuan dynasty, being a nomadic
military regime, nevertheless adopted centralism based on the bureaucracy following that of
Chinese Empire tradition. However, the Mongolian language was designated as the official
language, and Mongol people were appointed as government’s high officials and local
governors, and the central government was guarded by the Imperial guards. Thus actually
Mongolian traditional politics by close associates was carried out. People from Central
Asia and West Asia (Semu) were treated favorably among others. Muslim merchants were
entrusted with tax collection and trading goods. Mongols were positioned highest in the
ranking system at least initially, however, capable and talented people could be employed
and placed in key positions regardless of race. In the same way, initial Confucianism was
not well respected and thus the Imperial Examination system was abolished. But gradually
realizing it was not practical to govern the vast continent without enormous number of
bureaucrats, the Yuan promoted the establishment of institutes for studying Confucianism,
especially in Jiangnan, and in the beginning of the 14th century the Imperial Examination
was revived.
The Yuan dynasty collected tax strictly employing tax collectors but did not intervene in
the internal agricultural society much, and maintained the tenant farmer system as it was.
Also, traffic and trade networks were consolidated by the station relay system (jamchi) and
canals including the Grand Canal were restored. Because of this, urban commerce and
industry flourished. A monetary economy further developed. Paper money issued by the
Yuan, which guaranteed its convertibility into silver, was widely used, and sometimes
circulated even in West Asia.
The culture of common people continuously developed since the Song period even
under Mongol’s control, and folk songs and Zaju (雑劇, Yuan musical 元曲) concealing resistance
against Mongolian control became popular. Representative Zaju were, among others,
Xixiang Ji (西廂記), or Tale of the Western Chamber depicting free love rebelling against the
feudal restraint, Han Gong Qiu (漢宮秋, The story of the Han palace) dramatizing a tragedy about
Wang Zhao Jun who married to the Xiongnu and Pi Pa Ji (琵琶記, The Lute), a story about a
heroin who, with playing a lute, finally could meet again with her husband. Private
storytelling was also popular and original forms of Water Margin (水滸伝), Journey to the West
(西遊記) and Romance of the Three Kingdoms (三国志演義) were created. In the field of drawings and paintings, Zhao Mengfu (趙孟頫) succeeding traditions of Wang Xizhi (王羲之), and Huang Gongwang
(黄公望) and Ni Zan (倪瓚) of literati paintings appeared. And miniatures, which became popular as
illustration of stories, influenced the western world through the Il Khans. On the other hand, based on
the knowledge of Islamic astronomy, Guo Shoujing (郭守敬) made The Lunar and Solar Calendar
(Shou shi li 授時暦). This was used as the base for the Jokyo Calendar, which was made by Harumi
Sibukawa(渋川春海) in the Edo period of Japan.
In terms of religion, Taoism and Buddhism were popular among people the same as the
time of Tang and Song period. However as Phags-pa (パスパ), a pope of Sa skya sect of Tibetan
Buddhism, became a teacher for the emperor of Khubilai (帝師), Tibetan Buddhism prevailed
among Mongolian aristocrats. The excessive belief in and contribution to this religion was
one of the reasons for the financial bankruptcy in the final stage of the Yuan dynasty.
(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、144頁~145頁)
〇明代の思想と文化
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、229頁)
Thoughts and Culture in the Ming Period
Development of industries prompted growth of cities, and especially in Jiangnan. Urban
culture evolved with rich local gentries and merchants as the cores. Tea drinking became
customary and the use of pottery spread and public entertainment, as well as publishing
by wood printing, became prosperous. Due to this, dramas and novels were broadly read,
resulting in completion of the Four Great Classical Novels: Outlaws of the Marsh (水滸伝), Three
Kingdoms (三国志演義), Journey to the West (西遊記), and The Golden Lotus (金瓶梅), as interests
in scientific technologies rose, practical studies (practical science) advanced, and Compendium of
Materia Medica (Bencao Gangmu 本草綱目) by Li Shizhen (李時珍), Tiangong Kaiwu (天工開物)
by Song Yingxing (宋応星) and Nong Zheng Quan Shu (農政全書) by Xu Guangqi (徐光啓) and others
were published.
Such development of scientific technologies were influenced by Europe. Since the
middle of the 16th century, missionaries of the Society of Jesus visited the Ming one after
another, and the Italian Matteo Ricci (マテオ=リッチ, Li Madou 利瑪竇) and German Adam Schall
(アダム=シャール, Tang Ruowang 湯若望) introduced western scientific technology as a means of
propagation. The Ming scholar-bureaucrats were also stimulated, and Xu Guangqi (徐光啓) translated
Euclid’s Geometry (エウクレイデスの幾何学) (Original Geometry 幾何原本) together with
Matteo Ricci.
In the aspect of thoughts, while Neo-Confucianism emphasisized knowledge and culture,
in the beginning of the 16th century, Wang Yangming (王陽明) started the Philosophy of
Yang-Ming (陽明学), which preached that “Awareness comes only through practice”.
Genuine morality, with which the hearts of children and the general public were said to be
endowed, was to be executed.
Christianity, scientific technology, technical manuals and the Philosophy of Yang-Ming
all spread to Japan and other East Asian countries.
(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、171頁)
〇清代の経済と文化
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、234頁~235頁)
Economy and Culture of the Qing
The Ming declined, being unable to adapt to the development of a world economy in the
16th century, while the Qing adopted policies to acknowledge the status quo. Firstly, since
it was a Manchu dynasty and Mongolians were incorporated into the state structure, the
burden of defending the northern area was small. Also, regarding sea trade, the ban on the
maritime trade was lifted in 1684 and private trade was also allowed. Raw silk, potteries
and teas were exported from the Qing. In exchange a huge amount of foreign silver flowed
in.
In 1757, the Qing restricted trade with Western countries to the Guangdong (sic 広州) port only.
Foreign trade was undertaken by the Gong Hang (公行(コホン), Guangdong Thirteen Gong Hang (広東十三行)), a guild of licensed merchants. Foreign merchants and their families were allowed to live in
Macao (マカオ) but not in Guangzhou. They were forced to come in and go out from Guangzhou
for trading business, and thus, from a Western point of view, they were placed under strong control of
the Qing. In the latter half of the 18 th century, when import of tea from the Qing increased,
England requested to lift trade barriers to the Qing.
Regarding the tax system, the Qing succeeded the tax payment by silver such as the
Single-whip System (一条鞭法) which was already adopted in the late Ming period. In the beginning
of the 18 th century, a per capita tax (丁銀) was incorporated into the land tax (地丁銀) and subsequently
abolished to become a single tax on the land only. Therefore, the government did not
necessarily know the number of the small farmers’ family members, and became dependent
on local gentries for the tax collection and maintenance of public peace.
During the Qing period, urban culture, led by the local gentries and merchants,
continued to develop following the Ming period. Their lives were described in A Dream
of Red Mansions (紅楼夢) which depicted the secrets of human nature in daily lives of Manchu
aristocrats and Scholars (儒林外史), which dealt with the higher civil service examination and social
lives. Strange Tales from the Liaozhai Studio (聊斎志異), a collection of short weird novels, was well
received. The quality and techniques of potterymaking and industrial art objects were
improved, and their design gradually became more sophisticated and precise.
Regarding thoughts, during between the end of the Ming and the beginning of the Qing,
when political situation was highly unstable, Gu Yanwu (顧炎武) and Huang Zongxi (黄宗羲) insisted that study and learning be realistic, criticized the Qing’s governing system and paved the way
for the study of historical investigation (考証学). This study of historical investigation changed
character to the academic bibliographical study of Chinese classics under tight thought
control by the Qing, but its strict critical method of historical materials brought about the
development of the study of history, and historical science (Study of Historical Investigation of
the Qing dynasty (清朝考証学)) by Qian Daxin (銭大昕) and others flourished.
(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、176頁~177頁)