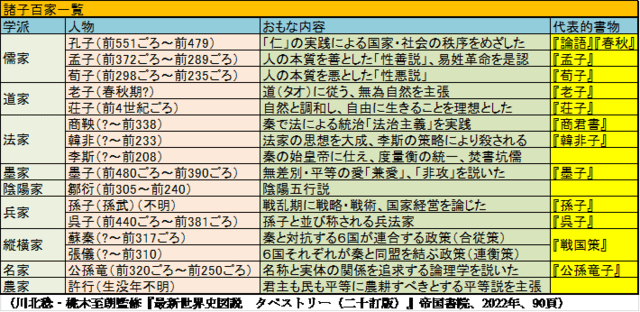(2023年10月8日投稿)
【はじめに】
今回のブログでは、高校世界史において、イスラーム文化(文明)について、どのように記述されているかについて、考えてみたい。
参考とした世界史の教科書は、次のものである。
〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]
〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]
また、前者の高校世界史教科書に準じた英文についても、見ておきたい。
〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]
【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】
本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社
〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]
【目次】
本村凌二『英語で読む高校世界史』
Contents
Introduction to World History
1 Natural Environments: the Stage for World History
2 Position of Japan in East Asia
3 Disease and Epidemic
Part 1 Various Regional Worlds
Prologue
The Humans before Civilization
1 Appearance of the Human Race
2 Formation of Regional Culture
Chapter 1
The Ancient Near East (Orient) and the Eastern Mediterranean World
1 Formation of the Oriental World
2 Deployment of the Oriental World
3 Greek World
4 Hellenistic World
Chapter 2
The Mediterranean World and the West Asia
1 From the City State to the Global Empire
2 Prosperity of the Roman Empire
3 Society of the Late Antiquity and Breaking up
of the Mediterranean World
4 The Mediterranean World and West Asia
World in the 2nd century
Chapter 3
The South Asian World
1 Expansion of the North Indian World
2 Establishment of the Hindu World
Chapter 4
The East Asian World
1 Civilization Growth in East Asia
2 Birth of Chinese Empire
3 World Empire in the East
Chapter 5
Inland Eurasian World
1 Rises and Falls of Horse-riding Nomadic Nations
2 Assimilation of the Steppes into Turkey and Islam
Chapter 6
1 Formation of the Sea Road and Southeast Asia
2 Reorganizaion of Southeast Asian Countries
Chapter 7
The Ancient American World
Part 2 Interconnecting Regional Worlds
Chapter 8
Formation of the Islamic World
1 Establishment of the Islamic World
2 Development of the Islamic World
3 Islamic Civilization
World in the 8th century
Chapter 9
Establishment of European Society
1 The Eastern European World
2 The Middle Ages of the Western Europe
3 Feudal Society and Cities
4 The Catholic Church and the Crusades
5 Culture of Medieval Europe
6 The Middle Ages in Crisis
7 The Renaissance
Chapter 10
Transformation of East Asia and the Mongol Empire
1 East Asia after the Collapse of the Tang Dynasty
2 New Developments during the Song Era ―Advent of Urban Age
3 The Mongolian Empire Ruling over the Eurasian Continent
4 Establishment of the Yuan Dynasty
Part 3 Unification of the World
Chapter 11
Development of the Maritime World
1 Formation of the Three Maritime Worlds
2 Expansion of the Maritime World
3 Connection of Sea and Land; Development of Southeast Asia World
Chapter 12
Prosperity of Empires in the Eurasian Continent
1 Prosperity of Iran and Central Asia
2 The Ottoman Empire; A Strong Power Surrounding
the East Mediterranean
3 The Mughal Empire; Big Power in India
4 The Ming Dynasty and the East Asian World
5 Qing and the World of East Asia
Chapter 13
The Age of Commerce
1 Emergence of Maritime Empire
2 World in the Age of Commerce
World in the 17th century
Chapter 14
Modern Europe
1 Formation of Sovereign States and Religious Reformation
2 Prosperity of the Dutch Republic
and the Up-and-Coming England and France
3 Europe in the 18th Century and the Enlightened Absolute Monarchy
4 Society and Culture in the Early Modern Europe
Chapter 15
Industrialization in the West and the Formation of Nation States
1 Intensified Struggle for Economic Supremacy
2 Industrialization and Social Problems
3 Independence of the United States and Latin American Countries
4 French Revolution and the Vienna System
5 Dream of Social Change; Waves of New Revolutions
Part 4 Unifying and Transforming the World
Chapter 16
Development of Industrial Capitalism and Imperialism
1 Reorganization of the Order in the Western World
2 Economic Development of Europe
and the United States and Changes in Society and Culture
3 Imperialism and World Order
World in the latter half of 19th century
Chapter 17
Reformation in Various Regions in Asia
1 Reform Movements in West Asia
2 Colonization of South Asia and Southeast Asia,
and the Dawn of National Movements
3 Instability of the Qing Dynasty and Alteration of East Asia
Chapter 18
The Age of the World Wars
1 World War I
2 The Versailles System and Reorganization of International Order
3 Europe and the United States after the War
4 Movement of Nation Building in Asia and Africa
5 The Great Depression and Intensifying International Conflicts
6 World War II
Part 5 Establishment of the Global World
Chapter 19
Nation-State System and the Cold War
1 Hegemony of the United States and the Development of the Cold War
2 Independence of the Asian-African Countries and the "Third World"
3 Disturbance of the Postwar Regime
4 Multi-polarization of the World and the Collapse of the U.S.S.R.
Final Chapter
Globalization of Economy and New Regional Order
1 Globalization of Economy and Regional Integration
2 Questions about Globalization and New World Order
3 Life in the 21st Century; Time of Global Issues
The Rises and Falls of Main Nations
Index(English)
Index(Japanese)
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・イスラーム文化(文明)の記述~『世界史B』(東京書籍)より
・イスラーム文化(文明)の記述~『詳説世界史』(山川出版社)より
・英文の記述~本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』(講談社)より
イスラーム文化(文明)の記述~『世界史B』(東京書籍)より
第2編 広域世界の形成と交流
第8章 イスラーム世界の形成
1 イスラーム世界の成立
2 イスラーム世界の発展
3 イスラーム文明
第8章 イスラーム世界の形成
1 イスラーム世界の成立
【預言者ムハンマドとアラブの大征服】
アラビア半島南部のイエメン地方は、季節風がもたらす降雨のめぐみと、乳香・没薬などの特産品、インド洋交易の収益によって経済的に富み栄え、古くからいくつもの国家が興亡し、独自の文化が発達した。いっぽう、半島の北・中部では、牧畜と商業によって生計を立てる遊牧民(ベドウィン)やオアシス農耕民が多くの集団に分かれてたがいに争い、集合離散をくりかえしていた。彼らアラブ人の間にはユダヤ教やキリスト教を信仰する者もいたが、多くは先祖伝来の多神教を信仰し、各地には神々をまつる神殿が建設された。
メッカに住むクライシュ族のハーシム家に生まれた商人ムハンマド(Muhammad, 570ごろ~632)は、610年ごろから神の啓示を受けた預言者として宗教活動を開始し、多神教の偶像崇拝を批判して、唯一神アッラー(Allah)への信仰を説くイスラーム教(Islam)を広めた。故郷の有力者らに迫害されたムハンマドは、622年に北方のオアシス都市メディナ(ヤスリブ)へ亡命し、この地に新たなムスリム共同体(umma ウンマ)を成立させた。彼らは多神教徒と数度の戦争を行い、630年にはメッカを征服することに成功した。
632年にムハンマドが没すると、残された人々は預言者の後継者としてカリフ(Caliph)の役職を設立し、クライシュ族から有力な信徒を選出して、ウンマの指導を任せた(正統カリフ時代 632~661)。第2代正統カリフのウマルは、アラブの大征服とよばれる大規模なジハード(聖戦)を行い、東ローマ帝国からシリアやエジプトなどの肥沃な土地を奪うとともに、642年のニハーヴァンドの戦いでササン朝ペルシアをやぶって、その領土を獲得した。ムスリム軍が征服した地域には軍営都市(misr ミスル)が建設され、カリフから任命されたアミール(総督)が治安の維持と征服地からの徴税を担当し、兵士には年金(ata アター)が支給された。
【ウマイヤ朝の成立】
661年に第4代正統カリフのアリー(Ali, 在位656~661)が不満分子によって暗殺されると、彼と対立していたシリア総督のムアーウィヤ(Muawiya, 在位661~680)が政権を握り、それまでの慣例をやぶって、自分の一族であるクライシュ族ウマイヤ家の出身者が代々のカリフ位を世襲する体制を確立した(ウマイヤ朝 Umayya, 661~750)。ウマイヤ朝はダマスカスに都を定め、さらなる征服戦争をおしすすめて、西方ではイベリア半島の西ゴート王国を滅ぼし、東方ではアフガニスタンや中央アジアを支配下に組みいれた。また、第5代カリフのアブド=アルマリク(Abd al-Malik, 在位685~705)は、ササン朝や東ローマ帝国の旧官僚が担っていた行政の用語をアラビア語に統一し、独自の金貨・銀貨を鋳造するなどの行政改革を行った。
(下略)
<イスラーム>
イスラームとは「自分のすべてを神にゆだねること(絶対帰依)」を意味するアラビア語で、その信徒はムスリムとよばれる。すべてのムスリムは神の前に平等であり、一般の信徒と神を仲介する聖職者は存在しない。
<イスラーム法>
9世紀以降に整えられたイスラーム法(シャリーア)は、啓典『クルアーン(Quran, コーラン)』と、ムハンマドの言行を伝えた伝承(ハディース)が基盤となっている。イスラーム法は、ムスリムの義務として神・天使・啓典・預言者・来世・天命の六つを信じること(六信)と、信仰告白・礼拝・断食・喜捨・巡礼の五つを行うこと(五行)を定め、その具体的な方法を規定している。たとえば断食は、ラマダーン月(イスラーム暦の第9月)の1か月間、日中は断食しなければならないとされるが、夜は盛大に飲み食いをする一種の祭りであり、また、旅人、妊婦、病人などは断食を免除されるなど柔軟な規定となっている。イスラーム法はまた、婚姻・相続などの社会規範や、国家や政治指導者に関する政治的規定も含み、国家や社会のあり方を規制している。
<一神教の歴史観>
われわれが学んでいる世界史は、近代になって発達した歴史学・文献学・考古学・言語学などの成果にもとづいている。したがって、前近代の人々が認識していた世界史は現代のものとは大きく異なっているはずである。
西アジアとヨーロッパの両世界では、一神教のユダヤ教・キリスト教・イスラーム教が支配的であり、いずれも旧約聖書に描かれた物語を世界史の大枠として共有していた。それによれば、世界の歴史は神による天地創造にはじまり、最初の人間であるアダムとエバ(イヴ)の楽園追放、大洪水とノアの箱舟、バベルの塔の建設と破壊、アブラハムの祝福、ヨセフの受難、モーセのエジプト脱出といった有名な物語をつむぎながら、人類は諸民族に分かれて世界中に広がっていったとされている。
こうした歴史観にもとづく話は、現代においてなお、30億人をこえる一神教世界の人々に共通の教養としての地位を保持しつづけており、彼らの文化と信念の源泉として強い力をもっている。
<シーア派とスンナ派>
イスラーム教の分派であるシーア派は、もともとアリーの子孫をウンマの指導者(イマーム)と認める政治的党派から出発した。彼らは、アリーの子孫にのみ神の命令を解釈する特別な能力がそなわっていると考え、独自の法学・神学体系を発展させたため、一つの宗派を形成するようになった。のちにイマームの血統がとだえると、法学者(ファキーフ)がイマームの意図にもとづいて信徒を指導するという考え方が生まれ、これが現代のイラン=イスラーム共和国にみられる政治・宗教体制につながっている。
いっぽう、スンナ派とは、正統カリフ、ウマイヤ朝、アッバース朝とつづいた政権の正統性を認める現状肯定派を母体とし、ウンマのなかで語り伝えられてきた預言者のスンナ(慣行)にしたがって神の命令を解釈しようとする立場をさす。彼らは、特定の人物の判断にではなく、ウンマ全体の合意にこそ神の意志があらわれると考え、10世紀ごろまでにいくつかの法学派・神学派をつくりあげた。こうして形成された、共同体の合意と団結を重視する人々の総体がスンナ派である。
スンナ派とシーア派の間には、長年にわたる闘争の歴史があり、それは現代においても一部の地域でつづいているが、両者とも『クルアーン(コーラン)』の教えにしたがうムスリムとしての立場は共通であり、平和裏に共存している地域も少なくない。
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、122頁~123頁、127頁、131頁)
3 イスラーム文明
【イスラーム世界の都市と商業】
7世紀にアラビア半島のメッカに生まれたイスラーム教には、もともと、商業を卑しめる考えがなかった。古代オリエント文明をひきついで、商業が高度に発達していた西アジアや北アフリカで主要な宗教となったのちも、イスラーム教は公正な取引など商人の倫理を重んじる宗教として発展していった。メッカに巡礼に行くことがムスリムの義務の一つに定められていたため、巡礼を目的としたムスリムの移動を禁じることは、イスラーム世界の支配者にはできなかった。イスラーム世界を縦横に走るメッカへの巡礼路は、同時に、商業のための道であり、また学問を求める旅の道でもあった。支配者は、巡礼路の安全を確保して、人、もの、情報の自由な移動を促進することが期待されていた。このようなイスラーム教に支えられたイスラーム文明は、商業を中心とする、高度に発達した都市文明としての性格を色濃くもっていた。
西アジア・北アフリカの都市周辺の農村では、灌漑農業が発達して、小麦、大麦などの穀物や、ナツメヤシ、ブドウなどの果樹が栽培されていた。9世紀以降になると米の生産もさかんになり、サトウキビ、バナナ、オレンジなど、南アジアや東南アジア原産の農作物も栽培されるようになった。これらの農作物は、自給自足のためだけではなく、都市民に売る商品として生産され、農場の経営者は、1年契約の農場労働者を雇うなどして、経営にあたった。
都市は、都市民が生産する手工業製品と農産物の取引を中心とする地域経済の中心であったが、同時に、都市間交易や遠隔地交易の拠点でもあった。遠距離の大規模な商取引のために、共同出資や小切手・手形といった決済手段などの商業システムが、イスラーム法のもとで整備された。交易網はイスラーム世界をこえて、東南アジア、中国、アフリカ、ヨーロッパにもムスリム商人が進出し、イスラーム法が国際取引の法として機能した。
イスラーム世界の中心となる大都市の人口は数十万人規模で、人口十数万人から数万人規模の都市は各地に数多くあった。都市の中心部にはモスク(mosque, 礼拝所)と常設店舗市があり、隣接して外部から訪れる商人のための隊商宿(キャラヴァンサライ karvansaray)、町の人や旅人が利用する公衆浴場や公衆便所があった。
住宅や店舗は賃貸物件が多かった。支配者や裕福な商人は、賃貸アパートや賃貸商店街を建設したが、それを私有せずに公共のための信託財産(ワクフ waqf)とした。モスクやマドラサ(学院)、道路などの公共施設は、ワクフからの収入によって維持されていた。
【マドラサとウラマー】
ギリシア語による学問をアラビア語で発達させた分野を、イスラーム世界では「外来の学問」とよんだ。これとは別に、イスラーム法学を中心とする「固有の学問」とよばれた領域があった。法の基礎である『クルアーン』(コーラン)がアラビア語で記されているため、アラビア語の文法学と詩学が、固有の学問の基礎であった。さらに、クルアーン解釈学やムハンマドの言行などの伝承(ハディース)を学ぶ伝承学が発達し、それらを基盤として法学があった。スンナ派では、四つの法学派が成立し、それぞれがたがいを認めながらも、独自な法学体系をつくっていった。また、イスラーム世界の歴史を学ぶ歴史学も発達し、タバリー(Tabari, 839~923)は『預言者たちと諸王の歴史』を編纂し、イブン=ハルドゥーン(Ibn Khaldun, 1332~1406)は『世界史序説』を著して、「文明の民(都市民)と粗野な民(荒野の民)との関係を通じて歴史が展開する」という独自の歴史理論を展開した。ガザーリー(Ghazali, 1058~1111)が神秘主義を理論化したことにより、神秘主義も学問の一つの領域となった。
法学を中心に、固有の学問を教授する機関としてマドラサ(madrasa)が、11世紀ごろから各地に設けられた。シーア派のマドラサであったカイロのアズハル学院も、アイユーブ朝の時代からは、スンナ派の学院として名声を誇った。マドラサで学問を修めた者はウラマー(ulama, 宗教知識人)とよばれ、裁判官(カーディー)、教師、礼拝の指導者などをつとめ、社会のエリートとして大きな影響力をもった。
マドラサの講義は、イスラーム世界全体で共通していて、どこで学んでも、同じ教養を身につけることができた。同じ教養をもち、同じ方法論で法判断をするウラマーの存在が、政治的な分裂にもかかわらず、イスラーム世界が一体性を維持してきた最大の要因であった。教養あるウラマーになるためには、なるべく多くの地域で学ぶことが望まれ、また教養あるウラマーは各地を遍歴して教えていた。『三大陸周遊記』で知られるイブン=バットゥータ(Ibn Battuta,
1304~68/69)は、イスラーム的知識人であるウラマーの一人である。
【イスラーム世界の芸術】
文学では、詩が著しく発達した。アラビア語の詩に加えて、9世紀後半からはペルシア語の詩がさかんにつくられ、四行詩の『ルバイヤート』を著したウマル=ハイヤーム(Umar Khayyam, 1048~1131)など、多数の詩人が輩出した。散文学では『千夜一夜物語(アラビアン=ナイト)』など大衆文芸が好まれた。
美術面では、偶像崇拝を否定するイスラーム教の影響から、絵画や彫刻などの造形美術は未発達であった。アラベスク(arabesque)とよばれる幾何学的な紋様が、建造物、陶器、書籍などを飾り、絵画ではミニアチュール(miniature, 細密画)が広まった。建築ではイスラーム文明を代表する芸術として発展し、高度な技術を駆使したドームと優雅な尖塔(ミナレット)を特徴とするモスクや墓廟が、多数建てられた。
<『千夜一夜物語(アラビアン=ナイト)』>
16世紀のマムルーク朝の時代までに現在の形となったアラビア語の長大な説話集。アッバース朝のハールーン=アッラシードなど、実在の人物も登場する。
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、132頁~135頁)
【8世紀の世界 文明世界の成立】
古代の帝国が民族移動などで解体したのち、8世紀にはふたたび広大な領域を支配する帝国が繁栄し、その帝国を中心として一つの文明を共有する広域の文明世界が成立した。東アジアには儒教・仏教の唐が、中央アジアから北アフリカにはイスラーム教のアッバース朝が、東ヨーロッパにはキリスト教のビザンツ帝国が栄え、それぞれ東アジア世界、イスラーム世界、東ヨーロッパ世界が形成された。また、フランク王国は、イスラーム勢力の侵攻を防ぎ、ビザンツ皇帝と対立するローマ教会との結びつきを強めて西ヨーロッパ世界をまとめていった。
唐は周辺諸国に大きな影響を与え、東アジア諸国は律令、漢字、儒教、仏教などを受容した。首都の長安は、諸外国の使節や留学生のほか、ソグド人、イラン人、アラブ人などの商人が訪れ、仏教、ゾロアスター教、マニ教、ネストリウス派キリスト教などの寺院も建てられた国際都市となった。広大な領域を支配したアッバース朝のもとではイスラーム法にもとづく統治がめざされ、さまざまな学問の研究がすすめられた。また、ムスリム商人は、ユーラシア大陸、アフリカ大陸の陸上交易や、インド洋、南シナ海の海上交易で活躍した。首都バグダードは学芸の中心地であるとともに、世界各地の物産が市場(バザール)の店頭を飾る国際都市として栄えた。ビザンツ帝国は、皇帝が教会を支配する独自の世界をきずいた。首都コンスタンティノープルは、絹織物など各種の手工業や商業がさかんで、貨幣経済は繁栄をつづけ、国際的な交易都市として栄えた。
<アーヘンの大聖堂>
ベルギーに近接するドイツ北西部の都市。フランク王国のカール大帝がしばしばこの地に滞在し、王宮、大聖堂を建てた。
<聖(ハギア)ソフィア大聖堂>
ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルに6世紀に建てられた円蓋のある大聖堂。円蓋の直径は32mにも達する。
<ウマイヤ=モスク>
8世紀前半にダマスカスに完成した現存する世界最古のモスク。もとはキリスト教の教会であったが、モスクとして増改築された。
<唐を訪れた外国使節>
唐の都長安には遠方より多くの使節が貢ぎ物をささげてやってきた。左の3人は接待をしている唐の役人で、右の3人が外国使節。黒服の人物はビザンツ帝国のの使者、その右が新羅の使者と考えられている。
<新羅の古墳公園>
新羅は7世紀後半に百済、高句麗を倒して半島全域を統一した。唐の冊封を受け、中国の制度を導入し、仏教文化を開花させた。
<遣唐使船>
7世紀前半にはじまった遣唐使は、唐の文化や政治制度の摂取に努めた。小型の4隻の船で渡航するのが一般的であった。
※なお、「8世紀の世界」の地図には、シャイレンドラ朝のボロブドゥールが記されている!
(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、136頁~137頁)
イスラーム文化の記述~『詳説世界史』(山川出版社)より
第Ⅱ部 第Ⅱ部概観
第4章 イスラーム世界の形成と発展
1 イスラーム世界の形成
2 イスラーム世界の発展
3 インド・東南アジア・アフリカのイスラーム化
4 イスラーム文明の発展
第Ⅱ部 第Ⅱ部概観
第4章 イスラーム世界の形成と発展
1 イスラーム世界の形成
【イスラーム教の誕生】
アラビア半島は大部分が砂漠におおわれ、アラブ人は各地に点在するオアシスを中心に古くから遊牧や農業生活を営み、隊商による商業活動をおこなっていた。6世紀後半になると、ササン朝とビザンツ帝国とが戦いをくりかえしたために、東西を結ぶ「オアシスの道」は両国の国境でとだえ、ビザンツ帝国の国力低下とともに、その支配していた紅海貿易も衰えた。そのため「オアシスの道」や「海の道」によって運ばれた各種の商品は、いずれもアラビア半島西部を経由するようになり、メッカの大商人はこの国際的な中継貿易を独占して大きな利益をあげていた。
この町にうまれたクライシュ(Quraysh)族の商人ムハンマド(Muhammad, 570頃~632)は、610年頃唯一神アッラー(Allah)のことばを授けられた預言者であると自覚し、さまざまな偶像を崇拝する多神教にかわって、厳格な一神教であるイスラーム教(Islam)をとなえた。しかし富の独占を批判するムハンマドはメッカの大商人による迫害をうけ、622年に少数の信者を率いてメディナに移住し、ここにイスラーム教徒(ムスリム Muslim)の共同体(ウンマ umma)を建設した。この移住をヒジュラ(hijra 聖遷)という。
630年、ムハンマドは無血のうちにメッカを征服し、多神教の神殿であったカーバ(Kaba)をイスラーム教の聖殿に定めた。その後アラブの諸部族はつぎつぎとムハンマドの支配下にはいり、その権威のもとにアラビア半島のゆるやかな統一が実現された。
イスラーム教の聖典『コーラン(Quran)』は、ムハンマドにくだされた神のことばの集成であり、アラビア語で記されている。その教義の中心はアッラーへの絶対的服従(イスラーム)であるが、そのおきては信仰生活だけではなく、政治的・社会的・文化的活動のすべてにおよんでいる。後世の学者たちが、ムスリムの信仰と行為の内容を簡潔にまとめたものが六信五行である。
【イスラーム世界の成立】
ムハンマドの死後、イスラーム教徒は共同体の指導者としてアブー=バクル(Abu Bakr 在位632~634)をカリフ(caliph)に選出した。アラブ人はカリフの指導のもとに大規模な征服活動(ジハード jihad<聖戦>)を開始し、東方ではササン朝を滅ぼし、西方ではシリアとエジプトをビザンツ帝国から奪い、多くのアラブ人が家族をともなって征服地に移住した。しかし、まもなくカリフ権をめぐってイスラーム教徒間に対立がおこり、第4代カリフのアリー(Ali 在位656~66)が暗殺されると、彼と敵対していたシリア総督のムアーウィヤ(Muawiya 在位661~680)は、661年ダマスクスにウマイヤ朝(Umayya 661~750)を開いた。アブー=バクルからアリーまでの4代のカリフを一般に正統カリフ(632~661)という。(下略)
(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、100頁~103頁)
4 イスラーム文明の発展
【イスラーム文明の特徴】
イスラーム帝国は、古くから多くの先進文明が栄えた地域に建設された。イスラーム文明は、これらの文化遺産と、征服者であるアラブ人がもたらしたイスラーム教とアラビア語とが融合してうまれた新しい都市文明である。バグダードやカイロなど大都市に発達したこの融合文明は、同時にイスラーム教を核とする普遍的文明であった。そのためこの文明はイスラーム世界のいたるところで受け入れられ、やがて各地の地域的・民族的特色を加えて、イラン=イスラーム文化・トルコ=イスラーム文化・インド=イスラーム文化などが形成された。
中世ヨーロッパはイスラーム教には敵対したが、11~13世紀にかけてスペインのトレドを中心に、アラビア語に翻訳された古代ギリシアの文献やアラビア科学・哲学の著作をつぎつぎとラテン語に翻訳し、これを学びとることによって12世紀ルネサンスを開花させた。イスラーム文明は、ギリシア文明をヨーロッパ文明へと橋渡しするうえでも、重要な役割をはたしたのである。
【イスラームの社会と文明】
西アジアのイスラーム社会は都市を中心に発展した。各地の都市には軍人・商人・職人・知識人などが住み、信仰と学問・教育の場であるモスクや学院(マドラサ)、および生産と流通の場である市場(スークあるいはバザール)を中心に都市生活が営まれた。またイスラーム帝国の成立によって、これらの都市を結ぶ交通路が整備され、このネットワークをつうじて新しい知識や生産の技術が、短期間のうちに遠隔の地へ伝えられたことが特徴である。
とくにパピルスや羊皮紙にかわる紙の普及は、イスラーム文明の発展にはかり知れないほどの影響をおよぼした。タラス河畔の戦いを機に唐軍の捕虜から製紙法を学んだイスラーム教徒は、サマルカンド・バグダード・カイロなどに製紙工場を建設し、やがてこの技術はイベリア半島とシチリア島を経て、13世紀頃ヨーロッパに伝えられた。
また10世紀以後のイスラーム社会では、都市の職人や農民のあいだに、形式的な信仰を排して神との一体感を求める神秘主義(スーフィズム sufism)が盛んになった。12世紀になると、聖者を中心に多くの神秘主義教団が結成され、教団員はムスリム商人の後を追うようにして、アフリカや中国・インド・東南アジアに進出し、各地の習俗を取り入れながらイスラームの信仰を広めていった。
イスラーム文明の担い手は、都市に住む人々とこれらの神秘主義者たちであった。またカリフやスルタンをはじめとする支配者たちがモスクや学院を建設し、これらの建物に土地や商店の収入をワクフ(waqf)として寄進することによって文化活動を積極的に保護したことも、イスラーム文明の発展をうながす要因の一つであった。
【学問と文化活動】
最初に発達したイスラーム教徒の学問は、アラビア語の言語学と、『コーラン』の解釈に基づく神学・法学であった。その補助手段として数多くの伝承(ハディース)が集められ、それが歴史学の発達をうながした。9~10世紀の歴史家タバリー(Tabari, 839~923)は年代記形式の大部な世界史『預言者たちと諸王の歴史』を編纂し、14世紀の歴史学者イブン=ハルドゥーン(Ibn Khaldun, 1332~1406)は『世界史序説』を著して、都市と遊牧民との交流を中心に、王朝興亡の歴史に法則性のあることを論じた。
イスラーム教徒の学問が飛躍的に発達したのは、9世紀初め以後、バグダードの「知恵の館」(バイト=アルヒクマ)を中心に、ギリシア語文献が組織的にアラビア語に翻訳されてからである。彼らはギリシアの医学・天文学・幾何学・光学・地理学などを学び、臨床や観測・実験によってそれらをさらに豊富で正確なものとした。インドからも医学・天文学・数学を学んだが、とくに数学(のちのアラビア数字)と十進法とゼロの概念を取り入れることによって、独創的な成果をあげることができた。フワーリズミー(Khwarizmi, 780頃~850頃)らは代数学と三角法を開発し、これらの成果は錬金術や光学でもちいられた実験方法とともにヨーロッパに伝えられ、近代科学への道を切り開いた。また、『四行詩集』(『ルバイヤート』)の作者ウマル=ハイヤーム(Umar Khayyam, 1048~1131)は数学・天文学にもすぐれ、きわめて正確な太陽暦の作成に関わった。
イスラーム教徒はギリシア哲学、とくにアリストテレスの哲学を熱心に研究した。イスラーム思想界は、10世紀以後しだいに神秘主義思想の影響を強くうけるようになったが、信仰と理性の調和はよく保たれていた。それは神学者がギリシア哲学の用語と方法論を学び、合理的で客観的なスンナ派の神学体系を樹立したからである。イスラーム信仰の基礎として神秘主義を容認したガザーリー(Ghazali, 1058~1111)は、このような神学者の代表である。また哲学の分野では、ともに医学者としても有名なイブン=シーナー(Ibn Sina, 980~1037; ラテン名アヴィケンナ Avicenna)とイブン=ルシュド(Ibn Rushd, 1126~98; ラテン名アヴェロエス
Averroes)がいる。
文学では、詩の分野が大いに発達し、説話文学も数多く書かれたが、アラブ文学を代表する『千夜一夜物語』(『アラビアン=ナイト』)は、インド・イラン・アラビア・ギリシアなどを起源とする説話の集大成であり、16世紀初め頃までにカイロで現在の形にまとめられた。また、メッカ巡礼記を中心とする旅の文学も盛んであり、イブン=バットゥータ(Ibn Battuta, 1304~68/69または77)はモロッコから中国にいたる広大な世界を旅して、帰国後、口述筆記によるアラビア語の『旅行記』(『三大陸周遊記』)を残した。
ミナレット(光塔)をもつモスク建築は、イスラーム世界に固有な都市景観をうみだしたが、美術・工芸の分野では繊細な細密画(ミニアチュール)や象眼をほどこした金属器、また装飾文様として唐草文やアラビア文字を図案化したアラベスク(arabesque)が発達した。
(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、115頁~119頁)
英文の記述~本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』(講談社)より
イスラーム文明
Part 2 Interconnecting Regional Worlds
Chapter 8 :Formation of the Islamic World
1 Establishment of the Islamic World
3 Islamic Civilization
1 Establishment of the Islamic World
■The Prophet Muhammad
It was Muhammad(ムハンマド), a native of Mecca in Arabia, who first preached Islam in the
7th century. In the Arabian peninsula, people introduced the technology using groundwater for
irrigation in the 1st millennium BC, and established oasis to live on agriculture in various
parts of Arabia, and because of this, cities developed there as well. At almost the same time,
nomads began to breed camels and engaged in caravan trade in cooperation with the
people of the city. When the monotheistic religions such as Judaism and Christianity had
been transmitted to Arabia since the 4th century, the majority of Arabs(アラブ人), residents of
Arabia, were polytheists who believed in various gods.
Mecca was one of the holy lands of Arabian polytheists, and various gods were enshrined
at the Kaaba(カーバ神殿) in Mecca. Qurayshi people(クライシュ族) in Mecca had become
merchants by organizing caravan trade since the middle of the 6th century and had made a society
centered on commerce.
Muhammad, a Quraysh merchant who believed in the one God(Allah[アッラー] in Arabic),
the same as the one God in Judaism and Christianity (Yahweh in Hebrew), called himself a prophet
after receiving revelation from Allah. He then preached faith in Allah. However, very
few people in Mecca followed his religion, and Muhammad, along with his followers,
were persecuted for their beliefs. Because of this, Muhammad and his followers moved
to Medina (メディナ Yasuribu ヤスリブ) in 622 (hijra[Hegira] ヒジュラ[聖運]). Muhammad
established Islam(イスラーム教) as a new monotheistic religion in Medina, defining unique rituals,
such as praying toward the Kaaba in Mecca. A follower of Islam is called a Muslim(ムスリム).
Muhammad created a Muslim community (umma ウンマ) in Medina, returned to Mecca and
conquered it in 630, placing most of the Arabian peninsula under his political influence in the
following year.
■Conquest by Muslims
After Muhammad died of illness in 632, Muslims made a system that allowed all
members to choose his successor (Caliph カリフ). They then swore allegiance to that person,
thus maintaining unity. The first four Caliphs chosen in this way were called the “Rightly Guided
Caliphs(正統カリフ)”.
Arabs, who became Muslims during this period, embarked on conquest (jihad [holy war]
ジハード[聖戦]) beyond the Arabian peninsula. In those days, Sassanian Persia and the Eastern Roman
Empire battled against each other repeatedly, exhausting themselves in the process. The
Muslim army defeated Sassanian at the Battle of Nahāvand(ニハーヴァンドの戦い) in 642 and
annexed its territory. The Muslim army then attacked Syria and Egypt just after the Eastern Roman
Empire recaptured them from the Sassanians and conquered the lands. Thus a huge empire where
Arabic Muslims ruled over many ethnic groups and believers of various religions was
created.
The Muslim army established military towns (misr ミスル) in the key areas of the land they
conquered. They received tax revenues from the conquered areas in the form of pensions
(ata アター), and continued conquest activities led by a Caliph-appointed Governor-General. The
conquered ethnic groups were guaranteed autonomy, safety, and were allowed to keep their
property as well as retain their own traditional faiths; such as Judaism and Christianity; but
they had to pay poll taxes (jizya ジズヤ) and land taxes(kharaj ハラージュ).
■From the Umayyad to the Abbasid
When Ali(アリー), the 4th Rightly Guided Caliph, was assassinated in 661, Muawiyah
(ムアーウィヤ) of the Umayyad, who was the Governor-General of Syria at the time and was
opposed to Ali, took up the position of the Caliph in Damascus. The Umayyad went on to
monopolize the post of caliph for generations to build the Umayyad dynasty(ウマイヤ朝).
During the Umayyad period, the Muslim army kept conquering from Central Asia in the east to
the Iberian peninsula in the west. This dynasty issued original gold and silver coins to link areas
which had been divided into the Eastern Roman Empire and the Sassanid until then, and made
a large, vast trade zone. Moreover, it established Arabic(アラビア語) as the official language
and built the foundation of the Islamic world…
(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、96頁~97頁)
3 Islamic Civilization
■Cities and Commerce in the Islamic World
Islam, born in Mecca in the Arabian peninsula in the 7th century, had no thought of
despising commerce in the beginning. Even after becoming main religion in West Asia
and North Africa, where the commerce had highly developed since Ancient Oriental
civilization, Islam evolved as a religion that respected the ethics, such as fair trade, of the
merchant. Since one of the main duties of Muslims was to go on a pilgrimage to Mecca, the
rulers in the Islamic world could not forbid Muslims to move for purpose of pilgrimage.
The pilgrimage route to Mecca, crisscrossing the Islamic world, was also the route for
commerce, and a road of the trip to seek learning. The rulers were expected to ensure the
safety of pilgrimage routes to promote free movement of people, things and information.
The Islamic civilization supported by Islam had a strong character as a highly developed
urban civilization(都市文明) with a focus on commerce.
In rural villages around cities in the Islamic world of West Asia and North Africa,
irrigated agriculture progressed, and grains such as wheat and barley, and fruits such as
dates and grapes, were being cultivated. Since the 9th century, cultivation of rice also
became active, and agricultural crops of South Asian or Southeast Asian origins such
as sugar cane, bananas and oranges were also being cultivated. These agricultural crops
were produced not only for self-sufficiency but also for sale, and the owners of the farms
employed farm workers under one-year contracts to manage farming.
The city was the center of the regional economy where people traded agricultural
products and handicrafts made by city folk. It was also a base for trade between cities
or with the outlands. The commercial systems, such as joint investments or methods
of payment using checks and bills, were improved for long-distance and large-scale
commercial trade under Islamic law. The trade network was extended outside of the
Islamic world. Muslim merchants(ムスリム商人) would advance to Southeast Asia, China,
Africa, and Europe, and Islamic law functioned as the law of international trade.
Population of large cities, which were the center of the Islamic world, was in hundreds
of thousands; there were many cities with the population of between tens of thousands and
well over a hundred thousand in various places. There were mosques(モスク
places of worship) and permanent market shops at the center of city. Caravanserai
(隊商宿 karvansaray[キャラヴァンサライ]) for merchants coming from outside, and public
baths and toilets for city people and travelers were located next to them.
Most of the houses and stores were rented. Although the rulers and the rich merchants
built apartments and shopping districts for rent, they made them into public trust assets
(waqf ワクフ) without owning them privately. Public facilities, such as mosques, madrasas
(マドラサ institute[学院]), roads, etc. were maintained by the income from waqf.
■Madrasa and Ulama
Some fields of studies, which had originally been in Greek and were developed in
Arabic, were called “foreign studies(外来の学問)” in the Islamic world. Apart from that,
there was a field called “specific studies(固有の学問)” with a focus on Islamic law. Since
the Quran which was the base of law, was written in Arabic, Arabic grammar and poetics
were the base of specific studies. In addition, the study of the Quran and the lore, sayings
and doings of Muhammad (hadith ハーディス) as the base of law, had evolved. For the
Sunni, four law schools were established and they accepted each other but made their own
separate original law systems. In addition, historiography, the learning of the history of
the Islamic world, made progress as well. Tabari(タバリー) compiled History of the
Prophets and the Kings(預言者と諸王の歴史), and Ibn Khaldun(イブン=ハルドゥーン),
representing Introduction to World History(世界史序説), explicated his original theory
of history, namely, “history is expanded through the relationship between the people
of civilization (urban people) and the people of savagery (wild people)”. Mysticism also
became one field of study theorized by Ghazali(ガザーリー).
Madrasas(マドラサ) were built as institutions to teach specific studies, mainly the study
of law, in many places since about the 11th century. The Al-Azhar institute(アズハル学院)
in Cairo, which had been built as a madrasa of the Shia, became proud of its reputation
as an institute of the Sunni since the days of the Ayyubid. People who learned at madrasa
were called ulamas(ウラマー intelligent persons), and served as judges, teachers, leaders
of worship, among other occupations, and were very influential as the elite of society.
As lectures in madrasas were common throughout the Islamic world, people were able
to acquire the same culture regardless of where they learned. The existence of ulamas who
had the same culture and made a legal judgment in the same methodology was the biggest
factor for the Islamic world to maintain the integrity in spite of its political divide. People
should better learn in many places to become cultured ulamas, and cultural ulamas went
to various places to teach. Ibn Battuta(イブン=バットゥータ) known for Rihla;
three continent tour(三大陸周遊記) was typical of the ulama who was an Islamic
intelligent person.
■Art of the Islamic World
Poetry evolved as literature remarkably. In addition to poetry in Arabic, much poetry was
also written in Persian since the second half of the 9th century, and a large number of poets
appeared one after another. For example, Umar Khayyam(ウマル=ハイヤーム), who wrote
Rubaiyat(ルバイヤート) of four-line poetry was one of them. In the field of prose,
mass literature including works such as Stories of the Thousand and One Nights
(Arabian Nights アラビアンナイト 千夜一夜物語) were preferred.
In terms of art, figurative art such as painting and sculptures did not progress because of
the influence of Islam, which prohibited the worship of idols. Geometric patterns
(called Arabesque[アラベスク]) decorated buildings, potteries and books. Miniature
(ミニアチュール) became popular in paintings. Architecture developed as an art
representing the Islamic civilization, and many mosques and Saints Mausoleums which
were characterized by domes and elegant steep towers (minaret ミナレット) were built,
making full use of advanced technology.
(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、105頁~107頁)
■World in the 8th century
After ancient empires were ruined by migrant movements and others, new
empires appeared again in the 8th century, which governed vast areas. Byzantine
Empire of Christianity, Abbasid dynasty of Islam and Tang dynasty of Confucianism
and Buddhism flourished. And three worlds centering around those empires were
formulated.
Frankish Kingdom 732 Battle of Tours-Poitiers
Byzantine Empire ~Constantinople
Abbasid dynasty 751 Battle of Talas Transmission of papermaking to West
Tang dynasty ~Chang’an
Southeast Asia Borobudur
(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、108頁~109頁)