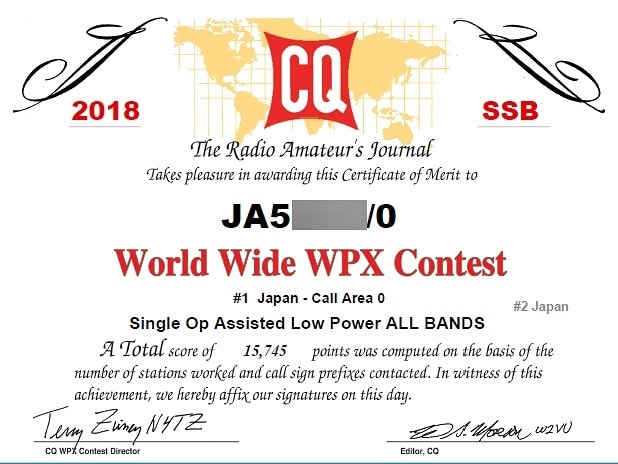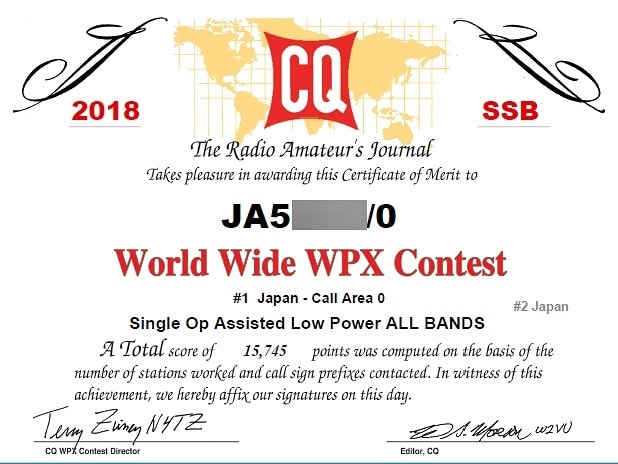前回の横手山山頂SOTA運用に続いて、先週末も
SOTA運用を目的に、上高井郡高山村の笠ヶ岳2,076m山頂に登りに行った。

今回は、HFでのCW運用が出来る様に、FT-817とPCをこんな感じにつないで運用の予定だ。
FT-817は5W出力だが、内臓バッテリーでは、2.5W以下でしか運用できないので、今回は、
JH0CJH局殿のブログの
こちらと
こちらの記事を参考に、18650のリチウムイオン電池4本を急遽Amazonで購入して持って行く事とした。

ちなみにCJH局殿はAmazonで3700mAHのバッテリー購入との事だが、残念ながら私が探した時は、品切れなのか3400mAHの物しかなかったので、これで作成した。
ダイオードは会社のごみ箱から拾ってきたPCのSW電源ユニットからブリッジダイオード(25A品)を部品取りして使用した。
ちなみに、FT-817用のリチウムイオン電池を使用した電池では、
6502.jpや
Wind Campで3セル構成の内臓タイプの物が有り、どちらにしようかとかなり悩んだ。
3セルの電圧で間に合うのか、4セルないとダメなのか?
そこでFT-817のVcc-Pow/Icc特性を計ってみた。

この測定結果から行くと、概ね12V以上ないと5Wを確保できない。3セルだと4V/セル、4セルだと3V/セル必要となる。
各メーカのセルの放電特性を確認する限り、0.5C放電だと、4Vは最初の15-30%しか確保できない。3V迄ならほぼ90-95%放電まで確保される。
結果として、全運用時間で5Wを目指すなら4セル必要。ただ2.5W迄なら9Vでも出るので、3セルでも5W~2.5W迄の運用と割り切れば、本体に内蔵できるのでそれなりのメリットはある。
まあ、5Wフルに出てるのと、少し下がって4W、3Wで運用しているのでは、相手のSレベルで1つ差が有るか無いかで大差ないのは判っているのだが、、、、、まあ5W出るならフルに出したいと言うのは人情か、、、
あと内蔵タイプは、セルサイズの都合で3000-3200mAHと多少容量が少なく運用時間が短くなるが、私の手に入れた3400mAHとは1割程度しか違わないので、運用時間的には大差ないと言った所か。
ちなみに、運用時間は、CQの空振りが多いと、送信1:受信1程度は考えておいた方が良いと思われ、私の用意した電池で3時間前後の運用時間が予想される。
SOTAの場合は、山頂までの登り下りの時間もあり、遅くまで山頂に居る事も少ない為、取り敢えずこれでどんな物か試してみると言った所だ。

↑前回の横手山から見た笠ヶ岳
さて、準備話が長くなったが、FT-817と18650電池、アンテナと釣り竿をもって山を目指す。

朝7時半過ぎに出て、一番頂上に近い登り口の峠の茶屋前に9時前に到着して、登山スタート。
笠ヶ岳の標高は2076mだが、峠の茶屋の標高は1903m程あり、山頂まで残り173m程だ。
これなら体力のない私にも登れそうだと選んだ次第である。

しかし、思った以上の急な登りが続く。階段になっている所も多いが、1段の段差も大きく、かなり息が切れる。
まあ無理は禁物。少し登っては切れる息を整えながらマイペースで登る。

頂上の少し手前では、先週降った雪が登山道に少し積もっていた。幸い緩んで溶けかけているので、何とか登る事も出来た。
普通は30分程度と言われているが、マイペースで40分ほどかけて登り、ようやく山頂に到着。

ここは、先週登った横手山と同じ山ノ内町と高山村の境界にある。
そんな訳で、前回と違うJCGから運用したかったので、山頂から出来るだけ南によって、高山村側からオンエアの準備をする。

と言う事で、今回はHF用に6m程度の釣り竿を立ててアンテナを立てた。
釣り竿の先端から電線をぶら下げて、無線機に付けたRHM8Bのコイル部の先端につないで、コイル部で同調を取る方式にした。

本当は、フルサイズDPとか、VCHアンテナとか用意したかったが、時間が無いので、今回はやっつけでこれにしました。
アンテナ設置・調整後、7MHzのCWで7.008MHzを確保して、SOTA Watch2にスポットしようとするが、携帯の電波がかなり不安定。
うまくマルチパスで強くなる所をピンポイントで探しながら、UPするが、なぜかfailedばかり返ってくる。
何度やっても上手くいかず、その内、他の局に周波数を取られてしまう。

実はこの時、間違ったSOTA番号でSPOT情報がアップ出来ていた事を後から後輩から聞いて知った。
家内にSPOTのUP方法を教えて、トライして貰い、私は、新たに7.005MHzを確保してCTESTWINでCWCQを出す。
5Wしか出力が出てないので、SPOT情報なしにSOTAチェイサーさんに見つけて貰うのはかなり厳しい。

山頂からの素晴らしい眺めを見ながら、空しく自分のCQだけが流れる。
しばらくするとCQの後に何か聞えてくるので呼ばれているかと思ったが、他の局同士のQSOの混信だったorz。
周波数を7.003MHzに変えて再びCQを出すもノイズも増えてきて何も応答がないままCQの連発。
なんだかんだ7MHzで1時間半近く掛かってボーズ状態。とても14/21MHzに出る気になれずに、せっかくの釣り竿も何も釣れないままお役御免で50MHzにQSY。
50MHzではRHM8Bに元から付いてるロッドアンテナを付けて約20%短縮1/4λホイップでCW/50.1975MHzでオンエア。

これも後から後輩から聞いたのだが、RBNにも7.003MHzと50.1976MHzで拾われていた様である。
そのせいか5分程CQを出すと、1局応答が有った。前橋の局長さんだ。
その後10分位CQを続けるが応答が無いので、あきらめて、今度は、50.2MHz/SSBでオンエア。
ちなみに、RBNに拾われると自動的にSOTA Watch2にも自動でUPされる様で、SOTA Watch2にも正しい情報がアップされていた。

50.2MHzでCQを出すと、先週の横手山でお相手頂いた長野市内の局長さんに呼ばれた。

↑前回登った横手山も良く見える。
その次に呼ばれたのは、なんと40年前の78年に四国常置場所から50MHzAMで交信した局長さんだった。いや~大昔にお会いした人にこんな所で再会するとは面白いものである。
その後も2局程呼ばれて、都合SSBで4-QSO、CWで1-QSOで5-QSOとなる。ちなみに長野の局長さんたちは、私が最近さぼっている、6mAMロールコールに参加している局長さんが多かったので、また今度ロールコールも参加しなければ、、、
さて当初予定は、12時までに終えて撤収予定だったが、既に12時をだいぶ回っていたので、早々に片づけて山頂を後にした。

降りてくると、行きには閉まっていた茶屋が開いていたので、お昼にキノコうどんを頂く。
ここの道路も11月6日から冬季閉鎖で、営業はこの日までだとか。
ちなみにうどんは本場さぬきの腰の有る麺とはいかないが、キノコのねっとり感満載のスープがなかなか美味しかった。
茶屋を出て帰途に就く途中で、行きに見かけた温泉「滝の湯」に寄った。

余り良く見ずに、すぐに露天風呂に入ったのだが、良く見ると露天風呂の途中に女湯と書かれたドアが有る。
これはひょっとして混浴?
と思ってると、おばさんがワンピース状の湯あみを着て入って来た。
先に旦那さんが入っていて、そちらと合流していた。
同じ様な感じで、結局3名ほど女性が入って来た。
皆さん40~50代位の感じだが、、、、

お風呂を出る時に見たらしっかり、露天風呂は混浴と書かれていた。
出る時に受付で聞いたら、ワンピースタイプの湯あみは貸し出している訳ではなく、自前で持参した物らしい。
別にバスタオルを巻けば入れるようでバスタオルの貸し出しもやっていたが、なぜかバスタオルで入る女の人はいなかった。
まあ安心感がだいぶ違うだろうけどね。
と言う訳で、今回はHFも出られる準備をしていったが、思う様にSPOT情報をアップ出来ずにHFでの交信は成立しなかった。
次回は、もう少しアンテナを何とかして、HFで交信したい物だ。
ちなみに電池は3時間程使ったが、まだ送信時に12V位の電圧が残っており、まだ暫く使えそうだった。
2018.11.04 (11/6 UP)