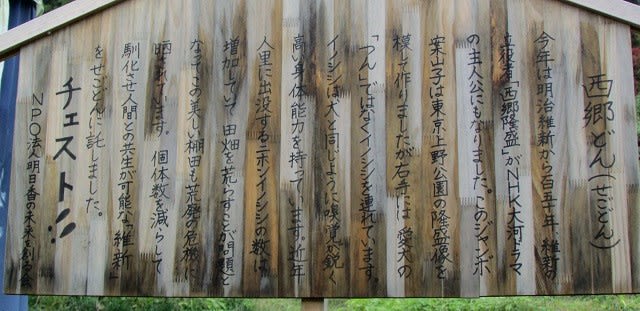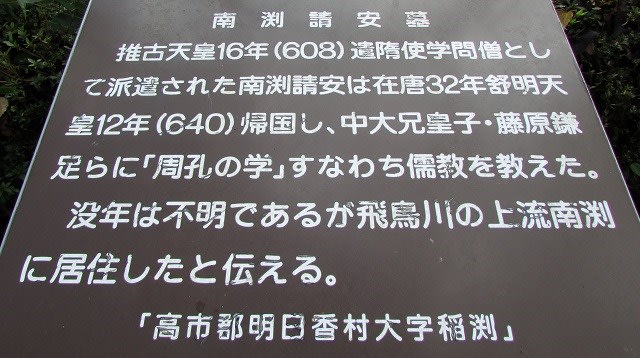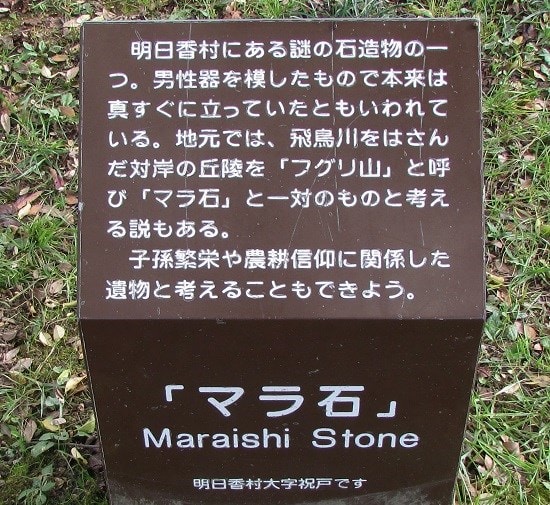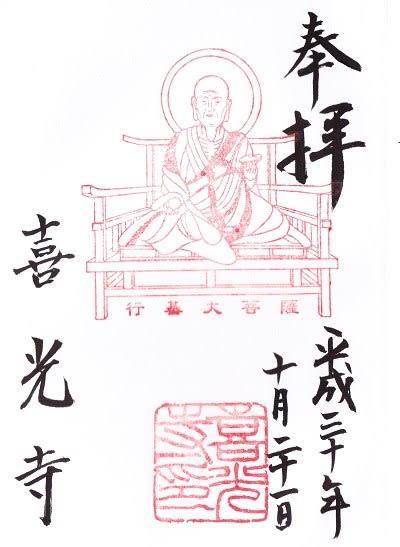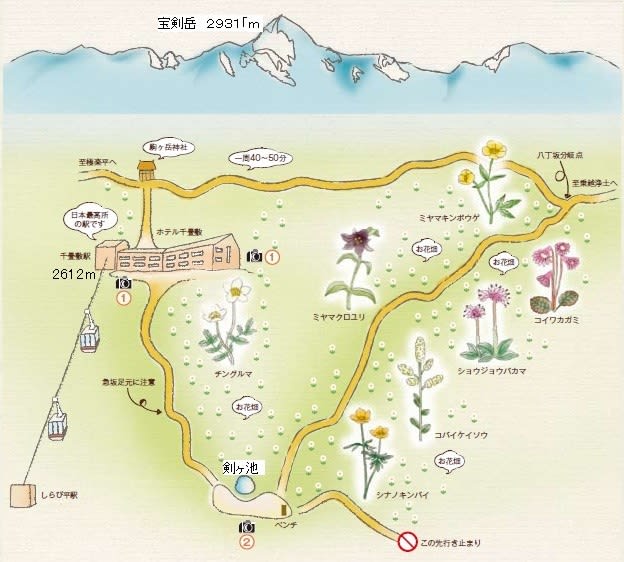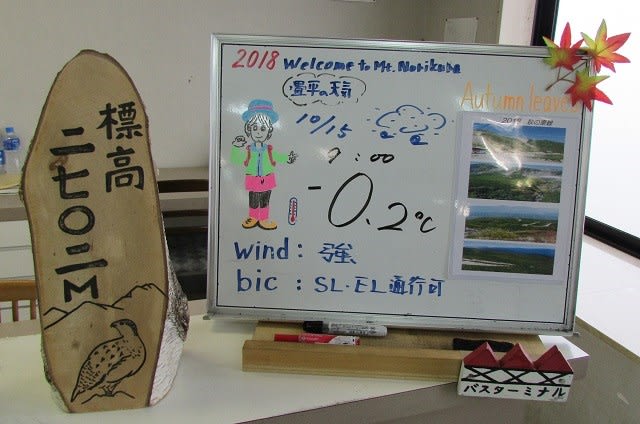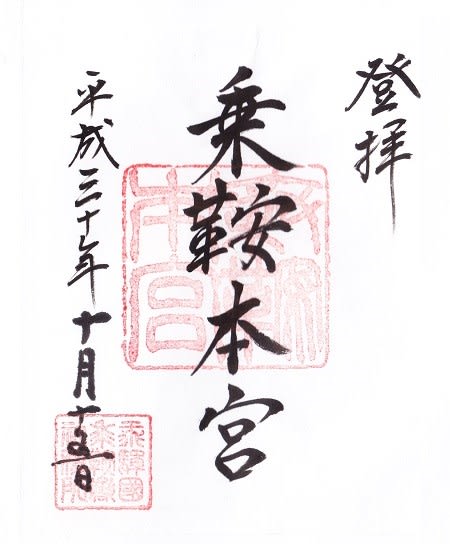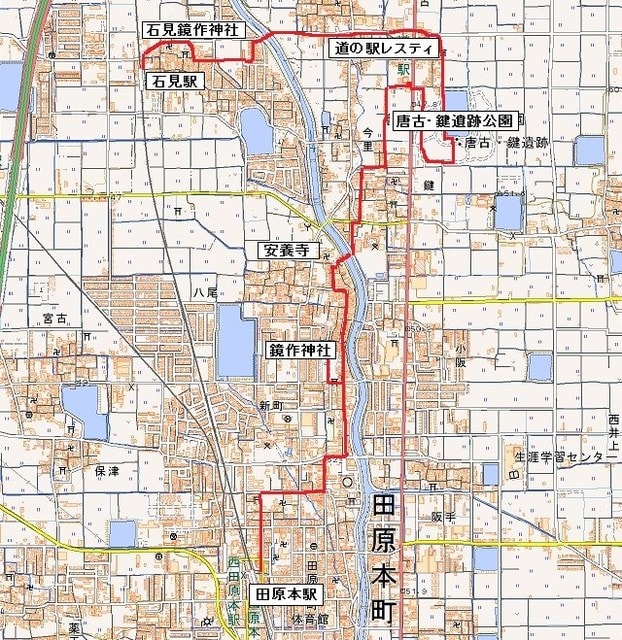5月30日(木)、青もみじを観に「東福寺」に、秋の紅葉シーズンとは異なり人出は少なかったです
若干順序はことなるのですが、国宝の「三門」、現存する最古最大の三門とのこと、立派です・・・・

猫のいる大涅槃図で知られる「本堂」です

京都を代表する紅葉の名所「通天橋」、今は青もみじが・・・・

通天橋のたか婆

庭は、青・青・青・・・・です


「開山堂」、庭園は江戸中期の名園です・・・・・

八角形の優美な「愛染堂」、南北朝時代の建築だそうです

「東福寺方丈」、東西南北の四庭が配され、「八相の庭」と称されています・・・・

「東庭」、北斗七星に見立てた石を配し「北斗の庭」と呼ばれています

「南庭」、八相の庭の中心的存在で、蓬莱・方丈・えいじゅう・こりょう・八海・五山が配されています

「西庭」、古代中国の田制「井田」に因み「井田市松」よばれています

西庭から北庭への途中から眼下に渓谷「洗玉澗」を一望します・・・

「北庭」、コケの緑と敷石の市松模様が有名です

最後に、庭の片隅にお地蔵さんが・・・・

「偃月橋」、三の橋川に架かる木造橋で通天橋と臥雲橋とともに東福寺三名橋と呼ばれています

最後にもう一度、青もみじを

行くのが1ヵ月位遅く、たか婆のイメージする「青もみじ」は濃くなりすぎていましたが・・・
若干順序はことなるのですが、国宝の「三門」、現存する最古最大の三門とのこと、立派です・・・・

猫のいる大涅槃図で知られる「本堂」です

京都を代表する紅葉の名所「通天橋」、今は青もみじが・・・・

通天橋のたか婆

庭は、青・青・青・・・・です


「開山堂」、庭園は江戸中期の名園です・・・・・

八角形の優美な「愛染堂」、南北朝時代の建築だそうです

「東福寺方丈」、東西南北の四庭が配され、「八相の庭」と称されています・・・・

「東庭」、北斗七星に見立てた石を配し「北斗の庭」と呼ばれています

「南庭」、八相の庭の中心的存在で、蓬莱・方丈・えいじゅう・こりょう・八海・五山が配されています

「西庭」、古代中国の田制「井田」に因み「井田市松」よばれています

西庭から北庭への途中から眼下に渓谷「洗玉澗」を一望します・・・

「北庭」、コケの緑と敷石の市松模様が有名です

最後に、庭の片隅にお地蔵さんが・・・・

「偃月橋」、三の橋川に架かる木造橋で通天橋と臥雲橋とともに東福寺三名橋と呼ばれています

最後にもう一度、青もみじを

行くのが1ヵ月位遅く、たか婆のイメージする「青もみじ」は濃くなりすぎていましたが・・・