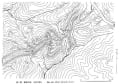日に日に暖かさが増していく今日この頃、城歩きのベストシーズンも終わりに差しかかりつつありますが、当会では令和4年度(2022年度)最後の見学会となる若狭・近江湖北方面の代表的な山城である後瀬山城・国吉城、玄蕃尾城・田上山城の見学会を下記のとおり企画いたしました。
この1泊見学会は、もともと令和元年度(令和2年5月)に計画していたものですが、コロナ禍により延期を重ね、この度ようやく4年ぶりに開催する運びとなったものです。
会員の皆様は勿論、会員外の皆様の参加も大歓迎いたしますので、多数の皆様のご参加をお願いいたします。
記
○見学会のねらい
現在の福井県西部にあたる旧若狭国の守護であった武田氏に由来する後瀬山城、国吉城、賤ヶ岳の合戦の陣城である玄蕃尾城、田上山城を訪ね、「織豊系城郭」成立前後の城郭の縄張りの特徴と変遷について考察する。
○実施日 令和5年(2023) 5月13~14日(土~日)
○見学地 【1日目】後瀬山城(小浜市)、国吉城(美浜町)
【2日目】玄蕃尾城(敦賀市・長浜市)、田上山城(長浜市)
○宿泊地 東横INN敦賀駅前(℡ 0770-20-1045)
○担当者 望月保宏・大木一幸
○参加費 会員25,000円、一般26,000円(資料館入館料、懇親会費含む)
○バス 市沢さんのバス
○乗車地 静岡駅北口一般車ロータリーの音楽観AOI側、東名日本坂PA、小笠PA、三方原PA
○身支度 ハイキング程度の服装(滑りにくい靴、雨具)、初日昼食弁当・飲み物類
○申込み 3月31日(金)までに、氏名・連絡先(携帯電話のある方は携帯電話番号)・乗車場所を明記の上、
静岡古城研究会事務局メール s-kojouken@outlook.com まで
○日程(予定)
【1日目:5月13日(土)】
7:30 静岡駅北口集合、出発
7:40 東名静岡IC
7:50 日本坂PA
8:20 小笠PA
8:40 三方原PA
(東名→名神→北陸道→若狭鶴舞道)
11:45 小浜IC
12:00~14:00 後瀬山城見学(昼食)
15:00~17:00 国吉城歴史資料館・国吉城見学
18:00 ホテル着
19:00~20:30 懇親会(ホテル近く「地魚料理 まるさん屋」120分飲み放題)
【2日目:5月14日(日)】
8:15 ホテル発
(玄蕃尾城入口バス駐車スペースから徒歩約50分)
9:30~11:00 玄蕃尾城見学
12:30~14:30 田上山城見学(昼食)
(見学後、木之本町散策、買い物 → 木ノ本駅)
15:30 木之本IC
(北陸道→名神→東名)
18:30 三方原PA
18:50 小笠PA
19:20 日本坂PA
19:30 東名静岡IC
19:40 静岡駅南口着、解散
*雨天決行、悪天候の場合又は時間の都合により、見学地・コースを変更することがあります。
○脚力レベル ★★★★☆(4/5)
※東名高速道路PAにて乗車希望の方は、赤い字のPAのいずれかを明記願います。
※またホテルの宿泊室で喫煙部屋を希望する際は、その旨も明記してください。(原則として禁煙部屋となります)
(主な見学地概要)
【後瀬山城】
大永2年(1522)に若狭守護第5代武田元光により築城されたことが文献上明らかになっている。
城跡は北西部に畝状竪堀や大規模な竪堀を配し、西部への防御を密にした縄張配置を行っている。これは、武田氏が若狭守護に任命されて以来確執のある丹後一色氏を意識していることが考えられる。
また、若狭を東西に通過する丹後街道を足下に置き、小浜湊を眼下に見下ろせる場所でもあり、日本海交易の主要港となっていた小浜湊の経済力を掌握する意図もあったものと思われる。
当山城跡の東稜上と北西稜上に配置される連郭群は切岸により区画されており、主要な部分において堀切を持っている。これらの連郭群は谷の横道と形容される連続した連絡道路により連結されており、情報交換施設として注目される。
永禄11年(1568)、越前朝倉氏の侵攻により武田元明が拉致されて以降一時荒廃するが、丹羽長秀の若狭拝領以降、城郭の再整備が実施されたと考えられる。この後、浅野長吉、木下勝俊と城は引き継がれ、慶長5年(1600)関ヶ原合戦の功により若狭国を拝領することになる京極高次が入城する。しかし、京極高次は北川と南川の河口に城郭(小浜城)の築城を開始し、後瀬山城は廃城となった。



【国吉城】
弘治2年(1556)、若狭国守護大名武田氏の家臣である粟屋越中守勝久は、三方郡佐柿の城山に国吉城を築いた。永禄6年(1563)、同城に越前朝倉氏の軍勢が攻め寄せたが見事撃退し、勝久は以後10年にわたって城を守った。元亀元年(1570)には織田信長の軍勢が入城し、同城から越前攻めに向かっている。
天正11年(1583)国吉城主となった豊臣秀吉の家臣木村常陸介定光は城の改修と町の整備に着手し、天正14年(1586)佐柿の町を開いた。
江戸時代に入り寛永11年(1634)に小浜城主となった酒井忠勝は、国吉城に替わって新たに町奉行所をつくり、三方郡と佐柿の町を治めた。城下町佐柿は丹後街道の宿場町として繁栄した。幕末には「天狗党の乱」に加わった水戸浪士の一部が准藩士屋敷に収容されている。
国吉城は近年、発掘調査や整備が進み、曲輪・石垣・土塁・堀切といった山城の構造物を見ることができる。また麓には、居館とみられる石垣も認められており、平時は居館で生活し、戦争時には山城に籠もるという、戦国時代の典型的な形態となっている。居館と山城の両方の遺構が現在でも残っている点は、全国的に見ても珍しい。




【玄蕃尾城】
福井県敦賀市刀根と滋賀県長浜市余呉町柳ヶ瀬の県境にあった山城である。天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いにおいて、柴田勝家の本陣が置かれた。平成11年(1999)7月13日に「玄藩尾城(内中尾山城)跡」として国の史跡に指定されている。また平成29年(2017)4月6日、「続日本100名城」(140番)に選定された。
同城は柳ヶ瀬山(中尾山)の尾根上に位置し、織田軍と朝倉軍が戦った刀根坂の戦いの舞台の刀根越(倉坂、久々坂ともいう)がすぐ南にある、また北国街道(現在の国道365号)を見下ろせる軍事上の要所に位置している。さらに南側の行市山には、中尾山と行市山を結ぶ軍道を整備したと伝わる勝家の家臣・佐久間玄蕃允盛政の砦があったという。賤ヶ岳の戦いの際に勝家・秀吉の両軍が布陣した山城の中でも、玄蕃尾城は空堀の深さ、土塁の高さが際立っており、また、現在においても、その遺構がよく残っている。また、定期的な草刈り整備が行われており、縄張り構造が非常によく分かる状態で維持されている。



【田上山城】
田上山砦は、天正11年(1583)3月に羽柴秀長によって築かれた。 天正10年(1582)6月本能寺に織田信長が斃れ、翌11年に近江湖北地方で羽柴秀吉と柴田勝家が織田家を二分して対峙した「賤ヶ岳の戦い」の際に築かれた陣城群の一つである。
玄蕃尾城に本陣を置いた柴田勝家に対し、弟秀長が陣取った田上山城が実際の秀吉軍本陣となった。天正11年4月20日夜に美濃大垣から駆け戻った秀吉は、田上山砦南側山麓にある木之本地蔵境内に陣取った。そして当地の美濃部勘右衛門に近隣の住民を集めさせ、田上山に登り味方の気勢を高めるため鯨波の声を挙げさせた。秀吉は勘右衛門らを案内に田上山を西に下り、賤ヶ岳北方の佐久間盛政軍に追撃を行い、この結果、盛政軍も含めた柴田軍は敗北し、越前を目指して潰走する。この賤ヶ岳の合戦で勝利した秀吉は天下人への階段を駈け上った。
田上山砦の縄張りは、山頂部に主郭を置き、Yの字状に伸びる尾根上に南の曲輪、北の曲輪、西の曲輪を配置している。 主郭と北の曲輪との間の堀切、北の曲輪の馬出を伴う虎口など、陣城としては結構複雑な縄張りとなっていて、城内・城外に15,000人もの軍勢を収容するのに十分な規模と思われる。