
お城のデータ
所在地 : 長浜市(旧・東浅井郡)湖北町丁野 map:http://yahoo.jp/lNAo
築城期:織豊期・ 元亀3年(1572)
築城者:中島宗右衛門直親
区 分 : 平山城
標 高:133.2m 比高差20m
遺 構 :主郭・副廓・囲い土塁、横堀、虎口、堀切、土橋
訪城日:2016.2.20
駐車場:(日本硝子独身寮の)に!
お城の概要

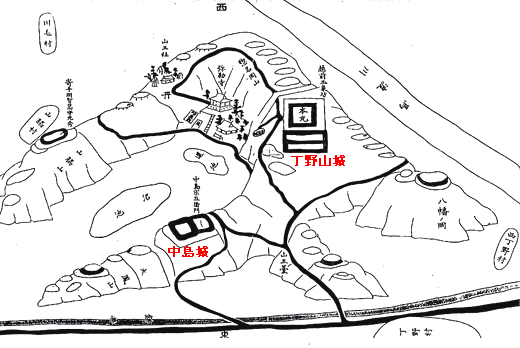 滋
滋
一般的に連郭式城郭の曲輪配置は、主曲輪を中心にして前後に曲輪を配していく。ところが曲輪が2つの小振りな城の場合、主曲輪の前面に副曲輪を置くのが常識である。これは主曲輪が直接敵の攻撃にさらされないことを配慮する当然の措置である。
この常識からすれば中島城は副曲輪(Bの曲輪)のある西側に敵を想定して築城されているのだが、西方には丁野山城が位置している。つまり、中島城は西方の丁野山城を敵方としていたことになる。




お城の歴史
丁野山城一帯は元亀4年の織田軍による小谷城攻め以降は、軍事的な緊張、および戦いはない。湖北では、唯一天正11年(1583)に賤ヶ岳の戦いがおこなわれているが、賤ヶ岳の戦いは余呉湖周辺の局地戦であるため、この中島城の遺構は元亀4年当時のものであると断定しても間違いはない。
だとすれば、丁野山城に立て籠もった朝倉氏に対して、中島城は織田軍が改修し丁野山城に対する付城として機能していたということになる。
付城といえば、元亀元年(1570)に姉川の戦いで敗れた浅井氏家臣の磯野員昌が佐和山城に籠城した時、織田軍が4つの付城を築いている。
また、天正6年(1578)高天神城の武田軍に対し、徳川家康が獅子ヶ鼻砦や小笠山砦、火ヶ峰砦など6つの付城を築いているが、いずれの場合も付城は1~3kmほどの距離で、丁野山城に対する付城・中島城の距離は異常に近い。
これは元亀4年当時、織田軍が浅井・朝倉軍に対して軍事的に極めて優勢であったことを物語っているのではないだろうか。
こう考えると、元亀4年8月12日に織田軍によって大嶽城を落とされただけで、田上山に陣取っていた朝倉義景が夜半に越前に向けて撤退した疑問も解ける。
元亀元年(1570)浅井氏が姉川合戦に敗れ、織田信長方に包囲されはじめると、小谷城の西に点々と分布する独立の山丘は、小谷城攻防にとって重要なものとなった。
織田信長は、元亀3年(1572)の小谷城攻めにおいて、小谷城根小屋のある清水谷の正面に位置する虎御前山に陣を築かせた。
浅井・朝倉軍は、虎御前山の北北西にある山丘の丁野山(岡山)および東に伸びる支尾根に城砦を構え、織田軍と対峙したと考えられる。
この山丘に構えられたのが丁野山城で、東に伸びる支尾根に築かれたのが中島城でる。浅井氏家臣の中島宗右衛門直親が守備したとされる。
天正元年(1573)4月12日武田信玄が信濃国駒場の陣中で亡くなると、信長は小谷城攻略を本格化させ、同年8月8日山本山城を開城させ、12日に大嶽城を、13日には丁野山城を落とした。
中島城も丁野山城とともに落城し、守将の中島宗右衛門は木之本の田部山城に退いたとされる。
中島城は小谷城を守る支城のひとつで、浅井氏の家臣である中島直親の居城であった。いつ頃築かれたのかは明らかとなっていないが、元亀3年(1572)には織田氏の侵攻に対して浅井長政と朝倉義景が合議し、中島城の守りを固めた上で尾根続きの岡山にある丁野山城を修築して朝倉勢を迎え入れている。
天正元年(1573)8月に織田勢は小谷城を包囲し、支城の大嶽城を落城させた勢いで中島城と丁野山城を攻めた。十倍程の敵に包囲された両城は攻め手の勧降を受け入れ、中島直親は織田勢に投降し、両城には火が放たれたという。










 虎御前山城
虎御前山城
 主郭土塁へ
主郭土塁へ
















元亀4年(1573)織田信長の小谷城攻めの時に、中島宗右衛門直親が守備していたと伝えられている。





















 長谷川博美先生に、現地案内・説明して頂きました。
長谷川博美先生に、現地案内・説明して頂きました。





 中島城・・・(遠景)駐車場より
中島城・・・(遠景)駐車場より
元亀4年当時の丁野山城、および朝倉義景が撤退したことについて、「信長公記」の元亀4年の条に記述がある。
信長公記の内容を要約すれば
8月12日に浅見対馬守の手引きで大嶽城の下にある焼尾砦に入り、大嶽城へ攻め入った。大嶽城には朝倉勢の斉藤・小林・西法院を大将として五百人ほどが立て籠もっていたが降参してきた。信長公は、本来なら打ち首にするところであるが、夜中の風雨のこととて朝倉義景は大嶽城が落ちたことを知るよしもないので、敵陣に送り返し大嶽城が落ちたことを知らしめよと下知された。
信長公は、朝倉義景は疋壇城,手筒山城、金ヶ崎城を頼りに退却するであろうから、疋壇口に伏兵を置いておけと指示された。
大嶽城が落ちたとの知らせを受けた朝倉義景は、手勢を北国街道の河内方面から越前に向かわせ、義景自身は馬廻り衆だけを従えて刀根街道から敦賀へ逃れるところを織田軍は刀根峠にて追いつき、敦賀までの11里の間に3,000人余りを討ち果たした。
こうして8月12日に織田軍が落とした城の数は、大嶽城、焼尾砦、月ケ瀬城、丁野山城、田部山城、義景の本陣・田上山城、疋壇城、手筒山城、金ヶ崎城、賤ヶ岳砦、若狭栗屋越中守の居城・国吉城への付城など、併せると10城となった。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、信長公記
今日も訪問、ありがとうございました。!!感謝!!



















