「血目笛時計」
僕のまわりには、もう、藍色のセロハンを今まで明るかったこの風景の上に貼りつけたように闇が、音をたてずにやって来ていた。
都会だというのに、夜空に月が、薄ぼけていず、くっきりとした輪郭をもって現れた。
僕は一日中、ここにいた。誰にも邪魔されなかった。長い間、月を見ていると、だんだん月は大きくなってくるようだった。
僕は高層マンションの屋上にいるのだ。マンションの下、僕の足のずうっと下の方から喨々とフエの音が聞こえてきた。僕はこれを待っていたのだ。朝から、ずっと。
僕は階段を駆け降りた。音のする方へと、長い長い階段を、何故か電灯が全て切れていて、階段も真っ暗だった。僕はところどころに貼り付いた窓から差し込む月明かりだけを頼りに、どんどんどんどん階段を降りていった。幸い今宵の月は物凄く大きく光量も激しい。
息を切らせて延々と降りて行くと、僕はついに見つけた。201号室。この部屋にいるはずだ。部屋の中からは、さっきのフエの音がまだ聞こえてくる。
僕は知りたいのだ。何故、僕が腕時計の音を愛するのか、何故、僕がまるで犬のように、フエの音にひっぱりまわされていたのか。きっと、このフエを吹いている本人なら教えてくれるだろう。男だろうか、女だろうか、若者だろうか老人だろうか。
僕がフエの音を初めて聞いたのは、ちょうど半年前、帰りのショッピングモールのラッシュの中だった。高く明るく夕暮れの街に響くフエの音、そして何かが僕に語りかけてきたのだ。
“腕時計の音の謎を解くには、フエの音の主に会え”、と。そう、僕は腕時計の音を愛している。愛している。僕はこの腕時計が無いとダメなんだ。一時も離せない。
僕は左手首に嵌めた腕時計を胸元に引き寄せギュッと抱きしめた。右手で左手首を抱えるように胸元と下顎で挟み込むようにギュッと。まるでフエの音に合わせるように、コチコチ、コチコチ、鳴っている。
インターホンを2度、鳴らしてみたが201号室からは何の応答も無かった。でも相変らず、フエの音は201号室の中からハッキリと聞こえてくる。
あたりは静まり返っていた。僕の腕時計の音とフエの音だけが静けさを、よりいっそう際立たせていた。
ふと、気づくと、ドアは少し開いていた。鍵は掛かっていなかった。僕は躊躇無く、ドアの中へ入った。
フエの音が大きくなった。201号室の中は真っ暗で、月明かりだけが光源だった。僕は玄関で靴を脱いで、そのまま廊下を進んで行った。右側がトイレやバスルーム、左側が物置や和室のようだった。音は突き当たりのリビングから聞こえてくる。
リビングのドアは開いていた。大きな窓を背に激しい月明かりを浴びて、テーブルの向こう側で若い女の人がフエを吹いていた。月の中で吹いてるみたいだった。
「こんばんわ。」
と、僕は言った。すると女の人は、フエをおろして、僕のほうをカッと目を見開いて見た。植物みたいな女性だと思った。フエの音が止んだ。
「よく来たわね。何も覚えてないでしょう?私の顔を、よく見なさい。」
と、その女の人は急に大きな声で僕に言った。覚えてない?僕は変な気分になった。勝手に入ってきた男に何を言ってるんだ?僕は、不安定な感じになり、彼女の顔を見つめた。
ハッとした。何かが変だ。彼女は僕に向かって、大きく目を見開いている。でも、目玉がおかしい。僕を見ていない。月光のせいで、そう見えるのか?いや違う。わかった。彼女は目が見えない。盲目なんだ。だから部屋中真っ暗でも平気なんだ。
「わかったようね。そう、わたしはメクラなのよ。見えないの。いい?めくら。めくらの妹。思い出せない?お兄ちゃん。」
お兄ちゃん、と彼女は言った。僕?僕に妹が?僕は彼女が何を言ってるのか分からなかった。ただ頭がくらくらして、自分が消えてしまいそうな気持ちの悪い感覚に襲われた。
僕は、こういう風によくなる。いつものように腕時計を胸元に持ってきてギュッと抱え込むと少し気分は落ち着いた。
「いいわ。説明してあげる、お兄ちゃん。わたしのパパは、わたしにフエをくれた。あなたのパパはあなたに腕時計をあげた。あなたのパパとわたしのパパは同じ顔、同じ格好、同じ年、オンナジ。でも違う人。あなたのママとわたしのママは同じ顔、同じ格好、同じ年、オンナジ。同じ人。最初にママが消えて、次にわたしのパパとあなたのパパが消えた。回りの人は消えたって言った。死んだんじゃないのよ。分かる?」
この女の人は何を言ってるんだろう?
僕は又、気分が悪くなってきたので、腕時計を顎で挟み込んでギュッとやった。ギュッとやった。コチコチコチコチ、音がする、ハッキリ僕に向かって鳴っている、時を刻んでいる。僕は完全に落ちついた。考える余裕ができた。
僕の父は死んだと聞いた。僕の母も死んだと聞いた。ずいぶん前だ。僕が小学3年生のときだ。夕暮れに父は、僕にこの腕時計をくれたんだ。物凄く真っ赤な夕暮れだった。太陽が沸騰して溶けてしまいそうな感じだった。
母が僕の影の伸びる、ずっと先の方で手を振っていた。僕と父は、母のほうへ向かって歩いていったんだ。だけど、僕が歩いて母に近づくと僕の影の先っちょが、どんどん母を越えてもっと向こうに伸びて行ってしまうので、父は、ここで待ってなさいと言って、僕を置いて母の方へ歩いて行った。
それから、どうなったっけ?いなくなったんだ。父と母が。近所の人は死んだと言った。親戚の人も死んだと言った。それから僕は、いつも腕時計を肌身離さずに持ってないと落ち着かなくなった。親戚の人の世話で高校へ行った。工場で働いた。コピー機を作る工場だ。そのうち親戚の人は死んだ。
僕は工場で主任になって、今、たしか30才だ。妹なんて、いない。
「お兄ちゃん、目が見えないで一人で残されるって、どんなに辛い事だが分かる?いい?わたしは小さい頃、病気で失明したの。ゆっくりと1年かけて見えなくなったの。パパとママが消えてから、わたしはずっと、この部屋で一人ぼっち。最初の頃は親戚の人が世話してくれたり民生委員の人が来て学校を紹介してくれて通ったわ。でも、そこを出ると何もする気が無くなった。市の福祉関係の人がやってきて、目が見えなくても働ける場所を世話するって何度も言われたけど、嫌だった。死んじゃいたかったの。だって人間は醜いから、嫌いだから。1週間に一度、福祉事務所の人が来てレトルトの食事を置いていってくれたり洗濯や掃除をしてくれるわ。レトルトを作ったりお風呂に入ったり、そのくらいは目が見えなくってすぐに慣れるわ。まだまだ遺産があるし、障害者手当ても出るし、食べるものと生活に不可欠なものだけ持ってきてくれるから一歩も外へ出ず、福祉事務所の人以外、誰にも会わないで生きてきた。ずっと、この10何年間。真っ暗の中でずっと暮らしてきた。わかる?それが、どんなに辛いか。お兄ちゃん。どう?思い出した?わたしのこと。フエの音を聞いたんでしょう?それでも全然、思い出せないんでしょう?だって、お兄ちゃん、分かってないものね。でも、フエの音に惹かれて来た。出てきた。わたしを助けに来た。わたしをパパとママに合わせに来た。いいわ、見てなさい。わたしが、これからすることを、わたしの目を。」
僕の身体は細かく震えていた。僕は、じっと、ただ腕時計を抱きしめてコチコチ鳴る音を聴いて、目の前の女性を見ていた。
この人は頭がおかしいんだ。僕は父と一緒に一軒家に住んでいた。妹なんかいない。こんなマンションに住んでいた覚えは無い。
母は?母は、どうだっけ?母は、時々来た。そうだ、母は、あの夕暮れの父が時計をくれた日よりもっと、ずっと前にあんまり家に来なくなった。
母は?いや、どうだった?母は?いや、僕は高校へ行ったんだっけ?工場?工場って工場で僕は、どんな仕事をしていた?今、僕は何をしている?
「しっかり見て!」
ピシャンと、頬を叩かれたような気がして、記憶のモヤモヤから逃れて改めて彼女の顔を見つめると、彼女は両手に鋭くとんがったハサミを左右に一つづつ持って、いきなり、見開いた自分の両目に左右同時に突き刺した。
ハサミは、カッと見開かれた目玉に勢いよく突き刺さり、先端を瞳孔の中にうずめていった。
彼女は、先端を突き刺したところで動きを止めて、次にグリグリとハサミを回わしながら、自分の両目を、チョキチョキと切り刻んでいった。
僕は気を失いそうだった。
腕時計をしっかり抱きしめてはいるものの身体中がグラグラした。頭がグルグル揺れた。
その時、今まで激しい月の陽射しのせいで見えなかったのだが、おそらく雲が月を横切ったのだろう。月光が遮られ外が部分的に暗くなり、窓に僕の姿が映った。窓が鏡の役目を果たして僕を映し出した。
僕は見た。僕は30才くらいじゃ無かった。僕は、どう見ても小学生だ。僕は誰だ?気がおかしくなったのだろうか?
「いあたぁぁぁぁいぃぃぃ!ひぃぃぃ!わたしの顔を見なさいー!ひぃぃぃぃ!」
再び、ハッとして僕は女の顔を見た。彼女は、ハサミを目玉から抜いて床に落としていた。
そして、彼女の眼孔からは真っ赤なまるで、あの父が腕時計をくれた時のような、ドロドロのじゅるじゅるの真っ赤な真っ赤な異常に肥大した太陽が溶けて世界にこぼれ出してくるように、真っ赤な血がドロドロじゅるじゅる、流れ落ちていった。
どんどんどんどん吹き出して、流れ落ちて行った。
僕が呆然と見つめていると彼女は、“ひぃぃいい、ひぃぃいい”と言いながら、テーブルに置いたフエを取り、“わたしについてらっしゃい”と言って、ドロドロじゅるじゅると眼孔から血を流しながら、ゆっくりと歩きだし、僕を横切り、廊下を抜けドアを出て行った。僕は、ぼんやりと自動人形みたいにして、その後を続いた。
「お兄ちゃん、あなたには見えないでしょう。わたしはメクラだけど、今、あの夕暮れの状景がハッキリと見えてるのよ、いたぁぁいぃぃ、ひぃぃぃ。あなたは月の出口からやってきたんでしょう、ね。ひぃぃぃぃぃ。わたしのフエの音に引き寄せられて。その腕時計の音は、お兄ちゃんに、お兄ちゃんのパパが消えた、あの真っ赤な夕暮れを思い出させるんでしょう?そうして自分をしっかり確かめられて安心するのよね。ひぃぃぃ。いいわ、教えてあげる。わたしが、どうせ役にたたない両目を潰して、ドロドロの血をお兄ちゃんに見せる事によって、お兄ちゃんは目に浮かぶようにハッキリと、ドロドロのじゅるじゅるの真っ赤なとろける太陽をもっとハッキリと思い出したでしょう?ひぃぃぃぃ。あの物凄い夕暮れを。ひぃぃぃ。その状景はお兄ちゃんの腕時計の音の中に刻まれていて、お兄ちゃんが強烈に思い出す事によって、わたしの中に入ってきたのよ。ひぃぃぃ。お兄ちゃんが、あの真っ赤な夕暮れの中で、お兄ちゃんのパパを失った時に、フエの音を聴いていたのを覚えてないの?わたしは、お兄ちゃんの腕時計の音を聞いていたのを覚えているわよ、わたしは、めくらだけあって、耳がいいのよ。ひぃぃぃぃぃ。」
彼女は、ゆっくりと階段を屋上へ向かって昇っていき、途中で、フエを吹き始めた。
僕は、でく人形みたいに、階段に真っ赤なドロドロじゅるじゅるの血を垂らしながら昇っていく、彼女の後をついていった。
フエの音が僕の耳に入ってくると、僕はさらにリアルに強烈にハッキリと、父の消えた、あの物凄い夕暮れ、ドロドロじゅるじゅるの沸騰する真っ赤なとろける太陽を思い出して行った。
僕の思い出の状景が、彼女の心の目に伝わっていくのがハッキリと分かった。
そして彼女と僕は、屋上に着いた。
彼女はフエを吹きながら僕の記憶をどんどん蘇らせ、僕の記憶をどんどん吸い取りながら、巨大な月に向かって、まるでそれが見えているかのように凛々しく立ち止まった。
そして振り向いた。
「お兄ちゃん、お兄ちゃんには今、何が見えている?大きな月でしょう、ね。ひっぃぃ。わたしは違うのよ。わたしは今、お兄ちゃんが子供の頃に見た、真っ赤なドロドロの太陽、じゅるじゅるじゅるじゅるオレンジの空いっぱいに煮たって溶け出してこぼれ出してきそうな夏の太陽が、現実には有り得ない夕陽が、ドロドロ、じゅるじゅるのとろける太陽が、背後からとてつもない巨大さと迫力で真っ赤にバチバチ燃えながら覆い被さってくるみたいだった夏の夕暮が全部、ハッキリと見えてるのよ、ひぃぃぃぃ。そして、太陽は、わたしの後ろに迫っていて、お兄ちゃんの影を屋上の向こう側に細く細く、先に行けば行くほど、細く細く作り出しているの。ひぃぃぃぃ。最後に教えてあげるわ。お兄ちゃんのパパと、わたしのパパは一卵性双生児。ママは一人。ママは先に消えたのよ。お兄ちゃんのパパも、わたしのパパもママの後を追ったの。わたしだけを残してね。ひぃぃぃ、いたぁぁぁいぃぃ。わたしも一緒に行きたかったの、でもダメだった、だって、わたしは目が見えなくて影の先っぽに行けないから、わたしが影を作る役目になるしかなかったの。ひぃぃぃぃ。ママはパパたちより、ずっと先に、お兄ちゃんの影を利用して、其の国に行ったのよ、ひぃぃぃぃ。」



そこまで言うと、妹は、巨大な月を背後に僕に向かってスタスタとフエを吹きながら歩いてきて、スッと通り過ぎて行った。真っ赤な血がボタボタ落ちた。
振り向くと、僕の影がだだっ広い屋上を巨大な月の陽射しによって、どんどん細く細く伸びていた。妹はフエを吹きながら、しっかりとした足取りで、僕のどんどん細くなる影の先っぽに向かって歩いて行った。
そうだ、あの時、フエが聞こえていた。僕の後ろから聞こえていた。僕の後ろから真っ赤な太陽が影をどんどん細く作り出していた。その影は妹の影だった。僕のじゃない。
母が、父よりずっと前に僕の影を利用して、其の国に行った。母の残像が真っ赤な異常なドロドロじゅるじゅるの夕陽の日に、たびたび現れて父を誘った。
父は、其の国に行く決意をし、僕に、腕時計を渡した。母が、父の双子のもう片方の人、妹のパパにフエを渡した。母の2人の子供、僕とメクラの妹、を繋げておいて、いつか妹も、其の国へ来れるように、と。
妹は目が見えないので、影を、入り口を作る役目に回らざるを得なかった。母は2人の双子の夫と、その子供、家族全員で、其の国に行くことを望んでいた。けど、影の役、誰かが犠牲になって、この世界に残らなければならなかった。
妹の吹くフエは、僕を月の出口から、こっちの腐った世界に呼び戻すため、僕の腕時計はコチコチ鳴る音で、目の見えない妹に腕時計の音に刻み込まれた僕の記憶の光景をハッキリと妹の脳の中に再現させるため。
同じ母親から生まれた一卵性双生児の2人の父の子供達。僕と妹。僕の父と妹のパパは違う。でも一卵性双生児で同じ顔、同じ格好、同じ年、オンナジ、母は一人、記憶は完全に何かを媒介すれば伝わる。
それは現実の体験と全く違わない。共時性、違うけど同一。謎は解けた。
「今度は、お兄ちゃんが残るのよぉぉおお!どぉんなに苦しいかー!一人ぼっちで残されて、ザマーミロ!!ひぃぃぃぃ!」
と、妹はフエを握ったまま絶叫すると、僕の影の細い先端から消えた。僕は高校なんて行ってなかった、工場なんかで働いてもいない、小学3年生のまんまだ。
僕は妹のパパに騙されたんだ。この世界の記憶を、かの国でさんざん聞かされて、月の出口から出てきた時には、すっかり洗脳されてたんだ。
そうだよな、妹のパパは妹に来て欲しかったんだろうな。僕の父は一卵性双生児の妹のパパと相談して決めたんだ。そろそろ交代だって・・・。
だって、誰か一人が犠牲にならなくちゃならないものな。僕の番が来たんだ。
僕は、今度、妹か、他の誰かの番が来るまで、この世界で一人ぼっちで、小学3年生のまんまで生きていけるだろうか?この腕時計は妹のフエのような役目を果たせるんだろうか?何だかつま先から背中を通って頭のテッペンまで、ぞぉぉぉぉぉっとした。
コチコチコチコチ鳴る腕時計を抱きしめて顔を上げると、物凄く巨大な月が天空にポッカリと浮いていた。真っ赤に見えた。

終
This novel was written by kipple
(これは小説なり。フィクションなり。妄想なり。)










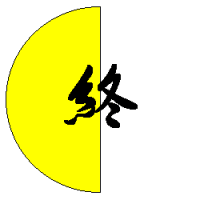
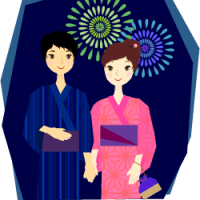
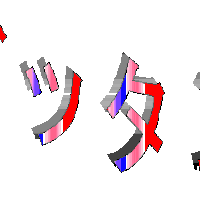


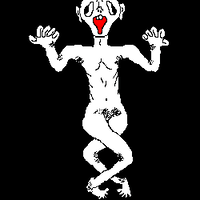
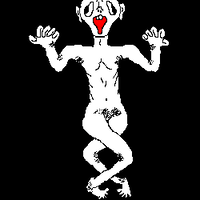
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます