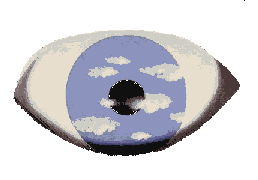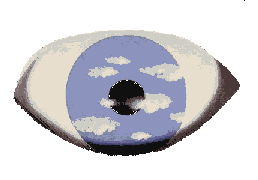♪
隣のテーブルの男がイソイソと黒い鞄にノートや書類やらを詰め込み、席を立った。そしてドアのチャイムを響かせ雨の中へ去って行ってしまった。
店内には冷気が流れ込み、もうもうと立ちこめた煙が多少、薄らいだ。
僕は“涼しいな”と思った。
店のあちこちで堰を切ったように会話が沸き起こった。彼女と僕もそうした。
「ねえ、これからどうするつもり?」
彼女はストローの紙を、くるくる巻いていた。
「当分、ぶらぶらするさ。別にやりたい事も無い」
ウエイトレスが床を歩く音。
「暮らしてゆけるの?」
「ああ」
彼女は昔のように左の眉を下げて話した。僕は彼女が昔、残していった本を手提げ袋から取り出し、渡した。
「これ俺の部屋に忘れていったろ。扇風機はイカれていたよ」
「あら、ありがとう。でも、…あなた、ヴィアン好きだったでしょう。確か、この本、私からのプレゼントじゃなかったかしら」
そうだったのかもしれない。
僕は又、煙草を吸った。レジの鳴る音。
思い出した。この本は彼女の言うとおり僕へのプレゼントだった。あの三枚の便箋に書いてあった。
僕は言った。
「いや、違う。これは君の本だ。プレゼントじゃない」
彼女の顔が曇り左眉が、ますます下がった。
「そう?そうかしら。じゃ、いいわ」
彼女は知っていた。その時、彼女は僕の言葉をどう思ったか、わからない。どうでもよい。もう。
「君は、これからどうするんだ。田舎へ帰ってから」
今度は僕が左手でストローの紙を丸め始めていた。何故だかは知らない。
「たぶん、結婚するわ」
僕の左手はストローの紙を引きちぎり、右手は煙草を揉み消した。
「そう。もう潮時だもんな」
彼女は一瞬、険しい目をした。
そして言った。
「でも、わからないわ。明日は明日の風が吹くわ」
風なんか吹きゃしない。風は過去に吹くんだ。そして全てを風化させる。酒と薬に浸って惨めな暮らしの中で死んでいったヴィヴィアン・リーは、よくその事を知っていただろう。
♪
去年の三月、まだ小さな会社に勤めていた頃、僕は出向先の上司と冗談半分に禁煙の約束をした。そして不思議と、それは長く続いた。
仕事は特にどうという事は無い。コンピュータの端末の前に一日中座ってプログラムを作るだけだった。すでに、あるプログラムをCOPYし、それに少し手直しを加えテストし、注文通りに動けば、それで終わりだ。僕は毎日、キーボードを叩き続け、それにつれて時は速度を増し次々に様々なものが失われ、過去に突き放された。
再び僕の回りで人が死に始め、街や流行や全てが風化し始めた。
ある夜、したたか酔っぱらった僕は、ある女性にこんな事を話した。
「オズの魔法使いの話は知っているよね。孤児の小さな女の子、ドロシーが。ある日竜巻に巻き込まれてオズの国へ行く。なんだかんだあるけど、そこでは結局、全てドロシーの都合のいい様に事が運ぶ。そんでドロシーは望み通りに再び故郷のカンサスの家に帰る。魔女の銀の靴の踵を三回、打ち鳴らすだけでね。ねえ、オズの国は本当にあったんだろうか?」
「映画では、それはドロシーの熱にうなされた際に見た夢だったはずよ」
「そう、夢だったんだ。しかし夢の中に、ちゃんとあったんだ。夢の中では本当に存在していたんだ。ねぇ、もしもだよ。今いるこの世界が誰かの夢だったらどうなる。ドロシーが入眠幻覚としてオズの国を創り上げたように、この世界の誰かが全てを創り上げているとしたら」
「じゃあ、その人が目覚めたら消えちゃう」
「そんなら、ドロシーが、いなくなったオズの国はどうなった?へへ、オズ・シリーズは、全部で四十巻あるんだよ」
「あらあら、それなら残された世界は、それなりに創世者なしに、何とかやってゆくんじゃないの?」
「うん、じゃあ、この世界、僕らの世界を創り出した夢想者は誰だと思う?ねえ、近頃、世界が何だか黴臭くなったと感じないかい?ちょうど四年くらい、前からさ」
「さあ?じゃあ、その人は四年くらい前にこの世界から消えた人ね」
「うん。この世界は、その人が生まれたときから始まった。その前の歴史も何もかも、その人の幻想の産物って事だ。その人は別の次元からやってきたんだ。無の中に実体化して、この宇宙を創り出した。そして肉体の消滅とともに再び別の次元に帰った。この世界は虚構の宇宙なんだよ。そして、その人は四十年生きて死んだ。で…・主人公のいなくなったこの世界は勝手にしやがれってんでポンと放り出された。それから世界は、次第に軽くなり古臭くなり焦点をぼかし消えてゆこうとしている。ぼろぼろと崩れていく。彼は、おそらくドロシーが再びオズに戻ったような事は、しないだろう。この世界は、もう創世者にしても収拾がつかなくなったからさ。死んで、それきりさ。僕らの世界は、もうじき終わりさ。そろそろ潮時だよ」
「その人って、いったい誰よ」
「ジョン・レノンさ」
僕は高笑いしてタンブラーやグラスを、ひっくり返した。まともじゃない。
その女性は立ち上がり目を剥いた。大勢の客がギョッとして僕を見た。
♂
そのプロジェクトは三ヶ月間でカットオーバーだった。要するに三ヶ月過ぎると僕は又どこか別の場所で同じような仕事をする事になった。
その三ヶ月の間、僕の右耳はじょじょに聞こえなくなった。再び僕は、いくつかの病院で診察を受けた。結果は相変わらず。異常なし。僕は眠れなくなった。右耳から絶えずジェット機の爆音が聞こえてきたからだ。しかし、この問題は、すぐに解決した。僕はヘッドホンで「セックス・ピストルズ」を聴きながら寝た。快い騒音は不快な耳鳴りを見事に追い払ったのだ。
僕は眠れるようになった。しかし、どういう訳か今度は左胸が痛み出した。内側でネズミが粘膜をかじっている様に感じた。それも何十匹のネズミが。
医者に診せると、またもや結果は同じ、異常なし。原因不明。僕は身体全体がズンズン重くなってゆく様に感じた。
そんな時に僕は、思わぬ事に気づいた。知らぬ間に僕は、ある女に恋していた。僕は本当に恋した事は無かった。いつも、苦しまぬため誰をも遠ざけていた。しかし今度は回避できなかった。おそらく本物の恋だったのだろう。「セックス・ピストルズ」も役にたたず僕は再び眠れなくなり、そしてキリキリと胸が痛んだ。
僕は何回か「好きだ」と言い、いつも彼女は無感動に拒否した。
彼女は、よくこう言った。
「だって、しょうがないもん」
地球上から、この(しょうがないもん)を全てとっぱらったら一体どうなるのだろう。やはりジョン・レノンの夢として静かに何もかもが消えてゆくのかも知れない。
僕の左肺のネズミは、たぶんその女のネズミだったんだろう。鬼と女は魔界の者にて、人を喰らう。これは本当だった。
女が僕の前から永久に去った時の言葉を憶えている。
それは、こうだ。
「じゃね」
女が、いなくなって僕の左胸は、その痛み方を変えた。ガサガサゴソゴソ鳴るのだ。おそらくボリス・ヴィアンの小説のように肺に睡蓮の花でも咲いたのだろう。
プロジェクトが終わり禁煙を約束した上司と別れて転勤すると、僕は再び煙草を吸い始めた。今度は二箱では効かず、三箱になった。
再び僕の回りで人は死ななくなり右耳は、シンとなった。つまり右耳は爆音を響かせる代わりに全く聞こえなくなってしまった。
特に、どうという事はない。まだ、左耳があった。
☆
僕は灰皿に山積みになった吸い殻を数えてみた。十二本。
外では雨が勢いをまし、まだ降り続けていた。いったい、いつになったら止むのだろう。
ブラッドベリの小説に雨の降り続ける惑星の話があった。その惑星の雨は、かつて一瞬たりとも止んだことが無い。不時着した隊員たちは全てを削りとる雨の中を太陽ドームを求めて、じめじめした奇態な植物の生い茂るジャングルを彷徨う。しかし、いくら歩き回っても太陽ドームは、すでに廃墟と化している。彼らは一人づつ狂っていき、死んでいく。雨は全てを溶かし全てを狂わせ消してゆく。精神をも記憶さえも。
僕は、ふと外の雨を見続けているうちに、この話を思い出した。
僕は十三本目に火をつけた。彼女との会話は一向に進まなかった。突然、どちらかが話し始め、すぐにぱったりと止み沈黙が長く続いた。おそらく、どちらも、もう話すべき時間を見失ってしまったのだろう。振り返る事のできる過去は記憶を浸食する雨や風に、すっかり喰い荒らされ未来につながるものは何も無いのだ。
僕は左耳を澄ませて音ばかりを探していた。
アスファルトを削る車の音。彼女の息。雨の音。グラスの触れ合う音。遠くから聞こえてる鐘の音。
鐘の音!雨の中を迷子のように彷徨う過去の音。
僕は思い出した。音を見付けた。「みつばちのささやき」で少女が聴いたオルゴール。それは、僕にとっては、小学校一年生の時に見た夢の中にあった。
夢の中で僕は深夜の校舎を訪れる。薄暗く静まり返ったガランとした廊下を僕は歩いていく。誰もいない廊下は長く長く伸び暗闇の中へ消えてゆく。何故か僕の教室だけ灯りが燈っている。僕は後ろの戸を開け中に入ってゆく。しかし、誰もいない。そして、そこには天井から巨大な鐘が吊り下がっている。声が、どこからとも無く聞こえてくる。
「お前は、ここに来てはいけない。ここはお前の来る場所ではない」
昼間になる。僕はランドセルを背負い再び、黄色い光に輝く廊下を歩いている。僕は教室の後ろ戸を開け中に入っていく。中には児童たちが僕に背中を向けて座っている。僕は「おはようございます」と言う。
すると子供たち全員が、いっせいに振り返り僕を見る。児童たちの顔は皆、真っ青で瞳の無い真っ白い目を光らせて気味悪く笑っている。僕はビックリして廊下に飛び出して一目散に走る。しかし、廊下に終わりは無い。しだいに、あたりは薄暗くなってゆき、笑い声がいつまでも僕を追ってくる。そのうち、僕は気づく。廊下に終わりが無いのではなく、僕がいくら走っても前へ進む事が出来ないのだ。後ろを振り返ると教室の後ろ戸が開いていて、中では、まだ皆が青白い顔をして僕の事を見ている。
そのうち、笑い声は鐘の音に変わり、僕の回りは何百もの鐘の音に取り囲まれる。場面が変わり、僕は父と母と弟と食事をしている。母が言う。
「今日は、あなたのお誕生日ですよ。素敵なプレゼントを送ります。部屋に戻ってごらんなさい」
僕と弟は部屋に戻り布団を敷いて一緒に寝る。あたりは暗くなり、夜がやってくる。ふと気づくと母が青白い顔をして足下に立っている。
「さあ、これがプレゼントですよ」
僕と弟の真上には、巨大な鐘が無数に天井からぶら下がっており、けたたましく鳴り始める。鐘の音に無数の笑い声が重なり、僕と弟は泣き叫ぶ。夜の教室が追ってきた。
僕のデジャヴの中でオルゴールは鐘だった。
♪
「最近、何か面白い映画見た?」
長い沈黙を彼女が破った。僕は十四本目を揉み消した。
「うん。最近、映画ばかり見ている」
「何?」
彼女は少し笑った。彼女のコーヒーカップは、カラだった。僕のは、まだ半分残っていた。
「ネバーエンディングストーリー」
「ああ、ミハイル・エンデのね。オズの魔法使いのドイツ版よ」
「…・・そう」
僕も少し笑った。
しばらくして僕らは店を出た。雨が横なぐりに僕らを襲った。どういう訳か彼女は僕にピッタリと身体を寄せてきた。僕は彼女の腰に手を回し強くひいた。コートが、ガサガサ音をたてた。
「あの頃に戻らないかしら、ねえ」
彼女は小さく、ささやいた。
「戻らないよ。あの頃なんてもう無いよ。なにもかも風化した。この街も何もかも変わった。僕も誰も」
「私も?」
「そうさ。違う?」
彼女は何も言わなかった。ただ下を向いてニッコリと笑った。
時の雨は幻かもしれない。この世界に静かに降りそそぎ、全てを削り去っていく。もしかしたら、この街、この世界が、ちっとも変わらなければ時の雨は降り注ぐ事は無いのかもしれない。
ちっとも変わらない世界を想像してみてほしい。いつも同じ車が走り、いつも同じ人々が店の隅にいて、いつも静かな曇り空。まるでキリコの絵のように建物の影が冷たく伸び、シンと静まり返っている。おそらく、そこには通り過ぎる時間も無い。失われるものも無い。永遠に、ただあるだけ。
悲しみも喜びも無く、音さえも吸い込まれる様に消えてゆく。
権力社会、強弱社会、様々な人々が、この世界で喧騒を創りあげた。しかし時は闇からの雨と風に引き裂かれ、置き去りにされる。それぞれの喧騒は、それぞれの不確かな記憶の中で時折り、カタコトと静かな足音をたてる。そして、その足音も、いつかは完全に消える。
彼女は故郷に帰り、おそらく最初に愛した男と結婚する。
記憶の中の足音は時折、ひょんなタイミングで先々につながる。
そして僕の場合、全ての足音は容赦なく僕を置き去りにした。
彼女と僕は、烈しい雨音の中で別れた。もう会う事も無い。又、遠くで鐘が鳴っていた。彼女の赤いセーターは雨にかすむ街の中に小さく、小さく消えていった。
僕は胸ポケットから煙草を、ひっぱりだして一本づつ、ポトポトと水たまりに落とした。煙草たちはゆっくりと溶けて奇妙な絵になった。それは、こんな形だった。

別れる時、彼女は僕に言った。
「じゃね」
♀
それから三ヶ月経ち、僕は死んだ。
トラックにひき潰された訳でも、サンシャインの天辺から飛び降りた訳でもない。
死んだのだ。
闇が押し寄せてきたのだ。
過去の遙か彼方から闇が僕の記憶を飲み込み、咀嚼し、変容させた。
闇は、ある時点までの記憶を解体させ僕を死という記憶の中に押し込んだ。僕を知っている人々の記憶にも僕の死という記憶が闇によって注入され、僕が生きていると思っている人間は一人もいなくなった。だから死んだのだ。
僕は死ぬまでの三ヶ月間、あの雨の日以来、一本も煙草を吸わなかった。
煙草を吸おうが吸うまいが特に、どうという事はなかった。
どうって事ないのさ。
僕は死ぬ時、唯ひとつ、天にいる、どこかの誰かさんに願い事をした。
それは、
(七歳までの幻の時間を再び手に入れたい)
それだけだった。
僕の葬式には親戚が二十人ばかりと、二人の友人がやってきた。初夏の香りに包まれて、皆、涼しそうだった。光の雫が、いたるところに降り注いでいた。
二人の友人だが、男の方は誰だかわかったが、女の方はどうしても思い出せなかった。おそらく僕の中の何かが思い出すのを拒んだのか、闇の風雨が記憶から彼女を削除したのだろう。
あちこちで静かに蝉たちが音をたてた。
|