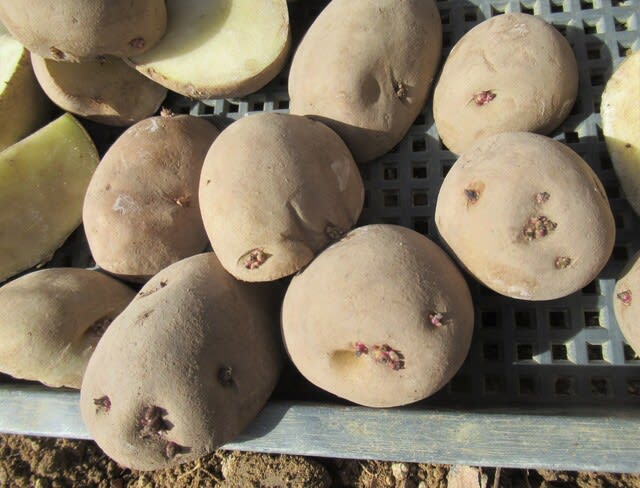冬越ししたアブラナ科野菜は春になると自然にトウが立ってきます。
ナバナ類はそもそもトウを穫るのが目的で、我が家でも
「つぼみ菜」は盛りになってきました。
葉物を穫るのが目的のアブラナ科にもトウが美味しいものが多い。我が家ではターサイや縮み雪菜。
今年は大寒の日を境に酷寒となり、花芽の方は意外に進みませんでした。
葉もしっかりした株が多く、濃緑で厚みが増し美味しいので、例年なら放置される時期になっても穫られていました。
しかし、3月に入ってからは気温が上がり、遅れていたトウも伸び出しました。
これがターサイ。
例年よりは少し遅いもののほとんどの株からトウが伸びてきました。
例年ほど穫り残された株は多くありませんが、それでもかなり残っています。
ターサイのトウは美味しく食べられます。今年はボリュームも結構あるようです。
花の咲き出したものからまだ伸びていないものまで個体差があるので、集中しないのも良い。
これは縮み雪菜。
ターサイと似ていますが、今のボリュームはこちらの方が良さそう。
こちらも例年より遅くまで収穫されていましたが、それでも大分残っています。
ターサイ同様こちらのトウも非常に美味しい。
茎立ち菜として作っている「仙台雪菜」とは全く別物で、縮み雪菜はターサイから育種されたもの。
トウに付いている葉も細かく縮れています。
トウの伸び出しはターサイより若干遅いようです。
これはチンゲンサイ。
外葉が枯れややボリューム不足です。
例年より残されている株は少ない。
チンゲンサイのトウはターサイや縮み雪菜に比べると味は落ちます。
それでも助っ人はよく穫っているようです。
これは水菜。
アブラナ科には間違いありません。花は綺麗な黄色の十字花です。
今はまだ蕾ながら近づけばハッキリと膨らんでいます。
ボリュームがなく食するには適さないと思いますが、食べるのに支障はありません。
これはハクサイ。
ハクサイを放置しておくとトウが伸び出します。
わき芽が残っていれば結構穫れて美味しい。
このハクサイのトウを穫るため、生育の悪い不結球の株を春まで残しておく方も見られます。