先週発表された平成21年度経済財政白書について、各社の報道の差が面白い。
たとえば産経新聞ではこう報じている。
非正規雇用が増加した背景として初めて、高齢化以外に
「労働法制の改正」を原因にあげた。麻生政権はこれまで
「小泉構造改革」で生じた“ほころび”の修復を掲げてきたが
白書の表現ぶりは
「行き過ぎた規制緩和が格差拡大を助長した側面もある」
と暗に認めた形だ。
これは大間違いだ。
「労働法制の改正」は「もう正規雇用は雇えない」というニーズの結果であって
原因ではない。本末転倒とはこのことだ。
ちなみに法改正してなかったら、請負やパートが増えていたか、失業率が上がって
いただけの話だ。
「労働法制の改正」という結果をいくらいじっても、原因は無くせないのは小学生
でもわかるロジックだろう。
まあ、百歩譲ってここまではいい。解釈によってはそう読めなくも無い書き方が
されているし。
この記事で最大の問題は後半部。
少なくとも白書のどこにも
「行き過ぎた規制緩和が格差拡大を助長した側面もある」
なんて書かれちゃいないのだ。
実際には、まったく逆である。
小泉政権の5年間にほぼ重なる02~07年において、実際には賃金格差は縮小している
こと、そしてその理由は失業率の1%近い改善にあると明記されている(236p)。
よく言っているように、小泉政権は(正社員の既得権にメスを
入れられなかったため)100点満点とは言えないものの、規制緩和で
格差を縮小させたのであり、野党が言うように労働再規制なんて
バカなことをやったらまた以前の失業率に戻るだけだ。
まあ、雇用労働者内での賃金格差だけは縮小するかもしれないが。
そして総論として、格差縮小の最大の特効薬は景気拡大であり、就業形態の多様化は
失業率を抑制できると明確に述べている(279p)。
ついでに言うと、非正規雇用の拡大は先進各国共通の現象であり、相対的にそれが
少ないのは、雇用規制の少ない英米であるとする分析も併記されている。
これも以前から指摘されている話だが、正社員の処遇見直しが可能なら、わざわざ
好きこのんで非正規雇用なんて使わない。
当たり前のロジックだ(なぜか日本のメディアは伝えようとしないのだが…)。
もうちょっと読み込みましょうよ産経さん。
そういう意味では、北海道新聞の編集委員は、読解力にかけては産経より上らしい。
白書は非正規労働や所得の格差にも焦点を当てている。社会問題化
している重い課題だ。問題なのは、派遣労働などの「多様な就業形態」
が失業者を減少させるとして、非正規労働の拡大を容認している点だ。
経営者にとって非正規労働者は使い勝手のいい労働力といわれてきたが
今回の不況ではまさに雇用の調整弁となった。安全網もないままに職も
住まいも失った人は数多い。
白書は「景気回復が最大の格差対策になる」と強調する。しかし2002年
から5年以上にわたった景気拡大期に非正規労働者が増え続け、働く人の
3分の1にもなった。この事実をどう考えるか。
まあ、頭の悪さはどっちもどっちだが(笑)
たとえば産経新聞ではこう報じている。
非正規雇用が増加した背景として初めて、高齢化以外に
「労働法制の改正」を原因にあげた。麻生政権はこれまで
「小泉構造改革」で生じた“ほころび”の修復を掲げてきたが
白書の表現ぶりは
「行き過ぎた規制緩和が格差拡大を助長した側面もある」
と暗に認めた形だ。
これは大間違いだ。
「労働法制の改正」は「もう正規雇用は雇えない」というニーズの結果であって
原因ではない。本末転倒とはこのことだ。
ちなみに法改正してなかったら、請負やパートが増えていたか、失業率が上がって
いただけの話だ。
「労働法制の改正」という結果をいくらいじっても、原因は無くせないのは小学生
でもわかるロジックだろう。
まあ、百歩譲ってここまではいい。解釈によってはそう読めなくも無い書き方が
されているし。
この記事で最大の問題は後半部。
少なくとも白書のどこにも
「行き過ぎた規制緩和が格差拡大を助長した側面もある」
なんて書かれちゃいないのだ。
実際には、まったく逆である。
小泉政権の5年間にほぼ重なる02~07年において、実際には賃金格差は縮小している
こと、そしてその理由は失業率の1%近い改善にあると明記されている(236p)。
よく言っているように、小泉政権は(正社員の既得権にメスを
入れられなかったため)100点満点とは言えないものの、規制緩和で
格差を縮小させたのであり、野党が言うように労働再規制なんて
バカなことをやったらまた以前の失業率に戻るだけだ。
まあ、雇用労働者内での賃金格差だけは縮小するかもしれないが。
そして総論として、格差縮小の最大の特効薬は景気拡大であり、就業形態の多様化は
失業率を抑制できると明確に述べている(279p)。
ついでに言うと、非正規雇用の拡大は先進各国共通の現象であり、相対的にそれが
少ないのは、雇用規制の少ない英米であるとする分析も併記されている。
これも以前から指摘されている話だが、正社員の処遇見直しが可能なら、わざわざ
好きこのんで非正規雇用なんて使わない。
当たり前のロジックだ(なぜか日本のメディアは伝えようとしないのだが…)。
もうちょっと読み込みましょうよ産経さん。
そういう意味では、北海道新聞の編集委員は、読解力にかけては産経より上らしい。
白書は非正規労働や所得の格差にも焦点を当てている。社会問題化
している重い課題だ。問題なのは、派遣労働などの「多様な就業形態」
が失業者を減少させるとして、非正規労働の拡大を容認している点だ。
経営者にとって非正規労働者は使い勝手のいい労働力といわれてきたが
今回の不況ではまさに雇用の調整弁となった。安全網もないままに職も
住まいも失った人は数多い。
白書は「景気回復が最大の格差対策になる」と強調する。しかし2002年
から5年以上にわたった景気拡大期に非正規労働者が増え続け、働く人の
3分の1にもなった。この事実をどう考えるか。
まあ、頭の悪さはどっちもどっちだが(笑)














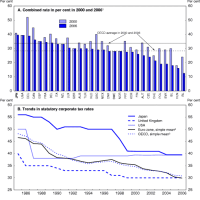





「行き過ぎた解雇規制が格差拡大を助長した側面もある」と事実を公表するのが報道機関の役目です。
民主党のマニフェストにも案の定、規制強化しか書かれていないですね。
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/14.html
どうって、一度正社員から外れた人が再び正社員になるのが非常に困難だという事実でしょうに。この状況の改善には、流動化が有効な処方箋だということも明らかでしょう。
(この編集委員さんはいくら給料もらってるんでしょうね)
話は変わりますが、民主党のマニフェストに自民党が噛み付いてますね。
「出来るわけないだろ」「カネはどこから出すんだ」といったコメントを吐く政治家さんたちを見ていると、前の会社の「ノンワーキングおじさま」たちを思い出してしまいます(苦笑)。
たしかに、民主党の主張にあいまいな部分もあるんですけどね・・・
公務員は終身雇用で、しかも雇用形態が四種類あった。奉任官、勅任官、親任官、ともう一つあった。そしてそれぞれに待遇が異なっていた。どれか一つは自らやめるといってもやめることはできなかった。
それをまねたに過ぎない。其れはあくまで人で不足がもたらし、其れにつれて、法律が整備された。
いずれにしても 結果として、政府の雇用形態が民間に定着した。ところが時勢が変わったために、其れが重荷になった。もともと公務員は軍隊で言うと一兵卒から雇用されると、それは貧乏が当たり前で、人々は其れから逃れるために、いろいろ工夫した。その仕事について家が建ち、子供を大学にまで行かせられるような金はくれなかった。戦後というきわめて異常な時代が長くつずいたため、その給料ベースが上昇したことが大きな問題で、それを下げることが、解雇規制をなくすことを意味する。
思うが今のような賃金体系では財政赤字は何をやっても無駄である。
戦前は工場労働者は会社が直接雇うことはなく、間に会社が入っていた。いわゆるホワイトカラーと、ブルーカラーは、入り口も、食堂も異なっていた。ホワイトカラーは終身雇用で会社が直接雇った。ブルーカラーは日雇いが原則であった。
これは多分西洋においても同じだと私は思う。戦後の特徴はブルーカラーにも終身雇用を導入したことで、我国独自の現象で、もとは人手不足である。
またホワイトカラーは課長で終わりという人が大半で、其れより上へ行く人はまた別な要素が必要で、あった。
いずれにしても変えないと大きな無理が来る。多分現代版戦争が変えると私は見ている。
そしてその時期は意外と近いとも思っている。大インフレでしょうね。
話は変わるがインドネシア人の介護士を我国へいれ、三年で介護士の資格を取らせるわけだが、同一職種、同一賃金となると、彼女らも同じ土俵に上げなければならない。ところが年功賃金だと、其れは別になる。非常にずるい考えがそこにあるが、世界経済がそれを許すだろうか。
実質何も考えていない。優れた人は世界中にいる。
http://www.youtube.com/watch?v=nGAGZbVsmYg&feature=related
民主党の支持層が中高年・老人から若手まで幅広いこと、連合を支持基盤としていることを考えると仕方無い面もありますが、これじゃ政権とっても党内で意見はまとまらないでしょう。
民主党は変化を期待できる点では自民よりはマシですが、雇用だけに限らずあらゆる面で意見にまとまりがない。
民主党に政権交替をしたあとにもう一度政界再編でも起こらないと、なかなか城さんが望むような改革は進まないでしょう
何を言いたいのかさっぱり分からない。
昔たまに朝日新聞を読むたび、「この前提からこの結論は出ないでしょうが。馬鹿か?」という記事が毎回必ずありました。いつも自分の思想どおりの結論を導き出せる、頭の悪い人は幸せだと思います。頭が良かったら、「その結論が出るわけない」ことに気がついてしまって、純粋に思想を主張する幸せな人生は送れませんものね。
規制緩和によってシャッター街になってしまった近所の商店街を見ていると、「ほんの10年前は・・・」と思う。子供の頃、たまに祖母に手を引かれて行ったすごい繁華街は、今は人もまばら。店を畳んで更地にし、駐車場にした靴屋もある。
法改正によって出店規制が緩和、駅前にできた大型のモールに全部、客を喰われた。商店街は(弱小)個人商店の集まりだし、全国展開しているモールに駅前を取られたらひとたまりもない。
「自由な社会だ。悔しければお前らも頑張れ」とフリードマンなら言うだろうが(言ってた)、このままの規制緩和策を取り続けるなら、「日本全国、JRの駅を降りたら、視界に入ってくる風景が均一化、旅先での体験も均一化」してくることは間違いないだろう。
あなたは出張先でJRの改札口を出る。そしたら改札横にスターバックスとマクドナルドが入っているので、そこで新幹線の疲れを一息。そして駅近の全国展開ビジネスホテルで、マニュアル化されているフロントの対応にまぁまぁ満足して、ホテル隣のセブンイレブンで買ってきた「期間限定・舞茸ご飯弁当」を食べながら、NEWS23を見る。次の日の朝は早いのでドトールでミラノサンドBを食べて、ブレンドコーヒーSを飲む。200円。値段にしては味は満足。そういえば先週、大阪に出張だったときも、今回の福岡出張と同じような購買パターン。だって安いんだからしょうがない。2週間後は東京か。どこへ行っても同じ消費パターン。
「だって質と価格を比較すれば、全国展開チェーンのほうが圧倒的にローカルより強いから。」
>規制緩和によってシャッター街になってしまった近所の商店街を見ていると、「ほんの10年前は・・・」と思う。子供の頃、たまに祖母に手を引かれて行ったすごい繁華街は、今は人もまばら。店を畳んで更地にし、駐車場にした靴屋もある。
>法改正によって出店規制が緩和、駅前にできた大型のモールに全部、客を喰われた。商店街は(弱小)個人商店の集まりだし、全国展開しているモールに駅前を取られたらひとたまりもない。
ロードサイトの大規模店に客を取られたという話もありますが、私に言わせると地場に根付いた店舗は店主の年齢と共に老化し新鮮さを失ってゆく。これは客層も老化して行くのだからある意味しかたがないという面もあり、新鮮さを失えば若者は街に魅力を感じなくなり、一層都市へ流出して行くことになる。
更に良いますと、地方はモータリゼーションが行き過ぎたこともあり、これは街に人が集まらなくなる、飲み屋街が寂れるというだけではなく、ドアtoドアの生活が当たり前になるとファッションなんかに気を使わなくなるんです。おそらく都市在住者と地方住民を比較すると被服費がかなり違うはず。
地方の商店街が寂れる理由は大規模店だけではないのですよ。
首都近郊でも寂れるところもあれば栄えているところもあるのです。