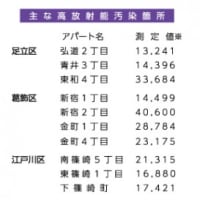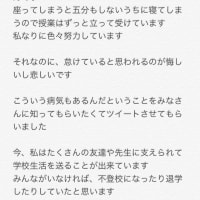*『死の淵を見た男』著者 門田隆将 を複数回に分け紹介します。63回目の紹介
『死の淵を見た男』著者 門田隆将
「その時、もう完全にダメだと思ったんですよ。椅子に座っていられなくてね。椅子をどけて、机の下で、座禅じゃないけど、胡坐をかいて机に背を向けて座ったんです。終わりだっていうか、あとはもう、それこそ神様、仏さまに任せるしかねぇっていうのがあってね」
それは、吉田にとって極限の場面だった。こいつならいっしょに死んでくれる、こいつも死んでくれるだろう、とそれぞれの顔を吉田は思い浮かべていた。「死」という言葉が何度も吉田の口から出た。それは、「日本」を守るために戦う男のぎりぎりの姿だった。(本文より)
吉田昌郎、菅直人、斑目春樹・・・当事者たちが赤裸々に語った「原子力事故」驚愕の真実。
----------------
**『死の淵を見た男』著書の紹介
第19章 決死の自衛隊
突然鳴り始めたアラーム P297~
一行が福島第一原発の正門についたのは、もう午後6時半頃のことだ。松井の所属する航空自衛隊と、齋藤らが乗る陸上自衛隊の消防車輛が到着した。
松井たち幹部は正門横にある警衛所に入った。ここでそれからおこなう作業について、東電の人間から詳細な説明を受けた。松井たちの前に、発電所内の地図が広げられた。
「これから3号機というところに放水をしていただだきます。いま正門にいますから、直接行くのではなく、いったん3号機と正門の間ぐらいのところに集まって待機し、そこから、一台ずつ行って放水してもらうことになります」
すでにあたりは真っ暗だった。警衛所の中では、全員がゴーグルをとった。建物の中は灯かりがついていた。蛍光灯に照らし出された中で説明する東電の人間の緊迫感が、松井に伝わってきた。
「説明してくれた東電の人は若い方だったですよ。正門と3号機との中間地点のところに一回集まって、そこから一台ずつ放水して戻ってくる、つまり一台が戻ったら、次の一台が行って、また放水して、というやり方であることが説明されました」
30分ほど説明はつづいた。
松井たち自衛隊側も、自分たちで順番を決めていった。最初に行くのは、陸上自衛隊の化学防護車にした。これがまず現場に行き、その段階で現場の放射線量の数値が想定以上になっていたら、「赤色灯をまわして、スピーカーで撤収の合図を出す」ということを決めたのである。
「案内は私たちがします」
最期にその若い東電の人間がそう言って打ち合わせは終わった。
「説明を受けてる時は、怖いというよりは、教えてもらった通りに、ちゃんと3号炉のところにつけるかな、という方が不安でした。東電の人が案内するといっても、厳密には、待機するところから3号炉までは一台ずつ自分たちで行かないといけない。そこから向こうは、”先で待ってる”ということなんです。教えられたのは一直線だったので、なんとか行けるだろうとは思いましたが・・・」
いよいよ松井たちの放水活動が始まった。まず先に行ったのが、打ち合わせ通り、陸上自衛隊の化学防護車である。
放射線の汚染状態の中でも、調査・測定が可能な特殊な偵察車輛である。まず、これが現場に降りていった。そのあとを松井たちの消防車が行くことになっていた。しばらく経って、化学防護車が帰ってきた。赤色灯もまわっおらず、スピーカーで撤収の合図も出されなかった。いよいよGOである。
「消防車としては、私たちが最初でした」
と松井は言う。
「暗い中をS字カーブのような坂をうねりながら下っていきました。それほど急な坂ではなかったです。基地を出発する前に衛生隊から渡された線量計はスティックタイプのものです。タイベックの下には、われわれの作業服、つまり、自衛隊でいう戦闘服のようなものを着ていますが、その胸のポケットに入れていました。それが、坂を下りてきて、2号炉と3号炉の手前の十字路の交差点みたいなところに来た時に突然、鳴りだしたんです」
ピピピピ・・・無機質なアラーム音がいきなり鳴り始めた。2人の線量計が同時になり始めたので、松井は驚いた。タイベックの下の自衛隊の作業着のポケットに入れている線量計だけに数値をみることもできない。
「隊長、線量計が鳴ってます。どうしましょうか」
(「突然鳴り始めたアラーム」は、次回に続く)
※続き『死の淵を見た男』~吉田昌郎と福島第一原発の500日~は、
2016/5/30(月)22:00に投稿予定です。
 |
![]()