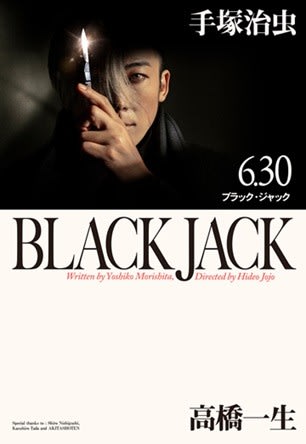「ダークサイドミステリー」はNHKのBSで時々放送されている。
「本当の謎は、人間の闇」
というサブタイトルがついている通り、
人間の歴史の闇である事件などを題材にした番組で、
自分好みの番組なので時々録画したりして見ていた。
歴史における闇やネガティブな事件ばかりを追求した、
禍々しい雰囲気の番組ではある。
ナビゲーター・栗山千明の妖しい雰囲気からも、不穏な空気を漂わせている。
そんな番組がNHKで放送されてるのだ。
ダークサイドミステリー
本当の謎は、人間の闇
https://www.nhk.jp/p/darkside/ts/4847XJM6K8/
背筋がゾワゾワ、心がドキドキ、怖いからこそ見たくなる。
世界はそんなミステリーに満ちている。
世間を揺るがした未解決の事件、常識を越えた自然の脅威、
いにしえの不思議な伝説、怪しい歴史の記録、作家の驚異の創造力…。

これまでも「ジェヴォータンの獣」や阿部定、
エド・ケイン(「サイコ」や「悪魔のいけにえ」のモデルになった殺人鬼)、
ゾディアックと称した連続殺人鬼など、極めて禍々しい題材を取り上げて来た。
見てないけれど他にも「日本・ユダヤ同祖論」、「秘密結社KKK」
「ニコラ・テスラ」「フランケンシュタイン誕生」「魔術師アリスター・クロウリー」など
まるでもう、いかにも面白怖そうな興味深いタイトルが並んでるのだ。
人の歴史の闇の部分、ダークサイドばかりを集めたそんな番組だが、
今回「悪徳の作家サド」を放送していた。
初回放送された時は知らなかったが最近になって再放送され録画して見た。
今まで「ダークサイドミステリー」が取り上げなかったのが不思議なほど、
番組にぴったりの題材であろう。
というか、満を持してサドを特集したのだろうか。
サディズムの語源となったマルキ・ド・サド(サド侯爵)。
さぞやえげつない描写が出て来るんだろう、と身構えていて、
録画をごはん時には見られないなと思ってたが、
(エド・ケインの時は怖かった…)
NHKの番組だから露骨な性描写などはまったくなかった。
むしろ形而上学的にサドの何が問題だったのか、
何を問うているのかを提示する番組だった。
https://www.nhk.jp/p/darkside/ts/4847XJM6K8/episode/te/6964WZPPQK/
悪徳の作家サド 闇の哲学〜危険すぎる“自由とは何か?”〜
初回放送日:2024年7月16日
サドの著作は読んだことはなくて噂?で知ってるくらいだ。
70年代には「悪徳の栄え」や「サドのジュスティーヌ」が流行っていたような気がする。
サドといえば日本では澁澤龍彦である。
サドの翻訳で知られたフランス文学者で、
自分は70年代に澁澤を全身に浴びて💦、
澁澤の思想にどっぷり浸かった身であった。
その澁澤経由で彼の書くエッセイでのみのサドの知識で、
あとはパゾリーニがサドの原作「ソドム120日」を、
ナチス時代に設定を移して映画化した「ソドムの市」を見たくらいだろうか。
「ソドムの市」は、
良く分からないが多分パゾリーニの嗜好もかなり入っていたような気がする。
スカトロジー描写が多かった。映画館では途中で退席する客もいた。
そんなかなりえげつない映画だったが…。
サドは貴族の生まれであるが、その生涯の殆どを監獄で過ごした。
かのバスティーユ牢獄にも幽閉されていた。
しまいにはナポレオン帝政のもと精神病院へ収容されそこで生涯を閉じた。
女性に暴行や虐待、乱交などをして犯罪とみなされ、
肛門性交の罪にも問われたという。
当時はキリスト教の倫理観が支配していた時代である。
神に対して敬虔で貞淑で道徳的であることが求められた。
しかしその実、貴族たちの生活は奔放で愛人を作り、性にも放埓だったという。
建前では貞淑でありつつ、欲望も隠さなかった。
そのような乱れた貴族生活を間近に見続けたサドは、
人間の矛盾を痛感したに違いない。
人間には負の面があり欲望を抑えきれない面もある。
それがサドをして神への反逆に向かわせたのではないだろうか。
生涯のほとんどを監獄で過ごし、自由を奪われたサドは、
想像の中でありとあらゆる悪徳の限りを尽くした。
自由を剥奪されたからこそ脳内で制限のない自由を爆発させた。
殺人やソドミー、近親相姦を肯定するまで。
それがサドの著作の数々だったのだと思う。
自己の頭の中の妄想だからこそ、自由に書けた。
狭い監獄の中で欲望を限界までつのらせ、ペンにぶつけたのだ。
牢獄の中で妄想を繰り広げ、自由とは何か、と思考を深めていった。
そして権威やモラルを破壊しつくすような「制限のない自由」という思考に辿り着いた。
「ダークサイドミステリー」では露骨で具体的な描写は避けていて、
サドの何が問題だったのかは分からなくなっていたが、
「ソドム120日」などは相当えげつない内容のはず。
(現在でも完訳は出ていないようだ)
サドの翻訳家・澁澤龍彦はサドの擁護者でもあった。
少し長くなるが澁澤の文章を引用してみる─
「しかしながら、よくよく考えてみると、いったいなぜ、
サドがそれほど長い期間を監禁されていなければならなかったのかという理由は、
きわめて曖昧になってくる。
何人かの情婦を持ったためか?
乞食女を鞭打ったためか?
娼婦に媚薬を飲ませたためか?義妹を誘惑したためか?
馬鹿馬鹿しい話だ。
そんなことは、封建時代の道楽者の大貴族たちの日常茶飯事ではないか。
もっとはるかに残酷なこと、
たとえば、女を狩りの獲物のように弓矢で追いつめて、
火にかけて炙ることを趣味としていたような道楽者の大貴族だって、
この時代には、さして珍しくはなかったのである。
・・・・・
「サドにおいて、社会が発見した罪なるものは、おそらく、
「仮借のない論理」という名の罪だったのである。
すべてをあからさまにいうことは、いつの時代においても罪だったのである。
18世紀は理性の時代と呼ばれるが、だれがサドのように、
その論理を極限まで、止まることなく徹底的に推し進めたろうか。」
・・・・・・
「……バスティーユの重い扉が目の前で閉まったとき、
真のサド侯爵が誕生したのだった。
おそらく、サドはこのとき、すべてをいう特権、自由の恐怖に酔う特権が、
じつは牢獄のなかにしかないことを無意識のうちに覚ったのである」
人間の闇、あらゆる欲望を曝したような著作は長く秘匿されやがて忘れられた。
シュルレアリスムが再びサドを見出したことで日の目を見たが、
200年も前の著作は今も恐怖を持って受け止められている。
もしかしてそれはサドの勝利なのだろうか。
「ソドム120日」の原稿は牢獄の壁に埋め込まれていたというが、
フランスでは国宝に指定されたという。
売り切れだが(>_<)一応↓表紙
悪魔のいる文学史 神秘家と狂詩人(中公文庫)
澁澤龍彦
↓ブログ村もよろしくお願いします!