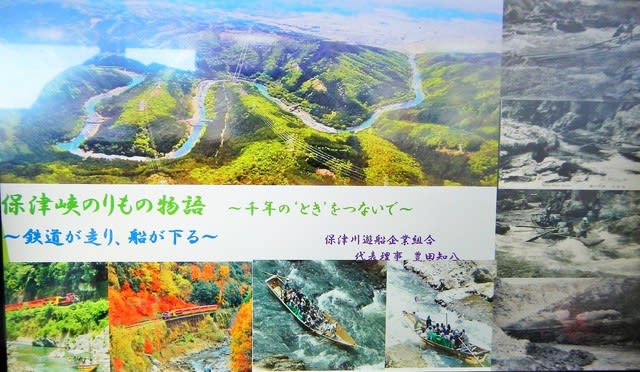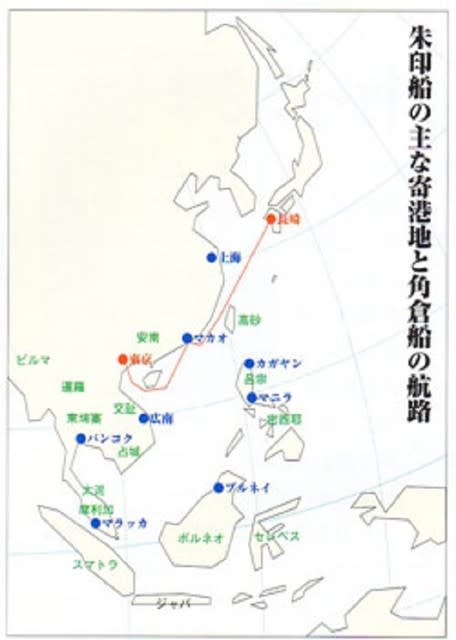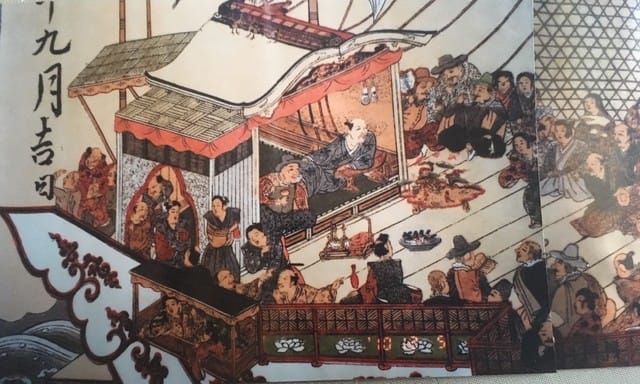2018年、今年も保津峡の紅葉が色づきはじめてきました。
保津峡、一番最初に色づくのは昔、丹波亀山藩の殿様が魚釣りをして遊んだと云われる「殿様の漁場」
そして、最も紅葉が美しいと云われる「女渕}が続きます。
JR保津峡駅とトロッコ列車が交差するトンネル前の若い紅葉(写真)は色合いの鮮やかさが際立つ所です。
秋の保津峡の先頭を切って赤くなるカエデたち。これらの木々が赤く染まる、保津峡の紅葉のスタートです。
黄色から橙色、赤色へと山の風景は徐々に移り変わっていきます。
四季の移ろいをリアルに感じることができる季節。
保津川下りで体感してみて下さい!
皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げます。
保津峡、一番最初に色づくのは昔、丹波亀山藩の殿様が魚釣りをして遊んだと云われる「殿様の漁場」
そして、最も紅葉が美しいと云われる「女渕}が続きます。
JR保津峡駅とトロッコ列車が交差するトンネル前の若い紅葉(写真)は色合いの鮮やかさが際立つ所です。
秋の保津峡の先頭を切って赤くなるカエデたち。これらの木々が赤く染まる、保津峡の紅葉のスタートです。
黄色から橙色、赤色へと山の風景は徐々に移り変わっていきます。
四季の移ろいをリアルに感じることができる季節。
保津川下りで体感してみて下さい!
皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げます。