「わが国は小中華」韓国が日本をずっと下に見続け恨む理由
4/11(土) 11:15配信
プレジデントオンライン
■日中2つの超大国に挟まれた国の末路
中国に隣接する朝鮮半島は、常に大陸からのプレッシャーにさらされる歴史をたどってきました。
それにもかかわらず、強大な中国に呑み込まれず、自分たちのアイデンティティを保ってきたことは、奇跡的とも言えます。
逆に言えば、生き残るためにはきれいごとを言ってはいられず、いろいろな手を尽くしてきました。
長年にわたり、その歴史が刷り込まれているのが現在の北朝鮮・韓国だということです。
そこを理解せず、現在の両国だけを見ていると、判断を誤るかもしれません。
1392年に建国され、日本に併合されるまで約500年続いた朝鮮王朝も、建国当初から中国の明朝と深いつながりがありました。
中国に呑み込まれることは避けたい。しかし、自分たちの力量もよくわかっているので、下手な抵抗をしても無駄である。
そこで、明朝中国の秩序体系をいわば丸ごと受け入れ、その中で自己主張をしていく形を早くから取るようになります。
明朝の対外秩序とは、どのようなものだったのか。
まず周辺の国々は、儒教の中心学派である朱子学に基づき、明朝の皇帝を天下の中心たる中華に君臨する天子と見なします。
そのため明朝皇帝に対する服属のあかしとして、その地の産物を貢ぎ物として天子のもとに持参(朝貢)し臣礼をとる、明朝皇帝は返礼としてその国の君長たることを認可する、というコンセプト・パフォーマンスです。
.
朝鮮王朝は、以上を受け入れ、明朝に対して朝貢関係を結びました。
この関係を、大国に事(つか)えるという意味で「事大」と呼びます。
さらに朝鮮王朝は朱子学を国家イデオロギーとし、明朝の官僚システムを積極的に取り入れました。
そうすることで、自分たちを「小中華」、すなわち中国に次ぐナンバー2、日本などその他の周辺国を野蛮な「夷狄(いてき)」と見なしたのです。
ただし、明朝は朝鮮を含めた周辺国をすべて同列の朝貢国と見なしていました。そのため、朝鮮は日本などを内心では見下しながらも、表向きは対等に交わる関係「交隣」を続けました。
■三国間のパワーバランスが変わる
朝鮮はこうした独自の対外関係を築いていましたが、16世紀後半、日本が急速な経済成長と国内統一を果たしたことによって、三国間のパワーバランスが変わります。
元寇の際は一方的に攻められて反撃できなかった日本が、その後約300年を経て強国化し、豊臣秀吉が朝鮮出兵に打って出ました。
これを機に朝鮮は、日本を「何を考えているかわからない、暴力的な脅威」と認識すると同時に、「中国に守ってもらおう」という意識が強くなります。
この朝鮮出兵は、朝鮮半島を舞台にした日本と明朝との戦争でした。
さらに300年後の日清戦争、その60年後の朝鮮戦争も、同様の構図です。
いずれも、日本やアメリカといった海洋のパワーと大陸のパワーとのぶつかり合いで、その接点が朝鮮半島だったわけです。
そのなかでどう生き延びていくか、朝鮮は考えていくことになります。
その後の中国では、明朝が日本との戦争によって衰退し、清朝が建国されました。
明朝は漢人の中華王朝でしたが、清朝は満洲人。朝鮮にとって夷狄の国であり、明朝とは比較になりません。
しかし、清朝を蔑みながらも服従し、徳川幕府が成立した日本とも対等の付き合いを行うようになりました。
朝鮮としては、軍事的には清朝にも日本にもかないません。
そのため、清朝とは「事大」、日本とは「交隣」の関係を保ち続けます。
一方、清朝は前代にいわゆる「倭寇」が沿岸部に盛んにやってきて、軍事的な脅威を与えたという認識で、日本とは関わりたくないという姿勢でした。
また、江戸時代の日本は「鎖国」の体制でしたから、その後の300年は三国間の均衡が保たれました。
この均衡を破ったのは、西洋列強の影響を受けた日本です。
西洋諸国は交易を求めてアジア各国に条約締結を迫り、清朝や朝鮮が大きくは変わらないなか、唯一突出して変わったのが日本でした。
明治維新を経て西洋化を推し進め軍事強国になりつつある日本を、清朝は強く警戒します。
「倭寇」や朝鮮出兵という「前科」があったからです。
その予想は当たり、1879年には清朝の属国だった琉球を一方的に日本に組み込む琉球処分を断行し、朝鮮とは1876年に、朝鮮を独立国と見なす江華島条約を結びました。
4/11(土) 11:15配信
プレジデントオンライン
■日中2つの超大国に挟まれた国の末路
中国に隣接する朝鮮半島は、常に大陸からのプレッシャーにさらされる歴史をたどってきました。
それにもかかわらず、強大な中国に呑み込まれず、自分たちのアイデンティティを保ってきたことは、奇跡的とも言えます。
逆に言えば、生き残るためにはきれいごとを言ってはいられず、いろいろな手を尽くしてきました。
長年にわたり、その歴史が刷り込まれているのが現在の北朝鮮・韓国だということです。
そこを理解せず、現在の両国だけを見ていると、判断を誤るかもしれません。
1392年に建国され、日本に併合されるまで約500年続いた朝鮮王朝も、建国当初から中国の明朝と深いつながりがありました。
中国に呑み込まれることは避けたい。しかし、自分たちの力量もよくわかっているので、下手な抵抗をしても無駄である。
そこで、明朝中国の秩序体系をいわば丸ごと受け入れ、その中で自己主張をしていく形を早くから取るようになります。
明朝の対外秩序とは、どのようなものだったのか。
まず周辺の国々は、儒教の中心学派である朱子学に基づき、明朝の皇帝を天下の中心たる中華に君臨する天子と見なします。
そのため明朝皇帝に対する服属のあかしとして、その地の産物を貢ぎ物として天子のもとに持参(朝貢)し臣礼をとる、明朝皇帝は返礼としてその国の君長たることを認可する、というコンセプト・パフォーマンスです。
.
朝鮮王朝は、以上を受け入れ、明朝に対して朝貢関係を結びました。
この関係を、大国に事(つか)えるという意味で「事大」と呼びます。
さらに朝鮮王朝は朱子学を国家イデオロギーとし、明朝の官僚システムを積極的に取り入れました。
そうすることで、自分たちを「小中華」、すなわち中国に次ぐナンバー2、日本などその他の周辺国を野蛮な「夷狄(いてき)」と見なしたのです。
ただし、明朝は朝鮮を含めた周辺国をすべて同列の朝貢国と見なしていました。そのため、朝鮮は日本などを内心では見下しながらも、表向きは対等に交わる関係「交隣」を続けました。
■三国間のパワーバランスが変わる
朝鮮はこうした独自の対外関係を築いていましたが、16世紀後半、日本が急速な経済成長と国内統一を果たしたことによって、三国間のパワーバランスが変わります。
元寇の際は一方的に攻められて反撃できなかった日本が、その後約300年を経て強国化し、豊臣秀吉が朝鮮出兵に打って出ました。
これを機に朝鮮は、日本を「何を考えているかわからない、暴力的な脅威」と認識すると同時に、「中国に守ってもらおう」という意識が強くなります。
この朝鮮出兵は、朝鮮半島を舞台にした日本と明朝との戦争でした。
さらに300年後の日清戦争、その60年後の朝鮮戦争も、同様の構図です。
いずれも、日本やアメリカといった海洋のパワーと大陸のパワーとのぶつかり合いで、その接点が朝鮮半島だったわけです。
そのなかでどう生き延びていくか、朝鮮は考えていくことになります。
その後の中国では、明朝が日本との戦争によって衰退し、清朝が建国されました。
明朝は漢人の中華王朝でしたが、清朝は満洲人。朝鮮にとって夷狄の国であり、明朝とは比較になりません。
しかし、清朝を蔑みながらも服従し、徳川幕府が成立した日本とも対等の付き合いを行うようになりました。
朝鮮としては、軍事的には清朝にも日本にもかないません。
そのため、清朝とは「事大」、日本とは「交隣」の関係を保ち続けます。
一方、清朝は前代にいわゆる「倭寇」が沿岸部に盛んにやってきて、軍事的な脅威を与えたという認識で、日本とは関わりたくないという姿勢でした。
また、江戸時代の日本は「鎖国」の体制でしたから、その後の300年は三国間の均衡が保たれました。
この均衡を破ったのは、西洋列強の影響を受けた日本です。
西洋諸国は交易を求めてアジア各国に条約締結を迫り、清朝や朝鮮が大きくは変わらないなか、唯一突出して変わったのが日本でした。
明治維新を経て西洋化を推し進め軍事強国になりつつある日本を、清朝は強く警戒します。
「倭寇」や朝鮮出兵という「前科」があったからです。
その予想は当たり、1879年には清朝の属国だった琉球を一方的に日本に組み込む琉球処分を断行し、朝鮮とは1876年に、朝鮮を独立国と見なす江華島条約を結びました。










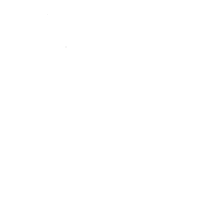

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます