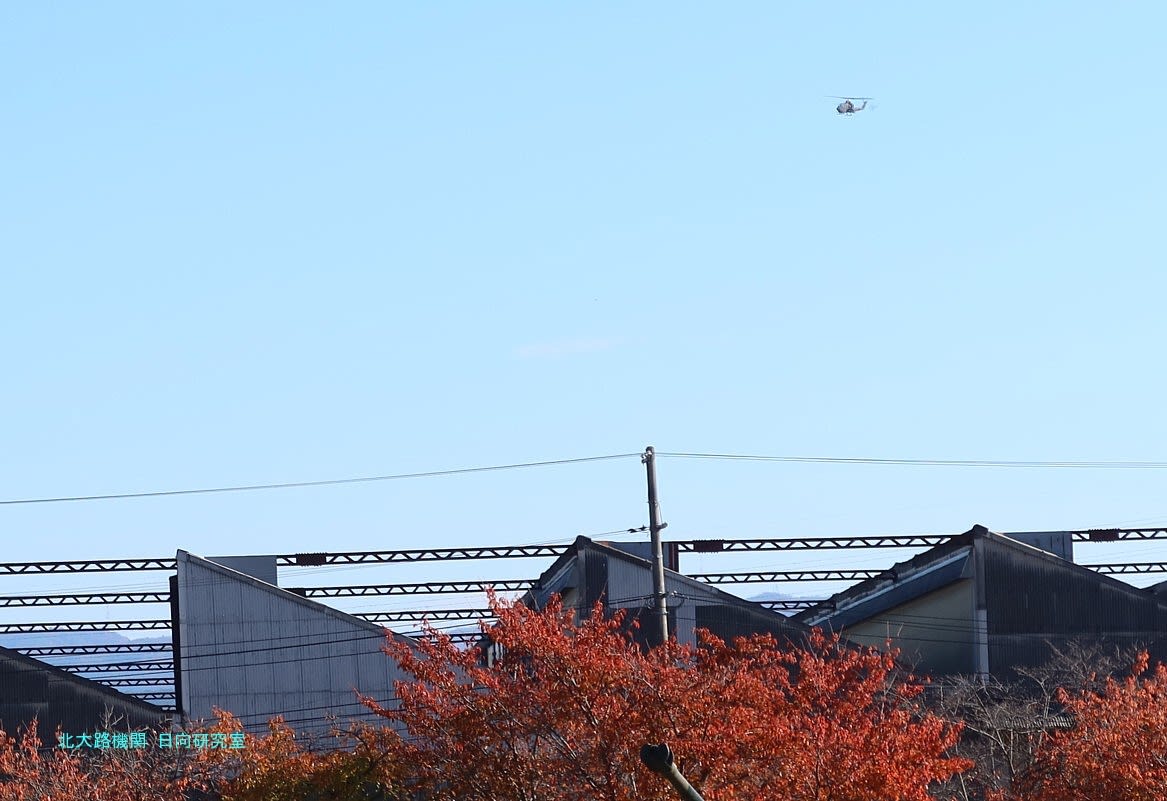■機甲師団支える73式装甲車
自衛隊を支え続けた老兵としまして北海道の73式装甲車を紹介しましょう、かつてはお隣滋賀の今津駐屯地にも配備されていた。

73式装甲車。陸上自衛隊唯一の機甲師団である第7師団記念行事における雄姿です。73式装甲車は乗員3名と人員9名を輸送する国産装甲車で重量13.4tのアルミ合金製装甲車、300hpの空冷ディーゼルエンジンを搭載し60km/hの機動力を有する装軌式装甲車です。

第7師団は自衛隊唯一の機甲師団であり、機動力を第一としています、機動力により防御線は迂回も包囲機動も突破も変幻自在であり、臨機応変の部隊陣形と強力な打撃力を兼ね備える事で、北海道防衛、想定される大陸からの機甲部隊侵攻を破砕するのが任務だ。

自衛隊に73式装甲車は350両が量産されました、1970年代中頃に一両の取得費用は一億円、当時の74式戦車が4億円といいますので、そんなものかと思われるかもしれませんが、その前型にあたる61式戦車の取得費用が1億円でしたので、なかなかに費用を要する。

SU-Tとして開発されました73式装甲車は前型の60式装甲車がNBC防護能力を有さない為に当時真剣に脅威であった戦術核による核戦場での生存性に問題があり、浮行性能を有さなかったために河川や湿地というウェットギャップでの踏破能力不足が懸念されていた。

74式戦車が制式化されますと60式装甲車はますます能力不足が懸念されまして、結果的に新型装甲車が開発される。当時は日本人の体格向上や装備の多様化により60式装甲車の車内は狭くなりすぎまして、定員はほぼ同じですが73式装甲車の車内容積は倍増したという。

全国の普通科部隊に73式装甲車を、高度経済成長期には当然考えられていたようですが、併せて小松製作所が開発した装輪装甲車である小型装甲車が本州九州を中心に当時急速に整備されていました高速道路網を利用し、本州九州に配備する構想もありました、しかし。

石油危機。73式装甲車が制式化されました1973年は中東にて第四次中東戦争が勃発し、自由主義圏の多くが親イスラエル政策を採っていたためにOPEC石油輸出国機構が石油輸出制限行うオイルショックが始まり、戦後一貫しての高度経済成長時代が終焉を迎えます。

10%経済成長の時代には7年間でGNI/GNP国民総生産が倍増したのですが、これが急にマイナス成長となったのです、当然財政難となり初の赤字国債発行が始まる、防衛費も影響を受けまして73式装甲車の量産計画も当然縮小され350両に留まってしまった、理由が。

東千歳の第7師団、機甲師団は機動力が第一ということは前述しましたが、73式装甲車は普通科連隊に戦車連隊や特科連隊にはもちろん、後方支援連隊の戦車直接支援部隊や通信大隊に施設大隊にも配備されていまして、戦車が全力で前進する場合にも随伴してゆく。

戦車大隊本部車両として本州や九州の戦車大隊にも73式装甲車は薄く広く配備されていましたが、73式装甲車にも老朽化の波が押し寄せまして、結果、陸上自衛隊は73式装甲車を北海道に集約配備する決定を、そして今は第7師団に集中配備する方向で縮小が続きます。

90式戦車は70km/hもの速力を発揮し、74式戦車の54km/hよりも更に早くなっています、出力重量比も高くなっていますので、それこそ馬力にものを言わせてどんどん不整地や急傾斜地を踏破してゆくことができるのですが、実は73式装甲車には厳しいともいわれる。

装軌装甲共通車両、としまして自衛隊は73式装甲車の後継開発を進めています。89式装甲戦闘車と車体を共通化させる計画であり、出力重量比も十分でしょう、73式装甲車は試作車にラインメタル20mm機関砲を搭載試験も行われており、漸くこれが実現するのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
自衛隊を支え続けた老兵としまして北海道の73式装甲車を紹介しましょう、かつてはお隣滋賀の今津駐屯地にも配備されていた。

73式装甲車。陸上自衛隊唯一の機甲師団である第7師団記念行事における雄姿です。73式装甲車は乗員3名と人員9名を輸送する国産装甲車で重量13.4tのアルミ合金製装甲車、300hpの空冷ディーゼルエンジンを搭載し60km/hの機動力を有する装軌式装甲車です。

第7師団は自衛隊唯一の機甲師団であり、機動力を第一としています、機動力により防御線は迂回も包囲機動も突破も変幻自在であり、臨機応変の部隊陣形と強力な打撃力を兼ね備える事で、北海道防衛、想定される大陸からの機甲部隊侵攻を破砕するのが任務だ。

自衛隊に73式装甲車は350両が量産されました、1970年代中頃に一両の取得費用は一億円、当時の74式戦車が4億円といいますので、そんなものかと思われるかもしれませんが、その前型にあたる61式戦車の取得費用が1億円でしたので、なかなかに費用を要する。

SU-Tとして開発されました73式装甲車は前型の60式装甲車がNBC防護能力を有さない為に当時真剣に脅威であった戦術核による核戦場での生存性に問題があり、浮行性能を有さなかったために河川や湿地というウェットギャップでの踏破能力不足が懸念されていた。

74式戦車が制式化されますと60式装甲車はますます能力不足が懸念されまして、結果的に新型装甲車が開発される。当時は日本人の体格向上や装備の多様化により60式装甲車の車内は狭くなりすぎまして、定員はほぼ同じですが73式装甲車の車内容積は倍増したという。

全国の普通科部隊に73式装甲車を、高度経済成長期には当然考えられていたようですが、併せて小松製作所が開発した装輪装甲車である小型装甲車が本州九州を中心に当時急速に整備されていました高速道路網を利用し、本州九州に配備する構想もありました、しかし。

石油危機。73式装甲車が制式化されました1973年は中東にて第四次中東戦争が勃発し、自由主義圏の多くが親イスラエル政策を採っていたためにOPEC石油輸出国機構が石油輸出制限行うオイルショックが始まり、戦後一貫しての高度経済成長時代が終焉を迎えます。

10%経済成長の時代には7年間でGNI/GNP国民総生産が倍増したのですが、これが急にマイナス成長となったのです、当然財政難となり初の赤字国債発行が始まる、防衛費も影響を受けまして73式装甲車の量産計画も当然縮小され350両に留まってしまった、理由が。

東千歳の第7師団、機甲師団は機動力が第一ということは前述しましたが、73式装甲車は普通科連隊に戦車連隊や特科連隊にはもちろん、後方支援連隊の戦車直接支援部隊や通信大隊に施設大隊にも配備されていまして、戦車が全力で前進する場合にも随伴してゆく。

戦車大隊本部車両として本州や九州の戦車大隊にも73式装甲車は薄く広く配備されていましたが、73式装甲車にも老朽化の波が押し寄せまして、結果、陸上自衛隊は73式装甲車を北海道に集約配備する決定を、そして今は第7師団に集中配備する方向で縮小が続きます。

90式戦車は70km/hもの速力を発揮し、74式戦車の54km/hよりも更に早くなっています、出力重量比も高くなっていますので、それこそ馬力にものを言わせてどんどん不整地や急傾斜地を踏破してゆくことができるのですが、実は73式装甲車には厳しいともいわれる。

装軌装甲共通車両、としまして自衛隊は73式装甲車の後継開発を進めています。89式装甲戦闘車と車体を共通化させる計画であり、出力重量比も十分でしょう、73式装甲車は試作車にラインメタル20mm機関砲を搭載試験も行われており、漸くこれが実現するのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)