
先日の教室(10.1 小玉精子先生)をベースに貝殻の種類を描き足しました。
右はコンク貝(コンクパールの母貝)です。左は手前が夜光貝、奥がほら貝です。
貝殻の色合いの美しさは、拙ブログ「さざえは色の宝壺」(2010.12.23付)で触れていましたが、
四周が海の日本では、多彩な色や形の貝殻に接することができ、蒐集家の方たちにはたまらないことでしょう。
昔から世界の各地域で、貝殻はその一部が螺鈿(らでん)として、
あるいは真珠を生む母貝などとして、装飾品の世界では珍重されてきました。
また、アメリカ、アフリカ、南太平洋諸島、中国などでは、「貝貨」(ばいか)として貨幣の役割も果たしていたようです。
その代表的な貝「宝貝」。
広辞苑(やや古い電子辞書)に「たからがい」と入力すると、宝貝そのものの説明のあと、
古代中国ではこの貝の一種を貨幣として使用したので、漢字の「財」や「資」など“経済”に「貝」を負うものが多いと。
漢字については“ああ、そうなんだ”と納得しながらも、広辞苑という辞書と中国・・・何かがあるのではないか、とも直感。
それは、かねてから、本辞書の、殊、中韓関係の内容には“歪さ”を感じていたからです。そこで他も調べてみました。
調べたた範囲でですが、他の辞書では、中国のことに触れていないか、触れても貨幣としてのことのみで漢字のことまでは触れていません。
確かに漢字のことは勉強にはなりましたが、
一方で、さすが中国・韓国に肩入れし過ぎてる(「注」参照)との評判の「広辞苑」だけのことはあるな、とも思いました。
でもここは乗りかかった舟、他に「貝」が入っている漢字にはどんなのがあるかと調べてみました。
アバウトなイメージながら、肯定的、否定的意味合いで分けますと
資、財、貴、賢、貫、賜、賀、賞、賛、貢、貞、贈、賓、贅、賑、貿、賃、貸、貯、販、購、買、費、貨、
賭、貧、負、債、賤、賄、賂、頑、賊、贔、屓、贋、賽
広辞苑には“経済”に関係するとされていますが、それだけでなく金銭や商いそれに社会生活そのものに関する用語も多いようです。
特に2段目には、中国そのものを象徴するような字が数多並んでいるように映ります。
渦状の「螺旋」。この形状も、日本や世界各国の建築物に見られるように、多くの建築家にとっての造形美なのでしょう。
ある学者さんによれば、DNAの構造も螺旋形だし、宇宙も、太陽系の惑星の回り方は、円ではなく螺旋状に回っているとか。
三次元の世界、しかも時間が入り、頭がついていけませんが、何やら面白そうな分野でもあるようです。
何気なく描いたカラスウリの蔓・・・こちらもひっそりながら渦巻いて・・・。
「注」
『広辞苑の罠』歪められた近現代史(水野靖夫著 祥伝社新書)
(本の帯の言葉:これでも日本の辞書といえるのか!)
は
右はコンク貝(コンクパールの母貝)です。左は手前が夜光貝、奥がほら貝です。
貝殻の色合いの美しさは、拙ブログ「さざえは色の宝壺」(2010.12.23付)で触れていましたが、
四周が海の日本では、多彩な色や形の貝殻に接することができ、蒐集家の方たちにはたまらないことでしょう。
昔から世界の各地域で、貝殻はその一部が螺鈿(らでん)として、
あるいは真珠を生む母貝などとして、装飾品の世界では珍重されてきました。
また、アメリカ、アフリカ、南太平洋諸島、中国などでは、「貝貨」(ばいか)として貨幣の役割も果たしていたようです。
その代表的な貝「宝貝」。
広辞苑(やや古い電子辞書)に「たからがい」と入力すると、宝貝そのものの説明のあと、
古代中国ではこの貝の一種を貨幣として使用したので、漢字の「財」や「資」など“経済”に「貝」を負うものが多いと。
漢字については“ああ、そうなんだ”と納得しながらも、広辞苑という辞書と中国・・・何かがあるのではないか、とも直感。
それは、かねてから、本辞書の、殊、中韓関係の内容には“歪さ”を感じていたからです。そこで他も調べてみました。
調べたた範囲でですが、他の辞書では、中国のことに触れていないか、触れても貨幣としてのことのみで漢字のことまでは触れていません。
確かに漢字のことは勉強にはなりましたが、
一方で、さすが中国・韓国に肩入れし過ぎてる(「注」参照)との評判の「広辞苑」だけのことはあるな、とも思いました。
でもここは乗りかかった舟、他に「貝」が入っている漢字にはどんなのがあるかと調べてみました。
アバウトなイメージながら、肯定的、否定的意味合いで分けますと
資、財、貴、賢、貫、賜、賀、賞、賛、貢、貞、贈、賓、贅、賑、貿、賃、貸、貯、販、購、買、費、貨、
賭、貧、負、債、賤、賄、賂、頑、賊、贔、屓、贋、賽
広辞苑には“経済”に関係するとされていますが、それだけでなく金銭や商いそれに社会生活そのものに関する用語も多いようです。
特に2段目には、中国そのものを象徴するような字が数多並んでいるように映ります。
渦状の「螺旋」。この形状も、日本や世界各国の建築物に見られるように、多くの建築家にとっての造形美なのでしょう。
ある学者さんによれば、DNAの構造も螺旋形だし、宇宙も、太陽系の惑星の回り方は、円ではなく螺旋状に回っているとか。
三次元の世界、しかも時間が入り、頭がついていけませんが、何やら面白そうな分野でもあるようです。
何気なく描いたカラスウリの蔓・・・こちらもひっそりながら渦巻いて・・・。
「注」
『広辞苑の罠』歪められた近現代史(水野靖夫著 祥伝社新書)
(本の帯の言葉:これでも日本の辞書といえるのか!)















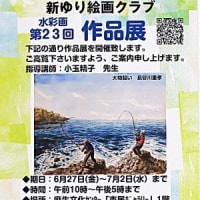








言われるまで貝がこのように漢字に関係をしていたとは全く気が付いていませんでした。否定的・肯定的区分も面白いですね。
それにカラスウリで螺旋状へと・・・
何かを見て、それをヒントに調べ、深めと次々に発想を発展させるのには感心するのみです。
優しさあふれる作品で癒されます。
それにしても貝の蘊蓄、恐れ入りました。