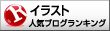「連続写真」。たまたま見つけたもので、何の写真かは知らない。古い写真をあしらった、古い雑誌かレコード・ジャケットだろうか。写っている男女が、なんとなく照れくさそうに見えて、特に女性がはにかみんでみえて、そこがいい。
肉体表現の一連の動きの流れを分割してみせる連続写真は、実際のところ“生命の輪切り”または“はにかみの輪切り”である。「人体の不思議展」などにあるような“肉体の輪切り”と同じなのだ。そこに写っているそれぞれの“瞬間”は、シャッターが切られるごとに、生命が細切れにされた瞬間であるだろう。そこに写っているのは“もうこの世に存在しなくなった魂の入れ物”としての人の思い出でしかないのである。
写真は、仮にそれがどんなにイキイキと見えても、常に“死”を写し取っている。写っているのは、印画紙の上でペッタンコにされて、息の根を止められた魂の抜け殻としての肉体や風景な訳だ。
写真は、何かの現象を静止させることによって、すべての生き物がいつか死ぬことを思い出させてくれる“非情の装置”だ。
特に、「連続写真」はその目的が、動きの表現(研究)にあるからこそ、逆説的に“動いていない”ことを伝え、それぞれに分割された瞬間とその行間から“二度と戻らない何か”感じさせる。
動きを撮ることを目的とする連続写真は、カメラマンの写真を支配しようという意識と力が弱くなるせいで、写真は写真そのものとして生きはじめ、特に生き物に対して、その非情さと悪意をむき出しにするようだ。彼女や彼が生きていようが死んでいようが知ったことではない。写真はただ無表情に“死”を写しだしてゆく。
女性から伝わってくる“はにかみ”。この“はにかみ”は“彼女の魂”に由来し、肉体に反映されたものである。連続写真は、その“はにかみ=魂”が、もう二度と戻ることのない過去だということを伝え、郷愁を誘う。彼女に対して、なにか現実的な思い出があるわけでもないのに郷愁の情を誘われるのは、写真が持つ魔法の力というよりは、あまりの写真の非情さゆえに感傷的になるからである。僕は写真が生命を閉じ込めることのできる装置だとは、どうしても思えないのだった。
“はにかみ”を感じ、“人の魂”を感じとるのは、まだ生きている僕の感傷から生まれた空想に過ぎないだろう。写真の“非情”は、見るものから“感傷”を引きだす。
また、“写真=死”は、逆説的に“かつて、そこに人が生きていた”ことを知らせてくれる。
写真は非情にも、鑑賞者が感じるだろう“情”を、予測して待ち受けているような節が感じられる。
だが、もしかするとそこにこそ“写真の非情”に秘められた“情”があるのかもしれない。