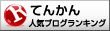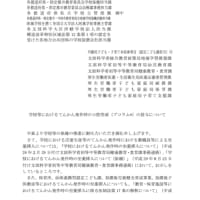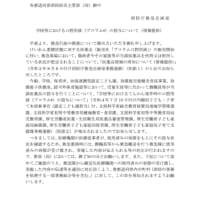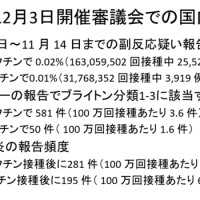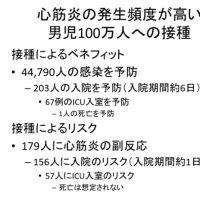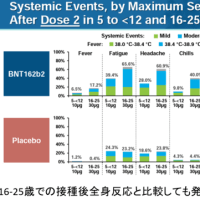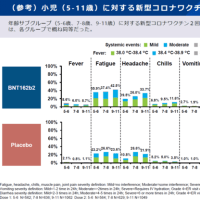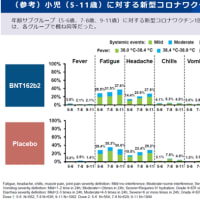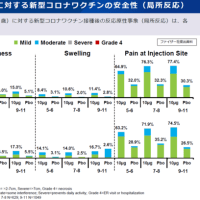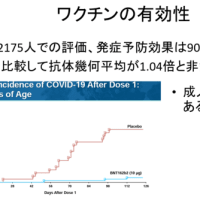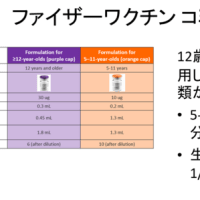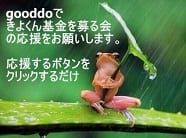ドラベ症候群は希少疾患ですが、インターネットなどを通じて、患者家族がつながって情報共有などが行われます。
患者会の方が作成されたホームページ(Dravet Syndrome Jp)ので中で患者会(ドラベ症候群 患者家族会)のことが紹介されています。
また、SMEI親の会(しゃぼん玉の会)という患者会もありますが、こちらは公式のホームページはないようで、個人の方のブログ(1)に入会方法が紹介されています。
このような取組の中で関係者の相互扶助が進むといいなと思います。
海外に目を向けると、Dravet Syndrome Foundation という財団法人では、疾患の啓発の他、寄附を募って研究活動を助成したり、学会を開催したり、患者家族のためのレクレーション等のイベントを運営しています。
医学会と協力しながら複数の国で活動しているInternational League Against Epilepsyという団体もあります。
国内で同様の研究支援活動をおこなっている基金にはきよくん基金があります。
イギリスにはDravet Syndrome UK というホームページもあるのですが、似たような蝶のデザインが使われているので調べてみると、紫の蝶がドラベ症候群の象徴として使われることがあるようです。
一般に蝶は、美しい姿で花から花へ自由に飛び回るイメージから、自由、希望、愛、喜び、幸福を示すイメージがある一方、蝶になってからの寿命が短く、傷つきやすく、天敵も多いことから、後悔、悲しみ、非恒久性、死を象徴することもあるようです。また、幼虫から成虫へ変態することから、変化、成長、死後の復活を意味することもあるようです。
そのあたりから紫の蝶が象徴として使われているものと推察しますが、何故紫なのかはよく分かりませんでした。