グリーンカードを持っていること(J-1ビザは受け付けない)を必須とするプログラムがたくさんありますが
これは私たちにとっては論外として
ホームページなどによく書かれているハードルを列挙します
1. 医学部卒業後5年以内である事
2. キャリアのブランクが無い事
3. 米国での臨床経験が1年以上ある事
4. 自分が応募する科を専門とする米国の医師による推薦状(LOR)が1枚以上ある事
ホームページでこれらの条件を見た時は絶望的になりました

私は2以外全部アウトでした。厳密に言うと、この2年はフルタイムではないのでオールアウト

これらの条件をクリアする為によく行われているのが横須賀や沖縄の海軍病院での研修と野口医学研究所主催のエクスターン研修です
海軍病院では、1年間研修をすると米国での経験と見なしてくれるようです。もっと大きいのが同時に4をクリアできる事です。つまり海軍病院の米国医師が推薦状を書いてくれるのはとても大きいのです。
野口のエクスターン研修はトーマスジェファーソン大学(TJU)関連病院とハワイ大学(UH)で研修するのですが
それらの施設で後にレジデントとしてマッチする可能性も高くなります
様々な(全ての)条件に抵触する私は、カンザスのNational Conferenceで多くのプログラムのディレクターと話をしてきました
履歴書を押し付けて質問をするふりをしつつ、なんとか自分を売り込もうといろいろ話をしてきましたが
そこで仕入れた話を上記の4つの条件に照らし合わせます
1. 医学部卒業後5年以内である事
- 5年とは限りませんが、卒後年数で区切っているプログラムはたくさんあります
- ただ生の声を聞いてみると、これは一応の条件であって、例外も認めるというプログラムもあるようです
2. キャリアのブランクが無い事
- これは,受験勉強やリサーチだけしていて、全くのブランクがある人を避ける為の条件のようです
3. 米国での臨床経験が1年以上ある事
- 結局、言語のバリアが無いかどうか?アメリカのシステムの中で機能できるかどうか?を知りたいようです
- 必ずしも必須条件ではなく、強い推薦状さえあれば大丈夫と複数のディレクターからいわれました
4. 自分が応募する科を専門とする米国の医師による推薦状(LOR)が1枚以上ある事~これが一番大事

- アメリカも実力主義とはいいつつ,結局はコネ社会です
- Strong recommendation,つまり「アメリカの医師による強いお勧めがある」があるというのが最も重要な鍵となります
- 私は最初、アメリカの家庭医研修育ちの日本人の先生方にLORを書いていただいていましたが、どれだけ優秀で、日本でどれだけ認知されていて、アメリカの家庭医育ちでも、LORの強さとしては、現役のアメリカ家庭医Facultyには及ばないと聞いていました。結局ぎりぎりになって或るUS Facultyの先生に書いていただけました! 本当に感謝です!

これらの条件をクリアできなくても、東京海上のNプログラム
に参加するなど、他にも方法はあります
結局言いたいのは
提示された条件をクリアしていなくても、
「その条件の背景に何があるのか」を情報収集して、一つずつクリアしていけば道は開ける、「何とかなる」ということです
ただ確実に留学を実現するには、やっぱり以下のいずれかを選択することをおすすめします
- 海軍病院で研修する
- 野口のエクスターン研修をする
- Nプログラムに参加する
- US facultyがティーチングに来ている施設で研修する(沖縄県立中部病院、音羽病院、手稲渓仁会病院、亀田メディカルセンターなど)















 拙書の紹介でした・・・
拙書の紹介でした・・・ こっちのほうは、たいした事ございません
こっちのほうは、たいした事ございません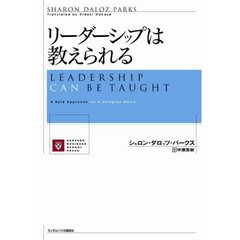
 ときどき
ときどき

 で愚痴っていました
で愚痴っていました


