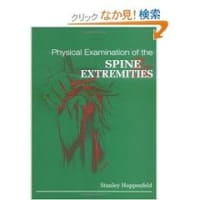「認定医制度はどうなっているのですか?」
「将来の保障はされるのですか?」
ほんの数年前まで医学生や研修医からよく聞かれたものです
「やっぱり内科認定医をとっておきたいです」
地域の診療所を中心に研修をしたあとに、市中病院へ転勤していった若手医師の言葉です
「そうか、将来の保障、専門性の保障が無いと若手はなかなか集まってくれないのか!」
そう思っていました
思っていましたので、3学会の合併や認定制度の流れなどをブログに書いたり、メーリングリストで発言したりしていました
が、どうやら若い人たちのメンタリティは急速に変化しているようです(全体の傾向として)
「医局の説明会でも、そのような質問はこの数年ぱったりと出なくなった」と上司から聞きました
新初期臨床研修医制度の影響が大きいように思います
これまでは関連病院(ジッツ)の多い大きな医局に入って、将来が保障されることが安心のよりどころでした
病院は認定医や専門医が何人という基準でさまざまな施設認可を受けますので、認定医や専門医をもっていることが、病院へ配属されるためのパスポートだったわけです
ところが新初期臨床研修医制度が始まり、医学生は自分でよりよい研修を受けられる施設をさがすことを始めました
さらにその後はすぐれた後期研修を受けられるところが、彼らの関心事です
学会の動向や、認定制度は検討事項の中で相対的に順位が下がっているようです
もうひとつは、新しい研修制度が引き金となった病院崩壊、医局崩壊
「大きな医局に入って、よい病院をあてがってもらう」ということが唯一に近いキャリアプランだった時代は終わったのです
「とにかくよい研修を受けて、自分の能力を高めればなんとかなる」
そうであれば、健全なメンタリティといえるでしょう
逆に認定制度の確立を待ち望んでいるのは、指導医層なのかもしれません