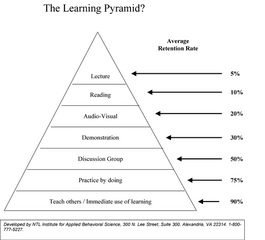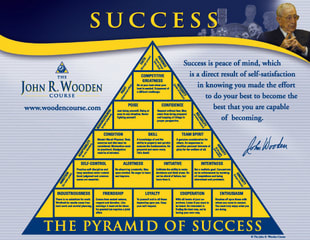「新小児科医のつぶやき」というブログで「総合医」についての記事を読みました。
「総合医を養成するにしても、内科、外科、小児科、産婦人科、救急を一通りできるようになるのに10年かかるだろう」というご意見でした。
的を得たご指摘で、特に訴訟の多い昨今、ジェネラルにやるにしても、家庭医のような守備範囲の広さは厳しいものがあります。
どの程度の期間修行すれば一人前になれるのか?家庭医療学会では家庭医の後期研修施設認定の要件を4年間の後期研修期間としています。
もちろん研修が終わったら完璧というのは無理な話で、生涯勉強し続ける「反省的実践家」という姿勢を身につけることが一番大事なことだと思います。
それはさておき、なぜ厚生労働省が「総合医」「かかりつけ医」制度を急いでいるのでしょうか?
今年の3月に「かかりつけ医制度」が報道されたときにまとめた文章を改変して載せます。(過激だったので、投稿できずにパソコンで眠っていました。)
-----------------------------------------------------------------
医療制度の変革の底流にあるもの~家庭医療はどこへ行くのか?
日本の医療は大きく揺らいでいる。
地域における医師不足のニュースが連日流れるなか、政府は医療費高騰の抑制をうったえ、診療報酬体系の相次ぐマイナス改訂。
そのなかでの在宅医療費はプラス改訂され、先日ニュースでは「かかりつけ医制度」の導入の流れが報道された。
家庭医療学会員の多くは、「何となく時代の流れは追い風かな?」と思われているのではないか。
しかしこうしたドラスティックな流れがどのような力学ですすんでいるのかを考えないと、「何となく追い風」に乗り遅れてしまうかもしれない。時代はこの1、2年でそれだけ大きく変わりつつあるのだ。
そこで今何が起きているのかを整理し、今後私たちがどのようにアクションをとっていくべきかを考えてみたいと思う。
何が今までの医療制度をつくってきたか?
現在の医療体制が形作られたのは、195年に「国民皆保険」と「フリーアクセス」制度が導入されてからである。世界に類を見ない優れた制度であり、長寿大国日本をつくりあげるのに多大な貢献をしてきたのは確かである。
しかし医療の高度専門化、細分化がすすみ、高価な医療機器が開発されるにつれ、医療費の高騰が問題となってきた。
現在の開業医の診療形態現在の開業医は、その多くが大病院で専門医として腕を磨いた後に、その専門家を掲げて開業している。どうしてこのような形態が出来上がったのかを考えてみると、そこには必然性がある。
フリーアクセスがあれば、「専門家」にかかりたいのは自然の流れである。どの医者へも自由に、金銭的な差もなくかかれるとすれば、なるべく大きな施設の専門家が選ばれるのは理である。腰が痛ければ大病院の整形外科を選ぶし、目がかすめば眼科にかかる。
近所の開業医が成り立っているのは、フリーアクセスが完璧ではないということが一番の要因だと思われる。特にアクセス制限が大きい。大病院は遠いし、長時間待たされる。
そして同じ開業医同士、特に都会で競争に勝つには開業医であっても専門性を武器にしていくのは戦略的な必然である。患者に選ばれるためには「専門」というのは目に見える分かりやすい差別化である。患者さんは大病院の専門医にかかりたいが、それは難しいので「○○病院の消化器内科部長をやっていた××先生」に診てもらうことで満足するのである。
家庭医療にフィールドはあるのか?
こういっては過激かもしれないが、 理論上「国民皆保険、フリーアクセス」の理想的な環境下では、家庭医療のフィールドは存在しない。
前述のように、患者さんがなるべく大きな施設の専門家にかかりたいと思うのが理だからである。
自分がどのような病気か分からず、何科にかかったら良いか分からない場合はジェネラリストにかかるだろうが、大病院の内科を選ぶだろう。
「近所の何でも相談できるなじみの医者」という理想の家庭医像なら選ばれるのではないか?との反論はもっともである。しかし「近所の何でも相談できるなじみの医者」を好む人がいるのは確かだろうが、「近所の何でも相談できるなじみの専門医」の方が選ばれる可能性は高い。前にも述べたが、そうやって多くの開業医は生き延びてきたのだ。
近所の消化器内科で胃薬をもらい、整形外科で腰をみてもらい、喉が痛いと耳鼻科にかかるのだ。患者さんはそうして自分で医師を自由選択している。
そこに「家庭医が専門です」、「何でもみます」とアピールしても、
「何でもみる」=「何も診ることができない」=「専門が無い」
と最初に解釈されるのは仕方が無い。
少なくとも家庭医の良さの本質が浸透していない現状では、個人が家庭医をアピールするには、かなりの労力と時間が必要とされる。
そんな労力を避けるために「家庭医」と自任しつつ、患者さんには「内科の△△です」などと名乗っているジェネラリストの先生も多いのではないだろうか?(実は私も・・・)
「国民皆保険、フリーアクセス」の理想的な環境下では家庭医のフィールドは無いと述べたが、現状でも家庭医が活躍できるニッチ(あえてニッチと表現する)な領域は存在する。
それは地域医療であり、都会の貧困層である。地域では物理的なアクセス制限があり、都会の貧困層は経済的な制限を受けているからである。(前者を地域医療振興協会、後者は都会の民医連などが積極的にカバーしている)
日本の医療にこれから何が起きるのか?
政府による医療費削減への戦略が着々と進んでいる。諸外国を見渡せば様々な方法で医療費抑制政策がとられている。
医療費を制限するには受けられる医療を金銭かシステムで制限するのが一番手っ取り早い。
ヨーロッパでは年齢による制限が一般的である。
例えば米国では保険による制限をかけている。(米国=medicare, medicade, terminalの保険)
そしてアクセス制限。一番分かりやすいのは英国のGP制度である。
在宅の重用~アクセス制限は始まった
近年、在宅医療が重用されている。保険改訂をみても明らかなように、厚生労働省は病院から在宅へ患者を誘導しようとしている。
もちろん在宅医療の良さ、住み慣れた環境でなるべく過ごしてもらうということの良さは否定しないし、私も在宅医療は大好きである。
しかし在宅が重用されているのは、本当は経済的な理由であることを忘れては行けない。
そしてこの在宅へのシフトこそが、これから始まるアクセス制限の第一歩だと思われる。通院できない入院中の患者を在宅へシフトするというのは、大変分かりやすいアクセス制限である。
さらに「かかりつけ医制度」である。75歳以上の高齢者向けに、公的なかかりつけ医を優遇するという制度が導入されるという。とりあえずかかりつけ医への金銭的優遇のみとし、アクセス制限は設けないとのことであるが、これも次への布石であろう。
受け皿となるかかりつけ医の浸透がすすめば、次にアクセス制限がすすめられるだろう。
医療制度の流れと家庭医療学会への提言
国民皆保険は基本的には堅持されるだろうが、色々な形で負担率はさらにあがっていくだろう。そして個人の任意保険などによるカバーの比率は上がって行くと思われる。
フリーアクセスは前述のように制限される方向になるだろう。かかりつけ医による受け皿が浸透すれば、英国式に近いゲートキーパー制度が導入される可能性が高い。
興味深いのは、近年の英国のGPでは完全なジェネラリストからサブスペシャリティを持ったGPへ全体の流れがシフトしていることだ。GPにインセンティブを与えて、一定の専門性を習得させて差別化をすすめている。
そういう意味では現在の日本の開業医と英国の純粋なGPとの中間の形態が最終的な理想型なのかもしれない。
家庭医療学会ではプライマリケア学会、日本総合診療医学会、医師会と協議をしながら現在は施設認定制度をすすめている。将来的には認定制度につながっていくのだろうが、プラマリケア医,ジェネラリストが共同歩調を取っていくという戦略は堅持する必要がある。
家庭医療学会が政府にアピールすべきこと(査読の入った論文で証明するのが望ましい)
日本でも家庭医療によって医療費が抑制できること
日本でもゲートキーパーとしての役割が十分に果たせる
こと
庭医療学会が国民にアピールすべきこと
家庭医というものの良さ、認知度を上げる
こと
家庭医療にとって時代は間違いなく追い風なのだが、政府と国民の動向に乗り遅れると、思わぬ方向に制度がずれていく恐れもある。変革はそれだけ大きく、急激にすすんでいるのである。