春一番も吹き、少しずつ暖かさが垣間見られるようになってきました

もうすぐ弥生3月、3月といえばおひな様、
南予にも結構観光的なおひな様があるみたいです
宇和島の伊達博物館では
「ひな人形とひな調度展」が4/10まで
宇和の愛媛県歴史文化博物館では
西条藩松平家中心の「おひなさま展」が4/110まで
そして八幡浜市の真穴地区の豪華な
「真穴の座敷雛」が4/2・3の2日間
開催されます
ここでひな祭りの「うんちく」を少し?
----------------------------------
ひな祭の始まり
お雛様が3月3日の行事となっていくのはだいたい江戸時代の初期の頃です。
元々3月3日は上巳(桃の節句)といい、曲水の宴が行われるとともにお祓いをする
慣習があったようです。これに流しびなが結びついて長い間に雛祭りの下地ができて
いたようです。
寛永6年(1629)の3月3日上巳に後水尾天皇の中宮東福門院和子の方が、
娘の興子(おきこ)内親王、すなわち後の明正天皇のために雛遊びを催したという
記事が西洞院時慶卿記に書かれており、これが記録されている最古の雛祭りとされます。
* 徳川家光の長女千代姫は寛永14年3月5日の生まれでした。そこで正保元年(1644)の
桃の節句を直前に控えた3月1日、7歳の佳儀のお祝いと兼ねて諸老臣より千代姫に
ひな人形のプレゼントがありました。以後大奥では女の子が生まれる度にひな人形が
贈られる風習が生まれました。
* 雛祭りが3月3日に定着したのは延宝年間(1673-1681)の頃のようです。このころから
俳句の歳時記に「ひな」が3月3日の言葉として必ず取り上げられるようになってきています。
この手の本への初出は寛永18年(1641)の誹諧初学抄ですが、それより後に出た同種の本で
全く触れていないものもありますので、その頃はまだ民間では定着には到ってなかったようです。
* 11代将軍将軍家斉の治世の大奥は大変な騒ぎでした。この将軍はたいへんな子沢山で、
女の子だけでも20人以上もうけていますので、そのそれぞれの女の子たちにあちこちから
ひな人形がプレゼントされる訳で、人形職人も立派なひな人形を作り上げるのに大忙しで
あったと言われます。
ひな人形の形式の変化
もともとひな人形というのは子供達がおままごとをするためのものでしたので、
初期の頃は非常に簡素なものでした。これは今でいえば立ち雛の形式です。ところが
江戸時代に入って、大人がプレゼントするものとなった時に質的な変化が起きます。
それまではひな人形をかざるにしてもせいぜい床の上に毛氈を敷いてその上に並べる
程度のものだったのが、きちんと台を付けたり段を組んだりして、立派な飾り付けを
するようになります。そして雛人形も豪華な衣装の座り雛が登場してきます。
この座り雛が登場した初期の頃のひな人形が寛永雛です。女雛・男雛ともに同じ模様の
小袖を着て、袖を広げて手は見えていません。サイズとしては10cm程度の大きさです。
これがやがて享保雛になりますと、サイズも40cmから60cmくらいと巨大なものも
作られるようになり、女雛は唐衣に裳姿、天冠を付け檜扇を持ち、男雛は束帯様装束で
白平絹袴をつけ、烏帽子をかぶって笏を持っていました。巨大なものになると
等身大のものまであったそうです。
江戸で享保雛がはやっている頃、京都に雛人形作りの大名人岡田次郎左衛門が出ます。
彼及びその弟子たちの作った雛人形は次郎左衛門雛と呼ばれ、やさしい曲線をうまく使って
顔も可愛いらしかったため、大人気となりました。他にも京都の人形作りの名家には
山科家・高倉家というのがあり、それぞれ山科雛・高倉雛として人気がありました。
現在のひな人形の主流につながる形式のものは古今雛といわれ、明和・安永年間
(1764-1781)頃に江戸で流行しはじめたようです。お道具がたくさん加わり、人形の容貌は
写実的で、装束は益々複雑になりました。

もうすぐ弥生3月、3月といえばおひな様、
南予にも結構観光的なおひな様があるみたいです
宇和島の伊達博物館では
「ひな人形とひな調度展」が4/10まで
宇和の愛媛県歴史文化博物館では
西条藩松平家中心の「おひなさま展」が4/110まで
そして八幡浜市の真穴地区の豪華な
「真穴の座敷雛」が4/2・3の2日間
開催されます
ここでひな祭りの「うんちく」を少し?
----------------------------------
ひな祭の始まり
お雛様が3月3日の行事となっていくのはだいたい江戸時代の初期の頃です。
元々3月3日は上巳(桃の節句)といい、曲水の宴が行われるとともにお祓いをする
慣習があったようです。これに流しびなが結びついて長い間に雛祭りの下地ができて
いたようです。
寛永6年(1629)の3月3日上巳に後水尾天皇の中宮東福門院和子の方が、
娘の興子(おきこ)内親王、すなわち後の明正天皇のために雛遊びを催したという
記事が西洞院時慶卿記に書かれており、これが記録されている最古の雛祭りとされます。
* 徳川家光の長女千代姫は寛永14年3月5日の生まれでした。そこで正保元年(1644)の
桃の節句を直前に控えた3月1日、7歳の佳儀のお祝いと兼ねて諸老臣より千代姫に
ひな人形のプレゼントがありました。以後大奥では女の子が生まれる度にひな人形が
贈られる風習が生まれました。
* 雛祭りが3月3日に定着したのは延宝年間(1673-1681)の頃のようです。このころから
俳句の歳時記に「ひな」が3月3日の言葉として必ず取り上げられるようになってきています。
この手の本への初出は寛永18年(1641)の誹諧初学抄ですが、それより後に出た同種の本で
全く触れていないものもありますので、その頃はまだ民間では定着には到ってなかったようです。
* 11代将軍将軍家斉の治世の大奥は大変な騒ぎでした。この将軍はたいへんな子沢山で、
女の子だけでも20人以上もうけていますので、そのそれぞれの女の子たちにあちこちから
ひな人形がプレゼントされる訳で、人形職人も立派なひな人形を作り上げるのに大忙しで
あったと言われます。
ひな人形の形式の変化
もともとひな人形というのは子供達がおままごとをするためのものでしたので、
初期の頃は非常に簡素なものでした。これは今でいえば立ち雛の形式です。ところが
江戸時代に入って、大人がプレゼントするものとなった時に質的な変化が起きます。
それまではひな人形をかざるにしてもせいぜい床の上に毛氈を敷いてその上に並べる
程度のものだったのが、きちんと台を付けたり段を組んだりして、立派な飾り付けを
するようになります。そして雛人形も豪華な衣装の座り雛が登場してきます。
この座り雛が登場した初期の頃のひな人形が寛永雛です。女雛・男雛ともに同じ模様の
小袖を着て、袖を広げて手は見えていません。サイズとしては10cm程度の大きさです。
これがやがて享保雛になりますと、サイズも40cmから60cmくらいと巨大なものも
作られるようになり、女雛は唐衣に裳姿、天冠を付け檜扇を持ち、男雛は束帯様装束で
白平絹袴をつけ、烏帽子をかぶって笏を持っていました。巨大なものになると
等身大のものまであったそうです。
江戸で享保雛がはやっている頃、京都に雛人形作りの大名人岡田次郎左衛門が出ます。
彼及びその弟子たちの作った雛人形は次郎左衛門雛と呼ばれ、やさしい曲線をうまく使って
顔も可愛いらしかったため、大人気となりました。他にも京都の人形作りの名家には
山科家・高倉家というのがあり、それぞれ山科雛・高倉雛として人気がありました。
現在のひな人形の主流につながる形式のものは古今雛といわれ、明和・安永年間
(1764-1781)頃に江戸で流行しはじめたようです。お道具がたくさん加わり、人形の容貌は
写実的で、装束は益々複雑になりました。














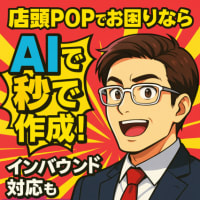

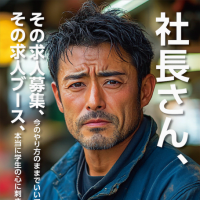


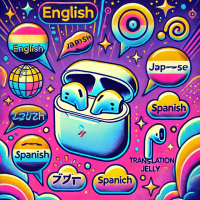
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます