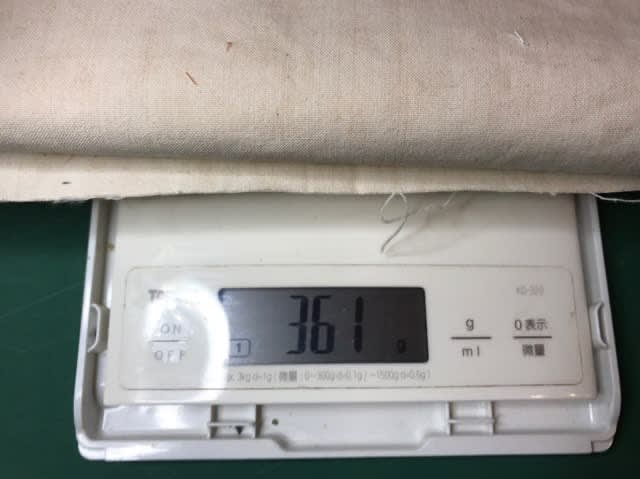昨年10月に取り掛かった結城紬の洗い張りからの袷の着物は、プーさんの一時帰国で見事中断
12月も何やかやと忙しく(ワンピースを縫ったりもしましたが)
年明けてやっと続きを始めています
袖が出来ました
この反物は、かなり古い物のようで、反物幅が9寸6分(36.5cm)しかありません
私の着物の袖幅は9寸(34cm)に統一してあります
今回も9寸幅にしましたが、袖付けの縫い代は2分😅

私としてはギリギリ許容範囲ですが、プロの仕立て屋さんなら、9寸幅には無理だと言われそう
昔の着物にはいいものがとてもたくさんありますが、現代の体格で着るには無理になってきました
袖幅を保持するために布を足すという手もありますが、柄を考えるとなかなか難しいなぁと思います
私が袖に別布を足して仕立てた着物を見たのは、NHKの朝ドラ「ごちそうさん」の杏さんの着姿でした
パリコレにも出ていた杏さんの高身長なら、やむを得ないなぁと思いながら見たものです
もちろん違和感なく着ていましたが
袖が出来たら仕立ての半分は出来た❗️
私が習った和裁師の先生は口癖のように言っていました
やっと半分💦
完成までまだまだかかります
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
今夜は焼き餃子

我が家は両面をしっかり焼いた餃子が好きです
で、今日はかなり上手く出来ました
ロッジのスキレットを買ってそろそろ一年かな
油もすっかり馴染んで扱いやすく、餃子では特に重宝しています
実はもう一回り小さなスキレットも欲しいのですが、我が家のIHクッキングは非対応
年齢的に、もう新しい物を買うより、今ある物で工夫していかなければと、自分に言い聞かせています
他に地場産のマグロが出ていたので、お刺身に
やはり生のマグロは美味しいなぁと、マグロ好きではない私も思います
今日も写真は撮り損ねていますが、味噌汁とキムチと、玄米ご飯も炊き立てはやはり美味しくて
体重が😰😰😰😰
恐ろしい事になっています
でも寒いと、色々食べたくなるし、甘いものも欲しいし
困ったものです
大人になるまで、餅なども含めて正月料理が苦手でした
いつも冬は体重が落ちて、夏に太っていたのですが
今では冬の方が
いえいえ、冬の方も😅