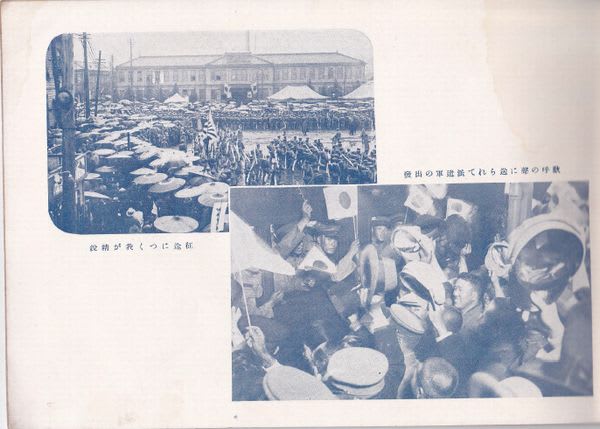夫の仕事の関係で、若い頃は大瀬戸、平戸、壱岐と長崎県内の離島や僻地を転々とした。
その中でも一番思い出深いのが、平戸での生活だった。
当時はまだ橋が架かっておらず、フェリーで平戸島に渡らなければならなかった。

平戸島には空いている住宅がなく、職場で用意されたのは人里離れた田平の住宅だった。病院もないようなまったく見知らぬ土地で、生後5ヶ月の赤ん坊を抱え途方に暮れる思いだった。
そんな時、「平戸に空き部屋が沢山ある住宅があり間借りできる」との話が舞い込んできた。問い合わせると「いいよ。」との返事で、引っ越したその日のうちに再度の引越しをやった。
県立猶興館高校の向い側の坂道を上り詰めた三叉路のそばにその住宅はあった。
総二階建ての大きな家で、一階の右半分を使っていい、ということになった。
8畳2間と6畳2間、それにダイニングと言えば聞こえはいいが広い板張りに、なぜか、流し台が3つも付いていた。
そこを好きなように使っていいと言って貰ったのだ。
電話で頼んだだけの、見も知らぬ他人の私たちを住まわせて下さったのだから驚きだが、驚きはそれだけではなかった。
2人目の子どもを平戸で生んだが、「赤ん坊を毎日風呂に入れるから」と風呂を大きくし温水器まで設置していただいたのだ。
あとで知ったのだが、平戸では有名な変人で頑固者として名が通っている方だった。
その方が亡くなられ、お葬式に夫と参列したのだった。霊柩車を見送って、久しぶりに平戸の町を歩いたが、日差しは柔らかいものの海からの風は冷たかった。


往路は西九州自動車道を通ったが、復路は旧道を通り佐々川の流量を見ようということになった。
「どこに行っても、石木ダムのことが頭から離れないね。」と夫と笑ったが、本当にそうなのだ。
おまけに、佐々町の清峰高校先の道路工事現場には、石木のゲート前に里村建設から派遣されていたガードマンのKさんがいるではないか。
車を止めて少し話をしたが、「石木の情報は自分たちには何も入ってこないんですよ。」とのことだった。

佐々川の流れも普段と変わらず、止まることなく悠々と流れていた。

この川の遊休水利権は、もっと有効に使われるべきだ。
そうすれば、石木ダム建設を中止しても、2年に1度渇水が起こっても、佐世保市民が水がなくて受忍の限界だという事態は絶対に起こることなどない。
その中でも一番思い出深いのが、平戸での生活だった。
当時はまだ橋が架かっておらず、フェリーで平戸島に渡らなければならなかった。

平戸島には空いている住宅がなく、職場で用意されたのは人里離れた田平の住宅だった。病院もないようなまったく見知らぬ土地で、生後5ヶ月の赤ん坊を抱え途方に暮れる思いだった。
そんな時、「平戸に空き部屋が沢山ある住宅があり間借りできる」との話が舞い込んできた。問い合わせると「いいよ。」との返事で、引っ越したその日のうちに再度の引越しをやった。
県立猶興館高校の向い側の坂道を上り詰めた三叉路のそばにその住宅はあった。
総二階建ての大きな家で、一階の右半分を使っていい、ということになった。
8畳2間と6畳2間、それにダイニングと言えば聞こえはいいが広い板張りに、なぜか、流し台が3つも付いていた。
そこを好きなように使っていいと言って貰ったのだ。
電話で頼んだだけの、見も知らぬ他人の私たちを住まわせて下さったのだから驚きだが、驚きはそれだけではなかった。
2人目の子どもを平戸で生んだが、「赤ん坊を毎日風呂に入れるから」と風呂を大きくし温水器まで設置していただいたのだ。
あとで知ったのだが、平戸では有名な変人で頑固者として名が通っている方だった。
その方が亡くなられ、お葬式に夫と参列したのだった。霊柩車を見送って、久しぶりに平戸の町を歩いたが、日差しは柔らかいものの海からの風は冷たかった。


往路は西九州自動車道を通ったが、復路は旧道を通り佐々川の流量を見ようということになった。
「どこに行っても、石木ダムのことが頭から離れないね。」と夫と笑ったが、本当にそうなのだ。
おまけに、佐々町の清峰高校先の道路工事現場には、石木のゲート前に里村建設から派遣されていたガードマンのKさんがいるではないか。
車を止めて少し話をしたが、「石木の情報は自分たちには何も入ってこないんですよ。」とのことだった。

佐々川の流れも普段と変わらず、止まることなく悠々と流れていた。

この川の遊休水利権は、もっと有効に使われるべきだ。
そうすれば、石木ダム建設を中止しても、2年に1度渇水が起こっても、佐世保市民が水がなくて受忍の限界だという事態は絶対に起こることなどない。