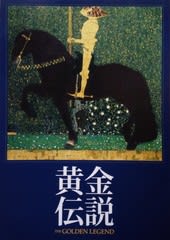伊万里駅:駅ビル2階に『伊万里・鍋島ギャラリー』があります。
360年前のものから展示があります。
ワンルームの展示室です。歴史順に展示され、わかりやすくなっています。
30分ぐらいですが見ごたえあります。
白い壁の展示室で蛍光灯の灯の元で見ますので、藍色も青磁も金襴も しっかり見えます。
淡い光の中の方が美しく見えるものですが、繊細な柄を見るには白い光は欲しいものです。
今は資料館になっている商館です。
ボランティアの方が説明してくださいました。

江戸時代 各地方各藩の方が陶器の買い付けに来ます。
来るといっても、注文を依頼し、作って焼いてなので、数か月逗留します。
主はこの方達が飽きないように、様々な芸事でもてなしたそうです。
様々な教養が必要だったとか・・・。

欄間も凝っています。

ビルトイン家具です。

ビルトインに興味を示した私に、ボランティアの方が、『開けてもいいですよ』
引出には使いこまれた段は取っ手の下の塗装の色が薄らいでいます。
開けやすい高さは、やはり日用品の場所ですね。
100年以上は経ているのに、狂わない引出。
たんすを作った人も、壁を作った人も技術力がすごい。
その一部、藩士なので刀を持ってきています。しまう引出、鍵付きです。

伊万里駅までの帰り道はゆっくり歩きながら 目で楽しみます。
ブロック塀:外部に磁器タイルは珍しいです。
微笑ましい水栓の花たち・・・濃紺部分は遠目に一瞬、柵のように見えます。

上部にはキャンドルを立てるタイプです。迫力あります。

壺に蓋と取っ手が付くと別物になりますね。

メインストリートの床には特産品などのさりげないお知らせ。
タイルの使い方・・・何かの折に参考にします。

唐津風の柄も使いようによっては洋風にも・・これいいかも・・
アイアンのデザインを思い出します。

伊万里からの直通バスで、博多のホテルへ。
このブログ[3:翌日の唐津行き]へ続きます。
―――――――――――――――――――――――――――*――――――――――――――――――――――――
一般の方を対象に『インテリアのレッスン』セミナーを
7~12月第3土曜日2-4時 全6回名古屋 栄で開催いたします。
インテリアに興味のある方がいらっしゃいましたら、是非ご参加ください。
詳細は http://iclesson.com へ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
360年前のものから展示があります。
ワンルームの展示室です。歴史順に展示され、わかりやすくなっています。
30分ぐらいですが見ごたえあります。
白い壁の展示室で蛍光灯の灯の元で見ますので、藍色も青磁も金襴も しっかり見えます。
淡い光の中の方が美しく見えるものですが、繊細な柄を見るには白い光は欲しいものです。
今は資料館になっている商館です。
ボランティアの方が説明してくださいました。

江戸時代 各地方各藩の方が陶器の買い付けに来ます。
来るといっても、注文を依頼し、作って焼いてなので、数か月逗留します。
主はこの方達が飽きないように、様々な芸事でもてなしたそうです。
様々な教養が必要だったとか・・・。

欄間も凝っています。

ビルトイン家具です。

ビルトインに興味を示した私に、ボランティアの方が、『開けてもいいですよ』
引出には使いこまれた段は取っ手の下の塗装の色が薄らいでいます。
開けやすい高さは、やはり日用品の場所ですね。
100年以上は経ているのに、狂わない引出。
たんすを作った人も、壁を作った人も技術力がすごい。
その一部、藩士なので刀を持ってきています。しまう引出、鍵付きです。

伊万里駅までの帰り道はゆっくり歩きながら 目で楽しみます。
ブロック塀:外部に磁器タイルは珍しいです。
微笑ましい水栓の花たち・・・濃紺部分は遠目に一瞬、柵のように見えます。

上部にはキャンドルを立てるタイプです。迫力あります。

壺に蓋と取っ手が付くと別物になりますね。

メインストリートの床には特産品などのさりげないお知らせ。
タイルの使い方・・・何かの折に参考にします。

唐津風の柄も使いようによっては洋風にも・・これいいかも・・
アイアンのデザインを思い出します。

伊万里からの直通バスで、博多のホテルへ。
このブログ[3:翌日の唐津行き]へ続きます。
―――――――――――――――――――――――――――*――――――――――――――――――――――――
一般の方を対象に『インテリアのレッスン』セミナーを
7~12月第3土曜日2-4時 全6回名古屋 栄で開催いたします。
インテリアに興味のある方がいらっしゃいましたら、是非ご参加ください。
詳細は http://iclesson.com へ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――




















 お二人の大きさから考えると1升瓶ぐらいの大きさかも?
お二人の大きさから考えると1升瓶ぐらいの大きさかも?






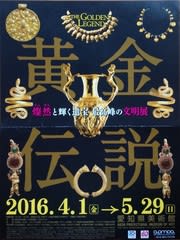 。
。