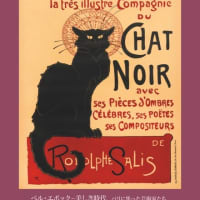ウズベキスタン大使館主催「ウズベキスタン・ウィーク・イン・ジャパン」工芸品編
皆さま、こんにちは!最近は暑い日が続いていますね・・・
心地の良い春はどこへやら、と、春が恋しくてたまりません。
これから梅雨に入るのかと憂鬱な気分になりかけていますが、そんな気分を吹き飛ばしてくれるイベントにご招待をいただきました
赤坂区民センター・区民ホールにて、5月15日(火)・16日(水)に開催された「ウズベキスタン・ウィーク・イン・ジャパン」。
心ゆくまでウズベキスタンの文化や芸術を堪能しました。
工芸品の展示に加え、民族楽器の演奏、伝統舞踊、主催者のお茶目なジョークなど盛りだくさんの内容でした

アートインプレッションのブログではイベントの一部をご紹介し、この楽しい気持ちを共有させて頂くと共に、
ウズベキスタンの文化・芸術について触れてみたいと思います
今回は、展示されていた工芸品をテーマにご紹介させて頂きます。
それでは、ウズベキスタンの妖艶で美しい文化の世界をお楽しみ下さい

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イベントで出会った素晴らしい工芸品をご紹介する前に、ウズベキスタンについてお話しさせて頂きたいと思います。
ウズベキスタンは、中央アジアの国でキルギスの西に位置しており、面積は、日本の約1.2倍(447,400㎢)。
人口は約3,020万人で、人口のほとんどをイスラム教スンニ派が占めています。
国内には100以上の民族がおり、多様性を重視する国としても知られているようです
公用語はウズベク語で、現在は1992年より制定された新正書法であるラテン文字で表記されていますが、キリル文字での旧正書法もいまだに残っているとか。
その証拠に、カラカルパクスタン共和国のヌクスに位置するイゴールサヴィツキー記念カラカルパクスタン美術館のリーフレットや公式ホームページは、キリル文字で表記されています。

画像:イゴールサヴィツキ−記念カラカルパクスタン美術館リーフレット
そしてその多様な文字を操るウズベキスタンの人々の聡明さは、歴史上の人物に裏付けされています
世界史の教科書にも登場する、天文学者/数学者として知られるフワーリズミー、
『医学典範』を著したイブン・スィーナーは、両者ともウズベキスタンの出身(※諸説有り)だとされています
そして、ウズベキスタンにある文化といえば、美しい建造物や工芸品を忘れてはなりません

グリ・エミル廟
(画像:The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Debelopmentホームページより)
URL:https://uzbektourism.uz/uz/
古都サマルカンドにあるグリ・エミル廟は、写真を通して観ても圧巻ですよね

いつか行きたいなあと夢を膨らませていた場所です

工芸品に関しては、今回のイベントで本物を間近に観ることができました。


(上)画面奥:チェス盤と駒、手前:ケース (下)チェス盤と駒
(撮影:弊社スタッフ野本)
カラフルで美しいチェス盤。細密に描かれた文様や人物像は、ウズベク文化の真骨頂とも言えます。
チェスの駒にも細かく衣服の模様が描かれています。上の写真、チェス盤の手前に描かれているのは、容れ物のようです。
チェス盤同様、細かな文様がケース一面に描かれています
下の写真に写るチェス盤は、色をふんだんに使用しているのにも関わらず、どの登場人物もお互いに邪魔をしないカラーリングですよね
そして、下に敷かれているテキスタイルは全て刺繍なんです

会場には、その素晴らしいテキスタイルで制作した民族衣装も展示してありましたので、そちらもご紹介致します。

(上)ウズベキスタンの民族衣装

(下)拡大写真
(画像:弊社スタッフ鈴木)
観てください、この豪華絢爛な刺繍!この細かなカーブは、手刺繍でないと出来ない技ですよね
少し光沢のある刺繍は、絹糸でしょうか・・・。実際に手に触れてみると、刺繍の部分は滑らかな手触り、生地自体には厚みがあります。
おめでたい時に着る衣装なのでしょうか?どういうシチュエーションで着るのか凄く気になります
そして極めつけは絨毯です


大判の絨毯でしたので、一部を撮影しました。
写真左、絨毯にあるキャプションをみると、素材はシルク そしてなんとこの絨毯、手織りのようです・・・
そしてなんとこの絨毯、手織りのようです・・・
素晴らしい工芸品の数々に囲まれ、日本にいながらにして非常に貴重な時間を過ごすことができました
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上、「ウズベキスタン・ウィーク・イン・ジャパン」より工芸品編をお伝えしました。
次回は、「ウズベキスタン・イン・ジャパン」コンサート編です