
Information「ALTI BUYOH FESTIVAL 2008」
―表象の森― ラバウルの将軍今村均
漫画家の水木しげるが、兵役でラバウルにいた時に、視察に来た今村均から言葉をかけられたことがあるという。その時の印象について「私の会った人の中で一番温かさを感じる人だった」と書いているそうな。-水木しげる「カランコロン漂泊記」-
あるいは「私は今村将軍が旧部下戦犯と共に服役するためマヌス島行きを希望していると聞き、日本に来て以来初めて真の武士道に触れた思いだった。私はすぐ許可するよう命じた。」とマッカーサーに言わしめたという。
また、1954(S29)年6月19日付朝日新聞の「天声人語」の末尾に、「自ら進んでニューギニア付近のマヌス島に行った。戦犯兵と共に労役に服している今村の姿は、彫りの深い一個の人間像とは言えよう」と書かれた今村均。
「聖書は父の如くに神の愛を訓え、歎異抄は母の如くに神-仏-の愛を訓えている――と。これは、一つのものの裏と表だけの違いである」
と、ラバウル戦犯収容所時代の獄中にあって、長息和男への手紙の末尾に認めた陸軍大将今村均は、戦時の前線においても聖書と歎異抄を携え日々読んでいたという。
角田房子「責任-ラバウルの将軍今村均」-新潮文庫S62刊、初版S59新潮社-は、1954(S29)年の晩秋、戦犯としての刑期を終えた今村が、かねて自宅の庭の一隅に作らせてあった三畳一間の小屋に自ら幽閉蟄居の身として、その余生を徹底して自己を見つめなおす罪責の意識のうちに過ごし、旧部下全員-それは戦死した者、刑死した者、運よく生還し戦後の荒波のなかに生きた者すべて-への償いのために生きて、1968(S43)年心筋梗塞で独り静かな往生を遂げたその生涯を詳細によく語り伝えてくれる。
<連句の世界-安東次男「芭蕉連句評釈」より>
「狂句こがらしの巻」-13
田中なるこまんが柳落るころ
霧にふね引く人はちんばか 野水
次男曰く、連句とは一口に云えば月花をたねにした遊である。二折・三十六句の歌仙では、初折の表五句目・裏八句目-これのみ短句-・二折の表十一句目を月、初折の裏十一句目・二折の裏五句目を花の定座とする。連句の約束は勝負事のルールとは違うから、右はうごかしてもさしつかえないが、破るにせよ守るにせよ一座を納得させる工夫がなければ、文芸の約束など無意味に等しい。
秋二句目、その座-裏八句目-にあたる野水が月の句を詠まなかったのは、初表の月が引き上げられていること、それにも増して、次座が杜国に当っていることを、睨み合わせたからである。下げて譲ったのだ-初表五句目の月の定座は杜国だった-。見易いことだが-尤もそう指摘した人はいない-、話作り、言葉探しの面白さはその先の読みにある。初表の月の座を、引き上げて下り月-有明-と作れば、裏は、引き下げて上り月に作るしか合せようはあるまい。
「柳落るころ」に対して「霧にふね引く」-曳舟は下りだ-と付けたのは、片や風物片や人事を以て、自らも下り・上りの向合せに作る興もあったには違いないが、主としては、譲った月の座-杜国-に対するしつらいである。
この成行のおよその読みは、野水だけではなく座の誰もが持っていた筈で、荷兮の「柳落るころ」も単なる零落のとりなしではなかったことがわかる。「落る」と誘っておいて、次なる月の定座の対応を興味深く計っているのだ。承けて、野水は非力なる体の曳舟の滑稽でかわした。曳く力を抜けば-「ちんば」をやめれば-、川舟は落ちる。「霧に棹さす人はちんばか」とでも作れば、たちまち曖昧になってしまう。月の座を譲る興も現れないし、「ちんばか」も死ぬだろう。「柳落るころ」を季節感のみで受け取って、詞の寄合-柳と川舟-などに安心していると、手もなく荷兮の術中に陥る、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。















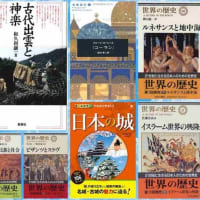




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます