
Information-四方館 DANCE CAFE –「Reding –赤する-」
―表象の森― 赤い唄たち
「赤」を題に含んで唄われ親しまれてきた曲は、おそらく青や黄など他の色名に比べても、白と双璧をなしてよほど多いにちがいない。なにしろこの国の旗とされる「日の丸」が「白地に赤く」なのだから、赤と白の対比は、この国の文化のかたちにさまざま象られ遺されている。
さしずめ童謡ですぐ念頭に浮かぶのは、
「赤い鳥小鳥 なぜなぜ赤い 赤い実を食べた」
「夕焼小焼の、赤とんぼ 負われて見たのは、いつの日か」などか。
「ふしぎな橋がこのまちにある」と唄い出される浅川マキの「赤い橋」には、その二番あたりで
「赤く赤くぬった橋のたもとには
紅い紅い花が咲いている」の一節が登場する。
流行り唄ではないが、同声二部合唱曲「赤い屋根の家」というのがある。
「でんしゃのまどから 見える赤いやねは
小さいころ、ぼくが すんでた あの家」とはじまり
「ずっと心の中 赤いやねの家 赤いやねの家」とリフレインされて、いまもう跡形もない幼い頃を過ごした家の赤い屋根が、少年時の自身の姿と重ね合わせられように立ち上がってくる。
<連句の世界-安東次男「風狂始末-芭蕉連句評釈」より>
「花見の巻」-23
熊野見たきと泣給ひけり
手束弓紀の関守が頑なに 珍碩
手束弓-たつかゆみ-
次男曰く、「吾が背子が跡ふみもとめ追ひゆかば紀の関守い留めてむかも」-万葉・巻四-、天皇の行幸に従って紀伊の国に下る夫に贈るとして、女に成替り笠金村が詠んだ歌である。
「紀の関-原文、木乃関-」は、大化2年に定められた畿内四囲の南限の背山かと思われるが、むろん関趾など残っていない。「い」は主格の下に付く強意の助詞。成替って詠むということは面白いもので、依頼者と作者との間にも問答のくすぐりを生む。「留めてむかも」、引留めるだろうか-通してくれるものでないかしら-女--いや通してくれぬかもしれんよ-作者-。
右の歌は「夫木和歌抄」にも採っているし、珍碩はこれを下に敷いて「熊野」との連想で付けたと考えてよかろうが、「紀の関守」と「手束弓」は寄合の詞である。
「あさもよひ紀の関守が手束弓ゆるす時なくまづ笑める君」-初見は源俊頼の歌学書「俊頼髄脳」永久3年頃成るか-。「あさもよひ」は「き」の枕詞。歌意は定かには捉えられぬが、次のような話を添えている。
「むかし男ありけり。女を思ひて深くこめて愛しけるほどに、夢にこの女、我は遙かなる所に行きなんとす、ただし形見をば留めんとす、我が代りにあはれにすべきなりと言ひける程に夢さめ、驚きて見るに女は無くて、枕に弓立てり。あさましく思ひてさりとて如何せんとて、その弓を近く傍らに立てて、あけくれに取り拭いなどして、身をはなつことなし。月日ふる程に又白き鳥になりて飛びいでて、遙かに南の方に雲に随きて行くを、尋ね行きて見れば、紀伊国に到りて人に又成りにけり。さて、この歌はその折に詠みたりけるとぞ」。
歌も話も伝承だが、その後これは「奥義抄」「今鏡」「袖中抄」なども載せ、
「引きとむる方こそなけれ行く年は紀の関守が弓ならなくに」-藤原俊成、長秋詠藻-
「引きとめよ紀伊の関守が手束弓春の別れを立ちや返ると」-藤原家隆、壬二集-
というような写しが詠まれる。下って、木下長嘯子にも
「雪の内に押しても春のたつか弓紀の関守や今日を知るらん」-挙白集-、がある。
前二者が歳暮と暮春の歌ならこれは立春に目をつけた云回しだ-春立つ、手束弓-、というところが工夫のみそで「手束弓紀の関守」と続けた歌はほかに無いようだ。
珍碩は、「挙白集」の初に収める年内立春の歌を知っていたのではないか。ならば、「頑に-押戻す-」と翻した俳はいっそう面白く読める、と。















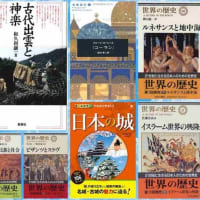




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます