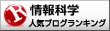連歌の規則からみて光秀の祈願にかかわる句は発句・脇句・第三・挙句の4つの句に絞られることがわかりました。
★ 愛宕百韻の解読捜査(標的の確定)
それではこの4つの句の表(おもて)の意味を解釈しておきましょう。これは素人の私では手に負えませんので専門家のお力をお借りします。連歌研究の第一人者である島津忠夫氏が下記の本に書いた解釈を採用します。「」内が島津氏による解釈文です。
新潮日本古典集成『連歌集』島津忠夫校注、新潮社刊
★ Wikipedia「島津忠夫」記事
発句 ときは今天(あめ)が下しる五月哉(かな) 光秀
「時は今、土岐の一族である自分が天下を治めるべき季節の五月となった。(本能寺の変を前にしての光秀の決意が「時は今」という初五(初めの5文字)の表現にもにじみ出している)」
脇句 水上(みなかみ)まさる庭の夏山 行祐
「折りしも五月雨(さみだれが)が降りしきり、川上から流れてくる水音が高く聞える夏の築山(眼前の愛宕山西之坊威徳院の庭の光景で応じる)」
第三 花落つる池の流れをせきとめて 紹巴
「花が散っている池の流れをせきとめて。(花による季移り。前句の庭の泉水は、水上の池の流れをせきとめて作ったものととる)」
挙句 国々は猶(なお)のどかなるころ 光慶
「桜の花が爛漫(らんまん)と咲くのどかな春、国々ものどかに治まる太平の世で。(型どおり祝言(しゅうげん)でこの一巻をめでたくおさめている)」
第三の解釈文の「花による季移り」とは発句・脇句が夏の季節を詠んでいるのに対して、第三は花で春を現していることを指しています。第三は変化・展開が必要なので季節を変えているわけです。
ところで、島津氏の発句の解釈は少しおかしいと思います。脇句以下は表(おもて)の意味で解釈しているので、発句も表の意味に解釈すべきです。発句だけは裏の意味で解釈するというのは調和がとれていません。
発句の表の意味は「今の季節をこの雨の下で五月だと知る」といったような解釈になると思います。そういった解釈をつけるべきだったと思います。
さて、裏の意味はどうなるでしょうか。光秀の詠んだ発句「ときは今あめが下なる五月かな」は「土岐氏は今、五月雨(さみだれ)にたたかれているような苦境に立たされている五月だ」という意味ですので、脇句以下も「土岐氏」をキーワードとして詠んだはずです。土岐氏についての知識がなければこれは解けません。このことに400年以上、誰も気付いた人はいませんでした。愛宕百韻の謎が解けなかったのも当然です。
★ 土岐氏解説集(土岐氏を知らずして本能寺の変は!)
次編では脇句・第三・挙句の表の意味を思い浮かべながら土岐氏の歴史を振り返ってみます。日本史研究上の初の試みです。必ずそこにヒントがあるはずです!!
お楽しみに。
<<続く>>
★ 愛宕百韻の解読捜査シリーズ
①捜査開始宣言
②標的の確定
③表の意味解釈
④土岐氏の流れ
⑤完全解読の意義
⑥遂に完全解読
★ 愛宕百韻の解読捜査(標的の確定)
それではこの4つの句の表(おもて)の意味を解釈しておきましょう。これは素人の私では手に負えませんので専門家のお力をお借りします。連歌研究の第一人者である島津忠夫氏が下記の本に書いた解釈を採用します。「」内が島津氏による解釈文です。
新潮日本古典集成『連歌集』島津忠夫校注、新潮社刊
| 連歌集 新潮日本古典集成 第33回島津 忠夫新潮社このアイテムの詳細を見る |
★ Wikipedia「島津忠夫」記事
発句 ときは今天(あめ)が下しる五月哉(かな) 光秀
「時は今、土岐の一族である自分が天下を治めるべき季節の五月となった。(本能寺の変を前にしての光秀の決意が「時は今」という初五(初めの5文字)の表現にもにじみ出している)」
脇句 水上(みなかみ)まさる庭の夏山 行祐
「折りしも五月雨(さみだれが)が降りしきり、川上から流れてくる水音が高く聞える夏の築山(眼前の愛宕山西之坊威徳院の庭の光景で応じる)」
第三 花落つる池の流れをせきとめて 紹巴
「花が散っている池の流れをせきとめて。(花による季移り。前句の庭の泉水は、水上の池の流れをせきとめて作ったものととる)」
挙句 国々は猶(なお)のどかなるころ 光慶
「桜の花が爛漫(らんまん)と咲くのどかな春、国々ものどかに治まる太平の世で。(型どおり祝言(しゅうげん)でこの一巻をめでたくおさめている)」
第三の解釈文の「花による季移り」とは発句・脇句が夏の季節を詠んでいるのに対して、第三は花で春を現していることを指しています。第三は変化・展開が必要なので季節を変えているわけです。
ところで、島津氏の発句の解釈は少しおかしいと思います。脇句以下は表(おもて)の意味で解釈しているので、発句も表の意味に解釈すべきです。発句だけは裏の意味で解釈するというのは調和がとれていません。
発句の表の意味は「今の季節をこの雨の下で五月だと知る」といったような解釈になると思います。そういった解釈をつけるべきだったと思います。
さて、裏の意味はどうなるでしょうか。光秀の詠んだ発句「ときは今あめが下なる五月かな」は「土岐氏は今、五月雨(さみだれ)にたたかれているような苦境に立たされている五月だ」という意味ですので、脇句以下も「土岐氏」をキーワードとして詠んだはずです。土岐氏についての知識がなければこれは解けません。このことに400年以上、誰も気付いた人はいませんでした。愛宕百韻の謎が解けなかったのも当然です。
★ 土岐氏解説集(土岐氏を知らずして本能寺の変は!)
次編では脇句・第三・挙句の表の意味を思い浮かべながら土岐氏の歴史を振り返ってみます。日本史研究上の初の試みです。必ずそこにヒントがあるはずです!!
お楽しみに。
<<続く>>
★ 愛宕百韻の解読捜査シリーズ
①捜査開始宣言
②標的の確定
③表の意味解釈
④土岐氏の流れ
⑤完全解読の意義
⑥遂に完全解読