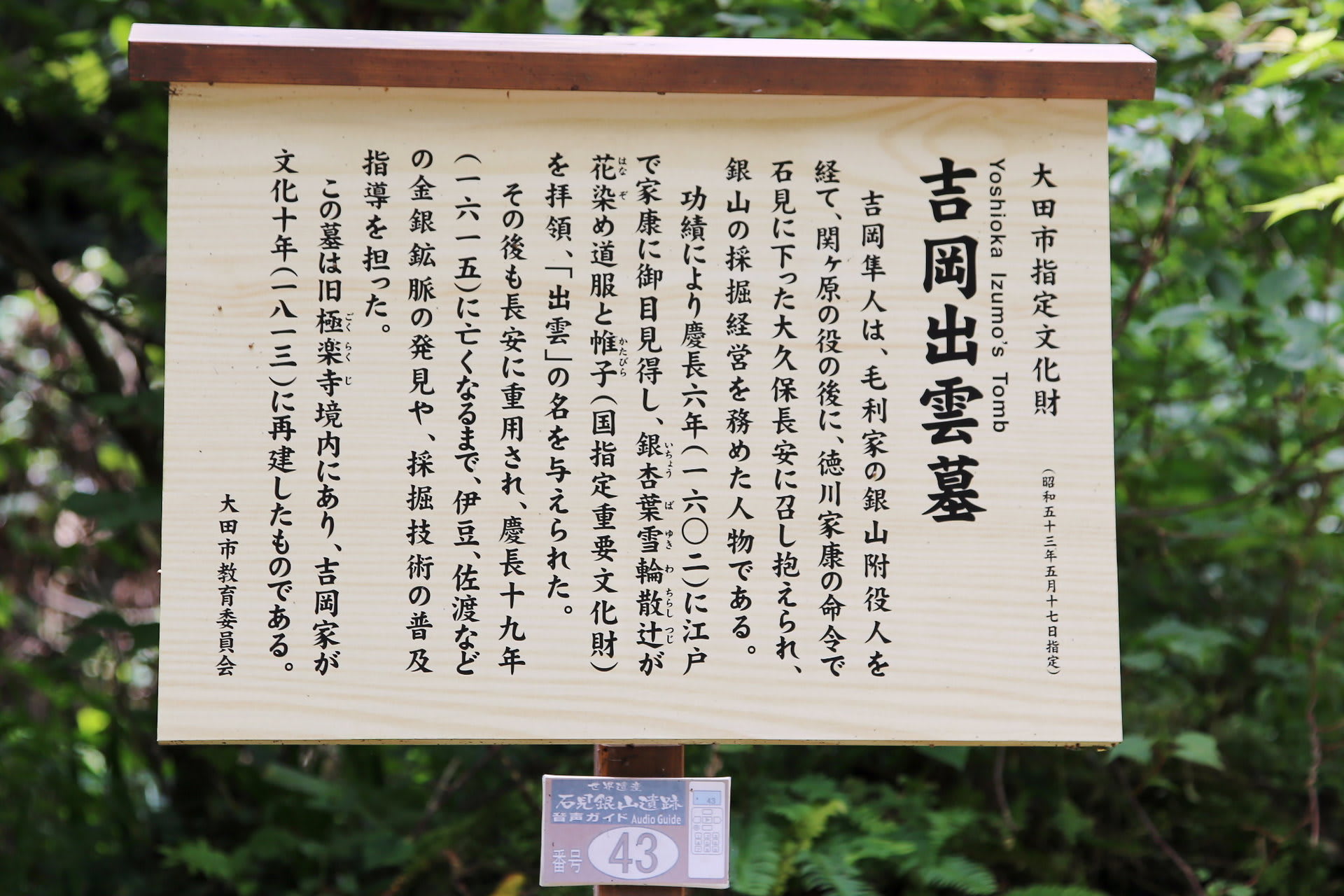100段ほどの石段の先に社殿がある。
龍源寺間歩を出たところが 栃畑谷である。
そこから「銀の小径」を下ったところに
「佐毘売山(さひめやま)神社」がある。
この神社 鉱山の守り神「金山彦命」を祀っており
石見銀山では 最大の神社
また 山神社では国内最大級の社殿がある。
資料によれば さひめ山とは 三瓶山の古名で
当初は、金山姫命・埴山姫命・木花咲耶姫命の
三柱の姫神を祀った姫山神社であったが
1430(永享6)年頃 周防の大内氏が石見国美濃郡益田村から
金山彦命を勧請合せて大山祇命をも祀って
五社大権現と称していた。
鉱山を領有した大内氏 尼子氏および毛利氏により
崇敬保護されたという。