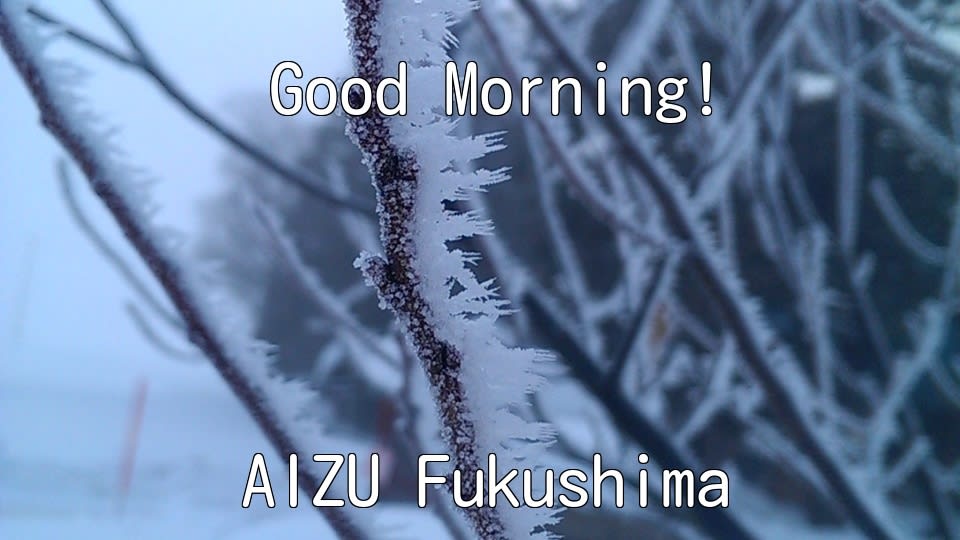おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。
ドミトリーを持つ宿屋を運営している私にとり、最大級に刺激的な本を読みました。
「ニッポンの海外旅行」(山口誠著)です。
1957年から2010年までの50数年間における、日本人の海外旅行の推移を追っている内容で、特にバックパッカーの旅行スタイルと「地球の歩き方」などのガイドブックの影響を、時代背景とともに論じているものです。
少々長くなりますが、気になった文章を引用します。
★ ★ ★
「買い・食い」行動を前に押し出してきた「歩かない」個人旅行が、長い独走の果てにたどりついたのは、旅先の日常生活が伝えてきた歴史や文化から切り離され、お金を介した消費行動だけで辛うじて接点を持つ「個人旅行」が「孤人旅行」と化した、脱文脈化する海外旅行の現状である。
「歩く」旅の系譜は、このまま途絶えてしまうのだろうか。いま、フロンマー(*)の節約旅行の復活を唱えれば、若者たちは海外旅行の魅力を再認識して、再び旅立つのだろうか。おそらく1970年代まで盛んにおこなわれていた長期・低予算・周遊の「歩く」旅をそのまま現在に復刻しようと試みても、それこそ歴史的文脈が異なるため、うまく機能しないだろう。必要なのは、「歩く」旅の可能性を模索して、現在の文脈において実現が可能な海外旅行のかたちとして提案することである。
ガイドブックを回路とした真似と追体験の循環は、新しい旅行のかたちを広めると同時に、さまざまな文化を醸成する推進力となってきた。真似と追体験の旅行は、常に退屈で貧しい体験だけを提供するとは限らない。それは後世へつなげる文化の土壌を背性する重要な実践の場にもなりうる。
文化とは、博物館や学校などで保存され、教えられる過去の知だけではない。さまざまな人々がそれを生き、日常生活において実践していくことで編み成され、伝えられていく社会的文脈の結晶体である。そうした文化を生き、編み成していく主体になる実践の一つとして、いまも旅行は、貴重な価値を有すると考えられる。
脱文脈化する「買い・食い」中心の短期旅行だけでは、今後も日本の海外旅行は衰えていき、やがて海外旅行の歴史も失われてしまうだろう。歴史と文化が循環する回路としてのガイドブックの可能性は、「歩く」旅の可能性を同じく、いまだ尽くされていない。
(*)「ヨーロッパ一日5ドルの旅」アーサー・フロンマー 1957
★ ★ ★
この著書は、日本から海外へ向かう人々のこと(アウトバウンド)を論じていますが、インバウンドで外国人客を受け入れることにも充分応用出来そうです。
著者は、1990年代より出現したインターネットによる旅行ガイドについても言及しています。ネット投稿などの口コミは、ガイドブック「地球の歩き方」創刊時に使われていた投稿スタイルの編集様式と、変化はないと言います。
つまり、この分野はネットでも、リノベーションされていません。
「歩く」旅の本質である、点と点をつなぐ線あるいは面としての旅は、現代ではほとんど失われてしまい、面に対しての口コミは存在すらしません。
長い年月をかけ、面を楽しむバックパッカーも消え失せ、そのガイドも書物から消え、ネットには存在しない。
しかし、過去から脈々と続く「人の営み」である日常生活は続く。
誤解を恐れずに言えば、「買い・食い」は、「お土産屋」と「飲食店」を点として商品提供するだけの観光ということ。
「面としての観光」には、口コミ投稿を含めた書物を、現代風にリノベーションする必要があるということ。人々には、そこを「歩いて」もらう必要があるのだ。
日本遺産となった「会津三十三観音」は、やっと点としての情報集約がはじまったばかり。会津で生きる我々は、これを面として情報提供し、人々が「歩く」ことを促すことが使命だろう。
伊勢神宮参拝などの「講」は、もともと日常生活を脱することを付随の目的として行われてきたもの。そこに、現地の日常生活を含んだ「面」を構成させる。旅人の持つ日常生活と、旅先での日常生活は違うものだから、その対比を強調させることが、リノベーションのポイントなのかもしれない。
「講」や「巡礼」などを目的とする旅行者実数は、1990年末期にはじまったバックパッカーの衰退と反比例し、確実に伸びています。このあたりも、この書籍はしっかりと分析されています。
この本は、私にとって、ものすごく刺激的な内容でした。
今日も素敵な一日を過ごしましょう。
※コメントは、旅人宿会津野Facebookにて承ります。
※ご予約は、旅人宿会津野ホームページにて承ります。