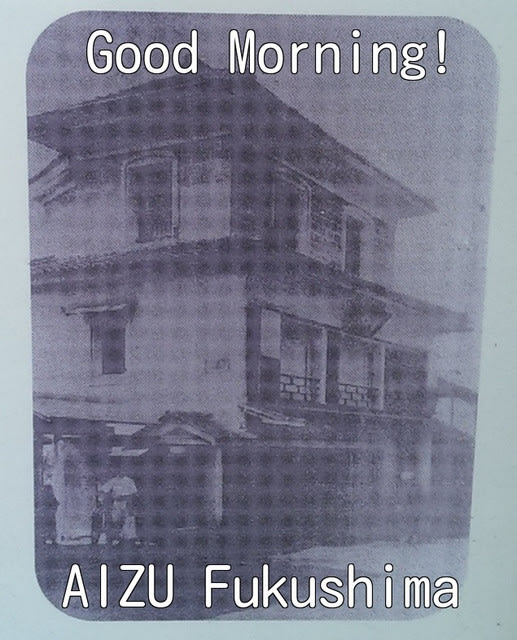おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。
引き続き、「日本の農業が必ず復活する45の理由」(浅川芳裕著)を読んでいます。
突然の衆議院選挙からまもなく10日がたちます。
小泉総理の時代、竹中平蔵が唱えた経済主義により、それまで再分配政策に傾いていた政治が市場主義に大きく傾きました。計画経済あるいは統制経済から自由経済への移行のため、市場で制約となるさまざまな規制の緩和が実施されてきたことは、みなさんもよく覚えていらっしゃることでしょう。
日本で統制経済といえば、コメの計画流通が長い間行われていましたが、これは小泉総理の時代である平成16年に計画流通米と計画外流通米の区分が廃止され、自由経済へと舵を切りました。
日本の穀物の聖域であるコメがこのように変化したにもかかわらず、いまだに統制経済が残る品目があります。
それは「小麦」です。
日本が外国から輸入する小麦は、国家貿易として政府が商社を通じ全量を買い上げ、国内の製粉会社に分配します。製粉会社に卸す価格も、価格安定化を理由として政府が決定します。不作などにより市場価格が高騰した場合は、税金で補てんする仕組みとなっていて、豊作で下落した場合は政府に利益が残ることになります。この剰余金が発生したときは、特別会計で処理し、天下り団体に支給される仕組みになっています。
一方、小麦の大生産地であるロシアの状況を考えると、ソビエト崩壊により統制経済から自由経済に移行が行われました。その過程で、生産効率の悪かった小麦生産を、自由経済のもとの民間業者が生産性向上に取り組んだ結果、採算コストは大幅に下がり、生産量は大幅に増えるという成果を得ています。だんだんと、小麦市場におけるロシアのシェアが広がり、いまでは、かつてからの大生産地である北米と肩を並べています。
世界の中の1地域に生産地が集中していると、もし不作が起きた場合に、価格の急変化が起きますが、大生産地が2つ以上ある場合は、それがかなり緩和されます。
近年では、2010年、2012年と、ロシアで大干ばつが発生し、一時価格が押し上げられました。日本政府は、継続的に小麦価格の値上げをしていますが、そのまま下がらない状態が続きます。
この仕組みにより、日本では、統制経済による高値が続き、麺やパンの買う人々の財布から、農水省天下り団体へとの、お金の流れができています。
再分配と市場主義は対局だと思っていましたが、結果的には統制経済というものは市場主義を通り越して、国家の集金装置として機能するのだと理解しました。
「行き過ぎた市場主義」という言葉をよく聴きますが、ここまで行き過ぎている統制経済を廃止することが、まず取り組むべき課題なのではないだろうかと思わされながら読書をしています。
今日も素晴らしい1日を過ごしましょう。
※コメントは、旅人宿会津野Facebookにて承ります。
※ご予約は、旅人宿会津野ホームページにて承ります。