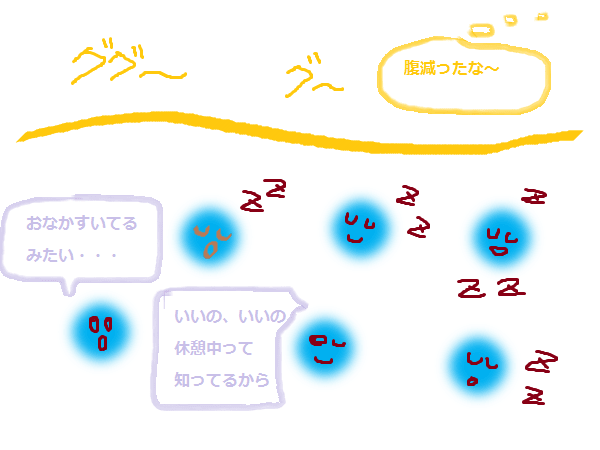最近、興味を持っている「食」の本を図書館で借りてきました。
「長生き」したければ、食べてはいけない!?
by 船瀬俊介
長生きをしたいというのではないのですが、近頃よく言われる 「健康寿命」 を考えて
参考になりそうだなと、読んでみることにしました。
この著者は「買ってはいけない」など、少し過激な内容の本を出しているので
(↑ 過激なほうがひきつける?)
そこは、割り引いておかなければと、少し構えていました。
内容は「小食」が人間の体にとって、とてもいいということが
いろいろな例を挙げて解説されています。
その一つとして、正岡子規の食事に触れた部分があります。
正岡子規の晩年は (といっても、たったの35歳)カリエスが進行して
ほとんど寝たきりで、寝返りもままならぬ状態でした。
その状態でありながら、大食漢の子規は、狂気とも言える量を食べていました。
今風に言うと、「爆食い」です。
ある日の食事
朝 粥 4杯、ハゼの佃煮、梅干砂糖漬け
昼 粥 4杯、カツオのさしみ、カボチャ、佃煮、梨2つ
夜 奈良漬茶飯 4杯、なまり節、なす、梨1つ
間食 牛乳ココア、菓子パン 10個
おかゆを4杯って!これが寝たきりの人の食事量かとおどろき。
その他にも、 間食に 柿十数個 など「爆食い」続きです。
あの「柿食えば~」の俳句も、柿をちょろっと食べたのではなく
十数個の爆食いの末の句だったのですね!
給料の半分が子規の食費に消えていた。
栄養学的に分析すると、子規は菓子パンが好きで、一度に十数個、
果物も好きで、やはり一度に大量に食べていた。
それは、大量の糖分が摂取されることになり、大量の酸化物が発生し、
酸化物を中和しようとカルシウムイオンが使われる。
カルシウムイオンは 骨から供給されるので、全身の骨格はスカスカになる。
そして、子規は脊椎カリエスの道へ。
発病後も、大食は変わらす、甘いものや、ここまで来ては害にしかならない高たんぱく食品を
継続的に、大量に食べて命を縮めることになった。
子規の世話をしていた、母と妹は自分たちは台所の隅で
おかず一つで食事をしていた。二人は皮肉なことに長寿をまっとうした。
食べ過ぎが体を壊すという例を正岡子規にとっていて、
子規のことを知ると同時に、栄養についての知識があれば
病気にもならなかったのにと思いました。
・
・
・
ところが、本では全くちがう展開になってきます。
私の感想の反対で、子規に「西洋の栄養学」の知識があったからこそダメだった!
というのです。まあ、知識のない母と妹は長生きしてますからね。
そのころ、ドイツから近代栄養学が入ってきて、必要なエネルギー、
栄養のある物(高たんぱく質)をたくさん取ることがよいことだと言われ始めた。
(これは、近年ではすでに見直しされていて、100年くらい学んできた栄養学自体が
揺らいでいる。)
西洋の知識が豊富だった子規は、新しく入って来た近代栄養学を信じて
食べまくっていた。それが、命取りとなってしまった。
子規とあろう人が 無知であるがために夭逝し、母と妹は 無知であるがために長寿だった。
小食では体を壊してしまうのでは?という恐怖がありますが
本では チリの採掘場で地下に閉じ込められるも、17日後に全員元気に
救出されたことに触れ、33人もの人が1日ツナ缶ひと匙で生き延び、
だれも、骨と皮になっていない理由も解説しています。
私も、だいぶ食事を減らしているつもりでしたが、
食べ物って、そんなに必要ないのかもしれないです。
生命維持の食事と、楽しみの食事を分けて考えたほうがいいかなと思っています。
ひとまず、実行してみたいのが、 「朝食抜き」です。
食べ物を消化吸収するのに 16時間~18時間かかるので
朝食を抜いて、内臓を休めると調子がいいそうです。
一度、やってみたのですがお腹が空いて続きませんでした。
今度は、理論がわかり、事例もよく読んだのでまたやってみます。
目覚めがスッキリして、日中の動きもよくなるそうです。
ポイントは おなかが空いても「ああ、今内臓が休んでいるな」と
空腹を楽しむことだそうです。
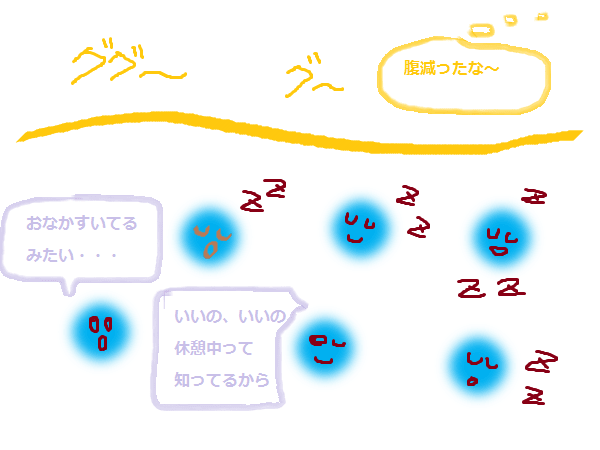
↑ 体内消化隊のみなさん