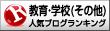「出す」6月24日
『元気は「もらう」ものか…自ら「出す」ものでしょ』という見出しの特集記事が掲載されました。『「元気をもらった」「勇気をもらった」という表現を改元前後の街頭インタビューでやたらと耳にした。もちろん以前から知ってはいたが、こうも立て続けに聞かされると、「元気や勇気は『もらう』ものではなく、自ら『出す』ものではないのか」と突っ込みたくなる』という「問題意識」から編まれた記事です。
記事では、『80年代に使われだした』『90年代半ばから急増した』などの調査結果が示され、それはそれで興味深いのですが、私は全く異なる点にこだわりました。そもそも元気を「出す」というが、出してしまったら元気は残らないのではないか、空っぽになりぐたっとした状態になってしまうのではないか、という疑問です。
実は、この記事が出る前に、つれあいと雑談の中でこんな話をしていたのです。もちろん、こんな問題は、言語学の専門家にとっては簡単に結論が出ているでしょうし、説明がなされているのでしょうが、不勉強な私はその内容を知りませんし、知ろうとも思ってきませんでした。
なぜ、こんな子供の屁理屈のようなことを考えたかというと、それは小学校教員の業としか言いようがありません。つまり、子供目線で常識を見直してみると、そこに面白い授業のネタが発見されることがあるという経験から、この問いを子供にぶつけてみたら、どんな授業になるかと考えてしまうのです。
落ち込んでいる子供に「おい、どうした?何があったか知らないが元気を出せ!」と肩を抱いて声を掛ける教員。それに応えて「お母さんにも言われた。それで元気を出したら、ぼくのなかに元気がなくなっちゃたんだよ」と言う子供。そんな場面を設定し、感想を言わせていくのです。そこから話を発展させ、「出す」という言葉の意味、イメージを確認させたり、「出す」を使った例文を作らせたり、「出す」が使われる場面を動作化させたりすることを通して、言葉そのものに関心をもたせていくのです。そしてさらに、同じように一見すると矛盾した状態を表す言葉の例を探させ、言葉探求の旅に出発させる構想です。小学校の教員でない人には分かりにくいかもしれませんが、いつでも面白いネタを探してしまう、良い小学校教員はお笑い芸人のような人種なのです。
『人を育て先駆者になれ』という見出しの記事が掲載されました。京王プラザホテル多摩の取り組みを取り上げた記事です。その中で、同ホテル取締役山川信彦氏が語っている言葉に注目しました。『仕事を任せて(部下が)何も言ってこないと、うまくいっていると期待してしまいます。「実はできませんでした」と後から言われるよりも、そういう(難しいという)サインを事前に投げかけてくれれば~』というものです。
山川氏の言葉を目にして、教員になって日の浅かった20代のころを思い出しました。当時、学級経営は大変うまくいっていました。子供たちとも保護者との関係もよく、毎日が「充実」していた感じでした。ただ一つの気がかりが、不登校だったHさんのことでした。学級替えで担任になる前からの不登校で、前担任からは、「原因は不明。全く心を閉ざしていて解決は難しい」という引継ぎを受けていました。
案の定、初日から欠席です。放課後に家庭訪問しても、顔を合わせることもできません。それからは毎朝、授業が始まる前に家庭訪問を繰り返しました。最初は決して顔を合わせず、私が半ば強引に部屋に入ろうとすると、Hさんは2階の窓から隣家の屋根に飛び移って逃げ出すありさまでした。しかし、根気よく家庭訪問を続けると、やがて部屋に入れてくれるようになり、短時間ですが、話もできるようになってきました。そして、1学期が終わりました。
私としては、前担任には全く心を閉ざしていたのに、私とは会って話ができるまで関係が改善されている、という認識でした。つまり、徐々に良い方向に進みつつあるという捉え方だったのです。
しかし、1学期の通知票を見た教頭は、「このHという子、1日も登校していないじゃないか」と驚き、私を問い詰めました。前述したとおり、私としては自分の努力で事態は改善しつつあると自負していましたから、詰問口調で責められることに納得がいきませんでした。そこには、Hさんが不登校であることは前年度からのことで、解決が難しいということは教頭も知っているはずなのに、という思いもありました。
でも話を聞いているうちに、教頭としては、担任も級友も変わり、心機一転Hさんが登校するのではという期待もあり、私から相談もないことから、うまくいっているのだと思っていたということが分かりました。そして、1週間なり半月なり、不登校が続いた時点で、私から方向と相談をすべき事例であったことを理解しました。完全なミスでした。
しかし、当時の私は不登校の子供を担任するのは初めてであり、一定期間不登校を続けた子供には、安易な登校刺激はよくないという研修会で聞きかじりの知識の影響もあり、気長に構えることこそ最善策という思い込みがあって、現状がうまくいっていない状況であるという認識すらもてていなかったのです。
つまり、山川氏が言う「困ってますのサイン」以前のレベルだったのです。この経験は、私に報告と相談の重要性を痛感させてくれました。若い教員の中には、SOSを発信する以前の問題として、危機であることの認識すらできていない人はいないでしょうか。管理職は自分の常識レベルで判断するのではなく、そうした若い教員がいるかもしれないという意識で職務を進めることが不可欠です。
『「守破離」受け継ぐ 小さんの孫 自分さらけ出し』という見出しの特集記事が掲載されました。五代目柳家小さん師匠を祖父にもつ柳家花緑氏を取り上げた記事です。その中に、『花緑さんは最近、読み書きが苦手な「発達障害(学習障害)」と判明したことを公表した(略)話すことで楽になりました。悪いのは自分じゃなくて、障害だから勉強ができなかったわけだし』という記述がありました。
最近、このような発言をよく目にします。その通りなのだろうと想像します。自分を責め続ける人生というのは苦しいものですし、その苦しみから逃れることで人生を前向きに生きるエネルギを得られるのであれば、素晴らしいことです。
しかし、それとは別に、その先はどうなっているのだろうか、という思いが浮かんできます。花緑氏は、『こういう症状を持った人が少数ならば、少数派は切り捨てられていいのかって思うんです。実はあなたの周りにもそういう人がいるんです。でも、発達障害だとわかれば、周りの人も理解できるし、受け入れられるようになるんですよ』とも述べていらっしゃいます。それならばよいのですが、現実はそうなってはいないのではないでしょうか。
まず、「ああ、あの人はそういう人なのね」という反応を示す人が少なくないということです。決して非難したり責めたりはしない、だった病人なんだから。でも自分たちとは異なる人種なんだよね。できるだけ関わるのは止めよう、というような反応や接し方をする人たちです。学校でも、こうした人が多数派なのではないでしょうか。
子供時代の花緑氏のように、授業中の動き回りおしゃべりをする子に対し、「Aさんは病気なの。だから注意しても意味がないの。放っておきなさい」と我が子に伝え、特に苦情を言うわけではありませんが、クラス替えのときには、「うちの子はAさんとは2年間も付き合ったのだから、次は別のクラスでお願いします」と当然の権利の行使のように言う保護者、そしてその申し出をもっともなことだと考える教員。さらに、そうした日頃は文句を言わない保護者を、理解ある保護者、協力的な保護者、良識ある保護者と評価する雰囲気さえあるのではないでしょうか。でも、こうした考え方は差別に他なりません。
極端な言い方をすれば、発達障害のある子供を、清掃工場や火葬場のような「迷惑施設」視し、不快だがそれが現実だからしかたがない、みんなでその被害を公平に負担するのが良識ある市民の在り方、というような冷たい向き合い方です。
残念ですが、学校の現状はまだこの段階であるように思えます。そしてこうした冷たい向き合い方は、外国人児童生徒や性的マイノリティの子供、特定の宗教規範に従う子などの課題においても存在するはずです。本当の理解や受け入れはまだまだ遠いという自覚が必要です。
「原点に返ると」6月22日
『論点』欄のテーマは、『裁判員負担と「刺激証拠」』でした。『裁判員の心理的な負担が指摘される中、遺体や傷の写真など、刺激の強い証拠(刺激証拠)の扱いが課題の一つに挙がる』ということで、裁判官と検察官がそれぞれの立場から意見を述べています。
刺激証拠の扱いは慎重にという立場の伊藤雅人東京地裁部統括判事は、『犯行の様子を口頭で聞くだけで気分が悪くなってしまう裁判員もいる。感受性は人それぞれで、公平性の観点からも、負担に最も弱い裁判員が耐えられるよう裁判官が配慮するのは当然』と述べ、行き過ぎた配慮は問題という立場の横田希代子東京高検総務部長は、『裁判所が考える刺激証拠の範囲が広がり、立証が困難になっている点は看過できない』と訴えます。
私は、この問題についてはほとんど何も知りません。ただ、現状について十分な知識をもっている専門家とされる人々の間で意見が対立する場合、原点に返ることが必要だと考えます。裁判について考えるとき、裁判は何のためにあるのか、ということが原点に当たると思います。
事実と法の規定に基づいて犯罪行為を裁くこと、それが裁判の原点だと考えます。それ以外のことは付属品にすぎません。そうした観点から考えると、伊藤氏の主張は、裁判員制度の維持充実に偏りすぎているように思えるのです。
裁判員制度は、民主社会である我が国において、国政の三権、立法・行政・司法のなかで、立法や司法については主権者である国民に意思が反映される仕組み、国会議員選挙と国民が選んだ議員による間接選挙で選出される内閣総理大臣、があるのに比べ、司法については、形骸化が指摘されて久しい総選挙時の最高裁判所判事の審査しかないことが問題だとして創設されたものです。
その考え方自体は正しいと思いますし、創設された制度の問題点を改善していくことも必要です。そして、改善に当たっては、伊藤氏が指摘するように、最も弱い裁判員を基準に考えるという姿勢も望ましいものです。しかし、そうした方向性でいくら考えても、袋小路に突き当たってしまい、この対立は解消されないのではないでしょうか。裁判員制度の維持拡充と正しい判決、この両者を比較すれば、後者こそ追求すべき価値であると思えるのです。
さて、学校教育について考えるとき、学校教育の原点は何でしょうか。様々な改革が進む中で、いくつかの政策が矛盾したり、専門家の間で意見が対立したり、成果についての評価が異なったりすることがあります。というよりも常にそうした状況が発生しています。そのとき、学校教育、公教育とは何のためにあるのか、という原点に戻って考えることで、方向性を見いだすべきだと思います。
教育基本法第1条では、教育の目的を「教育は(略)国民の育成を期して行われなければならない」としています。ここでいう国民とは、すべての国民、国民一人一人を意味します。特別なエリートを育てることでも、ある分野に秀で国家に貢献する人材を育てることでもなく、もちろんそれらを否定しているわけではありませんが、より大切なのは、教育の編み目から落ちこぼれてしまう人がいないということであるのは明白です。
この視点から現在進行形の学校教育改革を見直してみればよいのです。
「辛い道を」6月21日
客員編集委員近藤勝重氏が、連載企画『昨今ことば事情』欄に『「考えさせられますねえ」』という表題でコラムを書かれていました。その中で近藤氏は、臨床心理学者河合隼雄氏の著書の言葉を紹介なさっています。『子は自分の要求を安易に受け入れる父親には人間としてちゃんとした意見をもっているのか疑い、試そうと理不尽な要求をする』『本当の「対話」を望むなら、「決死の覚悟」がないと意味深い対話にはなり難い』というものです。
これらは、元農林水産事務次官による長男殺害事件に関わって、親子の在り方について述べる文脈で引用されたものですが、教員と子供の間においてもそのまま当てはまると考えます。私自身の苦い経験からも、そう確信できるのです。
私が教員になったときに担任した学級で子供同士のトラブルが発生しました。私はトラブルメーカー(と私が感じていた)の子供のご機嫌取りをすることで、事態を鎮静化しようとしました。彼女は私の味方になり、一時的にトラブルは解決したように見えましたが、それは嵐の前の静けさとも呼ぶべき状況に過ぎず、彼女は私に様々な「おねだり」をするようになりました。
勉強が分からないから放課後に教えてほしい、という彼女の「おねだり」に応え、毎日放課後に補習授業をしましたが、彼女は真剣に学ぶ姿勢は見せませんでした。そして他の子供は、「先生はWさんだけ特別扱いしている」と私を非難するようになりました。私の「安易な受け入れ策」は失敗したのです。
ダメな私は、今度は避難してきた側の子供を懐柔しようとしました。非難派の急先鋒であったSさんとその仲間と「話し合いの場」を設けたのです。そこでの私の本心は、「子供と向き合い子供の声に耳を傾ける」良い教員を演じることにありました。そんな上辺のポーズで子供たちをだませると思っていたのです。もちろんこの「話し合いポーズ作戦」も大失敗に終わりました。
その後、同学年の先輩教員の助言によってなんとか危機を脱することはできました。鈍感な私は自分の教員としての資質に疑問を抱くこともなく、その後も教員を続けましたが、今振り返ると、もし、鋭敏な感覚の持ち主であったら教員をやめていてもおかしくないほどの惨状だったのです。
子供相手に上辺の策は通用しません。教員は常に自分の「覚悟」を見つめ続ける必要があるのです。
「もう一つの効用」6月21日
『川崎事件から見えるもの』というテーマで、ノンフィクション作家吉岡忍氏が、インタビューに答えていました。その中で吉岡氏は、類似する多くの殺傷事件を挙げ、『加害者の多くは攻撃的な妄想を抱き、その高ぶりのままに犯行に及んでいる』と指摘しています。さらに、妄想は誰でも抱くがそれでも犯行に至らないのは『戦争や過酷な歴史のなかで人間がいかに残酷になるか、またそこで散らされた命がどれほど無念だったかに思い至って我に返る』と分析なさっているのです。
私はこのブログで、歴史を学ぶことの大切さを繰り返し述べてきました。その理由として挙げていたのは、過剰なナショナリズムや過激なポピュリズムの防波堤としての働きでした。しかし、吉岡氏は、個人の衝動的な犯罪防止という観点からも歴史を学ぶ効用を唱えているのです。正直なところ、私は考えたこともありませんでした。
吉岡氏は、『「歴史の蒸発」が大規模に起きたのは、1980年代から90年代初頭のバブル経済期だった』とし、『歴史は人間の偉大さもけなげさも残酷さも教えてくれる。また、ともにその歴史を背負って生きているという自覚が人と人を結びつける。こうした歴史の意義が欠落すると好き嫌いや気に入る、気に入らないだけの「いま」しか見えない人間になってしまう。孤立したまま妄想が肥大化し、暴走するのはここからである』と述べています。
ちなみに、吉岡氏が挙げた大量殺人事件は、1988年の幼女誘拐殺人から、95年地下鉄サリン事件、97年神戸小学生連続殺傷事件と続きます。時期的にも、吉岡氏の指摘に沿うのですが、それだけに自説に都合のよい事例を集めてきたのでは、という疑念も生じてきます。
しかし、吉岡説の適否はともかく、歴史を学ぶことで、見ず知らずの他人であっても共にその歴史を背負ってきた者同士という共感や連帯感、仲間意識のようなものを抱くことができるという指摘は貴重な視点だと思います。それは民主的な社会の形成者を育てるという学校教育の目的に寄与するものだからです。
歴史を学ぶ意義について、歴史学や社会学、心理学等多くの分野の専門家による検討が必要であるように思います。ただし、言うまでもありませんが、偽りの歴史、特定の人に都合よく改竄された歴史に基づく共感や連帯感であってはなりません。
「分からないは多様」6月20日
『連載企画 そばにいるよ』は、『個性と向き合い支え見守る』という標題で、放課後デイ指導員甲斐文花氏を取り上げていました。甲斐氏は、耳が聞こえないという障害がある指導員で、勤務する「デフキッズ」に通う子供たちは、ほとんどが聾学校の児童・生徒なのだそうです。
記事の中に、次のような記述がありました。『子どもたちが自分で考えられるよう、決して答えは示さない。「(私には子供たちと)同じ障害があるけれど、私の経験が子どもたちに合うかどうかは分からない」と思うから』。
私は聴覚障害者ではありません。だから聴覚障害児の思いも悩みも分かりません。そして、分からないことを当然だと考えています。分からないからこそ、少しでも思いや悩みに近づこうと努力する、という姿勢が大切だと考えています。多くの人が同じだと思います。一方で、「同じ」聴覚障害者である甲斐氏ならば、聴覚障害児を理解できるのではないかと考えてしまいがちです。私もその一人です。
そして、分かるという前提に立てば、自分の考え方やものの見方・捉え方、知識や経験を基にアドバイスをしてあげたいと考えるのが当然という意識になります。しかし、甲斐氏は、「同じ障害があっても一人一人違う」という立場で子供たちと接しているのです。
よく考えてみれば、当たり前のことです。同じ人間だから分かる、同じ日本人同士だから分かり合える、そんな考えで子供と向き合う教員はいないはずです。そんなことを言えば、ほとんどすべての子供を理解できることになります。しかし、それはほとんどすべての子供は同じであると言っているのに等しいのです。そんなはずはありません。それなのに、聴覚障害という括りの中の人については、聴覚障害者同士で分かり合える、という思い込みがあるのです。
何も聴覚障害者に限ったことではありません。多数派については一般的で多すぎるから一括りにはできないが、少数派については特殊でごく僅かだから一括りにできる、という発想が、多くの人にあるのです。障害者、性的マイノリティ、在日外国人、そうした表面的な部分にラベルを貼り、その中の個性を見ようとしない性癖があるのです。
そして、障害者なら、聴覚障害、視覚障害、肢体不自由などの障害種別ごとに、同じ悩みを抱える人というように、細分化すればするほど、その集団の中に多様な個性が存在することを忘れ、皆同じレベルを貼られた人にしてしまうのです。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーと少数派をさらに細かく分け、ステレオタイプで理解した気になるのです。中国人、韓国人、フィリピン人とカテゴライズし、それぞれ反日、感情が激しいなどとレッテルを貼り、知った気になっているのです。
教員は、子供をある指標で細分化し、何らかのグループに所属させ、そのグループにレッテルを貼ることで、子供を理解した気になってはなりません。そうした方法は理解法として容易であるだけに、つい安易な道に走りそうになる自分にブレーキを掛け続けなければなりません。
「何事も、無理矢理に」6月18日
文化人類学者上田紀行氏が、『測定への過信脱し創造性を』という表題でコラムを書かれていました。その中で上田氏は、『「測りすぎ なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?」(ジェリー・Z・ミュラー著、松本裕訳)』を取り上げています。
上田氏は、同書の内容に触れつつ、『年がら年中、評価する、されるための書類を書いたり、提出したりして、評価のための時間ばかり増大し、本来の生産的、創造的な仕事の時間がどんどん食われるような状況』と現状分析し、『測定し、評価するために投じられるコストが大きすぎて、それが逆にわれわれの生きることや社会のありかたを貧困化させている』と断じていらっしゃるのです。
同感です。しかし、ここまでの指摘は、今までも多くの立場の人からなされてきたことで、特筆するようなものではありません。上田氏の指摘に注目させられたのは、弊害をより細かく説明しているからです。
まず、『大事なものはすべからく測定できる。測定できるものこそが大事なものだ、という意識の転倒が生じた』という指摘です。この指摘は学校教育改革の大きな流れにも当てはまります。すぐに役立つ知識や技能の習得(測定しやすい)を重視し、歴史や哲学といった人文科学系の能力(測定しにくい)を軽視する傾向です。実用性重視と教養軽視と言い換えてもよいでしょう。
上田氏は、『アメリカの大学では昨今「卒業生の年収」が取りざたされる。学生の投資利益率を見るわけだ』というエピソードを紹介していらっしゃいますが、まさしく即効性のある知識技能偏重の行き着く姿です。年収という測定可能な数値が全てで、だからこそ年収を生む教育が大事という発想なのです。そしてこれは、我が国においても同じ方向性なのです。
次に、『ビジネスであればあまりに多くの時間と予算を測定に費やすと利益が減じるため抑制機能が働くが、大学や政府機関などではそれが働かない』という指摘です。私は大学卒業後すぐに教員になり、その後教委に勤務しました。ですから、民間企業のことは分かりませんが、公的機関では利益減という抑制機能が働かないという指摘はよく理解できます。しかも、「測りすぎ」という病と裏腹の関係にある「説明責任」は、公的機関の方がより多く負わされているのですから、学校などの公的機関が一度「測りすぎ」という病に罹ると、すぐに重症化してしまうのです。
公立校の教員には、残業という概念がありません。月70時間程の「残業」はほとんどがサービス残業です。ですから、そこに評価のための事務作業が何時間加わろうとも、教委も校長などの管理職も問題意識をもつことがないのです。頑張り屋のA教員が、評価のために70時間の残業を80時間に増やしたとき、コストがかかり過ぎだという話になるのではなく、B教員が「Aさんがやっているんだから私もやらないと」となるだけなのです。
そして最大の問題点が、『測れないものを測れたと見誤る』です。この点については、私には苦い思い出があります。私は教委勤務時代に「指導力不足教員研修」を担当していました。同研修は、指名研修でした。つまり、「あなたは指導力不足です」という評価が必要であり、「あまたの指導力不足は解消されました」という評価も必要になるということです。
しかし、教員の指導力というものは、測定可能なのか、という問題が当初からついて回りました。私になり詳細な評価項目と基準を作り、それぞれの点数配分を決め、恣意的な要素を除く努力をしました。公平性や客観性、透明性については、それなりのものが作れたという自負があります。しかし、全てなのか、この評価項目以外に評価すべき対象はないのか、と問われれば、自信をもってイエスとは言い切れません。何か数値化できない、測定不能の「雰囲気」や「たたずまい」、人間性や個性といった抽象的なものが教員の指導力にはあるような気がするのです。評価や測定を深めれば深めるほど、そうした曖昧模糊としたものが見えなくなってしまうような思いがついて回ったものです。
学校における「測りすぎ」については、常に検討が必要だと考えます。
大学生がつくる紙面「キャンパる」に、東洋大のS氏が、『しょうらいのゆめ』という表題でコラムを書かれていました。その中でS氏は、『「しょうらいのゆめ」。自己紹介カードを渡された小学生の私は戸惑っていた(略)空欄は許されないようだった。苦し紛れに映画監督と書いた。映画は好きだが監督になりたいと思ったことはない。まるっきりのうそに、周囲が首を傾げる様子を鮮明に覚えている』と書かれています。
そして、『その後もこの問いは「進路」や「ライフプラン」と名前を変えて襲い掛かった』『どうやら人というものは、将来のために生きているらしい。では、夢を持ったことのない私は、どう生きたらいいのだろうか』と続けているのです。そして今、就活時期を迎えたS氏は、『目的地も持たぬまま、ただ歩けと言われているような気分』と述べられています。よく分かります。私もS氏と同じような子供であり、学生であったからです。
もちろん、私はS氏ほどには悩みませんでした。小学校の卒業文集に書く「しょうらいのゆめ」など誰も真剣に考えていませんでしたし、中高で「ライフプラン」を書かされることもありませんでした。「進路」は、どの都立高を受験するか、どの大学の入学試験を受けるか、というだけのことでした。そして、それらは、自分の学力で自ずから絞られていました。
つまり、私の学生時代は、S氏のような「目的地をもたない」者が珍しくなかったのです。それで非難されることはありませんでした。親にも「将来どうするんだ」と問い詰められたことがありませんでした。教員採用試験を受けることも、筆記試験を通って面接を受けに行くときも、親には「ちょっと出かけてくる」と告げただけでした。もちろん、スーツを着て出かけたので、遊びに行ったとは思っていなかったでしょうが。そして、4月1日に初出勤するとき、「今日から〇〇小に勤めるから。5年生の担任」と言いました。母親と姉は、「大丈夫なの?」と言っただけで、父親は何も言いませんでした。誤解のないように言っておきますが、我が家は大変仲のよい家族でした。
そんなものだったのです。私は優秀な学生ではありませんでしたが、普通にまじめな学生でした。両親は基本的に私を信頼していたのでしょう。エリートにはならないが、平均的な社会人として自立していくと思い、疑うこともなかったのでしょう。
昔話は、今の時代には参考とはならないことは百も承知です。とはいえ、S氏のように、小学生の時代から常に「将来のため」を意識させられる学校教育が望ましいのか否か、考えてみる必要はあると思います。キャリア教育の美名と共に。
『美探究 メーク男子 SNS・就活印象UP狙い』という見出しの記事が掲載されました。記事のよると、『ファンデーションや色つきリップクリーム、まゆ毛を描くアイブローなどメーキャップ商品を購入する男性が増えている』ということです。しかも、若者だけでなく『年代は20~60代と幅広い』のだそうですから驚いてしまいます。さらに、『シミを隠す「コンシーラー」にネイルカラー…』と今後も男性向けメーキャップ商品は続々と販売されるのだそうです。
正直、嘆かわしいという思いがぬぐえないのですが、まあ時代の変化とはそうしたものです。時代遅れの老兵は消え行くのみ、です。とはいえ、こうした記事を目にすると、30年近く昔、指導主事試験の勉強をしていたときのことを思い出します。当時、面接や小論文などで、教員の服装について訊かれることがよくありました。その内容は、女性教員がピアスをしていたら、男性教員がロン毛だったら、女性教員が髪を金髪に染めてきたら、さらに膝上10CMのミニスカートを穿いてきたら、というような状況で、どのように指導するかというものでした。
服装や化粧は自己表現の一種であり、服装の自由と職場規律や公務員としての信用維持、職場規律の問題、思春期を迎えた児童生徒への影響、保護者の思惑など、考える視点はたくさんあり、それだけに見識が問われる良問だったのです。当時、セクハラは漸く意識されるようになっていましたが、まだパワハラについてはそうした概念は乏しく、今から思えば、随分乱暴な回答をする人もいましたが、それもその時代の現状を表すものだったのでしょう。
やがて、時代は進み、髪を顎の下まで伸ばし、きれいに手入れを怠らない若い男性教員が、「かっこいい」「清潔感がある」などと保護者からも受け入れられる時代となりました。むしろ、昔ながらのカチッとした七三分けにした定年間近の教員が「毎日頭洗ってるのかしら」「不潔!」と言われてしまうようにさえなっています。
とはいえ、男性教員が、ファンデーションや色つきリップクリームを使い、コンシーラーでシミを消し、桜色にネイル(さすがにデコネイルはしないでしょう)をして出勤する時代がすぐに来るとは思えません。必ず過渡期があり、その中で新旧の価値観がぶつかり、「守旧派」から非難される時期があるはずです。その時期、管理職は対応に苦しむことになりそうです。私見では、教員は保守的(政治的意味ではなく)であるべきです。時代が変わった後、ひっそりと付いていくくらいでちょうどよいのです。あと10年くらいかな?