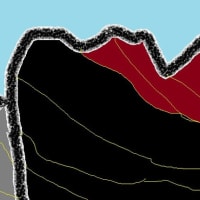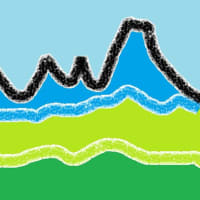男見えざりければ、女、男の家にいきてかいまみけるを、男ほのかに見て、
百年に一年たらぬつくも髪われを恋ふらしおもかげに見ゆ
とて、いで立つけしきを見て、うばら、からたちにかかりて、家にきてうちふせり。
伊勢物語六十三段は後味の悪い話と解説されていることが多く、歳をかさねてくると余計そう感じる読者は多そうだ。好色な女が子ども三人を呼んで、夢の作り話で、いい男と出会いたいと間接的に頼むと、三男だけが業平に会わせようと計画して、たまたま遭った業平に頼み込む。業平さんはなんでもいいよの人なのか、あはれがって、相手にしてやった。しかしそれきりだったので、女は男をのぞきに行く。それが上の場面である。ここの場面はなかなかのもので、「つくも髪」がまぼろしに見えるよとうたって出で立つ男を見て、茨やカラタチのとげに刺さられながら帰宅してふとんの上で待っている女が人間の姿を感じさせる。われわれがいやな気持ちになるのはその人間の姿のせいである。このあと、女は無事男ともう一回共寝したらしいのだが、そこでナレーターが
この人は思ふをも、思はぬをも、けぢめ見せぬ心なむありける。
と訳わかんないことを言って締める。思うに、人の気持ちというのは文章に表せてしまうほどの何よりもよりも大きく、上の茨にまみれて帰宅する女の姿のようなものである。われわれのなかには「気持ちにより添う」とか、「なんとか目線」とかのフィクションでしか心の問題を耐ええない人がある。近代文学に描かれてきたように、親子の関係だって、お互いの心理が見える関係の方が、大きな誤解があるときよりも危険である。そもそも心理は言葉では代替できないものだからである。歳を重ねてくるとたぶん、そういう自明のことを忘れがちであり、自分の人生の業績だけが自分にのし掛かってくる。われわれが記憶とか業績みたいなものが好きなのは、それが言葉であるにもかかわらず、背後にあるものが大きすぎて心理的なものに見えるからでもあろうし、量というのはそれだけで現在の具体的な心理に対して圧倒する何かを感じさせるからである。
上の話の場合、女が自分の欲望を自分の子に託したのがすごく背後の心理の存在を感じさせている。これは、女の、子に対する何かの当てつけだったのかもしれない。だから、語り手は女を茨まみれにしたりして酷い仕打ちをしたのではなかろうか。わたくしの妄想だが、この過程では――心理の内容と質の問題が、内容量の問題にすり替わってしまった後なので、ほんとうの問題が何だったのか分からなくなってしまっている。ハラスメントの発生である。日本のよくある「報恩」もそうやって、だいたい悲惨な結末を迎える。
親は子どもに言葉がない頃から自分の心理を見つめて生きている。この理不尽な非対称性が悲劇を生む。親子関係とは、親の圧倒的な心理問題として存在している。子どもははじめから敗戦を宿命づけられている。大概は、子が子であることをやめることで(――だいたいは親になることによって)それを乗り越えたふりをする。ただ、特に最近は、社会が人を孤立した大人になることを許さず、比喩的な「子」であることを要求する。また、親になることは、子どものためにより社会への馴致を要求されることになりがちである。とにかく、子育てとは、日本の社会的制度の復習以外の何物でもない。教員がいつの間にかものすごく道徳心を持った人物として自分を誤認しがちなのはそのせいである。
われわれは、個人であろうとすれば、親になるしかなく、しかし親になることによって個人ではいられなくなるジレンマのなかにある。大変に暴力的な事態だとわたくしは思う。一番いいのは、親になったあと、出家してしまうことであるが、こんなことを出来るのはほんの一握りの人物である。