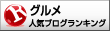ニーダーザクセン州都である人口約50万人のハノーファーにデュッセルドルフから引っ越したのは東西ドイツの壁が開いてすぐ後、1989年の末でした。実はその数ヶ月前にハノーファーに家を探しに来て、北部に位置するボツフェルト市域に一戸建ての家をすでに借りていたのです。地下室のある家具付き2階建で、前後に芝生の庭があり、ガレージの付いた立派な家です。大家の両親が自分で建てて住んでいたので良い建築材料を使っていたし、内装も住みやすく設えてあり、交通の便が良い静かな住宅地の一角でした。それぞれの入り口が隣り合う隣人、二クロヴィッチさんとの関係も良く、すぐ裏に大家のボルトマン氏が住んでいて何かと便利だったのを思い出します。裏の畑の一部を借りて枝豆などの日本の野菜を作っていたのもこの頃です。

ボツフェルト市域の賃貸家
近所の、足を中心に少し白が混ざった黒猫が頻繁に来るようになり、夜の食後のひと時をよく一緒に過ごしました。余程うちが気にいったらしく、毎朝雨の日も雪の日も裏庭の木立の影にうずくまって待っていて、テラスに続く台所の戸を開けると同時に駆け寄って来ました。大変賢いけれども気性が激しいいたずら猫で、近所の住人からは嫌われていたようです。うちでもミルクのパックに牙を立てたり、私など一年にわたって引っかかれ続けました。タクシーで出かけるときに、我々が連れ去られると思ったのか、運転手を威嚇したり、この家を引っ越すときには連れて行って欲しい素振りを見せたりして、深い愛情を感じさせる猫でした。本来の名前はありましたが、我々はメグミと名付けていました。後日ニクロヴィッチさんに聞くところによると、その後しばらくの間は毎朝台所の戸が開くのをジッと待っていたそうです。
邦人家族や留学生を沢山呼んで、大きなテラスのある裏庭でバーベキュウ・パーティーなどを頻繁に催しました。妻も私も若く、同年代の日本人が多かったので盛んに人との交際をしていましたし、ドイツに来て初めて一戸建てに住むようになり、家に関する雑用、例えば芝刈りなども、割と嬉々としてやっていました。まだ人生の上り坂に居たのです。
1994年に東京築地のがんセンターに勉強をしに行く機会を与えられました。たったの3週間でしたが、日本の労働条件とその環境がどのようなものであるかを知り得たと思います。
それ程強く意識した覚えはないのですが、おそらく意識下で、日本では働きたくないと思ったのでしょう。帰独してすぐに、家を買うか建てるかしてじっくり腰を据えることを考えるようになりました。初めのうちは中古の一戸建てを探して何軒か見に行きましたが、考えていた価格レベルでは、スペイン風とか、日本風とか、庭または屋内にプールを備えたレジャー施設風とか、それぞれの施工主の極端な嗜好が反映されていて、私たちの好みにぴったりのものがありませんでした。それならいっそうのこと新築しようということになって、比較的早く土地も建築会社も見つけることが出来ました。ハノーファー市の南部に位置するドェーレンという市域で、ここも静かな、かつ交通の便の良い住宅地。通ってくるピアノの生徒のことを考えると、交通の至便さは必要な条件だったのです。
今まで全く接触のなかった建築会社の人や職人を沢山知り合って彼らの世界を知り得たし、今考えると少しばかり後悔する点もありますが、全体としては上手く行ったと思うし、家を新築するプロセスを全て経験出来たのは有意義だったと思います。

現在の家
しかし、これ程雑用が増えるとは思っていませんでした。家の維持のための事務的な雑用の他、庭の手入れも大変だし、小さな修理は自分でします。今年 (2015年) 新築してからで20年になるので、最近はいろいろと破損するところが多くなっています。2、3年前には続いて3回も暖房設備の破損や豪雨などによる地下室の水害で雑用が一段と多かったのです。庭仕事は10年くらい前から人に頼んでいます。ポーランド人のいわゆる „もぐり” の庭師ですが、非常に真面目な人なので満足しています。この家に越してから、最初の頃は人をよく招待していましたし、今でも年に一度、大抵は、彼が音大生の頃から知っていて現在ウィーンの音大の教授をしているクラウス・シュティッケンによるピアノのハウスコンサートをしています。コンサートの際の音響のために天井をブロック1個分高くしているのです。
最近は人を招待することが目立って少なくなって来ました。我々2人とも年を取ったからか、そういうことが非常に億劫になってしまったのです。妻は生徒にピアノの教授と趣味の作陶、それに加えて2022年現在では野菜作りも、私は日本文化に関する講演の準備と講演旅行、そして城館ホテルの取材旅行を主にやっています。
ところで、今の家にもメグミがいました。メグミ2世です。
家を新築してすぐの頃、研究室の英国人秘書であるタイケさんから声をかけられました。
「猫が一匹迷い込んで来たけれども、すでに2匹いるので飼えない。あなたの家で飼わないか。」
と言うのです。とりあえず猫を見に行ったのですが、そのまま連れて帰りました。妻が言うには、何でも、心の中で
『うちに来るか?』
と訊いたところ、タイミングよく、
『ニャッ!』
と返事をしたそうです。
メグちゃんは獣医から „猫エイズ“ の宣告を受たことがあります。しかし、抗体が検出されたというだけで血液検査は異常なかったし、もちろん感染症の症状は全くありませんでした。発症を抑える治療法が確立されているからでしょうか、„猫エイズ“で死ぬことはありませんでした。そして、メグちゃんと暮らして20年めに老衰で死にました。今は庭の片隅で静かに眠っています。

メグミの墓
現在新しい猫が居ます。胸が白くて白足袋をはいた黒猫で、名前はミカ。シャムネコの血が半分入ったハーフです。メグミはおっとりしたオス猫でしたが、ミカはけっこう気難しいメスです。

ミカ
ハノーファー医科歯科大学で仕事を始めた時、研究室の秘書の一人、シュナイダーハインツェさんが、
「ハノーファーの良さが分かるには最低5年住まないといけません。」
と言ったことを思い出します。ハノーファーに来て今年 (2015年) で26年が過ぎました。
〔2015年12月〕〔2022年9月 加筆・修正〕