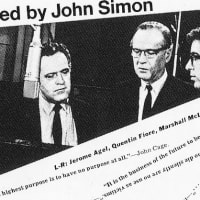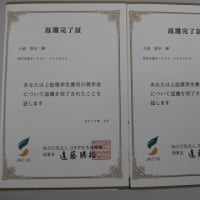松江市の教育委員会が市内の小中学校図書館に置いてある漫画『はだしのゲン』に閲覧規制をかけようとして、大きな騒動になった。クレーマーが右寄りの人だったために、議論がウヨサヨ論争に流れてしまい、規制の表向きの理由だったはずの「発達に合わせた表現の適性」については議論が深められないままになってしまった。これは表現の自由の問題だというわけである。ただ、そのロジックについては気をつけておきたいことがる。
最初に言っておくと、僕は閲覧制限に反対である。現在手元に作品はないけれども、僕も『はだしのゲン』を小学校高学年の頃に読んだ。その記憶では、家族も失い、放射能を浴びながらもなんとか生き抜こうとする主人公のバイタリティには心動かされた。同じ戦争を扱った作品でも、主人公が無抵抗なまま大人しく死んでゆく『火垂るの墓』より全然好きだ。
僕が閲覧制限をかけるべきではないと思うのは、それが良い作品だからである。しかしながら、この閲覧制限を「言論弾圧」とか「検閲」とラべリングして、知る権利の侵害だとみなす立場もあるようだ。知る権利アプローチを正しく理解している者は、所蔵の可否についてその書籍の価値から議論することを避ける。作品の良し悪しとは無関係に、あらゆる表現の所蔵や閲覧を制限してはいけないというのである。日本図書館協会は、学校図書館をそうした機関とみなしている1)。
しかし、知る権利アプローチには三つの問題がある。第一に、学校図書館の不所蔵は作品の社会的な抹殺ではない。その外の世界において、この作品に接触する機会は絶たれていない。『はだしのゲン』ならば書店でも漫画喫茶でも公共図書館でもそれは簡単に手に入るだろう。閲覧制限が知る権利の侵害となるならば、それを置かない学校図書館はより強く非難されなくてはならない。そうしないならばダブルスタンダードである。
第二に、知る権利を学校図書館に適用することは、学校図書館の教育機関としての性格と齟齬をきたす。その蔵書が、教育目的に沿ってコントロールされるのは当然である。子どもが求めるすべての資料を購入することはできない。結局、その蔵書が世間的に受容できる最大公約数的なものにとどまり、児童・生徒の日常有する「情報要求」を満たすものにならないというのは受け入れざるえないことである。そこからはずれた児童・生徒の関心は私的な手段に満たさざるをえない。しかし、知る権利アプローチに従うと、複数の情報要求のあいだに扱いの差を設けることは不正となるので、あらゆる資料を受け入れるべきだという実現不可能な要求につながってしまう。
それが実際に適用される場合は「特定の言論を優遇するのは不公正なので、対抗的な言論を持つ資料を所蔵しよう」という話になるだろう。今回のケースでは、『はだしのゲン』に対して『竹林はるか遠く』や小林よしのりの『戦争論』を入れようという提案が該当する(実際ネット上で多く見かけられる)。そうすれば、左右の言論のバランスがとれた蔵書一群を作ることができるだろう。その一方で、学校図書館で相対的に優先したいはずの他の書籍の予算が食われてゆく結果になる。
第三に、知る権利アプローチは、学校図書館蔵書に対するクレームを倫理的に悪とみなしてしまう。学校図書館蔵書に意見する親や教師は頭の固いファシスト扱いされる恐れがあるのだ。これでは学校図書館蔵書に関する生産的な議論の可能性を閉ざしてしまう。しかし、資料選択者も無謬でない。子どもに読ませたくない内容の所蔵資料に対するクレームがあり、親・教師・学校図書館の担当者が議論して、正当な手続きを経て最終的に合意に至るならば、その除籍や除架があってもおかしくないはずである。その際議論されるべきなのは、対象となった作品の価値や学校図書館への適性であって、言論の自由ではない。
学校図書館の資料選択者は事実上、価値に基づいて資料を選んでいる。しかし、日図協の主張に従えば、資料選択者は価値中立の立場から自分の選択を擁護し、外部からの介入を拒絶できるということになる。これは欺瞞にしか見えない。このような論理は、学校図書館の理解者であるべき一部の親や教育関係者を警戒させ、場合によっては敵対させる危険性もある。
以上のように、知る権利アプローチは学校図書館蔵書をめぐる議論を大きく歪めてしまうものである。それは学校図書館に適用するのにふさわしくない。その所蔵資料をめぐっては、その価値や適性の点で議論した方がストレートで世間的に理解されやすいはずである。
この結論に対する予想される反論も十分理解しているつもりだ。「価値について合意がありうるならば、それではどうして学校図書館蔵書間で蔵書が似たようなものにならないのか」。あるいはもっと根源的には「相互に妥協が不可能な「比較不能な価値の迷路」に陥ったときはどうするのか?」。この反論には簡単には答えられない。しかし、これは重要な問いであり、図書館の資料選択者ならば考えておくべきことである。僕の見るところ、大きな問題は、図書館関係者が「図書館の自由」に依拠して価値相対主義を表向き採用するようになってしまったために、実際に行っている資料選択を十分説明できる理論を開発してこないままになってしまったことである。
--------------------------------------------------
1) 日本図書館協会図書館の自由委員会 / 中沢啓治著「はだしのゲン」の利用制限について(要望)
http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/jiyu/hadashinogen.html
最初に言っておくと、僕は閲覧制限に反対である。現在手元に作品はないけれども、僕も『はだしのゲン』を小学校高学年の頃に読んだ。その記憶では、家族も失い、放射能を浴びながらもなんとか生き抜こうとする主人公のバイタリティには心動かされた。同じ戦争を扱った作品でも、主人公が無抵抗なまま大人しく死んでゆく『火垂るの墓』より全然好きだ。
僕が閲覧制限をかけるべきではないと思うのは、それが良い作品だからである。しかしながら、この閲覧制限を「言論弾圧」とか「検閲」とラべリングして、知る権利の侵害だとみなす立場もあるようだ。知る権利アプローチを正しく理解している者は、所蔵の可否についてその書籍の価値から議論することを避ける。作品の良し悪しとは無関係に、あらゆる表現の所蔵や閲覧を制限してはいけないというのである。日本図書館協会は、学校図書館をそうした機関とみなしている1)。
しかし、知る権利アプローチには三つの問題がある。第一に、学校図書館の不所蔵は作品の社会的な抹殺ではない。その外の世界において、この作品に接触する機会は絶たれていない。『はだしのゲン』ならば書店でも漫画喫茶でも公共図書館でもそれは簡単に手に入るだろう。閲覧制限が知る権利の侵害となるならば、それを置かない学校図書館はより強く非難されなくてはならない。そうしないならばダブルスタンダードである。
第二に、知る権利を学校図書館に適用することは、学校図書館の教育機関としての性格と齟齬をきたす。その蔵書が、教育目的に沿ってコントロールされるのは当然である。子どもが求めるすべての資料を購入することはできない。結局、その蔵書が世間的に受容できる最大公約数的なものにとどまり、児童・生徒の日常有する「情報要求」を満たすものにならないというのは受け入れざるえないことである。そこからはずれた児童・生徒の関心は私的な手段に満たさざるをえない。しかし、知る権利アプローチに従うと、複数の情報要求のあいだに扱いの差を設けることは不正となるので、あらゆる資料を受け入れるべきだという実現不可能な要求につながってしまう。
それが実際に適用される場合は「特定の言論を優遇するのは不公正なので、対抗的な言論を持つ資料を所蔵しよう」という話になるだろう。今回のケースでは、『はだしのゲン』に対して『竹林はるか遠く』や小林よしのりの『戦争論』を入れようという提案が該当する(実際ネット上で多く見かけられる)。そうすれば、左右の言論のバランスがとれた蔵書一群を作ることができるだろう。その一方で、学校図書館で相対的に優先したいはずの他の書籍の予算が食われてゆく結果になる。
第三に、知る権利アプローチは、学校図書館蔵書に対するクレームを倫理的に悪とみなしてしまう。学校図書館蔵書に意見する親や教師は頭の固いファシスト扱いされる恐れがあるのだ。これでは学校図書館蔵書に関する生産的な議論の可能性を閉ざしてしまう。しかし、資料選択者も無謬でない。子どもに読ませたくない内容の所蔵資料に対するクレームがあり、親・教師・学校図書館の担当者が議論して、正当な手続きを経て最終的に合意に至るならば、その除籍や除架があってもおかしくないはずである。その際議論されるべきなのは、対象となった作品の価値や学校図書館への適性であって、言論の自由ではない。
学校図書館の資料選択者は事実上、価値に基づいて資料を選んでいる。しかし、日図協の主張に従えば、資料選択者は価値中立の立場から自分の選択を擁護し、外部からの介入を拒絶できるということになる。これは欺瞞にしか見えない。このような論理は、学校図書館の理解者であるべき一部の親や教育関係者を警戒させ、場合によっては敵対させる危険性もある。
以上のように、知る権利アプローチは学校図書館蔵書をめぐる議論を大きく歪めてしまうものである。それは学校図書館に適用するのにふさわしくない。その所蔵資料をめぐっては、その価値や適性の点で議論した方がストレートで世間的に理解されやすいはずである。
この結論に対する予想される反論も十分理解しているつもりだ。「価値について合意がありうるならば、それではどうして学校図書館蔵書間で蔵書が似たようなものにならないのか」。あるいはもっと根源的には「相互に妥協が不可能な「比較不能な価値の迷路」に陥ったときはどうするのか?」。この反論には簡単には答えられない。しかし、これは重要な問いであり、図書館の資料選択者ならば考えておくべきことである。僕の見るところ、大きな問題は、図書館関係者が「図書館の自由」に依拠して価値相対主義を表向き採用するようになってしまったために、実際に行っている資料選択を十分説明できる理論を開発してこないままになってしまったことである。
--------------------------------------------------
1) 日本図書館協会図書館の自由委員会 / 中沢啓治著「はだしのゲン」の利用制限について(要望)
http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/jiyu/hadashinogen.html