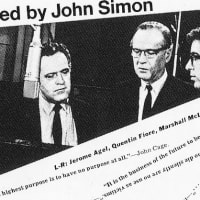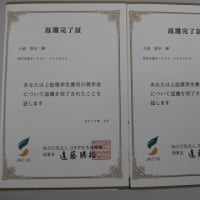山口浩「「TSUTAYA図書館」と「図書館論争」のゆくえ」(Synodos, 2015.11.27)という記事を読んだのでコメント。TSUTAYA図書館からはじまり近年まで図書館利用者の偏りまで多岐にわたって図書館問題を指摘する長い論考である。著者はH-Yamaguchi.netの方ようで。
僕が専門家ぶるのも気が引けるが、少々補足したくなる点があった。著者は図書館について建設的な態度で提言してくれている。この点は評価したい。けれども、著者のアドバイスは特に目新しいものではなく、「そういう考えではまずいのではないか」と近年の図書館関係者が見直してきた考えそのものだ。記事中、要点の一つとして"19世紀の技術と社会を前提とした生まれた現代の図書館のあり方は、それらが大きく変化した21世紀の状況に合わせて変えていく必要がある"と掲げられている。これと似たような話は、図書館関係者ならばさんざん内輪で聴かされてきただろう。そもそも啓蒙・教養志向図書館観vs.現実のニーズという図式自体は、1990年前後に貸出サービス肯定論として一部の図書館員が掲げ、前者を克服して後者を止揚するために使用されたものだ。(なお図書館の選書の世界ではニーズと需要は別物だが、以下ではごっちゃにして記す)。
著者によれば、サービス提供者である図書館員と住民が図書館に求めるニーズにミスマッチがあるという。この認識は正しい。ただ、こうした認識から誕生した初の図書館が武雄市図書館、というわけではなくて、貸出サービスを主に据えた全国各地にあるような今の公共図書館がそれにあたる。これらは1970年代以降に設置されており、「無料貸本屋」と批判された2000年前後を越えて現在までその基本的な方向性を維持している。啓蒙志向の古めかしい図書館の克服という話はつい最近登場したものではなくて、40年の歴史があるのである。図書館利用者層が特定の層に偏っているという話も、米国では1930年代末から繰り返されており(参考)、日本でも1980年代頃から確認されてきたことである。近年の調査でなおも利用者層が限定的であるということは、19世紀的な図書館の限界を表しているということではなくて、開館時間が拡大されかつ蔵書も大衆的になった現在の図書館でさえこの程度、というように解釈すべきものなのだ。(利用者層の偏りは近年流行の滞在型図書館でもおそらく克服できないだろう)。
以上を踏まえた上で、現在満たしているニーズ以上の、さらなるニーズを満たすというのはどういうことかということを、納税者として図書館に関与する人には考えてほしいと思う。無料貸本屋論で懸念されたのは、貸出が図書館の業績評価の最大の指標となっていることだけではなくて、図書館サービスが民間サービスをクラウンディングアウトしているという点にもあった。その議論で直接問題視された新刊書籍市場に対する図書館の影響は明らかではないが、たぶん影響は大きくないけれども、ゼロだとは言えないだろう。また、図書館は本とは無関係なその他の余暇サービスとも競合する。無料でかつアメニティが高いならばなおさらだ。さらに多くの来館者を呼べる、すなわちより多数の住民のニーズを満たすという理由で、民間ビジネスと競合する領域に行政が参入するのを正当化していいものなのだろうか。
民間委託されようが図書館は公営である。近所に本屋が無い、あるいはスターバックスがないからという理由で、どこまで行政がそれらを代替していいのか。10代男子が図書館に来ないからといって『少年ジャンプ』を図書館に置いてよいだろうか?あるいは将来、仮に法律が変わって有料サービスが可能になるかもしれないとして、ニーズがあるからという理由で、アダルトビデオやレンタカーを、民間サービスより少し安い値段で図書館が提供するというのは肯定できるだろうか。もしかたしたら住民の間で多数決を採れば上のようなことが支持されるかもしれない。けれども違和感は無いか?公と民の間にはどこかに一線があるはずだ。その一線を守ろうとすると、図書館はそんなに多様になれないかもしれない可能性がある。
ただし、公と民の間の一線がどう決定されるかについては議論があるようだ。著者の言うように住民のニーズ(記事では利用者のニーズなのか有権者のニーズなのかが曖昧だが)によって、民主主義的に意思決定されるという立場もありうる。その場合は、支持さえあれば図書館はどんなサービスでも提供できるだろう。「足による投票」論もそういう発想にあり、地方自治体レベルではそれで問題がないのかもしれない。
一方で、私的領域に民主的意思決定が侵入するのを制限しようとする立場(いわゆる「立憲主義」もそう)もあるわけで、この場合には公立図書館のやることは限界づけられなければならないということになる。このとき、公的供給される図書館がどうしても民間の領域を侵してしまうことを説明する必要が出てくる。そこで「民間では供給できないことを図書館がしている」という論理を展開することになる。そういうわけで教養だとか文化という理念は今でも重要なのだ。それらを高邁で不毛という理由で捨ててしまえば──すなわち世に存在する書籍の間に価値の違いはない(あるいはあらゆる余暇の間にもない)という価値相対主義的な立場をとるならば──、図書館はかつて貸本屋がやってたことを奪って大規模にやっているだけの、不効率な官製ビジネスにすぎなくなる。
図書館の話の基本に据えるべきことは、民間が参入したくなるような価格で読書機会を供給しようとしても、需要はとても小さいという点である。ニーズや需要を根拠にできるならば、CCCは代官山蔦屋をモデルとした書店を自身の投資で武雄市や海老名市に建てただろう。しかし、図書館とは税金によって建設され、サービス価格を無料にまで押し下げてやっと利用者が出てくるという代物である。公立図書館がやっている共同書庫および資料閲覧と貸本サービスというのは、民間業者ならば採算が合わないからと手を出さないビジネスだ。けれども必要だからという理由でわざわざ公費が投入されているのである。なぜか?と問われて、「文化」「教養」あるいは「情報」「権利」という理念が出てくる。現実の図書館を知っていれば、そうした理念を馬鹿馬鹿しいと思う人もいるかもしれない。実際、達成されているかどうかも怪しい。もしそういう疑問を持つならば、民間委託を唱えるよりも公立図書館不要論を唱えたほうが潔いと思える。もはや図書館を公的供給する根拠が崩れているからだ。
以上は僕の考えではあるが、現在の一部の図書館関係者の間になんとなく存在するコンセンサスを反映してみようと試みたものだ。図書館におけるニーズへの対応という話をするならば、やはり行政サービスでどこまで応えてよいかについて著者の考えを披瀝してほしいと感じる。一応、著者は記事の最後で図書館関係者が支持しそうな理念で議論をパッケージしている。だが、重視されるのは「利用者(または有権者)の選択」だ。そして、ニーズへの対応という話ならば、民間に任せたほうがよい、ということになるのではないだろうか。いや、個人的にはカフェや書店が併設されていても、個人情報が少々抜かれようと大きな問題ではないと考えるので、武雄市図書館に関する話に限れば著者と評価はそう変わらないのかもしれない(蔵書と分類を除く)。しかし、「利用者の選択」に同意しろというならば、それは図書館と利用者だけの問題ではなくて、さまざまな民間サービスも巻き込む問題であって、軽々しく「そうですね」と頷くことができないところなのだ。
以上。でも上の記事は、これまでの図書館関係者の間で交されてきた議論を知らない人が見ると事態はこういう風に見えるということがよくわかって興味深かった。
僕が専門家ぶるのも気が引けるが、少々補足したくなる点があった。著者は図書館について建設的な態度で提言してくれている。この点は評価したい。けれども、著者のアドバイスは特に目新しいものではなく、「そういう考えではまずいのではないか」と近年の図書館関係者が見直してきた考えそのものだ。記事中、要点の一つとして"19世紀の技術と社会を前提とした生まれた現代の図書館のあり方は、それらが大きく変化した21世紀の状況に合わせて変えていく必要がある"と掲げられている。これと似たような話は、図書館関係者ならばさんざん内輪で聴かされてきただろう。そもそも啓蒙・教養志向図書館観vs.現実のニーズという図式自体は、1990年前後に貸出サービス肯定論として一部の図書館員が掲げ、前者を克服して後者を止揚するために使用されたものだ。(なお図書館の選書の世界ではニーズと需要は別物だが、以下ではごっちゃにして記す)。
著者によれば、サービス提供者である図書館員と住民が図書館に求めるニーズにミスマッチがあるという。この認識は正しい。ただ、こうした認識から誕生した初の図書館が武雄市図書館、というわけではなくて、貸出サービスを主に据えた全国各地にあるような今の公共図書館がそれにあたる。これらは1970年代以降に設置されており、「無料貸本屋」と批判された2000年前後を越えて現在までその基本的な方向性を維持している。啓蒙志向の古めかしい図書館の克服という話はつい最近登場したものではなくて、40年の歴史があるのである。図書館利用者層が特定の層に偏っているという話も、米国では1930年代末から繰り返されており(参考)、日本でも1980年代頃から確認されてきたことである。近年の調査でなおも利用者層が限定的であるということは、19世紀的な図書館の限界を表しているということではなくて、開館時間が拡大されかつ蔵書も大衆的になった現在の図書館でさえこの程度、というように解釈すべきものなのだ。(利用者層の偏りは近年流行の滞在型図書館でもおそらく克服できないだろう)。
以上を踏まえた上で、現在満たしているニーズ以上の、さらなるニーズを満たすというのはどういうことかということを、納税者として図書館に関与する人には考えてほしいと思う。無料貸本屋論で懸念されたのは、貸出が図書館の業績評価の最大の指標となっていることだけではなくて、図書館サービスが民間サービスをクラウンディングアウトしているという点にもあった。その議論で直接問題視された新刊書籍市場に対する図書館の影響は明らかではないが、たぶん影響は大きくないけれども、ゼロだとは言えないだろう。また、図書館は本とは無関係なその他の余暇サービスとも競合する。無料でかつアメニティが高いならばなおさらだ。さらに多くの来館者を呼べる、すなわちより多数の住民のニーズを満たすという理由で、民間ビジネスと競合する領域に行政が参入するのを正当化していいものなのだろうか。
民間委託されようが図書館は公営である。近所に本屋が無い、あるいはスターバックスがないからという理由で、どこまで行政がそれらを代替していいのか。10代男子が図書館に来ないからといって『少年ジャンプ』を図書館に置いてよいだろうか?あるいは将来、仮に法律が変わって有料サービスが可能になるかもしれないとして、ニーズがあるからという理由で、アダルトビデオやレンタカーを、民間サービスより少し安い値段で図書館が提供するというのは肯定できるだろうか。もしかたしたら住民の間で多数決を採れば上のようなことが支持されるかもしれない。けれども違和感は無いか?公と民の間にはどこかに一線があるはずだ。その一線を守ろうとすると、図書館はそんなに多様になれないかもしれない可能性がある。
ただし、公と民の間の一線がどう決定されるかについては議論があるようだ。著者の言うように住民のニーズ(記事では利用者のニーズなのか有権者のニーズなのかが曖昧だが)によって、民主主義的に意思決定されるという立場もありうる。その場合は、支持さえあれば図書館はどんなサービスでも提供できるだろう。「足による投票」論もそういう発想にあり、地方自治体レベルではそれで問題がないのかもしれない。
一方で、私的領域に民主的意思決定が侵入するのを制限しようとする立場(いわゆる「立憲主義」もそう)もあるわけで、この場合には公立図書館のやることは限界づけられなければならないということになる。このとき、公的供給される図書館がどうしても民間の領域を侵してしまうことを説明する必要が出てくる。そこで「民間では供給できないことを図書館がしている」という論理を展開することになる。そういうわけで教養だとか文化という理念は今でも重要なのだ。それらを高邁で不毛という理由で捨ててしまえば──すなわち世に存在する書籍の間に価値の違いはない(あるいはあらゆる余暇の間にもない)という価値相対主義的な立場をとるならば──、図書館はかつて貸本屋がやってたことを奪って大規模にやっているだけの、不効率な官製ビジネスにすぎなくなる。
図書館の話の基本に据えるべきことは、民間が参入したくなるような価格で読書機会を供給しようとしても、需要はとても小さいという点である。ニーズや需要を根拠にできるならば、CCCは代官山蔦屋をモデルとした書店を自身の投資で武雄市や海老名市に建てただろう。しかし、図書館とは税金によって建設され、サービス価格を無料にまで押し下げてやっと利用者が出てくるという代物である。公立図書館がやっている共同書庫および資料閲覧と貸本サービスというのは、民間業者ならば採算が合わないからと手を出さないビジネスだ。けれども必要だからという理由でわざわざ公費が投入されているのである。なぜか?と問われて、「文化」「教養」あるいは「情報」「権利」という理念が出てくる。現実の図書館を知っていれば、そうした理念を馬鹿馬鹿しいと思う人もいるかもしれない。実際、達成されているかどうかも怪しい。もしそういう疑問を持つならば、民間委託を唱えるよりも公立図書館不要論を唱えたほうが潔いと思える。もはや図書館を公的供給する根拠が崩れているからだ。
以上は僕の考えではあるが、現在の一部の図書館関係者の間になんとなく存在するコンセンサスを反映してみようと試みたものだ。図書館におけるニーズへの対応という話をするならば、やはり行政サービスでどこまで応えてよいかについて著者の考えを披瀝してほしいと感じる。一応、著者は記事の最後で図書館関係者が支持しそうな理念で議論をパッケージしている。だが、重視されるのは「利用者(または有権者)の選択」だ。そして、ニーズへの対応という話ならば、民間に任せたほうがよい、ということになるのではないだろうか。いや、個人的にはカフェや書店が併設されていても、個人情報が少々抜かれようと大きな問題ではないと考えるので、武雄市図書館に関する話に限れば著者と評価はそう変わらないのかもしれない(蔵書と分類を除く)。しかし、「利用者の選択」に同意しろというならば、それは図書館と利用者だけの問題ではなくて、さまざまな民間サービスも巻き込む問題であって、軽々しく「そうですね」と頷くことができないところなのだ。
以上。でも上の記事は、これまでの図書館関係者の間で交されてきた議論を知らない人が見ると事態はこういう風に見えるということがよくわかって興味深かった。