沢村昭洋さんの沖縄通信・・・沖縄の湧水を歩く (その1)
沢村昭洋
沖縄にはたくさんの湧水がある。沖縄本島は、北部は山が高く、谷川がある。でも中南部は、丘陵はあっても山らしい山はない。土地は琉球石灰岩が地表を被っているので、雨水が浸透して地下水が流れている。高台の下の崖の所や低い土地でも窪みになったところなど、水がわき出ている。
湧水は、島の人々にとって命の源であった。集落のあるところ、かならず湧水がある。水の湧き出るところは、石積みで整備し、貯水池を設けて、住民が共同で使用してきた。

こんな湧水を、沖縄では「カー」と言う。井戸とも呼んでいるが、大和でいう井戸とはまるで異なる。大和では地下水のありそうなところに、縦穴を掘った。昔は、つるべで水を汲み上げた。その後は、手押しのポンプで汲み上げていた。こういう井戸も沖縄にないわけではない。でも少ない。多いのは、自然の湧水である。井泉と呼ぶのが適しているかもしれない。
井泉の名称としては、通常、地表に水が湧き出て、すぐそのまま利用できるところを「カー」。斜面の奥に水源があり、石や木で樋(トイ)をつくり、水を導きだしているところは「ヒージャー(樋川)」と呼ぶ。「カー」と区別している。
「カー」は漢字を当てるとすれば「川」ではなく「井」である。首里王府で編纂した『琉球国旧記』では、「井(かあ)」と記している。ときには、「川」を使っている井泉もあるが、大和でいう川ではない。あくまで湧水である。
本島だけでも、一つの集落にいくつかの井戸がある。しかも、その湧水のある場所の地形や水の出方、利用の仕方はさまざまである。井泉といってもその姿はすべて同じものはない。地域ごとに異なる。まるで城の城壁のように、半円形に高く見事な石積みがされているところもあれば、素朴な井泉もある。上水道が普及してもう使われなくて、そのまま放置していると危険なので、コンクリートで蓋をしたり、鉄柵で囲い鍵をしているところもある。いまの姿は変わっていても、長年にわたり、住民の命と暮らしを支えてきた水源にはかわりない。島に生きる人々の水への思いは、大和で考えるよりはるかに大きい。
だからどこの井泉でも、必ず住民が祈願する拝所がある。そして、いまなお人々が日々、祈願に訪れる。そんな井泉の拝所を見ると、いかに島の人々にとって、井泉がかけがえのない役割を果たしてきたのか、そういう意味ではいまなお神聖な場所であることを、うかがい知ることができる。
たくさんの湧水をすべて見て回ることは不可能だ。たいていは、地域回りなどをしていて、井泉に出会う。そんな、歩いて見た湧水を紹介したい。
沢村さんの沖縄通信 目次
(カテゴリーから連続画像で見ることができます)
沢村さんのブログレキオ・島唄アッチャー 奥さんのブログレキオいくぼー日記











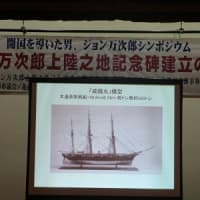







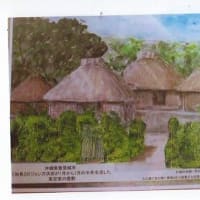
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます