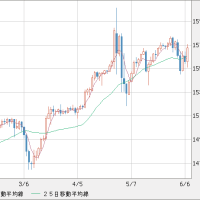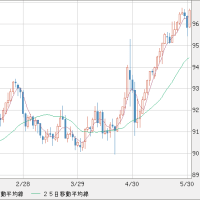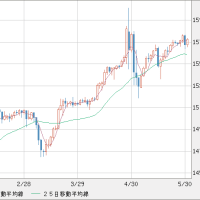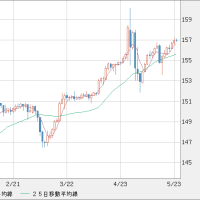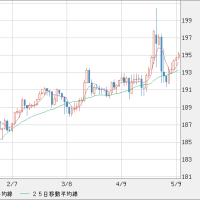最近めっきり格差是正の声が聞かれなくなり、
組合が自分達の仲間内の給与削減を牽制するための
浅ましい政治的言説に成り下がってしまった観がある。
給付付き税額控除の導入論議が進んでいる今、
もう一度論点を整理しておかないと政治力で左右されるという
我が国の歪んだ社会保障給付の二の舞になるであろう。
母子家庭や就学前教育、育児・介護分野の低所得労働者支援など、
今の内から優先順位を決めておく必要がある。
当ウェブログは、低所得層からの納税が税収全体に占める割合は
著しく低く、社会のあり方に根本的な問題があるという
格差是正派の現状認識の方が歪んでいる可能性を指摘した。
↓ 参考
あなた方は99%ではなく、3%にも満たないのだ。- 日本で反格差デモが支持されない理由
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/079e8cf08b08723f935b5d7df9a66533
近年メディアでの露出がめっきり減った勝間和代女史は、
アメリカの貧困層に肥満が多い理由のひとつとして、
「調理能力が失われていること」を挙げている。
つまり手軽でカロリー過多なジャンクフードばかり食べているということだ。
▽ 巻末にひっそり掲載されている
大阪大の大竹文雄教授は、実証研究を元に以下の指摘をされている。
○高学歴、高所得であるほど忍耐強い傾向がある
○中毒財(喫煙やギャンブル等)に依存する者は不幸度が高い
○必要でも後回しにする行動の多い者は、中毒財依存や負債も多い
しかも深刻なのは、子供の将来に強く影響を与えるのは
就学前の教育だということが研究で明らかになっている点だ。
これは学校教育や社会人の段階での改善の困難さを強く示唆する。
▽ こちらを参照のこと
以下の困難校ルポからは、意欲の低さや暴力、衝動性、劣悪な家庭環境といった
一部のアンダークラスの抱える根深い問題が分かる。
多大なコストと労力を投入しても改善するかどうかは不明だ。
▽ 著者の教条的な主張とは逆に、事態の深刻さと困難がありありと分かる
国民健康・栄養調査:女性の肥満、所得で差 200万円未満25%、600万円以上13%(毎日新聞)
http://mainichi.jp/life/health/news/20120201k0000m040057000c.html
予想通りといった数値だろう。
しかし厚労省のコメントは明確に誤っている。
医療や情報へのアクセスで数値が左右されるのであれば、
大都市圏と地方で差がつくはずだ。
地方の方が喫煙率が高く、肥満が多いという現象を
我々は目撃しているであろうか。
無意識的に自分たちの仕事(=予算)を増やそうとする
官庁側の本能的な情報操作にも困ったものだ。
所得低いほど生活習慣に問題あり 国民健康・栄養調査(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120201/bdy12020112070001-n1.htm
比較すると毎日新聞と産経新聞のスタンスの違いが分かる。
注目したいのは産経で野菜の摂取量に言及している点で、
「高価だから野菜が買えない」ということはあり得ないから、
その階層における支配的価値観や生活習慣にも原因があると言わざるを得ない。
所得階層別に健康や食事の現状・意識を調査すれば
厚労省のコメントがいかに迂闊なものかが分かるだろう。
組合が自分達の仲間内の給与削減を牽制するための
浅ましい政治的言説に成り下がってしまった観がある。
給付付き税額控除の導入論議が進んでいる今、
もう一度論点を整理しておかないと政治力で左右されるという
我が国の歪んだ社会保障給付の二の舞になるであろう。
母子家庭や就学前教育、育児・介護分野の低所得労働者支援など、
今の内から優先順位を決めておく必要がある。
当ウェブログは、低所得層からの納税が税収全体に占める割合は
著しく低く、社会のあり方に根本的な問題があるという
格差是正派の現状認識の方が歪んでいる可能性を指摘した。
↓ 参考
あなた方は99%ではなく、3%にも満たないのだ。- 日本で反格差デモが支持されない理由
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/079e8cf08b08723f935b5d7df9a66533
近年メディアでの露出がめっきり減った勝間和代女史は、
アメリカの貧困層に肥満が多い理由のひとつとして、
「調理能力が失われていること」を挙げている。
つまり手軽でカロリー過多なジャンクフードばかり食べているということだ。
▽ 巻末にひっそり掲載されている
 | 『暴走する資本主義』(ロバート・ライシュ,東洋経済新報社) |
大阪大の大竹文雄教授は、実証研究を元に以下の指摘をされている。
○高学歴、高所得であるほど忍耐強い傾向がある
○中毒財(喫煙やギャンブル等)に依存する者は不幸度が高い
○必要でも後回しにする行動の多い者は、中毒財依存や負債も多い
しかも深刻なのは、子供の将来に強く影響を与えるのは
就学前の教育だということが研究で明らかになっている点だ。
これは学校教育や社会人の段階での改善の困難さを強く示唆する。
▽ こちらを参照のこと
 | 『競争と公平感―市場経済の本当のメリット』(大竹文雄,中央公論新社) |
以下の困難校ルポからは、意欲の低さや暴力、衝動性、劣悪な家庭環境といった
一部のアンダークラスの抱える根深い問題が分かる。
多大なコストと労力を投入しても改善するかどうかは不明だ。
▽ 著者の教条的な主張とは逆に、事態の深刻さと困難がありありと分かる
 | 『ドキュメント高校中退―いま、貧困がうまれる場所』 |
国民健康・栄養調査:女性の肥満、所得で差 200万円未満25%、600万円以上13%(毎日新聞)
http://mainichi.jp/life/health/news/20120201k0000m040057000c.html
”所得が比較的低い人ほど喫煙率が高く、女性は肥満の割合が高い傾向がみられることが厚生労働省が10年に実施した国民健康・栄養調査で分かった。国が所得水準と生活習慣との関連について調査したのは初めて。【佐々木洋】
調査対象の約3200世帯の所得を「600万円以上」「200万~600万円未満」「200万円未満」に3区分し、「体形」「食生活」「運動」などの項目で比較した。
喫煙者の割合は「600万円以上」の世帯が男性27.0%、女性6.4%、「200万~600万円未満」は男性33.6%、女性8.8%、「200万円未満」は男性37.3%、女性11.7%と、所得が低いほど増加する傾向が認められた。
身長体重の数値から「肥満」と分類される人の割合は、男性は所得とは関連が認められなかったのに対し、女性は3区分ごとに13.2%、21.0%、25.6%と差が付いた。
一方、成人の喫煙率は男性32.2%(前年比6ポイント減)、女性8.4%(同2.5ポイント減)で男女とも86年の調査開始以来、過去最低を記録した。下げ幅も少なくとも03年以降では最大で、たばこ税の増税に伴う10年10月の値上げが影響した可能性もある。
厚労省は、所得により生活習慣に差があることについて「健診や医療、健康づくりに関する情報へのアクセスといった点で影響が出ている可能性がある」としている。”
予想通りといった数値だろう。
しかし厚労省のコメントは明確に誤っている。
医療や情報へのアクセスで数値が左右されるのであれば、
大都市圏と地方で差がつくはずだ。
地方の方が喫煙率が高く、肥満が多いという現象を
我々は目撃しているであろうか。
無意識的に自分たちの仕事(=予算)を増やそうとする
官庁側の本能的な情報操作にも困ったものだ。
所得低いほど生活習慣に問題あり 国民健康・栄養調査(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120201/bdy12020112070001-n1.htm
”世帯所得が低いほど、朝食を欠かしたり、運動習慣がなかったりするなど、生活習慣に問題がある人の割合が高くなる傾向があることが31日、厚生労働省の平成22年国民健康・栄養調査で分かった。
生活習慣に問題があると、脳卒中や高血圧症、糖尿病といった生活習慣病のリスクが高まる。厚労省は「所得が低いほどバランスのいい食事がとれず、健康への配慮ができていないのでは」と分析しており、25年度から始まる「次期健康づくり計画」で格差縮小を図る施策を打ち出す方針。
調査は22年11月に実施。生活習慣と所得の関係は、世帯所得を200万円未満▽200万円以上600万円未満▽600万円以上に分けて調べた。
それによると、成人の習慣的な喫煙者の割合は男女ともに世帯所得が低いほど高く、肥満(BMI=体格指数25以上)の人や運動習慣がない人の割合は女性で、習慣的に朝食を食べない人の割合は男性で、それぞれ高くなった。野菜の摂取量も、男女とも世帯所得が低いほど少なかった。
一方、全体の習慣的喫煙者の割合は前年比3.9ポイント減の19.5%で、初めて2割を切った。喫煙者のうち禁煙希望者は同比3.4ポイント増の37.6%で過去最高。
これを受け、厚労省は次期健康づくり計画に、禁煙希望者全員が禁煙に成功した場合の喫煙率「12.2%」を34年度までの目標値として明記する方針。次期がん対策推進基本計画にも同じ目標値を盛り込む。”
比較すると毎日新聞と産経新聞のスタンスの違いが分かる。
注目したいのは産経で野菜の摂取量に言及している点で、
「高価だから野菜が買えない」ということはあり得ないから、
その階層における支配的価値観や生活習慣にも原因があると言わざるを得ない。
所得階層別に健康や食事の現状・意識を調査すれば
厚労省のコメントがいかに迂闊なものかが分かるだろう。