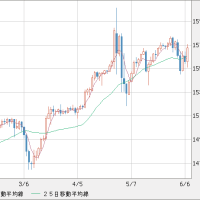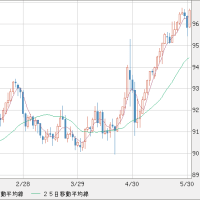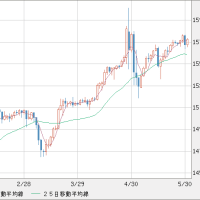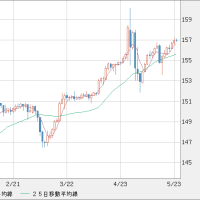台湾が脱原発を宣言したが、その後の産経新聞の反応が非常に面白い。
BBC記者の批判的な報道を引用して検証もせず、
いかにも権威追従的な記事内容となっている。
ドイツが脱原発を決めた際に自らがいかなる報道を行ったかを忘却して
台湾の脱原発宣言でも同じ轍を踏み、懲りずにまた同じ過ちを繰り返そうとしている。
実際、ドイツは着々と脱原発に成功しつつあり、
既に原子力のシェアは半分程度に急低下、
再生可能エネルギー比率は3割を超えている。
それだけでなく、何よりも原発推進派と原子力利権勢力にとって不都合なのは、
経済パフォーマンスにおいて日本がドイツに大敗していることだ。
原子力がただの利権に過ぎず、経済成長に結びつかないレントでしかないことは、
数値が明々白々に証明したと言える。
原発推進派や利害関係者は、なぜ脱原発を決めたドイツよりも
安倍政権下の日本の経済成長率や実質賃金上昇率が劣っているのか、はっきりと説明すべきである。
原発再稼働を進めるのと寧ろ逆相関で、日本の成長率はみるみる下がっているではないか!
ドイツの脱原発には確かに問題もあり、全ては肯定できない。
太陽光発電の買取制度の改革が遅れたのは先行者としてやむを得ない面もある。
また、風力の適地が需要地から遠いという地理的な要因も課題となっている。
しかし、政策面で明らかに日本よりも優れている点が二つあり、
バイオマスは熱利用とコージェネを優遇しており発電偏重の日本より賢いこと、
そしてコージェネ発電の買い取り制度で省エネを促進していることである。
ドイツの再生可能エネの主力がバイオマスであることはよく知られている。
電力だけに拘る視野狭窄ではなく、総合的なエネルギー効率の向上を図っているからこそ
ドイツは日本よりも経済パフォーマンスが良いのである。
▽ 再生可能エネでも省エネでもきめ細かく政策や制度を調整するのがドイツの特徴
当ウェブログが以前から指摘しているように、
国内の保守退嬰勢力が日本のエネルギー政策に嘴を挟み、質を下げているのは明白だ。
「日本のエネルギー政策が本質的に利権擁護的で、
革新においては枝葉末節的でダイナミズムに欠けるのは、
第一に制度設計やインセンティブ設計の下手さがある上に
典型的な利権癒着政権がのさばっているからである」
「但し、その保守退嬰を助長しているのが日本企業であるとの側面も見逃せず、
原子力利権と結託して再稼働という「カネのなる木」にしがみついて
公益を僭称して実際は一部企業の収益ばかりを優先する財界の姿勢にも問題がある」
「国民から徴収したカネで左団扇、努力せずに電力コストを低減させる
(実態は国民へのツケ回しでしかない)怠惰な企業は日本経済を成長させない」
「風力のような震災に強く、地域経済を支える再生可能エネに投資し、
エネルギー効率を高めるコージェネや省エネを推進する企業こそ公益に資するものだ」
「そうした企業がごく少ないことこそ日本経済の大問題であり、
我が国の成長率が低迷しているのにエネルギー消費の増加率がそれを上回るという
実に情けない醜態をもたらす元凶に他ならない」
「原子力大国フランスですら再生可能エネルギーの雇用創出効果に着目している」
「原発再稼働を求める理由は純粋に利己的なもので、
関連企業やエネルギー多消費企業の収益向上のためだ。
公益のためというのは見え透いた口実に過ぎない」
「国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の試算によれば、
再生可能エネルギーへの投資により最大の経済効果を得られる国は
他でもない、この日本だと言う。その額は20兆円に迫る」
「経済効果が最大のケースではGDPが3.6%(約18兆円)の成長、
最小のケースでも2.3%の成長に繋がるということだから、
政府が試算したTPPの経済効果よりも勝っている。
(TPPのような農業等の国内産業への打撃がほぼゼロなので、再生エネ投資の「完勝」である)」
「理由は明白で、膨大な化石燃料を輸入する必要がなくなり、
それを国内で自給できるようになるからだ」
「我が国の、保守退嬰で身内の利害しか眼中にない
圧力団体の主張は矢張り間違っていたことが明らかになった」
「同時に、我が国の経済停滞を招いている元凶が、
利権勢力と癒着し新規投資を実質的に妨害している
自民党政権のエネルギー政策の「次元の低さ」にあることも証明されたと言えよう。
(だから消費が沈滞し、マイナス成長に陥ったのだ)」
「投資額の伸びを見れば、安倍政権の愚かで利権擁護のエネルギー政策が
投資抑制の害悪をもたらしているのは明白である。
伸び率ではインドや英国の8分の1以下、中国の5分の1以下、アメリカの2分の1以下。
話にもならない「劣等生」でしかないのが実態だ」
「低コストで合理的な再生可能エネルギーの普及拡大を図らない限り、
日本の内需沈滞は変わらないであろう」
「ブルームバーグの調査会社が衝撃的な見通しを発表している。
世界の風力発電と太陽光発電が急拡大し、
2040年までに発電能力の42%に達するとのことだ」
「更に衝撃的なのは日本に関する見通しで、
2015年の13%から2040年は32%に急拡大するという。
2倍以上も発電能力が増大する訳だ」
「世界では再生可能エネルギーへの投資が伸び続けており、
風力や太陽光の発電コスト低下も続いている。
(投機的で劣等生の原子力とは大違いである)」
「勿論これは「発電能力」に過ぎないので
電源シェアとしては恐らく半分以下だろうが、それでも大変なことである」
「我が国は矢張り再生可能エネルギーの潜在力が豊かで、
コストに配慮しながら普及促進策を進めれば
夢の「純国産エネルギー」を大幅に伸ばすことができるのだ」
「燃料輸入を減らし、投機的な原子力のリスクを減らせるだけでなく、
このエネルギー資源に乏しい日本においてエネルギー自給率を高め、
災害に強い電源を手に入れることができるということをも意味する」
「電事連の次期会長が「原子力はエネルギーに乏しい日本では重要な電源」と
事実上、原発による特定大手事業者の利益を擁護する発言を行った直後だから、
「原子力業界」にとっては自らの近視眼と自己利益擁護を証明した形になってしまった」
「「社会からの信頼回復」は、原発再稼働に固執する限りあり得ない。
「原子力は独占できる我々には重要な電源」が本音であろう。
関電や九電の収益推移と原発稼働率を比較すればすぐに分かる話だ」
「ヤツコ委員長がいみじくも喝破したように、
いまだに公的補助が必要な原子力にはもはや将来性はない。
核軍備の副産物として細々と生き延びるしか道はないのだ」
「風力発電や太陽光発電は急激にコストが低下しており、
公的補助が殆ど不要になって原子力の劣位が愈々明確になる。
省エネも飛躍的に進むので、多くの国で原子力の存在自体が不要になろう。
(風力や太陽光に乏しい国は例外だが、日本はどちらの潜在資源も豊富である)」
だから同じ人口減少でもドイツ経済に負けるのである。
▽ 自民党政権下では、利権勢力がエネルギー政策に介入して制度を歪めてきた
パリ協定で遅刻ぎりぎりの出遅れとなっても、反省すらしていないのは情けない限りだ。
「エネルギー政策は利権勢力と癒着した内向き、
外交は独善的でリアルポリティークが分からない」
「そうした実態が事実で証明されつつある安倍政権は、
周知のようにパリ協定でも大失態を国際社会に晒している」
「アメリカも、中国も、インドも、エネルギー効率は日本より低い。
温室効果ガスを大幅に削減するには日本の環境技術が絶対に必要である」
「原発輸出など寝言を言って中露のダンピングに惨敗しているのに
全く反省もしないからこうした大失敗に陥るのが何故分からないのか」
「日本のコージェネや地中熱、風力発電、新型太陽電池、環境対応車の技術がなければ
どうやって米中印のような国が低炭素を実現できると言うのだろうか」
「パリ協定よりTPPを優先という馬鹿丸出しの官邸方針が
こうした大失敗の元凶である。まさに国益を損なうと言っても過言ではない」
「米中の動きを確実に捉えて俊敏に動いたのがEU、
ノーマークで油断し切っていたのが安倍政権である。
外交における安倍政権の実力不足が露骨に出た形だ」
「安倍政権は、エネルギー政策においても外交力においてもインドに惨敗している。
インドは風力発電に適する場所が少ないので低炭素化のハードルは日本以上に高い。
日本の省エネ技術がどうしても必要な筈なのだが。。
官邸の判断ミスのため、日本は大きなビジネスチャンスから遠ざかりつつある」
いつまで経っても思考停止で保守退嬰の安倍政権や御用メディアに痛撃を与え、
エネルギー政策を「正常化」させ、日本経済を甦らせなければならない。
↓ 参考
パリ協定で米中印から置き去り、お粗末な安倍政権の「官邸主導」- 省エネ・再生可能エネ技術が活かせない
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/5c679bc9a9741feb1cea00757417106f
2040年には風力と太陽光発電が32%を占める見通し、世界では42%に - 原子力は存在価値なし
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/8845aa016e793fd94f25a61f22ab2dee
日本は再生エネ投資で20兆円に迫る経済効果、TPPの試算効果をも超える -「資源輸入国は大きな経済効果」
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/82ef8df18698fb1c9419871369a4ad54
中国は2030年まで再生可能エネ比率50%超か、安倍政権の面目丸潰れ-「風力55倍、太陽光862倍に」
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d2d60cd5e21f98c4ee168f41ab65323d
▽ 再生可能エネ・省エネへの投資が雇用増・経済効果をもたらすというのは、既に世界の常識
台湾が原発全廃へ 福島第一事故受け、25年までに停止(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASJBQ5Q7SJBQUHBI014.html
日本企業にとっては台湾の脱原発は大変な朗報である。
日本の誇る、地中熱やコージェネ等の省エネ技術が絶大な威力を発揮するだけでなく
地熱発電の技術がまさに今、台湾が必要としているからだ。
日本企業の生み出した、オフィルビル間で太陽光発電の電気を融通する仕組みも
台北や高雄で急速に普及し、親日的な台湾の人々を喜ばせることとなろう。
行政院の計画説明にBBC記者が切り込んだ! 「なぜそんなに楽観的なのか?」 エネルギー自給率1% 電力不安も…(産経新聞)
http://www.sankei.com/world/news/161023/wor1610230032-n1.html
絶好の好機に気付かない産経新聞は、斜に構えて相変わらずのスタンスだ。
もしエネルギー政策を正しく理解しているならば、
鍵を握っているのが制度設計と省エネ促進であること、
日本の優れた省エネ技術がビジネスにとっても日台友好のためにも重要だと論じる筈だが。。
ドイツ、再生エネ3割超す脱原発決定5年 廃炉費用が課題(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM06HAT_W6A600C1FF8000/
産経新聞が散々批判的な報道をしていたドイツの脱原発の現状はこうだ。
必ずしも成功とは言えないが、明らかに失敗ではない。
ドイツの経験から言えば、台湾の脱原発も充分可能性ありと見るのが妥当である。
風力の適地が日本よりも少ないと思われるので、
再生可能エネが20%に達するかどうかは何とも言えないが、
日本の省エネ技術とノウハウを導入すれば、台湾の脱原発など余裕である。
BBC記者の批判的な報道を引用して検証もせず、
いかにも権威追従的な記事内容となっている。
ドイツが脱原発を決めた際に自らがいかなる報道を行ったかを忘却して
台湾の脱原発宣言でも同じ轍を踏み、懲りずにまた同じ過ちを繰り返そうとしている。
実際、ドイツは着々と脱原発に成功しつつあり、
既に原子力のシェアは半分程度に急低下、
再生可能エネルギー比率は3割を超えている。
それだけでなく、何よりも原発推進派と原子力利権勢力にとって不都合なのは、
経済パフォーマンスにおいて日本がドイツに大敗していることだ。
原子力がただの利権に過ぎず、経済成長に結びつかないレントでしかないことは、
数値が明々白々に証明したと言える。
原発推進派や利害関係者は、なぜ脱原発を決めたドイツよりも
安倍政権下の日本の経済成長率や実質賃金上昇率が劣っているのか、はっきりと説明すべきである。
原発再稼働を進めるのと寧ろ逆相関で、日本の成長率はみるみる下がっているではないか!
ドイツの脱原発には確かに問題もあり、全ては肯定できない。
太陽光発電の買取制度の改革が遅れたのは先行者としてやむを得ない面もある。
また、風力の適地が需要地から遠いという地理的な要因も課題となっている。
しかし、政策面で明らかに日本よりも優れている点が二つあり、
バイオマスは熱利用とコージェネを優遇しており発電偏重の日本より賢いこと、
そしてコージェネ発電の買い取り制度で省エネを促進していることである。
ドイツの再生可能エネの主力がバイオマスであることはよく知られている。
電力だけに拘る視野狭窄ではなく、総合的なエネルギー効率の向上を図っているからこそ
ドイツは日本よりも経済パフォーマンスが良いのである。
▽ 再生可能エネでも省エネでもきめ細かく政策や制度を調整するのがドイツの特徴
 | 『日本林業はよみがえる―森林再生のビジネスモデルを描く』(梶山恵司,日本経済新聞出版社) |
当ウェブログが以前から指摘しているように、
国内の保守退嬰勢力が日本のエネルギー政策に嘴を挟み、質を下げているのは明白だ。
「日本のエネルギー政策が本質的に利権擁護的で、
革新においては枝葉末節的でダイナミズムに欠けるのは、
第一に制度設計やインセンティブ設計の下手さがある上に
典型的な利権癒着政権がのさばっているからである」
「但し、その保守退嬰を助長しているのが日本企業であるとの側面も見逃せず、
原子力利権と結託して再稼働という「カネのなる木」にしがみついて
公益を僭称して実際は一部企業の収益ばかりを優先する財界の姿勢にも問題がある」
「国民から徴収したカネで左団扇、努力せずに電力コストを低減させる
(実態は国民へのツケ回しでしかない)怠惰な企業は日本経済を成長させない」
「風力のような震災に強く、地域経済を支える再生可能エネに投資し、
エネルギー効率を高めるコージェネや省エネを推進する企業こそ公益に資するものだ」
「そうした企業がごく少ないことこそ日本経済の大問題であり、
我が国の成長率が低迷しているのにエネルギー消費の増加率がそれを上回るという
実に情けない醜態をもたらす元凶に他ならない」
「原子力大国フランスですら再生可能エネルギーの雇用創出効果に着目している」
「原発再稼働を求める理由は純粋に利己的なもので、
関連企業やエネルギー多消費企業の収益向上のためだ。
公益のためというのは見え透いた口実に過ぎない」
「国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の試算によれば、
再生可能エネルギーへの投資により最大の経済効果を得られる国は
他でもない、この日本だと言う。その額は20兆円に迫る」
「経済効果が最大のケースではGDPが3.6%(約18兆円)の成長、
最小のケースでも2.3%の成長に繋がるということだから、
政府が試算したTPPの経済効果よりも勝っている。
(TPPのような農業等の国内産業への打撃がほぼゼロなので、再生エネ投資の「完勝」である)」
「理由は明白で、膨大な化石燃料を輸入する必要がなくなり、
それを国内で自給できるようになるからだ」
「我が国の、保守退嬰で身内の利害しか眼中にない
圧力団体の主張は矢張り間違っていたことが明らかになった」
「同時に、我が国の経済停滞を招いている元凶が、
利権勢力と癒着し新規投資を実質的に妨害している
自民党政権のエネルギー政策の「次元の低さ」にあることも証明されたと言えよう。
(だから消費が沈滞し、マイナス成長に陥ったのだ)」
「投資額の伸びを見れば、安倍政権の愚かで利権擁護のエネルギー政策が
投資抑制の害悪をもたらしているのは明白である。
伸び率ではインドや英国の8分の1以下、中国の5分の1以下、アメリカの2分の1以下。
話にもならない「劣等生」でしかないのが実態だ」
「低コストで合理的な再生可能エネルギーの普及拡大を図らない限り、
日本の内需沈滞は変わらないであろう」
「ブルームバーグの調査会社が衝撃的な見通しを発表している。
世界の風力発電と太陽光発電が急拡大し、
2040年までに発電能力の42%に達するとのことだ」
「更に衝撃的なのは日本に関する見通しで、
2015年の13%から2040年は32%に急拡大するという。
2倍以上も発電能力が増大する訳だ」
「世界では再生可能エネルギーへの投資が伸び続けており、
風力や太陽光の発電コスト低下も続いている。
(投機的で劣等生の原子力とは大違いである)」
「勿論これは「発電能力」に過ぎないので
電源シェアとしては恐らく半分以下だろうが、それでも大変なことである」
「我が国は矢張り再生可能エネルギーの潜在力が豊かで、
コストに配慮しながら普及促進策を進めれば
夢の「純国産エネルギー」を大幅に伸ばすことができるのだ」
「燃料輸入を減らし、投機的な原子力のリスクを減らせるだけでなく、
このエネルギー資源に乏しい日本においてエネルギー自給率を高め、
災害に強い電源を手に入れることができるということをも意味する」
「電事連の次期会長が「原子力はエネルギーに乏しい日本では重要な電源」と
事実上、原発による特定大手事業者の利益を擁護する発言を行った直後だから、
「原子力業界」にとっては自らの近視眼と自己利益擁護を証明した形になってしまった」
「「社会からの信頼回復」は、原発再稼働に固執する限りあり得ない。
「原子力は独占できる我々には重要な電源」が本音であろう。
関電や九電の収益推移と原発稼働率を比較すればすぐに分かる話だ」
「ヤツコ委員長がいみじくも喝破したように、
いまだに公的補助が必要な原子力にはもはや将来性はない。
核軍備の副産物として細々と生き延びるしか道はないのだ」
「風力発電や太陽光発電は急激にコストが低下しており、
公的補助が殆ど不要になって原子力の劣位が愈々明確になる。
省エネも飛躍的に進むので、多くの国で原子力の存在自体が不要になろう。
(風力や太陽光に乏しい国は例外だが、日本はどちらの潜在資源も豊富である)」
だから同じ人口減少でもドイツ経済に負けるのである。
▽ 自民党政権下では、利権勢力がエネルギー政策に介入して制度を歪めてきた
 | 『エコ・ウオーズ 低炭素社会への挑戦』(朝日新聞特別取材班) |
パリ協定で遅刻ぎりぎりの出遅れとなっても、反省すらしていないのは情けない限りだ。
「エネルギー政策は利権勢力と癒着した内向き、
外交は独善的でリアルポリティークが分からない」
「そうした実態が事実で証明されつつある安倍政権は、
周知のようにパリ協定でも大失態を国際社会に晒している」
「アメリカも、中国も、インドも、エネルギー効率は日本より低い。
温室効果ガスを大幅に削減するには日本の環境技術が絶対に必要である」
「原発輸出など寝言を言って中露のダンピングに惨敗しているのに
全く反省もしないからこうした大失敗に陥るのが何故分からないのか」
「日本のコージェネや地中熱、風力発電、新型太陽電池、環境対応車の技術がなければ
どうやって米中印のような国が低炭素を実現できると言うのだろうか」
「パリ協定よりTPPを優先という馬鹿丸出しの官邸方針が
こうした大失敗の元凶である。まさに国益を損なうと言っても過言ではない」
「米中の動きを確実に捉えて俊敏に動いたのがEU、
ノーマークで油断し切っていたのが安倍政権である。
外交における安倍政権の実力不足が露骨に出た形だ」
「安倍政権は、エネルギー政策においても外交力においてもインドに惨敗している。
インドは風力発電に適する場所が少ないので低炭素化のハードルは日本以上に高い。
日本の省エネ技術がどうしても必要な筈なのだが。。
官邸の判断ミスのため、日本は大きなビジネスチャンスから遠ざかりつつある」
いつまで経っても思考停止で保守退嬰の安倍政権や御用メディアに痛撃を与え、
エネルギー政策を「正常化」させ、日本経済を甦らせなければならない。
↓ 参考
パリ協定で米中印から置き去り、お粗末な安倍政権の「官邸主導」- 省エネ・再生可能エネ技術が活かせない
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/5c679bc9a9741feb1cea00757417106f
2040年には風力と太陽光発電が32%を占める見通し、世界では42%に - 原子力は存在価値なし
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/8845aa016e793fd94f25a61f22ab2dee
日本は再生エネ投資で20兆円に迫る経済効果、TPPの試算効果をも超える -「資源輸入国は大きな経済効果」
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/82ef8df18698fb1c9419871369a4ad54
中国は2030年まで再生可能エネ比率50%超か、安倍政権の面目丸潰れ-「風力55倍、太陽光862倍に」
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d2d60cd5e21f98c4ee168f41ab65323d
▽ 再生可能エネ・省エネへの投資が雇用増・経済効果をもたらすというのは、既に世界の常識
 | 『グリーン経済最前線』(末吉竹二郎/井田徹治,岩波書店) |
台湾が原発全廃へ 福島第一事故受け、25年までに停止(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASJBQ5Q7SJBQUHBI014.html
”台湾の蔡英文(ツァイインウェン)政権が2025年に「原発ゼロ」にすることを決め、行政院(内閣)は、再生エネルギー事業への民間参画を促す電気事業法の改正案を閣議決定した。太陽光と風力発電を中心に再生エネの割合を20%まで高めることを目指す。東日本大震災後の反原発の民意を受けたもので、改正案は近く立法院(国会)で審議に入り、年内の可決を目指す。
世界的にはドイツが2022年までの原発全廃を決めるなど、欧州を中心に脱原発の動きがある。一方、増える電力需要に応えるため中国やインドが原発を増設させており、アジアでは台湾の取り組みは珍しい。
改正案は20日に閣議決定され、6~9年かけて発送電分離も行う。
〔中略〕
台湾では原発が発電容量の14.1%(15年)を占め、現在は第一~第三原発で計3基が稼働中。だが、東京電力福島第一原発の事故で台湾でも反原発の世論が高まり、原発ゼロを公約に5月に就任した蔡氏が政策のかじを切った。台湾も日本と同様に地震が多い。稼働中の全原発は25年までに40年の稼働期間満了となる。同法改正案では25年までに全原発停止と明記し、期間延長の道を閉ざす。”
日本企業にとっては台湾の脱原発は大変な朗報である。
日本の誇る、地中熱やコージェネ等の省エネ技術が絶大な威力を発揮するだけでなく
地熱発電の技術がまさに今、台湾が必要としているからだ。
日本企業の生み出した、オフィルビル間で太陽光発電の電気を融通する仕組みも
台北や高雄で急速に普及し、親日的な台湾の人々を喜ばせることとなろう。
行政院の計画説明にBBC記者が切り込んだ! 「なぜそんなに楽観的なのか?」 エネルギー自給率1% 電力不安も…(産経新聞)
http://www.sankei.com/world/news/161023/wor1610230032-n1.html
”【台北=田中靖人】台湾の蔡英文政権が2025年の「脱原発」に向けたエネルギー政策の具体化に乗り出した。行政院(内閣に相当)は20日、再生可能エネルギー普及に向け、発送電分離に向けた改正法案を決定。再生エネ発電量を20%に引き上げるため、太陽光・風力発電を大幅に増やす計画も策定した。ただ、計画実現をめぐり内外から厳しい目が向けられている。
「澎湖はグリーンエネルギーを台湾(本島)に供給する重要な電源になる」
海風を利用し、台湾で最も早く風力発電を始めた台湾海峡の離島、澎湖諸島の陳光復県長(知事)は19日、訪れた海外メディアにこう強調した。澎湖は現在、人口約10万人分の約15%を供給。25年までに、太陽光も加えた発電能力を増強して再生エネ供給率を100%とし、余剰分は海底ケーブルで約60キロ離れた台湾本島に送電する計画だ。
台湾はエネルギー自給率が1%と海外依存度が高い。だが蔡総統は、東京電力福島第1原発事故後の反原発機運の高まりを受け、総統選で「非核家園(原発のない故郷)」を25年に実現すると公約。商業利用中の原子炉6基は、運転期間40年の「寿命」を延長せず順次、停止し、代わりに再生エネで自給率を向上させ、「循環型経済」を実現するとしている。
〔中略〕
背景には、「脱原発」に対する内外の懐疑的な見方を払拭したい思惑がある。電力の不足と価格上昇への不安が経済界で強く、海外からの投資意欲も減退すれば、中国依存経済からの脱却を目指す蔡政権にとり、死活問題にもなりかねない。ただ疑念払拭は容易ではない。
「短期間の計画で、なぜそんなに楽観的なのか」
行政院が20日に開いた説明会で、英BBCの記者から厳しい質問が出た。再生エネ率20%を達成する25年までに、関連投資は約1兆7000億台湾元(約5兆6000億円)、約10万人の雇用を生む-。よどみなく説明していた経済部能源局(資源エネルギー庁)の局長は「新政権が25年と定めた。われわれの任務は目標を達成することだ」と答えただけだった。”
絶好の好機に気付かない産経新聞は、斜に構えて相変わらずのスタンスだ。
もしエネルギー政策を正しく理解しているならば、
鍵を握っているのが制度設計と省エネ促進であること、
日本の優れた省エネ技術がビジネスにとっても日台友好のためにも重要だと論じる筈だが。。
ドイツ、再生エネ3割超す脱原発決定5年 廃炉費用が課題(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM06HAT_W6A600C1FF8000/
”【フランクフルト=加藤貴行】ドイツ政府が2022年までの脱原発を閣議決定し、6日で5年を迎えた。国内の発電量に占める原子力発電所の比率は 10年の22%から15年に14%まで低下、電力大手は事業モデルの組み替えを急ピッチで進める。再生可能エネルギーの比率は30%を超え、課題の石炭火力依存度は少しずつ低下した。脱原発は順調にみえるが、廃炉の進め方など課題も残る。
「消費者に向いたビジネスモデルに転換…〔以下略〕”
産経新聞が散々批判的な報道をしていたドイツの脱原発の現状はこうだ。
必ずしも成功とは言えないが、明らかに失敗ではない。
ドイツの経験から言えば、台湾の脱原発も充分可能性ありと見るのが妥当である。
風力の適地が日本よりも少ないと思われるので、
再生可能エネが20%に達するかどうかは何とも言えないが、
日本の省エネ技術とノウハウを導入すれば、台湾の脱原発など余裕である。